大学受験英語
学習体制
オリジナル学習サイクル
学習は「授業 ➡ 自習(→質問 → 24時間以内に回答)➡ 次回授業」というサイクルで、市販・オリジナル教材を使用しながら進めていきます。この流れの中で、生徒さんの理解度やペースを細かく確認しながら、年間・月間・日別の学習計画を柔軟に調整いたします。
「365日・24時間以内」サポート
授業日以外でも、ご質問には「365日・24時間以内」に必ず返答いたします。学習のつまずきをそのままにせず、常に安心して次のステップへ進める環境を整えております。
少人数会員制
少人数会員制だからこそ実現できる「寄り添うサポート」で、生徒さんとご家庭に安心と確かな成長をお届けいたします。
学習ステップ
- 語彙・文法
- 知識レベル→意識レベル→無意識レベル
- リスニング・リーディング
- 精聴→多聴
- 精読→多読→速読
- スピーキング・ライティング
- 瞬間英作文・自由英作文(80~150字)
学習項目
語彙
語彙を身につけるには、実際に使いながら覚えることが大切です。しかし、日本では外国人と接する機会が少なく、学習しても英語を使う場面がなかなかありません。そんなときに役立つのが「英語の読書」です。
ただし、自分のレベルに合った英語の教材を見つけるのは意外と難しいものです。研究によると、英文をスムーズに理解するには、その中の単語の95%以上を知っている必要があると言われています。逆に、知っている単語が65%程度しかない場合、文章は次のように見えてしまいます。
The world's _____ problem is _____ due to human activities. Many _____ are facing _____ because of deforestation and _____ . The _____ of fossil fuels has also contributed to _____ change. Experts say that if we do not take _____ action, the situation will continue to _____ , leading to more _____ in the future. Governments and _____ organizations are trying to _____ solutions, but progress is still _____. It is important for everyone to _____ steps to _____ the environment for future _____ .
このように、単語が抜けて見えるため、辞書を引きながらでないと読めません。しかし、95%の単語を知っていれば、文章は次のように見えます。
The world's climate problem is worsening due to human activities. Many species are facing _____ because of deforestation and pollution. The burning of fossil fuels has also contributed to climate change. Experts say that if we do not take immediate action, the situation will continue to _____, leading to more natural disasters in the future. Governments and environmental organizations are trying to _____ solutions, but progress is still slow. It is important for everyone to take steps to protect the environment for future _____.
空所extinction/deteriorate/implement/generations
このレベルなら、多少の知らない単語があってもスムーズに読めます。
語彙力を増やすためのポイント
自分のレベルに合った教材を選び、知らない単語が全体の5%程度になるものから始めましょう。そうすることで、無理なく語彙力を増やしながら、英語をスムーズに読めるようになります。
- 単語練習(標準)
- 熟語練習(標準)
英単語練習(標準:英検2級・日東駒専レベル)
●●●は単語・例文の日本語意味
1 believe ( I believe everything will turn out fine. ) ●●●
2 consider ( Please consider my proposal carefully. ) ●●●
3 expect ( We expect him to arrive by noon. ) ●●●
4 decide ( She decided to join the music club. ) ●●●
5 allow ( The teacher allowed extra time for the exam. ) ●●●
6 remember ( Remember to bring your umbrella today. ) ●●●
7 worry ( Don’t worry about the small details. ) ●●●
8 concern ( His health is a matter of great concern. ) ●●●
9 suggest ( Can you suggest a good restaurant nearby? ) ●●●
10 explain ( Let me explain how this machine works. ) ●●●
11 describe ( Could you describe the painting in more detail? ) ●●●
12 improve ( Practicing daily will improve your skills. ) ●●●
13 produce ( The factory produces thousands of products annually. ) ●●●
14 create ( Let’s create something unique together. ) ●●●
15 provide ( The hotel provides free breakfast to guests. ) ●●●
16 increase ( We need to increase our efficiency at work. ) ●●●
17 grow ( Tomatoes grow well in sunny areas. ) ●●●
18 develop ( The company plans to develop new software. ) ●●●
19 rise ( The sun rises in the east. ) ●●●
20 raise ( They raised funds for charity through the event. ) ●●●
21 follow ( Please follow the instructions step by step. ) ●●●
22 require ( This task requires a lot of patience. ) ●●●
23 fill ( Could you fill this form for me, please? ) ●●●
24 support ( He always supports his friends during difficult times. ) ●●●
25 share ( We should share ideas to make progress. ) ●●●
26 face ( You must face challenges with courage. ) ●●●
27 touch ( The story touched her deeply. ) ●●●
28 store ( We store extra goods in the warehouse. ) ●●●
29 pay ( I need to pay my bills today. ) ●●●
30 deal ( They struck a deal after long negotiations. ) ●●●
31 save ( Save some money for future emergencies. ) ●●●
32 happen ( What will happen if the project gets delayed? ) ●●●
33 occur ( The accident occurred late last night. ) ●●●
34 work ( She works hard to achieve her dreams. ) ●●●
35 change ( The weather can change quickly in spring. ) ●●●
36 run ( He runs every morning to stay fit. ) ●●●
37 turn ( Turn left at the next intersection. ) ●●●
38 return ( She promised to return the borrowed book. ) ●●●
39 stand ( He stood silently during the ceremony. ) ●●●
40 lie ( The book lies on the table near the window. ) ●●●
41 brain ( Regular exercise is beneficial for the brain. ) ●●●
42 mind ( Her mind was full of creative ideas. ) ●●●
43 language ( Learning a new language can open many doors. ) ●●●
44 thought ( His thoughts on the topic were insightful. ) ●●●
45 knowledge ( Sharing knowledge helps everyone grow. ) ●●●
46 skill ( Cooking is a skill that improves with practice. ) ●●●
47 technology ( Modern technology has revolutionized communication. ) ●●●
48 culture ( Japanese culture fascinates many visitors. ) ●●●
49 experience ( Traveling gives you valuable experience. ) ●●●
50 result ( Hard work often results in success. ) ●●●
51 reason ( What’s the reason for your late arrival? ) ●●●
52 cause ( Smoking is a leading cause of lung diseases. ) ●●●
53 effect ( The effect of the new policy was evident. ) ●●●
54 matter ( It doesn’t matter as long as you’re happy. ) ●●●
55 sense ( I can’t make sense of this puzzle. ) ●●●
56 way ( This is the best way to approach the problem. ) ●●●
57 term ( “On time” is a commonly used term in business. ) ●●●
58 situation ( We’re working on improving the current situation. ) ●●●
59 condition ( The car is in excellent condition. ) ●●●
60 position ( She took a position at a leading firm. ) ●●●
61 environment ( Protecting the environment is everyone’s responsibility. ) ●●●
62 nature ( Spending time in nature is refreshing. ) ●●●
63 research ( Scientific research leads to discoveries. ) ●●●
64 rule ( Always follow the rules to maintain order. ) ●●●
65 interest ( He has a keen interest in astronomy. ) ●●●
66 value ( The value of kindness cannot be overstated. ) ●●●
67 view ( The view from the mountain top is breathtaking. ) ●●●
68 sound ( The sound of the waves was relaxing. ) ●●●
69 form ( Fill out this form for registration, please. ) ●●●
70 case ( This is a unique case worth studying. ) ●●●
71 role ( The actor played a challenging role in the film. ) ●●●
72 age ( At the age of ten, she started learning piano. ) ●●●
73 care ( Take care when handling fragile items. ) ●●●
74 risk ( He took a risk by starting his own business. ) ●●●
75 human ( Understanding human behavior is fascinating. ) ●●●
76 free ( Feel free to reach out for help anytime. ) ●●●
77 sure ( Are you sure about your decision? ) ●●●
78 certain ( I’m certain he’ll succeed in his project. ) ●●●
79 main ( The main goal of the project is to improve safety. ) ●●●
80 major ( This city is a major cultural hub. ) ●●●
81 minor ( There are minor issues that need resolving. ) ●●●
82 clear ( The instructions were clear and easy to follow. ) ●●●
83 likely ( It’s likely to rain later today. ) ●●●
84 possible ( Is it possible to finish the task by tomorrow? ) ●●●
85 similar ( His ideas are similar to mine. ) ●●●
86 close ( We’re very close to completing the project. ) ●●●
87 common ( This is a common method used in engineering. ) ●●●
88 general ( He has a general idea about the topic. ) ●●●
89 ordinary ( She finds joy in ordinary moments. ) ●●●
90 specific ( Could you give me more specific details? ) ●●●
91 particular ( I have a particular interest in modern art. ) ●●●
92 individual ( Each individual brings unique talents to the team. ) ●●●
93 unique ( This antique piece is truly unique. ) ●●●
94 rare ( Sightings of the rare bird have been reported. ) ●●●
95 therefore ( He missed the train; therefore, he’ll be late. ) ●●●
96 thus ( She completed the tasks; thus, she was rewarded. ) ●●●
97 moreover ( He’s kind and smart; moreover, he’s funny. ) ●●●
98 furthermore ( Furthermore, the proposal includes several advantages. ) ●●●
99 besides ( Besides painting, she enjoys playing the violin. ) ●●●
100 nonthless ( It was challenging, but he succeeded nonetheless. ) ●●●
101 notice ( I didn’t notice the mistake until it was too late. ) ●●●
102 note ( Please note that the meeting has been rescheduled. ) ●●●
103 discover ( She discovered a new way to solve the problem. ) ●●●
104 realize ( He realized he left his keys at home. ) ●●●
105 recognize ( I didn’t recognize her after so many years. ) ●●●
106 encourage ( Teachers should encourage their students to ask questions. ) ●●●
107 force ( The storm forced them to stay indoors. ) ●●●
108 order ( They ordered pizza for dinner. ) ●●●
109 affect ( The weather can affect your mood. ) ●●●
110 offer ( He offered to help with the heavy boxes. ) ●●●
111 demand ( The workers demanded better wages. ) ●●●
112 argue ( They argued about the best way to plan the trip. ) ●●●
113 claim ( She claims to have seen a rare bird in the park. ) ●●●
114 object ( Many residents objected to the new building plans. ) ●●●
115 challenge ( He challenged his friend to a game of chess. ) ●●●
116 involve ( The project involves multiple departments. ) ●●●
117 include ( The recipe includes fresh vegetables and spices. ) ●●●
118 contain ( This box contains important documents. ) ●●●
119 relate ( Can you relate this story to your own experiences? ) ●●●
120 connect ( The bridge connects the two islands. ) ●●●
121 refer ( Please refer to the instructions for further details. ) ●●●
122 contact ( You can contact me at this number if needed. ) ●●●
123 compare ( She compared the two products before buying one. ) ●●●
124 measure ( We need to measure the length of the table. ) ●●●
125 mark ( Please mark the items you want to purchase. ) ●●●
126 approach ( He approached the problem in a creative way. ) ●●●
127 reach ( They finally reached the top of the mountain. ) ●●●
128 achieve ( Hard work helps you achieve your goals. ) ●●●
129 receive ( She received a gift from her colleague. ) ●●●
130 complete ( He completed the assignment ahead of the deadline. ) ●●●
131 lead ( She leads the team with confidence and skill. ) ●●●
132 win ( They won the championship after a tough match. ) ●●●
133 lose ( He lost his wallet during the trip. ) ●●●
134 fail ( The project failed due to a lack of resources. ) ●●●
135 miss ( Don’t miss the opportunity to attend the event. ) ●●●
136 lack ( The team lacks experience in this field. ) ●●●
137 reduce ( We need to reduce waste in our daily lives. ) ●●●
138 avoid ( Try to avoid making the same mistake twice. ) ●●●
139 limit ( The government limited access to certain areas. ) ●●●
140 prevent ( Regular exercise can help prevent illnesses. ) ●●●
141 wear ( She wore a beautiful dress for the party. ) ●●●
142 bear ( I can’t bear the noise any longer. ) ●●●
143 focus ( He focused on his studies to pass the exam. ) ●●●
144 author ( The author of this book is very famous. ) ●●●
145 professor ( The professor gave an insightful lecture. ) ●●●
146 sentence ( The sentence was difficult to understand. ) ●●●
147 passage ( Please read this passage carefully before answering. ) ●●●
148 message ( I left a message on her voicemail. ) ●●●
149 statement ( His statement clarified the situation. ) ●●●
150 topic ( The topic of today’s discussion is climate change. ) ●●●
151 article ( I read an interesting article about space exploration. ) ●●●
152 issue ( Environmental pollution is a serious issue we must address. ) ●●●
153 theory ( His theory explains the phenomenon in detail. ) ●●●
154 evidence ( There is no clear evidence to support the claim. ) ●●●
155 experiment ( The scientist conducted an experiment to test the hypothesis. ) ●●●
156 subject ( Mathematics is my favorite school subject. ) ●●●
157 government ( The government announced a new policy on healthcare. ) ●●●
158 policy ( The company has a strict no-smoking policy. ) ●●●
159 education ( Access to quality education is essential for every child. ) ●●●
160 company ( She works for a multinational company in Tokyo. ) ●●●
161 colleague ( My colleagues are supportive and hardworking. ) ●●●
162 industry ( The automobile industry is growing rapidly. ) ●●●
163 trade ( International trade plays a crucial role in the economy. ) ●●●
164 economy ( The country’s economy is recovering steadily. ) ●●●
165 customer ( The store provides excellent service to its customers. ) ●●●
166 benefit ( Regular exercise has many health benefits. ) ●●●
167 figure ( The sales figures for last month were impressive. ) ●●●
168 rate ( The birth rate in this region has declined. ) ●●●
169 chance ( This is your chance to make a great impression. ) ●●●
170 opportunity ( She seized the opportunity to study abroad. ) ●●●
171 project ( The team is working hard to complete the project on time. ) ●●●
172 practice ( Practice makes perfect in any skill. ) ●●●
173 effort ( His efforts to solve the problem were commendable. ) ●●●
174 quality ( The quality of this product is excellent. ) ●●●
175 quantity ( We need a large quantity of materials for the construction. ) ●●●
176 amount ( A small amount of sugar is added to the recipe. ) ●●●
177 scientific ( Scientific discoveries have transformed our lives. ) ●●●
178 political ( The political situation in the country is stable. ) ●●●
179 social ( Social media has changed how people communicate. ) ●●●
180 official ( He received an official invitation to the event. ) ●●●
181 financial ( Financial planning is important for a secure future. ) ●●●
182 expensive ( This car is too expensive for my budget. ) ●●●
183 various ( There are various options available for accommodation. ) ●●●
184 normal ( It’s normal to feel nervous before a big exam. ) ●●●
185 familiar ( This song sounds familiar to me. ) ●●●
186 appropriate ( Please wear appropriate clothing for the interview. ) ●●●
187 necessary ( It’s necessary to have a passport for international travel. ) ●●●
188 correct ( Please ensure that the information is correct before submitting. ) ●●●
189 available ( The book is available at the library. ) ●●●
190 typical ( It was a typical summer day with clear skies. ) ●●●
191 positive ( She always has a positive outlook on life. ) ●●●
192 negative ( He avoided negative thoughts during his recovery. ) ●●●
193 passive ( His response to criticism was quite passive. ) ●●●
194 physical ( Physical exercise is important for maintaining good health. ) ●●●
195 mental ( Mental health should be prioritized just as much as physical health. ) ●●●
196 rather ( I would rather stay home than go out tonight. ) ●●●
197 instead ( He chose tea instead of coffee this morning. ) ●●●
198 otherwise ( Finish your work quickly; otherwise, you may miss the deadline. ) ●●●
199 somehow ( Somehow, he managed to complete the task in time. ) ●●●
200 somewhat ( She looked somewhat tired after the long journey. ) ●●●
201 wonder ( I wonder if he will attend the party. ) ●●●
202 suppose ( Suppose we leave now; will we catch the train? ) ●●●
203 imagine ( Imagine living in a house by the sea. ) ●●●
204 regard ( He is highly regarded for his expertise. ) ●●●
205 wish ( I wish I could visit Paris someday. ) ●●●
206 determine ( The results will help determine the next steps. ) ●●●
207 express ( She expressed her gratitude to everyone. ) ●●●
208 represent ( This logo represents the company’s values. ) ●●●
209 identify ( Can you identify the person in the photo? ) ●●●
210 mention ( Did I mention that the meeting was rescheduled? ) ●●●
211 solve ( We need to solve this problem before it escalates. ) ●●●
212 prove ( He couldn’t prove his argument with solid evidence. ) ●●●
213 communicate ( Good leaders communicate clearly with their teams. ) ●●●
214 respect ( Always respect the opinions of others. ) ●●●
215 prefer ( I prefer quiet evenings to loud parties. ) ●●●
216 design ( She designed the layout for the new website. ) ●●●
217 establish ( The company was established in 1995. ) ●●●
218 found ( He found his lost wallet under the couch. ) ●●●
219 publish ( She plans to publish her first novel next year. ) ●●●
220 serve ( The waiter served us delicious desserts. ) ●●●
221 supply ( The store supplies fresh fruits and vegetables daily. ) ●●●
222 apply ( You should apply for the scholarship before the deadline. ) ●●●
223 treat ( He treated his guests with kindness and hospitality. ) ●●●
224 search ( She searched everywhere for her missing ring. ) ●●●
225 prepare ( We need to prepare for the upcoming presentation. ) ●●●
226 protect ( Sunscreen helps protect your skin from harmful UV rays. ) ●●●
227 pick ( Please pick up the book from the shelf for me. ) ●●●
228 fit ( These shoes fit perfectly and are very comfortable. ) ●●●
229 gain ( He gained valuable experience from his internship. ) ●●●
230 enter ( She entered the room quietly to avoid disturbing anyone. ) ●●●
231 spread ( The news spread quickly across the town. ) ●●●
232 advance ( Technology has advanced significantly in recent years. ) ●●●
233 tend ( Children tend to ask a lot of curious questions. ) ●●●
234 depend ( Success depends on your dedication and hard work. ) ●●●
235 exist ( Evidence shows dinosaurs existed millions of years ago. ) ●●●
236 decline ( The population of the species has declined over time. ) ●●●
237 decrease ( The government aims to decrease the unemployment rate. ) ●●●
238 waste ( Don’t waste your time on unnecessary arguments. ) ●●●
239 damage ( The storm caused significant damage to the buildings. ) ●●●
240 suffer ( Many people suffer from seasonal allergies. ) ●●●
241 act ( He acted bravely to save the child from danger. ) ●●●
242 perform ( The band performed brilliantly at the concert. ) ●●●
243 species ( Tigers are an endangered species. ) ●●●
244 variety ( The store offers a variety of snacks and beverages. ) ●●●
245 degree ( She earned her degree in engineering last year. ) ●●●
246 range ( This course covers a wide range of topics. ) ●●●
247 standard ( These standards ensure the quality of the product. ) ●●●
248 medium ( Watercolor is my favorite artistic medium. ) ●●●
249 advantage ( His height gives him an advantage in basketball. ) ●●●
250 task ( Completing this task on time requires careful planning. ) ●●●
251 rest ( After a long day, he needed a good rest. ) ●●●
252 purpose ( The purpose of this event is to raise awareness. ) ●●●
253 feature ( One unique feature of this phone is its long battery life. ) ●●●
254 factor ( Time management is a key factor for success. ) ●●●
255 shape ( The table has a round shape. ) ●●●
256 image ( The advertisement uses a powerful image to convey its message. ) ●●●
257 detail ( Please share the details of the meeting with me. ) ●●●
258 character ( He is a fictional character in the novel. ) ●●●
259 function ( This button has an important function in the machine. ) ●●●
260 structure ( The building’s structure is both strong and elegant. ) ●●●
261 ground ( The ground was wet after the heavy rain. ) ●●●
262 influence ( Her words had a great influence on my decision. ) ●●●
263 disease ( The doctors are working hard to find a cure for the disease. ) ●●●
264 pain ( He felt a sharp pain in his shoulder. ) ●●●
265 medicine ( Take this medicine twice a day after meals. ) ●●●
266 death ( The news of her death shocked everyone. ) ●●●
267 fear ( He overcame his fear of public speaking. ) ●●●
268 memory ( This place brings back many fond memories. ) ●●●
269 emotion ( Her speech was filled with deep emotion. ) ●●●
270 movement ( The movement for equality is gaining momentum. ) ●●●
271 region ( This region is known for its beautiful landscapes. ) ●●●
272 climate ( The climate in this area is perfect for growing grapes. ) ●●●
273 temperature ( The temperature dropped significantly last night. ) ●●●
274 community ( The local community came together to help those in need. ) ●●●
275 population ( The population of the city has been increasing steadily. ) ●●●
276 generation ( This generation values technology and innovation. ) ●●●
277 present ( He gave her a beautiful present for her birthday. ) ●●●
278 recent ( The recent changes in the policy were well-received. ) ●●●
279 current ( What is the current status of the project? ) ●●●
280 ancient ( The museum has artifacts from ancient civilizations. ) ●●●
281 previous ( His previous job was in the marketing industry. ) ●●●
282 serious ( The team is facing a serious problem that needs to be solved. ) ●●●
283 careful ( Be careful while crossing the busy street. ) ●●●
284 responsible ( She is responsible for managing the team’s budget. ) ●●●
285 active ( He is very active and participates in many sports. ) ●●●
286 afraid ( She is afraid of heights and cannot climb tall buildings. ) ●●●
287 aware ( Are you aware of the new rules at the workplace? ) ●●●
288 patient ( Be patient; everything will work out in time. ) ●●●
289 whole ( He spent the whole day working on the project. ) ●●●
290 low ( The water level in the river is unusually low this year. ) ●●●
291 huge ( The company made a huge profit last year. ) ●●●
292 blank ( She stared at the blank page, searching for inspiration. ) ●●●
293 central ( The park is located in the central area of the city. ) ●●●
294 safe ( Wearing a helmet while biking is a safe practice. ) ●●●
295 wild ( Wild animals should be treated with caution. ) ●●●
296 eventually ( She eventually decided to pursue her dream of becoming a writer. ) ●●●
297 unfortunately ( Unfortunately, the concert was canceled due to bad weather. ) ●●●
298 seemingly ( He is seemingly calm despite the stressful situation. ) ●●●
299 afterward ( Afterward, they went out for dinner to celebrate. ) ●●●
300 altogether ( The plan failed altogether due to unforeseen issues. ) ●●●
301 assume ( I assume you’ve already completed the assignment. ) ●●●
302 guess ( Let me guess what your favorite color is—blue? ) ●●●
303 associate ( Many people associate summer with beach vacations. ) ●●●
304 desire ( His desire to succeed motivates him every day. ) ●●●
305 indicate ( The results indicate progress in the project. ) ●●●
306 respond ( He didn’t respond to my message until the next day. ) ●●●
307 reply ( She replied politely to the email. ) ●●●
308 attempt ( He made several attempts to fix the problem. ) ●●●
309 manage ( She managed to complete the task on time. ) ●●●
310 maintain ( It’s important to maintain a balanced diet and exercise routine. ) ●●●
311 unite ( The group united to work towards a common goal. ) ●●●
312 join ( Would you like to join us for dinner tonight? ) ●●●
313 attract ( The colorful flowers attract butterflies and bees. ) ●●●
314 match ( Her shoes match perfectly with the dress. ) ●●●
315 attack ( The troops launched a surprise attack on the enemy base. ) ●●●
316 seek ( He seeks advice from his mentor for career growth. ) ●●●
317 engage ( The audience engaged actively in the discussion. ) ●●●
318 succeed ( She worked hard and succeeded in achieving her dream. ) ●●●
319 marry ( They decided to marry after dating for several years. ) ●●●
320 attend ( I plan to attend the conference next week. ) ●●●
321 satisfy ( His performance satisfied the expectations of his manager. ) ●●●
322 survive ( The fish can survive in both fresh and salt water. ) ●●●
323 promote ( The organization promotes environmental sustainability. ) ●●●
324 earn ( He earned the respect of his colleagues through hard work. ) ●●●
325 feed ( They feed the stray cats every evening. ) ●●●
326 taste ( The soup tastes delicious with fresh herbs. ) ●●●
327 smell ( The kitchen smells amazing when cookies are baking. ) ●●●
328 adapt ( She adapted quickly to the new environment. ) ●●●
329 adopt ( They adopted a puppy from the animal shelter. ) ●●●
330 adjust ( You need to adjust the settings on the camera for better photos. ) ●●●
331 separate ( The teacher asked the students to separate into groups. ) ●●●
332 exchange ( They exchanged dollars for yen. ) ●●●
333 replace ( The damaged parts need to be replaced immediately. ) ●●●
334 remove ( Please remove your shoes before entering the house. ) ●●●
335 release ( The company will release its latest product next month. ) ●●●
336 disappear ( The magician made the coin disappear with a simple trick. ) ●●●
337 observe ( We observed several rare birds during our hike. ) ●●●
338 estimate ( The contractor estimated the cost of repairs at $5000. ) ●●●
339 reveal ( The artist revealed her new painting at the gallery event. ) ●●●
340 emerge ( A new leader emerged from the group discussions. ) ●●●
341 arise ( Several questions arose during the discussion. ) ●●●
342 citizen ( Every citizen has the right to vote in elections. ) ●●●
343 career ( She pursued a career in architecture. ) ●●●
344 income ( His income has increased steadily over the years. ) ●●●
345 billion ( The company’s annual revenue exceeded a billion dollars. ) ●●●
346 bill ( The waiter handed us the bill after dinner. ) ●●●
347 charge ( How much do they charge for home delivery? ) ●●●
348 item ( This store offers discounts on selected items. ) ●●●
349 scale ( The earthquake was measured at 7.0 on the Richter scale. ) ●●●
350 site ( The ancient ruins are located at this historical site. ) ●●●
351 section ( This book has a detailed section on climate change. ) ●●●
352 crop ( Farmers are expecting a good crop this season. ) ●●●
353 diet ( A balanced diet is essential for good health. ) ●●●
354 source ( The main source of their income is agriculture. ) ●●●
355 resource ( Water is a valuable natural resource. ) ●●●
356 moment ( Please wait a moment while I check the information. ) ●●●
357 decade ( The city has changed a lot in the last decade. ) ●●●
358 stage ( She is at the final stage of her research. ) ●●●
359 aspect ( Every aspect of the project must be reviewed carefully. ) ●●●
360 sort ( What sort of movies do you enjoy watching? ) ●●●
361 instance ( For instance, teamwork is key to success. ) ●●●
362 link ( There is a direct link between exercise and mental health. ) ●●●
363 contrast ( In contrast to his calm demeanor, she seemed very nervous. ) ●●●
364 access ( Students have access to the university library 24/7. ) ●●●
365 device ( This new device helps monitor heart rates accurately. ) ●●●
366 survey ( The survey revealed customer satisfaction was high. ) ●●●
367 technique ( He used a unique technique to solve the puzzle. ) ●●●
368 content ( The content of the book was both educational and engaging. ) ●●●
369 surface ( The surface of the lake was smooth and reflective. ) ●●●
370 concept ( The concept of time travel fascinates many scientists. ) ●●●
371 difficulty ( He had difficulty solving the math problem. ) ●●●
372 trouble ( She is in trouble for missing the deadline. ) ●●●
373 criminal ( The criminal was arrested by the police last night. ) ●●●
374 attitude ( Her positive attitude inspired everyone around her. ) ●●●
375 habit ( It’s important to develop good study habits. ) ●●●
376 whatever ( Do whatever you think is best for the situation. ) ●●●
377 urban ( Urban areas are often bustling with activity. ) ●●●
378 rural ( Life in rural villages is peaceful but challenging. ) ●●●
379 local ( We visited a local market to buy fresh produce. ) ●●●
380 native ( She is a native speaker of French. ) ●●●
381 smart ( He is smart enough to solve even the hardest puzzles. ) ●●●
382 intelligent ( Dolphins are considered highly intelligent animals. ) ●●●
383 intellectual ( The debate was filled with intellectual arguments. ) ●●●
384 potential ( This new technology has great potential for growth. ) ●●●
385 moral ( She stood firm on her moral principles. ) ●●●
386 private ( He prefers to keep his personal life private. ) ●●●
387 equal ( Every individual deserves equal opportunities. ) ●●●
388 fair ( The team agreed on a fair solution to the issue. ) ●●●
389 entire ( She spent the entire weekend finishing the project. ) ●●●
390 initial ( His initial reaction to the news was one of surprise. ) ●●●
391 essential ( Good communication is essential for team success. ) ●●●
392 significant ( This study has produced significant results. ) ●●●
393 terrible ( The weather was terrible during their vacation. ) ●●●
394 digital ( She prefers reading digital books on her tablet. ) ●●●
395 direct ( He gave a direct answer to the question. ) ●●●
396 nearly ( The store is nearly empty after the big sale. ) ●●●
397 merely ( It’s merely a suggestion, not a rule. ) ●●●
398 seldom ( He seldom takes time off from work. ) ●●●
399 lately ( Lately, she has been feeling more energetic. ) ●●●
400 apart ( They were sitting apart from each other at the meeting. ) ●●●
401 trust ( You can trust him to handle the situation responsibly. ) ●●●
402 promise ( I promise to call you as soon as I arrive. ) ●●●
403 predict ( Scientists predict that the weather will improve tomorrow. ) ●●●
404 reflect ( The mirror reflects an image of the room. ) ●●●
405 recall ( I can’t recall where I left my glasses. ) ●●●
406 rely ( He relies on his family for emotional support. ) ●●●
407 commit ( She committed to finishing the project on time. ) ●●●
408 appreciate ( I really appreciate your help with this matter. ) ●●●
409 praise ( The teacher praised her students for their hard work. ) ●●●
410 doubt ( I doubt he will arrive on time. ) ●●●
411 complain ( He complained about the poor service at the restaurant. ) ●●●
412 ignore ( She decided to ignore the negative comments. ) ●●●
413 warn ( The doctor warned him about the dangers of smoking. ) ●●●
414 gather ( The children gathered around the storyteller. ) ●●●
415 acquire ( She acquired a new language skill through online courses. ) ●●●
416 examine ( The mechanic examined the engine for any issues. ) ●●●
417 score ( He scored the winning goal in the final match. ) ●●●
418 judge ( Don’t judge a book by its cover. ) ●●●
419 select ( Please select the options that best suit your needs. ) ●●●
420 divide ( The cake was divided equally among the guests. ) ●●●
421 distinguish ( It’s hard to distinguish between the twins. ) ●●●
422 graduate ( She graduated from university with honors. ) ●●●
423 shift ( There has been a shift in public opinion about the issue. ) ●●●
424 hide ( The cat hid under the sofa during the thunderstorm. ) ●●●
425 mix ( Mix the ingredients thoroughly before baking. ) ●●●
426 fix ( He fixed the broken chair with glue and screws. ) ●●●
427 display ( The art gallery displayed a collection of modern paintings. ) ●●●
428 define ( Can you define the term “sustainability” for me? ) ●●●
429 invent ( Alexander Graham Bell invented the telephone. ) ●●●
430 vary ( Opinions on this topic vary greatly among experts. ) ●●●
431 expand ( The company plans to expand its operations overseas. ) ●●●
432 evolve ( Languages evolve over time as cultures change. ) ●●●
433 confuse ( The instructions confused some of the participants. ) ●●●
434 consume ( He consumes a lot of energy drinks during work. ) ●●●
435 compete ( Athletes from around the world compete in the Olympics. ) ●●●
436 repeat ( Please repeat the question for clarification. ) ●●●
437 repair ( The plumber repaired the leaking faucet quickly. ) ●●●
438 remind ( Can you remind me to send the email later? ) ●●●
439 refuse ( She refused to accept the gift out of modesty. ) ●●●
440 reject ( The board rejected the proposal after much discussion. ) ●●●
441 deny ( He denied all the accusations made against him. ) ●●●
442 destroy ( The fire destroyed several houses in the village. ) ●●●
443 audience ( The audience clapped enthusiastically after the performance. ) ●●●
444 race ( He won first place in the bike race. ) ●●●
445 conflict ( The story highlights the conflict between tradition and progress. ) ●●●
446 debate ( The candidates engaged in a lively debate on environmental policies. ) ●●●
447 struggle ( She struggled to carry the heavy bag up the stairs. ) ●●●
448 strategy ( A good strategy is essential to win the game. ) ●●●
449 progress ( She has made significant progress in her studies. ) ●●●
450 principle ( He follows the principle of honesty in all his dealings. ) ●●●
451 element ( Water is a crucial element for all living beings. ) ●●●
452 origin ( The origin of this tradition dates back hundreds of years. ) ●●●
453 birth ( The birth of her child was a joyful occasion. ) ●●●
454 ancestor ( He learned about his ancestors through family records. ) ●●●
455 cell ( The human body is made up of millions of cells. ) ●●●
456 gene ( Scientists are studying genes to understand hereditary diseases. ) ●●●
457 scene ( The movie opens with a dramatic scene of a thunderstorm. ) ●●●
458 trend ( Eco-friendly products are becoming a popular trend. ) ●●●
459 traffic ( The heavy traffic delayed their arrival. ) ●●●
460 track ( He keeps track of his expenses using a mobile app. ) ●●●
461 series ( The author released a new book in her popular series. ) ●●●
462 context ( Understanding the context is crucial to interpreting this text. ) ●●●
463 background ( She shared her professional background during the interview. ) ●●●
464 basis ( The basis of their argument was flawed. ) ●●●
465 status ( What is the current status of the application? ) ●●●
466 volunteer ( She volunteers at the local animal shelter every weekend. ) ●●●
467 staff ( The staff at the hotel were very helpful and courteous. ) ●●●
468 duty ( It is our duty to protect the environment. ) ●●●
469 labor ( The labor involved in constructing the bridge was immense. ) ●●●
470 reward ( Hard work brings its own rewards. ) ●●●
471 aim ( The aim of this project is to reduce energy consumption. ) ●●●
472 fun ( We had a lot of fun at the amusement park yesterday. ) ●●●
473 crowd ( A large crowd gathered to watch the street performance. ) ●●●
474 revolution ( The industrial revolution changed the way people lived and worked. ) ●●●
475 poverty ( Many organizations work to combat poverty around the world. ) ●●●
476 consequence ( Every action has its consequences, whether good or bad. ) ●●●
477 sequence ( The sequence of events in the novel was intriguing. ) ●●●
478 complex ( The situation became more complex as new information emerged. ) ●●●
479 complicated ( The instructions for assembling the furniture were complicated. ) ●●●
480 false ( The information turned out to be false. ) ●●●
481 alternative ( We need to find an alternative route to avoid the traffic. ) ●●●
482 extreme ( The athletes pushed themselves to the extreme to win the race. ) ●●●
483 ideal ( This location is ideal for a family picnic. ) ●●●
484 primary ( Her primary goal is to finish her education. ) ●●●
485 worth ( This old painting is worth a lot of money. ) ●●●
486 obvious ( It was obvious that he was nervous about the presentation. ) ●●●
487 legal ( The company ensures that all its operations are legal. ) ●●●
488 commercial ( The building is used for both residential and commercial purposes. ) ●●●
489 artificial ( Artificial intelligence is transforming various industries. ) ●●●
490 chemical ( This experiment involves mixing different chemicals. ) ●●●
491 biological ( Biological studies focus on living organisms and their processes. ) ●●●
492 former ( He met a former classmate at the reunion. ) ●●●
493 mobile ( Mobile phones have become an essential part of daily life. ) ●●●
494 straight ( Go straight ahead, and you’ll find the museum on the right. ) ●●●
495 regular ( Regular exercise is key to maintaining good health. ) ●●●
496 independent ( She became independent after moving out of her parents’ house. ) ●●●
497 overseas ( He plans to study overseas after graduating. ) ●●●
498 unlike ( Unlike her brother, she prefers quiet places. ) ●●●
499 via ( We traveled to Kyoto via the Shinkansen. ) ●●●
500 whereas ( He likes coffee, whereas she prefers tea. ) ●●●
501 perceive ( He perceived a slight change in her tone of voice. ) ●●●
502 fascinate ( The intricate patterns of the painting fascinated the visitors. ) ●●●
503 bore ( His repetitive stories began to bore the audience. ) ●●●
504 disappoint ( I didn’t want to disappoint my parents by failing the test. ) ●●●
505 imply ( His comment seemed to imply that he didn’t trust her. ) ●●●
506 recommend ( I highly recommend trying the new Italian restaurant downtown. ) ●●●
507 demonstrate ( The teacher demonstrated how to solve the math problem on the board. ) ●●●
508 conclude ( After reviewing the evidence, they concluded that the experiment was a success. ) ●●●
509 announce ( The company announced the launch of its new product yesterday. ) ●●●
510 appeal ( The charity appealed to the public for donations. ) ●●●
511 address ( He addressed the audience confidently during the presentation. ) ●●●
512 advertise ( They advertised the event on social media to attract more participants. ) ●●●
513 invite ( She invited her friends over for a dinner party. ) ●●●
514 afford ( I can’t afford to buy a new car right now. ) ●●●
515 purchase ( She purchased a new laptop for her online classes. ) ●●●
516 participate ( Many students participated in the science fair. ) ●●●
517 belong ( These books belong to the school library. ) ●●●
518 conduct ( The professor conducted an interesting experiment in class. ) ●●●
519 behave ( Please behave politely when meeting new people. ) ●●●
520 operate ( The factory operates 24 hours a day to meet the high demand. ) ●●●
521 organize ( The committee organized a charity event for the community. ) ●●●
522 host ( She hosted a wonderful dinner for her colleagues. ) ●●●
523 combine ( You should combine your efforts to achieve the best results. ) ●●●
524 deliver ( The package was delivered to my house this morning. ) ●●●
525 locate ( The map helped us locate the nearest gas station. ) ●●●
526 encounter ( During the hike, we encountered a group of deer in the forest. ) ●●●
527 surround ( Beautiful mountains surround the peaceful village. ) ●●●
528 explore ( The children love to explore the woods near their home. ) ●●●
529 stick ( He used tape to stick the poster to the wall. ) ●●●
530 strike ( The workers went on strike to demand better working conditions. ) ●●●
531 hurt ( She hurt her ankle while running on the track. ) ●●●
532 bite ( The dog bit into the juicy piece of meat eagerly. ) ●●●
533 tear ( She accidentally tore the paper while trying to remove it from the notebook. ) ●●●
534 aid ( The volunteers provided aid to the victims of the flood. ) ●●●
535 press ( He pressed the button to start the elevator. ) ●●●
536 burn ( Be careful not to burn yourself while cooking. ) ●●●
537 flow ( The river flows gently through the lush green valley. ) ●●●
538 preserve ( It’s important to preserve historical landmarks for future generations. ) ●●●
539 borrow ( Can I borrow your notes to study for the exam? ) ●●●
540 steal ( Someone stole my wallet while I was shopping. ) ●●●
541 escape ( The prisoners tried to escape but were caught by the guards. ) ●●●
542 neighbor ( Our neighbor helped us carry the heavy furniture inside. ) ●●●
543 household ( This household recycles all its waste to help the environment. ) ●●●
544 resident ( The residents of the building were evacuated during the fire drill. ) ●●●
545 vehicle ( His vehicle broke down on the way to work. ) ●●●
546 wheel ( The car’s wheel got stuck in the mud. ) ●●●
547 delay ( The flight was delayed due to bad weather conditions. ) ●●●
548 fuel ( The storm caused a power outage, leaving the area without electricity. ) ●●●
549 pollution ( Air pollution is a major concern in urban areas due to increased vehicle emissions. ) ●●●
550 atmosphere ( The cozy atmosphere of the café made it a perfect spot for reading. ) ●●●
551 electricity ( The invention of electricity revolutionized the way we live and work. ) ●●●
552 cancer ( Early detection of cancer can significantly improve treatment outcomes. ) ●●●
553 plague ( The plague spread rapidly through the city in the 14th century. ) ●●●
554 threat ( Climate change poses a significant threat to coastal regions. ) ●●●
555 flood ( The flood damaged many homes and displaced thousands of residents. ) ●●●
556 earthquake ( The earthquake shook the city and caused widespread destruction. ) ●●●
557 disaster ( The disaster relief team arrived quickly to assist the survivors. ) ●●●
558 crisis ( The financial crisis affected economies around the world. ) ●●●
559 victim ( The victims of the fire received support from the community. ) ●●●
560 wealth ( He used his wealth to fund educational programs for underprivileged children. ) ●●●
561 fund ( They set up a fund to support scientific research. ) ●●●
562 capital ( Tokyo serves as the capital city of Japan. ) ●●●
563 profit ( The company made a substantial profit from its new product. ) ●●●
564 talent ( She has a natural talent for playing the piano. ) ●●●
565 capacity ( The hall has a seating capacity of 500 people. ) ●●●
566 scholar ( He is a scholar specializing in ancient languages. ) ●●●
567 tradition ( It’s a tradition to visit family during the New Year in many cultures. ) ●●●
568 literature ( She majored in English literature at university. ) ●●●
569 lecture ( The professor’s lecture on quantum physics was both informative and engaging. ) ●●●
570 manner ( His polite manner left a good impression on everyone. ) ●●●
571 symbol ( The dove is a universal symbol of peace. ) ●●●
572 analysis ( The analysis of the data revealed some interesting trends. ) ●●●
573 version ( This is the updated version of the software with new features. ) ●●●
574 perspective ( The book offers a unique perspective on historical events. ) ●●●
575 vision ( His vision for the future includes renewable energy for all. ) ●●●
576 sight ( The sight of the sunset over the ocean took her breath away. ) ●●●
577 insight ( His insight into the issue helped us find a solution. ) ●●●
578 bilingual ( Being bilingual is an advantage in many international careers. ) ●●●
579 capable ( She is capable of handling multiple projects at once. ) ●●●
580 willing ( He is willing to volunteer for the community event this weekend. ) ●●●
581 eager ( The children were eager to start their summer vacation. ) ●●●
582 amazing ( The view from the mountaintop was absolutely amazing. ) ●●●
583 calm ( She remained calm under pressure and handled the situation well. ) ●●●
584 quiet ( The library was so quiet that you could hear a pin drop. ) ●●●
585 senior ( As a senior member of the team, he mentored the younger staff. ) ●●●
586 elderly ( The program offers assistance to elderly individuals living alone. ) ●●●
587 firm ( She gave a firm handshake to show her confidence. ) ●●●
588 severe ( The severe weather conditions forced schools to close. ) ●●●
589 tough ( The tough leather jacket lasted for many years. ) ●●●
590 rapid ( The company experienced rapid growth in its early years. ) ●●●
591 immediate ( Immediate action is necessary to address the urgent situation. ) ●●●
592 vast ( The vast desert stretched out as far as the eye could see. ) ●●●
593 enormous ( The elephant is an enormous animal compared to others. ) ●●●
594 broad ( The museum’s collection covers a broad range of art styles. ) ●●●
595 narrow ( The narrow street made it difficult for cars to pass. ) ●●●
596 tiny ( The baby held a tiny flower in her hand. ) ●●●
597 efficient ( The new system is highly efficient and saves a lot of time. ) ●●●
598 constant ( The constant noise from the construction site was annoying. ) ●●●
599 nearby ( They went to a nearby café for a quick coffee break. ) ●●●
600 distant ( The distant mountains looked beautiful in the early morning light. ) ●●●
601 insist ( She insists on paying for dinner every time. ) ●●●
602 intend ( He intends to finish the project by next week. ) ●●●
603 inspire ( Her speech inspired me to follow my dreams. ) ●●●
604 emphasize ( The teacher emphasized the importance of teamwork. ) ●●●
605 propose ( I propose we start the meeting at 10 a.m. ) ●●●
606 persuade ( She persuaded her parents to let her travel abroad. ) ●●●
607 convince ( He convinced me to try the new restaurant. ) ●●●
608 admit ( She admitted that she had made a mistake. ) ●●●
609 favor ( I favor going to the park over staying indoors. ) ●●●
610 excuse ( Please excuse my late arrival; the train was delayed. ) ●●●
611 interpret ( Can you interpret the meaning of this symbol? ) ●●●
612 translate ( He translated the letter into English. ) ●●●
613 concentrate ( It’s hard to concentrate with all this noise. ) ●●●
614 criticize ( The reviewer criticized the movie for its weak plot. ) ●●●
615 blame ( Don’t blame others for your own mistakes. ) ●●●
616 oppose ( Many people oppose the construction of the new factory. ) ●●●
617 inform ( Please inform me if there are any changes to the schedule. ) ●●●
618 grant ( The committee granted her permission to present her findings. ) ●●●
619 obtain ( She obtained the necessary documents for her application. ) ●●●
620 transform ( The old warehouse was transformed into a modern art gallery. ) ●●●
621 alter ( You can alter the size of the text in the settings. ) ●●●
622 arrange ( He arranged the chairs in a circle for the group discussion. ) ●●●
623 interact ( The kids interacted well with each other during the activity. ) ●●●
624 handle ( She handled the situation with great professionalism. ) ●●●
625 extend ( They extended their trip by two days to explore more. ) ●●●
626 settle ( The dispute was settled after long negotiations. ) ●●●
627 contribute ( Everyone contributed ideas to improve the project. ) ●●●
628 construct ( The company constructed a new bridge over the river. ) ●●●
629 consist ( The dish consists of rice, chicken, and vegetables. ) ●●●
630 suit ( This jacket suits you perfectly; the color matches your eyes. ) ●●●
631 tie ( He tied the shoelaces tightly before running. ) ●●●
632 differ ( Their opinions differ on how to solve the issue. ) ●●●
633 hate ( I hate getting stuck in traffic during rush hour. ) ●●●
634 dislike ( She dislikes spicy food and always avoids it. ) ●●●
635 disagree ( I disagree with his decision to cancel the event. ) ●●●
636 regret ( I regret not taking the opportunity to study abroad. ) ●●●
637 employ ( The company employs over 500 people worldwide. ) ●●●
638 hire ( They hired a professional photographer for the event. ) ●●●
639 absorb ( Plants absorb sunlight to produce energy through photosynthesis. ) ●●●
640 expose ( The documentary exposed the truth about illegal practices. ) ●●●
641 breathe ( She breathed deeply to calm herself before the speech. ) ●●●
642 root ( The tree’s roots spread deep into the soil. ) ●●●
643 immigration ( The government introduced new immigration policies. ) ●●●
644 tribe ( The tribe has preserved its traditions for centuries. ) ●●●
645 landscape ( The landscape was breathtaking with its rolling hills and clear skies. ) ●●●
646 agriculture ( Agriculture is the backbone of this country’s economy. ) ●●●
647 soil ( The soil in this region is perfect for growing crops. ) ●●●
648 mine ( They explored the abandoned mine for hidden treasures. ) ●●●
649 mass ( The mass of the earth attracts objects towards its surface. ) ●●●
650 quarter ( The team completed the project in the first quarter of the year. ) ●●●
651 era ( The invention of the internet marked the beginning of a new era. ) ●●●
652 circumstance ( Under these circumstances, we have no choice but to postpone the event. ) ●●●
653 phenomenon ( The northern lights are a fascinating natural phenomenon. ) ●●●
654 custom ( It’s a custom in Japan to bow when greeting someone. ) ●●●
655 religion ( Religion plays a significant role in many people’s lives. ) ●●●
656 civilization ( Ancient civilizations built impressive structures like pyramids. ) ●●●
657 universe ( The universe is constantly expanding, according to scientists. ) ●●●
658 diversity ( Cultural diversity enriches our lives and fosters understanding. ) ●●●
659 trait ( Kindness is a trait that everyone admires. ) ●●●
660 review ( She wrote a detailed review of the new restaurant. ) ●●●
661 occasion ( Her wedding was a joyful occasion celebrated by friends and family. ) ●●●
662 campaign ( The charity campaign successfully raised funds for the hospital. ) ●●●
663 board ( The board of directors decided to implement new policies. ) ●●●
664 facility ( The sports facility includes a swimming pool and tennis courts. ) ●●●
665 court ( The court ruled in favor of the defendant. ) ●●●
666 trial ( The new drug is undergoing clinical trials to ensure its safety. ) ●●●
667 laboratory ( Scientists conducted experiments in the laboratory to test their theories. ) ●●●
668 instrument ( The guitar is his favorite musical instrument. ) ●●●
669 instruction ( Follow the instructions carefully to assemble the furniture. ) ●●●
670 document ( She signed the document to finalize the agreement. ) ●●●
671 target ( The company set a target of increasing sales by 20%. ) ●●●
672 outcome ( The outcome of the experiment exceeded expectations. ) ●●●
673 muscle ( Regular exercise helps strengthen your muscles. ) ●●●
674 wage ( The workers demanded higher wages for their efforts. ) ●●●
675 gender ( Gender equality is an important issue in modern society. ) ●●●
676 confidence ( She spoke with confidence during the presentation. ) ●●●
677 credit ( He received credit for his contribution to the team’s success. ) ●●●
678 conscious ( She is conscious of the impact her actions have on the environment. ) ●●●
679 anxious ( He felt anxious before the big exam. ) ●●●
680 asleep ( The baby fell asleep shortly after drinking milk. ) ●●●
681 alive ( The flowers made her feel alive and joyful. ) ●●●
682 alike ( They look alike but have very different personalities. ) ●●●
683 excellent ( His excellent performance earned him a promotion. ) ●●●
684 odd ( She had an odd feeling that she was being watched. ) ●●●
685 sensitive ( He is very sensitive to criticism and takes it personally. ) ●●●
686 sensible ( Choosing a sensible solution is often the best approach. ) ●●●
687 violent ( The violent storm caused widespread damage to the region. ) ●●●
688 military ( He served in the military for five years. ) ●●●
689 nuclear ( The nuclear power plant provides energy to thousands of homes. ) ●●●
690 contemporary ( This contemporary art exhibition showcases innovative works. ) ●●●
691 elementary ( She teaches elementary school students basic math and science. ) ●●●
692 annual ( The annual festival attracts thousands of visitors. ) ●●●
693 chief ( The chief engineer oversaw the entire construction project. ) ●●●
694 actual ( The actual cost of the project was higher than estimated. ) ●●●
695 virtual ( Virtual reality offers immersive gaming experiences. ) ●●●
696 numerous ( He made numerous attempts to solve the challenging puzzle. ) ●●●
697 multiple ( The system experienced multiple failures during the test. ) ●●●
698 widespread ( The news of the discovery gained widespread attention. ) ●●●
699 sufficient ( There is sufficient evidence to support the claim. ) ●●●
700 empty ( The room was empty except for a single chair. ) ●●●
701 confirm ( Could you confirm the date of the meeting? ) ●●●
702 illustrate ( This graph illustrates the growth in sales over the past year. ) ●●●
703 spell ( Can you spell your name for me, please? ) ●●●
704 bother ( I don’t want to bother you, but could you help me with this? ) ●●●
705 annoy ( His constant interruptions annoyed everyone in the room. ) ●●●
706 disturb ( Please do not disturb the wildlife in this area. ) ●●●
707 discourage ( Negative feedback can discourage people from trying again. ) ●●●
708 embarrass ( She felt embarrassed when she forgot her lines on stage. ) ●●●
709 frighten ( The loud noise frightened the baby. ) ●●●
710 puzzle ( The unexpected result puzzled the researchers. ) ●●●
711 upset ( She was upset when she lost her favorite book. ) ●●●
712 stimulate ( Bright colors can stimulate creativity and imagination. ) ●●●
713 beat ( His team beat their rivals in the final match. ) ●●●
714 blow ( A strong wind blew the papers off the table. ) ●●●
715 injure ( He injured his leg while playing soccer. ) ●●●
716 cure ( Scientists are working to find a cure for the disease. ) ●●●
717 recover ( She recovered quickly after the surgery. ) ●●●
718 overcome ( He overcame his fear of speaking in public. ) ●●●
719 quit ( She decided to quit her job to pursue her passion. ) ●●●
720 transfer ( He was transferred to another branch of the company. ) ●●●
721 transport ( This truck is used to transport goods across the city. ) ●●●
722 export ( Japan exports high-quality cars to many countries. ) ●●●
723 import ( The country imports a large portion of its food. ) ●●●
724 invest ( She invested her savings in the stock market. ) ●●●
725 investigate ( The police are investigating the cause of the fire. ) ●●●
726 manufacture ( This factory manufactures electronic devices. ) ●●●
727 react ( He reacted calmly to the unexpected news. ) ●●●
728 award ( She received an award for her outstanding achievements. ) ●●●
729 ban ( Smoking is banned in most public places. ) ●●●
730 prohibit ( The school prohibits the use of cell phones during class. ) ●●●
731 forbid ( Her parents forbid her from staying out late at night. ) ●●●
732 abandon ( The villagers abandoned their homes due to the flood. ) ●●●
733 freeze ( The water in the lake froze during the winter. ) ●●●
734 lift ( Could you help me lift this heavy box? ) ●●●
735 hang ( She hung her coat on the hook by the door. ) ●●●
736 shake ( He shook hands with his new business partner. ) ●●●
737 stretch ( She stretched her arms after sitting for a long time. ) ●●●
738 lay ( He laid the book on the table and started reading. ) ●●●
739 stare ( He stared at the painting, admiring its beauty. ) ●●●
740 gaze ( They gazed at the stars on a clear night. ) ●●●
741 capture ( The photographer captured a perfect moment during the event. ) ●●●
742 breed ( Farmers breed animals to improve their livestock. ) ●●●
743 mammal ( Whales are the largest mammals in the ocean. ) ●●●
744 ape ( Apes share many similarities with humans in behavior. ) ●●●
745 insect ( The garden is full of beautiful flowers and buzzing insects. ) ●●●
746 infant ( The infant slept peacefully in her mother’s arms. ) ●●●
747 organ ( The heart is an essential organ in the human body. ) ●●●
748 web ( The spider spun a delicate web in the corner. ) ●●●
749 fossil ( Paleontologists discovered a dinosaur fossil in the desert. ) ●●●
750 battle ( The soldiers fought bravely in the historic battle. ) ●●●
751 enemy ( The soldiers were prepared to face their enemy in battle. ) ●●●
752 weapon ( Advanced weapons were used in the military exercise. ) ●●●
753 arm ( She raised her arm to signal for help. ) ●●●
754 army ( The army protected the country during the crisis. ) ●●●
755 navy ( The navy launched a rescue operation in the sea. ) ●●●
756 border ( The town is located near the border between two countries. ) ●●●
757 barrier ( Language barriers can make communication difficult. ) ●●●
758 philosophy ( His philosophy emphasizes the value of simplicity in life. ) ●●●
759 psychology ( Psychology helps us understand human behavior and emotions. ) ●●●
760 alarm ( The alarm woke him up early in the morning. ) ●●●
761 harm ( Excessive sun exposure can harm your skin. ) ●●●
762 depression ( Regular exercise can help alleviate symptoms of depression. ) ●●●
763 disadvantage ( One disadvantage of living in the countryside is limited access to public transportation. ) ●●●
764 shortage ( There was a shortage of water due to the drought. ) ●●●
765 stock ( The store is running low on stock during the holiday season. ) ●●●
766 loan ( He applied for a loan to buy his first car. ) ●●●
767 budget ( The government introduced a budget plan for the next fiscal year. ) ●●●
768 innovation ( Technological innovation drives progress in various industries. ) ●●●
769 union ( The workers’ union negotiated better salaries for its members. ) ●●●
770 unit ( The new unit of measurement will be implemented nationwide. ) ●●●
771 material ( This material is ideal for building sturdy furniture. ) ●●●
772 substance ( Scientists are studying the substance’s properties in the lab. ) ●●●
773 stuff ( He packed his stuff and moved to a new apartment. ) ●●●
774 proportion ( The proportion of women in the workforce has increased. ) ●●●
775 edge ( She stood at the edge of the cliff and admired the view. ) ●●●
776 code ( The programmer wrote a complex code for the new software. ) ●●●
777 mystery ( The disappearance of the ship remains a mystery. ) ●●●
778 curious ( I am curious to know more about the latest developments. ) ●●●
779 strict ( My teacher is strict about turning in assignments on time. ) ●●●
780 frank ( To be frank, I think the presentation could have been better. ) ●●●
781 polite ( He is always polite when speaking to his elders. ) ●●●
782 aggressive ( His aggressive approach to sales led to an increase in profits. ) ●●●
783 accurate ( The weather forecast was accurate for the entire week. ) ●●●
784 exact ( Can you tell me the exact time of the meeting? ) ●●●
785 proper ( Proper care is essential for maintaining good health. ) ●●●
786 blief ( She gave a brief summary of her research findings. ) ●●●
787 extraordinary ( The view from the mountaintop was extraordinary. ) ●●●
788 flexible ( A flexible schedule allows employees to balance work and life. ) ●●●
789 pleasant ( We had a pleasant conversation during the train ride. ) ●●●
790 comfortable ( This chair is incredibly comfortable to sit in. ) ●●●
791 stable ( The ladder must be stable before you climb it. ) ●●●
792 thick ( The forest was so thick that little sunlight reached the ground. ) ●●●
793 thin ( She sliced the bread into thin pieces for sandwiches. ) ●●●
794 abstract ( The artist’s abstract paintings were difficult to interpret. ) ●●●
795 concrete ( He provided concrete evidence to support his claims. ) ●●●
796 absolute ( Absolute honesty is critical in building trust. ) ●●●
797 prime ( The prime minister addressed the nation in a televised speech. ) ●●●
798 vital ( Drinking water is vital for survival. ) ●●●
799 contrary ( Contrary to popular belief, he enjoys solitude. ) ●●●
800 regardless ( Regardless of the challenges, she remained determined to succeed. ) ●●●
801 permit ( The school does not permit the use of mobile phones during classes. ) ●●●
802 suspect ( I suspect that the train will be delayed due to the weather. ) ●●●
803 pursue ( She decided to pursue a career in engineering. ) ●●●
804 pretend ( The children pretended to be astronauts during their playtime. ) ●●●
805 calculate ( He calculated the total cost of the trip, including flights and hotels. ) ●●●
806 guarantee ( This product comes with a one-year guarantee. ) ●●●
807 acknowledge ( She acknowledged the hard work of her team during the meeting. ) ●●●
808 impress ( His speech impressed everyone at the conference. ) ●●●
809 urge ( The doctor urged him to exercise more regularly. ) ●●●
810 convey ( The letter conveyed her deep gratitude to the team. ) ●●●
811 celebrate ( We celebrated her graduation with a big party. ) ●●●
812 admire ( I admire her dedication to helping those in need. ) ●●●
813 devote ( He devoted his life to advancing medical research. ) ●●●
814 dominate ( The company dominates the market with its innovative products. ) ●●●
815 eliminate ( Regular exercise can help eliminate stress. ) ●●●
816 restrict ( The new policy restricts the use of plastic bags in the city. ) ●●●
817 isolate ( The patient was isolated to prevent the spread of the disease. ) ●●●
818 endanger ( Deforestation endangers many wildlife species. ) ●●●
819 secure ( They secured funding for their new project. ) ●●●
820 reserve ( We reserved a table at the restaurant for dinner. ) ●●●
821 possess ( He possesses excellent leadership skills. ) ●●●
822 launch ( The company launched its new smartphone last week. ) ●●●
823 detect ( The sensors can detect even the slightest movement. ) ●●●
824 reverse ( He reversed his car into the parking space. ) ●●●
825 convert ( You can convert this file into a PDF format. ) ●●●
826 hurry ( Hurry up, or we’ll miss the train! ) ●●●
827 rush ( The ambulance rushed to the scene of the accident. ) ●●●
828 roll ( The ball rolled down the hill and into the stream. ) ●●●
829 crash ( The car crashed into the wall, but fortunately, no one was injured. ) ●●●
830 bury ( They buried the time capsule in the backyard for future generations. ) ●●●
831 dig ( The workers dug a hole to plant the tree. ) ●●●
832 attach ( Please attach your resume to the application form. ) ●●●
833 melt ( The chocolate melted in the hot sun. ) ●●●
834 accompany ( She accompanied her friend to the doctor’s appointment. ) ●●●
835 assist ( The librarian assisted me in finding the right books for my research. ) ●●●
836 cope ( She managed to cope with the stress of her new job. ) ●●●
837 lend ( Can you lend me your notebook for the afternoon? ) ●●●
838 rent ( They rented an apartment near the city center. ) ●●●
839 owe ( I owe you an apology for the misunderstanding. ) ●●●
840 apologize ( He apologized sincerely for his mistake. ) ●●●
841 forgive ( She forgave him for forgetting their anniversary. ) ●●●
842 tongue ( He bit his tongue accidentally while eating. ) ●●●
843 dialect ( This region is known for its unique dialect. ) ●●●
844 accent ( Her British accent is charming and easy to understand. ) ●●●
845 colony ( The ants built a large colony under the tree. ) ●●●
846 grain ( The farmer harvested a good crop of grain this year. ) ●●●
847 harvest ( They celebrate the harvest with a festival every autumn. ) ●●●
848 ingredient ( Fresh ingredients are key to delicious cooking. ) ●●●
849 portion ( He ate only a small portion of the cake. ) ●●●
850 hunger ( Hunger is a pressing issue in many parts of the world. ) ●●●
851 obesity ( People suffering from obesity often lack exercise. ) ●●●
852 burden ( The financial burden was too much for the small family to handle. ) ●●●
853 emergency ( In case of an emergency, dial the local helpline immediately. ) ●●●
854 debt ( He is working hard to pay off his student loan debt. ) ●●●
855 contract ( She signed a contract to join the company for two years. ) ●●●
856 client ( The client was satisfied with the service provided by the firm. ) ●●●
857 therapy ( Therapy can help people recover from emotional trauma. ) ●●●
858 physician ( The physician prescribed medicine to treat her condition. ) ●●●
859 democracy ( Democracy allows citizens to have a voice in their government. ) ●●●
860 election ( The election results will be announced later today. ) ●●●
861 vote ( Every citizen has the right to vote in the election. ) ●●●
862 candidate ( Each candidate presented their plans during the debate. ) ●●●
863 minister ( The prime minister addressed the nation regarding the recent developments. ) ●●●
864 conference ( The international conference focused on climate change. ) ●●●
865 ceremony ( The graduation ceremony was a memorable event for everyone. ) ●●●
866 institution ( This institution is known for its excellent academic programs. ) ●●●
867 corporation ( The corporation expanded its business operations globally. ) ●●●
868 cooperation ( Cooperation among team members is essential for success. ) ●●●
869 authority ( The local authority issued new regulations for construction projects. ) ●●●
870 theme ( The theme of the movie revolves around friendship and courage. ) ●●●
871 notion ( The notion that hard work leads to success is widely accepted. ) ●●●
872 hypothesis ( The scientist tested her hypothesis through multiple experiments. ) ●●●
873 discipline ( Discipline is the key to achieving long-term goals. ) ●●●
874 route ( We took a scenic route to enjoy the countryside views. ) ●●●
875 routine ( Having a daily routine can help manage stress effectively. ) ●●●
876 destination ( Our destination for this trip is a small island off the coast. ) ●●●
877 domestic ( Domestic flights are usually cheaper than international ones. ) ●●●
878 ethnic ( The festival celebrated ethnic diversity and cultural heritage. ) ●●●
879 alien ( In science fiction, alien species often have unique traits. ) ●●●
880 visible ( The mountain was barely visible through the thick fog. ) ●●●
881 verbal ( Verbal communication is essential in expressing ideas clearly. ) ●●●
882 fundamental ( Freedom of speech is a fundamental right. ) ●●●
883 conventional ( The conventional methods of farming are being replaced by modern technology. ) ●●●
884 relevant ( Her suggestions were highly relevant to the topic being discussed. ) ●●●
885 rational ( His rational approach helped resolve the complex issue. ) ●●●
886 precise ( Please give me precise instructions on how to operate this device. ) ●●●
887 principal ( The principal aim of the project is to promote renewable energy. ) ●●●
888 crucial ( It’s crucial to stay informed about the latest developments in the field. ) ●●●
889 permanent ( The artist created a permanent installation for the museum. ) ●●●
890 intense ( The competition was intense, and everyone gave their best effort. ) ●●●
891 equivalent ( This computer’s performance is equivalent to that of a high-end model. ) ●●●
892 frequent ( She made frequent visits to the library to study. ) ●●●
893 sudden ( A sudden change in weather caught everyone off guard. ) ●●●
894 temporary ( The company offered him a temporary position for six months. ) ●●●
895 internal ( The doctor is investigating internal symptoms of the condition. ) ●●●
896 external ( The external design of the building is modern and sleek. ) ●●●
897 distinct ( There is a distinct difference between these two concepts. ) ●●●
898 extinct ( Dinosaurs have been extinct for millions of years. ) ●●●
899 exhausted ( She felt exhausted after working all day. ) ●●●
900 evil ( The movie’s villain had a truly evil plan. ) ●●●
901 greet ( She greeted her friends with a warm smile. ) ●●●
902 chat ( They enjoyed chatting about their favorite hobbies. ) ●●●
903 remark ( His remark about the weather made everyone laugh. ) ●●●
904 utter ( She couldn’t utter a single word after hearing the news. ) ●●●
905 command ( The officer commanded the troops to move forward. ) ●●●
906 declare ( He declared his intention to run for office. ) ●●●
907 pronounce ( Can you pronounce this difficult word correctly? ) ●●●
908 correspond ( The two colors correspond to different teams. ) ●●●
909 imitate ( Children often imitate their parents’ behavior. ) ●●●
910 resemble ( She closely resembles her mother. ) ●●●
911 exhibit ( The museum is exhibiting rare paintings from the Renaissance. ) ●●●
912 distribute ( The teacher distributed the handouts to all the students. ) ●●●
913 attribute ( He attributes his success to hard work and determination. ) ●●●
914 evaluate ( The manager evaluated the employees’ performance. ) ●●●
915 assess ( We need to assess the risks before starting the project. ) ●●●
916 desearve ( She deserves recognition for her dedication to the team. ) ●●●
917 weigh ( He weighed the pros and cons before making a decision. ) ●●●
918 strengthen ( Daily practice will strengthen your skills. ) ●●●
919 weaken ( The lack of resources weakened their efforts. ) ●●●
920 approve ( The board approved the new policy unanimously. ) ●●●
921 assign ( The teacher assigned each student a specific task. ) ●●●
922 sustain ( They worked hard to sustain the growth of their business. ) ●●●
923 accomplish ( She accomplished her goals through hard work and perseverance. ) ●●●
924 relieve ( The medicine relieved him of his headache. ) ●●●
925 frustrate ( The constant delays frustrated the entire team. ) ●●●
926 scare ( The loud thunder scared the little boy. ) ●●●
927 resist ( It’s hard to resist the temptation of chocolate. ) ●●●
928 protest ( The workers protested against unfair wages. ) ●●●
929 shut ( Please shut the door to keep the noise out. ) ●●●
930 defeat ( Their team defeated the defending champions in the final. ) ●●●
931 neglect ( He neglected his health while focusing on work. ) ●●●
932 retire ( He plans to retire after working for 30 years in the company. ) ●●●
933 reform ( The government promised to reform the outdated policies. ) ●●●
934 collapse ( The building collapsed after the earthquake. ) ●●●
935 ruin ( The unexpected rain ruined their picnic plans. ) ●●●
936 sink ( The ship sank after hitting the iceberg. ) ●●●
937 pile ( She piled the books on the desk neatly. ) ●●●
938 derive ( Many English words are derived from Latin. ) ●●●
939 yield ( The farm yielded a good harvest this year. ) ●●●
940 occupy ( The family occupies a small house on the outskirts of the city. ) ●●●
941 wrap ( She wrapped the gift in colorful paper. ) ●●●
942 embrace ( They embraced each other warmly after a long time apart. ) ●●●
943 length ( The length of the river makes it one of the longest in the world. ) ●●●
944 height ( His height makes him an excellent basketball player. ) ●●●
945 volume ( The volume of the container is measured in liters. ) ●●●
946 sum ( The sum of the two numbers is 15. ) ●●●
947 frame ( He bought a wooden frame for his favorite photo. ) ●●●
948 boundry ( The river serves as a natural boundary between the two countries. ) ●●●
949 district ( This district is known for its historical landmarks. ) ●●●
950 territory ( The animals mark their territory to keep others away. ) ●●●
951 square ( The children played soccer in the town square. ) ●●●
952 empire ( The Roman Empire was one of the greatest civilizations in history. ) ●●●
953 heritage ( Traditional dance is part of the region’s cultural heritage. ) ●●●
954 fee ( There is a small entrance fee to visit the museum. ) ●●●
955 discount ( The store is offering a 20% discount on all items this week. ) ●●●
956 charity ( She donated to the charity to help those in need. ) ●●●
957 mission ( Their mission is to provide clean drinking water to remote areas. ) ●●●
958 profession ( He chose teaching as his profession. ) ●●●
959 slave ( The history of slaves teaches us the importance of human rights. ) ●●●
960 witness ( The witness provided crucial evidence during the trial. ) ●●●
961 incident ( The incident occurred late at night near the park. ) ●●●
962 insurance ( It’s important to have health insurance for emergencies. ) ●●●
963 welfare ( The government introduced new measures to ensure public welfare. ) ●●●
964 treasure ( Pirates are often depicted searching for buried treasure. ) ●●●
965 leisure ( She enjoys reading books during her leisure time. ) ●●●
966 priority ( Safety is our top priority during this operation. ) ●●●
967 reputation ( The company has a reputation for producing high-quality goods. ) ●●●
968 honor ( It was an honor to meet the Nobel Prize winner. ) ●●●
969 statue ( The statue in the square commemorates the war heroes. ) ●●●
970 architecture ( The architecture of the ancient temple is breathtaking. ) ●●●
971 logic ( His argument lacked clear logic and supporting evidence. ) ●●●
972 mechanism ( The mechanism of the clock is complex but fascinating. ) ●●●
973 clue ( The detective found a clue that helped solve the case. ) ●●●
974 means ( Transportation by train is the fastest means to get there. ) ●●●
975 trap ( The hunters set a trap to catch wild animals. ) ●●●
976 trick ( She used a clever trick to win the game. ) ●●●
977 guard ( The guard stood at the entrance to check visitors’ IDs. ) ●●●
978 innocent ( The court declared him innocent after the trial. ) ●●●
979 guilty ( He felt guilty for forgetting his friend’s birthday. ) ●●●
980 rude ( It’s rude to interrupt someone while they’re speaking. ) ●●●
981 shy ( She is too shy to speak in front of a large audience. ) ●●●
982 liberal ( He has a liberal approach to solving problems and values freedom. ) ●●●
983 stupid ( It was a stupid mistake, but he learned from it. ) ●●●
984 reluctant ( She was reluctant to join the discussion due to lack of preparation. ) ●●●
985 generous ( He is generous with his time and often helps others. ) ●●●
986 modest ( She is modest about her achievements and avoids bragging. ) ●●●
987 lonely ( He felt lonely after moving to a new city without friends. ) ●●●
988 pure ( The air in the mountains is fresh and pure. ) ●●●
989 grand ( The grand ceremony was attended by thousands of guests. ) ●●●
990 adequate ( The room was small but adequate for their needs. ) ●●●
991 apparent ( It was apparent that she had put a lot of effort into her project. ) ●●●
992 classic ( This novel is a classic example of 19th-century literature. ) ●●●
993 remote ( The cottage is located in a remote area far from the city. ) ●●●
994 solid ( The table is made of solid wood and is very durable. ) ●●●
995 raw ( Eating raw vegetables can be good for your health. ) ●●●
996 plain ( She prefers plain clothing over fancy outfits. ) ●●●
997 primitive ( The tools used by early humans were quite primitive. ) ●●●
998 steady ( The patient showed steady improvement after the treatment. ) ●●●
999 slight ( There was a slight difference between the two designs. ) ●●●
1000 subtle ( The artist’s use of color added subtle beauty to the painting. ) ●●●
1001 delight ( The children’s laughter brought delight to everyone in the room. ) ●●●
1002 entertain ( The magician entertained the audience with his amazing tricks. ) ●●●
1003 fulfill ( She fulfilled her dream of becoming a successful author. ) ●●●
1004 cheer ( The crowd cheered loudly during the soccer match. ) ●●●
1005 amuse ( His funny stories amused everyone at the party. ) ●●●
1006 anticipate ( We anticipate that the results will be announced tomorrow. ) ●●●
1007 confront ( He confronted his fears and overcame them. ) ●●●
1008 undergo ( The patient will undergo surgery next week. ) ●●●
1009 exceed ( Her performance exceeded everyone’s expectations. ) ●●●
1010 overwhelm ( The beautiful scenery overwhelmed her with joy. ) ●●●
1011 shoot ( The photographer shot stunning pictures of the sunset. ) ●●●
1012 murder ( The detectives investigated the mysterious murder case. ) ●●●
1013 rob ( The thieves robbed the bank during the night. ) ●●●
1014 deprive ( Lack of sleep can deprive you of energy during the day. ) ●●●
1015 rid ( She worked hard to rid her home of clutter. ) ●●●
1016 interrupt ( Please don’t interrupt the speaker during the presentation. ) ●●●
1017 interfere ( His interference caused delays in the project’s completion. ) ●●●
1018 bully ( The teacher addressed the issue of bullying among the students. ) ●●●
1019 defend ( She defended her friend against unfair criticism. ) ●●●
1020 rescue ( The firefighters rescued the family from the burning house. ) ●●●
1021 accuse ( He was accused of breaking the rules during the competition. ) ●●●
1022 sue ( She decided to sue the company for negligence. ) ●●●
1023 wander ( They wandered through the forest, exploring its beauty. ) ●●●
1024 chase ( The dog chased the ball eagerly. ) ●●●
1025 arrest ( The police arrested the suspect after a thorough investigation. ) ●●●
1026 submit ( Please submit your assignment by the end of the day. ) ●●●
1027 punish ( He was punished for arriving late to class repeatedly. ) ●●●
1028 resolve ( They resolved their conflict through open communication. ) ●●●
1029 justify ( Can you justify your reasons for making this decision? ) ●●●
1030 restore ( The old painting was restored to its original glory. ) ●●●
1031 modify ( She modified the recipe to suit her taste. ) ●●●
1032 impose ( The government imposed new taxes to address the economic crisis. ) ●●●
1033 compose ( He composed a beautiful melody for the piano. ) ●●●
1034 classify ( The librarian classified the books into different genres. ) ●●●
1035 substitute ( She used honey as a substitute for sugar in the recipe. ) ●●●
1036 shrink ( The sweater shrank after being washed in hot water. ) ●●●
1037 lean ( She leaned against the wall while waiting for the bus. ) ●●●
1038 fold ( He folded the paper neatly before placing it in the envelope. ) ●●●
1039 load ( They loaded the truck with boxes for delivery. ) ●●●
1040 pour ( Please pour me a glass of water. ) ●●●
1041 float ( The small boat floated gently on the lake. ) ●●●
1042 shine ( The sun shone brightly on the beach. ) ●●●
1043 editor ( The editor reviewed the article for any mistakes. ) ●●●
1044 poetry ( She enjoys writing poetry in her free time. ) ●●●
1045 usage ( The instructions explain the correct usage of the device. ) ●●●
1046 sector ( The technology sector is growing rapidly. ) ●●●
1047 span ( His career spans over three decades in the music industry. ) ●●●
1048 literacy ( Promoting literacy among children is a priority for the program. ) ●●●
1049 symptom ( A headache is often a symptom of stress or fatigue. ) ●●●
1050 phase ( The project is currently in its initial phase of development. ) ●●●
1051 surgery ( The surgery was successful, and the patient is now recovering. ) ●●●
1052 virus ( The doctor explained how the virus spreads in crowded places. ) ●●●
1053 poison ( This plant contains a natural poison that can be dangerous if ingested. ) ●●●
1054 protein ( Protein is an essential nutrient for building muscles. ) ●●●
1055 liquid ( Pour the liquid into the container carefully to avoid spillage. ) ●●●
1056 oxygen ( Plants release oxygen during the process of photosynthesis. ) ●●●
1057 globe ( The globe on his desk shows the countries he has visited. ) ●●●
1058 pole ( The North Pole is covered in ice throughout the year. ) ●●●
1059 valley ( The valley was filled with blooming flowers in the spring. ) ●●●
1060 conservation ( Conservation efforts are crucial for protecting endangered species. ) ●●●
1061 channel ( The television channel broadcasted the news live. ) ●●●
1062 glacier ( The melting glacier is a sign of climate change. ) ●●●
1063 pioneer ( She is a pioneer in the field of renewable energy research. ) ●●●
1064 prospect ( The prospect of a promotion motivated her to work harder. ) ●●●
1065 enthusiasm ( His enthusiasm for the project inspired the entire team. ) ●●●
1066 passion ( She has a passion for painting and spends hours in her studio. ) ●●●
1067 fortune ( He made a fortune by investing in real estate. ) ●●●
1068 obstacle ( They overcame many obstacles to achieve their goal. ) ●●●
1069 prejudice ( Prejudice often arises from a lack of understanding. ) ●●●
1070 justice ( The court’s decision restored a sense of justice to the community. ) ●●●
1071 opponent ( His opponent in the chess tournament was highly skilled. ) ●●●
1072 sacrifice ( Parents often make sacrifices for the well-being of their children. ) ●●●
1073 fault ( It was not her fault that the project was delayed. ) ●●●
1074 prison ( He spent several years in prison for his crimes. ) ●●●
1075 shelter ( The organization provides shelter for homeless individuals. ) ●●●
1076 committee ( The committee will review the proposals and choose the best one. ) ●●●
1077 ritual ( The morning ritual included coffee and a quick read of the newspaper. ) ●●●
1078 mature ( He has become more mature and responsible over the years. ) ●●●
1079 moderate ( She prefers a moderate amount of spice in her food. ) ●●●
1080 neutral ( The referee remained neutral throughout the match. ) ●●●
1081 optimistic ( She is optimistic about the company’s future growth. ) ●●●
1082 pessimistic ( His pessimistic attitude made it difficult to stay motivated. ) ●●●
1083 radical ( The radical reforms changed the entire education system. ) ●●●
1084 rough ( The surface of the road was rough and uneven. ) ●●●
1085 smooth ( The dancer’s movements were smooth and graceful. ) ●●●
1086 fluent ( He is fluent in three languages and works as a translator. ) ●●●
1087 casual ( They had a casual lunch at a nearby café. ) ●●●
1088 instant ( The app provides instant updates on the latest news. ) ●●●
1089 incredible ( The view from the top of the mountain was incredible. ) ●●●
1090 genuine ( Her genuine concern for others made her well-loved by everyone. ) ●●●
1091 precious ( Family memories are precious and should be cherished. ) ●●●
1092 prominent ( He is a prominent figure in the field of technology. ) ●●●
1093 blind ( She has been blind since birth but has achieved so much. ) ●●●
1094 deaf ( The deaf community has its own rich culture and language. ) ●●●
1095 harsh ( The harsh winter weather made travel difficult. ) ●●●
1096 prompt ( He gave a prompt response to the emergency situation. ) ●●●
1097 inevitable ( Change is inevitable in the world of technology. ) ●●●
1098 marine ( Marine life is diverse and includes creatures of all sizes. ) ●●●
1099 tropical ( The tropical rainforest is home to many exotic species. ) ●●●
1100 Arctic ( The Arctic region is known for its extreme cold and ice-covered landscape. ) ●●●
1101 forecast ( The weather forecast predicts rain for the entire weekend. ) ●●●
1102 speculate ( Economists speculate that the market will recover soon. ) ●●●
1103 bet ( I bet he’ll arrive late as usual. ) ●●●
1104 quote ( She quoted a famous line from Shakespeare in her essay. ) ●●●
1105 consult ( You should consult a doctor if the symptoms persist. ) ●●●
1106 dispute ( The two parties are in a legal dispute over the property. ) ●●●
1107 accumulate ( Over time, dust accumulated on the old bookshelf. ) ●●●
1108 grasp ( He finally grasped the concept after several explanations. ) ●●●
1109 grip ( She tightened her grip on the handle as the train moved. ) ●●●
1110 seize ( The police seized illegal items during the raid. ) ●●●
1111 comprehend ( It’s difficult to comprehend the scale of the universe. ) ●●●
1112 constitute ( These factors constitute the main reasons for the project’s delay. ) ●●●
1113 reinforce ( The teacher reinforced the lesson with real-world examples. ) ●●●
1114 resort ( They resorted to using candles when the electricity went out. ) ●●●
1115 donate ( She donated a large sum of money to the children’s hospital. ) ●●●
1116 obey ( The dog obeyed its owner’s commands perfectly. ) ●●●
1117 dedicate ( He dedicated his life to protecting the environment. ) ●●●
1118 transmit ( The radio station transmits signals across the country. ) ●●●
1119 equip ( The soldiers were equipped with the latest technology. ) ●●●
1120 bind ( The contract legally binds both parties to the agreement. ) ●●●
1121 pose ( The question posed by the professor sparked a lively discussion. ) ●●●
1122 pause ( She paused the movie to answer a phone call. ) ●●●
1123 hesitate ( Don’t hesitate to ask questions if you have any doubts. ) ●●●
1124 split ( They decided to split the bill equally among the group. ) ●●●
1125 bend ( He bent down to pick up the coin from the floor. ) ●●●
1126 tap ( She tapped on the window to get my attention. ) ●●●
1127 boil ( Boil the water before adding the pasta. ) ●●●
1128 bow ( The performers bowed to the audience at the end of the show. ) ●●●
1129 conceal ( He tried to conceal his surprise but couldn’t. ) ●●●
1130 dispose ( Please dispose of the trash in the designated bin. ) ●●●
1131 cheat ( Cheating on exams is strictly forbidden. ) ●●●
1132 distract ( The loud music distracted her from her studies. ) ●●●
1133 exclude ( The list excludes items that are no longer available. ) ●●●
1134 astonish ( His sudden announcement astonished everyone in the room. ) ●●●
1135 thrill ( The roller coaster ride thrilled the kids with its speed and turns. ) ●●●
1136 leap ( The cat leaped gracefully onto the roof. ) ●●●
1137 postpone ( They decided to postpone the meeting until next week. ) ●●●
1138 dismiss ( The teacher dismissed the class early due to the heat. ) ●●●
1139 resign ( He resigned from his position to pursue other opportunities. ) ●●●
1140 withdraw ( She withdrew her application after accepting another offer. ) ●●●
1141 fade ( The colors on the old photograph had faded over time. ) ●●●
1142 vanish ( The magician made the coin vanish right before our eyes. ) ●●●
1143 continent ( Asia is the largest continent in terms of landmass. ) ●●●
1144 geography ( She is fascinated by the geography of different countries. ) ●●●
1145 ecology ( Ecology studies how organisms interact with their environment. ) ●●●
1146 inhabitant ( The inhabitants of the village welcomed us warmly. ) ●●●
1147 suburb ( They moved to a quiet suburb to escape the busy city life. ) ●●●
1148 furniture ( The furniture in the living room is both stylish and comfortable. ) ●●●
1149 refrigerator ( The refrigerator keeps our food fresh for longer periods. ) ●●●
1150 garbage ( Please take the garbage out before it starts to smell. ) ●●●
1151 trash ( Please don’t forget to take out the trash tonight. ) ●●●
1152 litter ( People should avoid littering to keep the environment clean. ) ●●●
1153 trace ( The archaeologists found traces of an ancient civilization. ) ●●●
1154 row ( They planted flowers in neat rows along the fence. ) ●●●
1155 core ( Trust is the core of a strong relationship. ) ●●●
1156 orbit ( The satellite remains in orbit around the Earth. ) ●●●
1157 galaxy ( The Milky Way galaxy is home to billions of stars. ) ●●●
1158 myth ( There are many myths surrounding the origins of this ancient temple. ) ●●●
1159 faith ( She has great faith in her abilities to succeed. ) ●●●
1160 wisdom ( His wisdom and experience make him a great mentor. ) ●●●
1161 obligation ( We have a moral obligation to help those in need. ) ●●●
1162 privilege ( It’s a privilege to be part of such an incredible team. ) ●●●
1163 discrimination ( The law aims to eliminate discrimination in the workplace. ) ●●●
1164 ambition ( Her ambition drove her to achieve remarkable success. ) ●●●
1165 illusion ( The magician’s performance created the illusion of floating. ) ●●●
1166 instinct ( His instinct told him to avoid the dangerous path. ) ●●●
1167 shame ( She felt deep shame for breaking her promise. ) ●●●
1168 humor ( His sense of humor lightened the mood during the meeting. ) ●●●
1169 courage ( It takes courage to stand up for what you believe in. ) ●●●
1170 sympathy ( She expressed her sympathy for the family’s loss. ) ●●●
1171 tragedy ( The earthquake was a tragedy that affected many lives. ) ●●●
1172 fate ( They believe their meeting was written in fate. ) ●●●
1173 destiny ( She followed her destiny and achieved her lifelong dreams. ) ●●●
1174 abuse ( The organization works to prevent abuse and support victims. ) ●●●
1175 wound ( He treated the wound with antiseptic and bandages. ) ●●●
1176 fever ( The child was recovering from a high fever. ) ●●●
1177 infection ( Antibiotics are used to treat bacterial infections. ) ●●●
1178 brave ( The brave firefighter saved the cat from the burning house. ) ●●●
1179 brilliant ( Her brilliant idea solved the problem in no time. ) ●●●
1180 gentle ( He spoke in a gentle tone to calm the nervous child. ) ●●●
1181 noble ( Helping others is a noble act that brings joy to everyone. ) ●●●
1182 royal ( The royal family attended the grand ceremony. ) ●●●
1183 sacred ( This forest is sacred to the indigenous people of the region. ) ●●●
1184 holy ( The pilgrimage takes visitors to many holy sites. ) ●●●
1185 decent ( He did a decent job on the presentation, considering the time constraints. ) ●●●
1186 grateful ( She felt grateful for the support from her friends and family. ) ●●●
1187 fond ( He has fond memories of his childhood in the countryside. ) ●●●
1188 selfish ( It’s selfish to always put your own needs first. ) ●●●
1189 awkward ( There was an awkward silence after her unexpected comment. ) ●●●
1190 awful ( The food tasted awful, and we had to throw it away. ) ●●●
1191 ultimate ( Achieving her ultimate goal required years of dedication. ) ●●●
1192 dynamic ( The dynamic performance captivated the audience. ) ●●●
1193 tremendous ( She made a tremendous effort to complete the project on time. ) ●●●
1194 abundant ( This region is abundant in natural resources. ) ●●●
1195 dull ( The lecture was so dull that many students lost interest. ) ●●●
1196 urgent ( It’s urgent to address the issue before it escalates. ) ●●●
1197 spare ( Do you have any spare time to help with this task? ) ●●●
1198 tight ( The schedule was tight, leaving little room for flexibility. ) ●●●
1199 shallow ( The water in the pond is shallow enough to walk through. ) ●●●
1200 superficial ( His comments were superficial and lacked depth. ) ●●●
1201 whisper ( She whispered a secret into her friend’s ear. ) ●●●
1202 yell ( He yelled loudly to catch the attention of the passerby. ) ●●●
1203 scream ( The horror movie made everyone scream in fright. ) ●●●
1204 nod ( She nodded in agreement during the discussion. ) ●●●
1205 swallow ( He swallowed the pill with a glass of water. ) ●●●
1206 yawn ( The long meeting made everyone yawn repeatedly. ) ●●●
1207 cough ( He coughed due to the cold weather outside. ) ●●●
1208 hug ( They hugged each other warmly after years of separation. ) ●●●
1209 sweep ( She swept the floor clean after dinner. ) ●●●
1210 polish ( He polished the silverware until it gleamed. ) ●●●
1211 decorate ( We decorated the room with balloons for the birthday party. ) ●●●
1212 shed ( The tree shed its leaves during autumn. ) ●●●
1213 drag ( He dragged the heavy suitcase across the airport floor. ) ●●●
1214 spoil ( The heat spoiled the fresh vegetables left outside. ) ●●●
1215 burst ( The balloon burst with a loud pop when it hit a sharp edge. ) ●●●
1216 explode ( The fireworks exploded beautifully in the night sky. ) ●●●
1217 compromise ( Both sides agreed to compromise to resolve the disagreement. ) ●●●
1218 exaggerate ( He exaggerated the difficulty of the task to avoid doing it. ) ●●●
1219 exploit ( The company exploited its resources to increase profit. ) ●●●
1220 utilize ( She utilized her skills to successfully manage the project. ) ●●●
1221 irritate ( His constant interruptions irritated everyone in the room. ) ●●●
1222 insult ( She felt insulted by his rude comments during the meeting. ) ●●●
1223 deceive ( He deceived them by pretending to be someone else. ) ●●●
1224 violate ( The new policy aims to protect individuals from violations of their rights. ) ●●●
1225 disgust ( The sight of the polluted river disgusted the visitors. ) ●●●
1226 endure ( She endured many hardships before achieving success. ) ●●●
1227 tolerate ( He tolerates spicy food but prefers milder flavors. ) ●●●
1228 suspend ( The event was suspended due to unforeseen circumstances. ) ●●●
1229 cease ( The company decided to cease operations in the area. ) ●●●
1230 appoint ( She was appointed as the new director of the department. ) ●●●
1231 undertake ( The team decided to undertake the challenge despite the risks. ) ●●●
1232 overtake ( The car overtook the truck on the highway with ease. ) ●●●
1233 proceed ( Please proceed to the next step of the application process. ) ●●●
1234 commute ( She commutes by train every day to work. ) ●●●
1235 flourish ( The company flourished in the competitive market due to its innovative ideas. ) ●●●
1236 thrive ( Plants thrive in environments with proper sunlight and water. ) ●●●
1237 venture ( He decided to venture into a new industry after years in retail. ) ●●●
1238 accustom ( She quickly accustomed herself to the new culture. ) ●●●
1239 rear ( They built a playground at the rear of the school. ) ●●●
1240 inherit ( She inherited her grandmother’s antique jewelry collection. ) ●●●
1241 blossom ( The cherry trees blossom beautifully in spring. ) ●●●
1242 esteem ( He is held in high esteem by his colleagues for his integrity. ) ●●●
1243 merchant ( The merchant sold spices and textiles in the bustling market. ) ●●●
1244 fare ( The taxi fare to the airport was surprisingly reasonable. ) ●●●
1245 voyage ( The voyage across the ocean lasted several weeks. ) ●●●
1246 crew ( The ship’s crew worked tirelessly to navigate through the storm. ) ●●●
1247 luggage ( She packed her luggage for the long journey ahead. ) ●●●
1248 horizon ( The sun set beautifully over the horizon. ) ●●●
1249 lightning ( The sudden lightning lit up the dark sky. ) ●●●
1250 dawn ( He woke up early to enjoy the serenity of dawn. ) ●●●
1251 astronomy ( Astronomy helps us understand the universe and its mysteries. ) ●●●
1252 statistics ( The statistics show a significant rise in employment rates. ) ●●●
1253 dimension ( The building has impressive dimensions and a unique design. ) ●●●
1254 faculty ( The university faculty consists of experienced professors and researchers. ) ●●●
1255 scheme ( The government introduced a new scheme to support small businesses. ) ●●●
1256 viewpoint ( She shared her viewpoint on the environmental impact of the project. ) ●●●
1257 output ( The factory’s output increased significantly after modernization. ) ●●●
1258 outlook ( He has a positive outlook on life despite facing challenges. ) ●●●
1259 tuition ( The tuition for the course was covered by the scholarship. ) ●●●
1260 proverb ( The old proverb says, “A stitch in time saves nine.” ) ●●●
1261 biography ( I recently read a fascinating biography of Albert Einstein. ) ●●●
1262 narrative ( The narrative of the movie was both engaging and emotional. ) ●●●
1263 chapter ( This chapter explains the basic concepts of quantum physics. ) ●●●
1264 string ( He tied the package with a strong string to secure it. ) ●●●
1265 tag ( The price tag on this shirt shows it’s on sale. ) ●●●
1266 peasant ( In medieval times, peasants worked the land for their lords. ) ●●●
1267 livestock ( The farmer raises livestock such as cattle and sheep. ) ●●●
1268 famine ( The famine caused widespread suffering across the region. ) ●●●
1269 fatigue ( After working for hours, he felt extreme fatigue and needed rest. ) ●●●
1270 motive ( The police are investigating the motive behind the crime. ) ●●●
1271 sweat ( Sweat dripped from his forehead after the intense workout. ) ●●●
1272 peer ( She was nervous about presenting her ideas in front of her peers. ) ●●●
1273 glance ( A quick glance at the schedule told her she was running late. ) ●●●
1274 glimpse ( He caught a glimpse of the celebrity walking down the street. ) ●●●
1275 luxury ( Staying at the five-star hotel was a rare luxury for them. ) ●●●
1276 prosperity ( Economic prosperity often leads to improved living standards. ) ●●●
1277 fame ( The artist gained international fame for her unique style. ) ●●●
1278 keen ( She has a keen interest in learning new languages. ) ●●●
1279 inclined ( He was inclined to agree with the new proposal. ) ●●●
1280 competent ( She is highly competent and can handle complex tasks efficiently. ) ●●●
1281 superior ( His performance was far superior to what we had expected. ) ●●●
1282 inferior ( The materials used in this product are inferior to others in the market. ) ●●●
1283 cruel ( The cruel treatment of animals must be stopped immediately. ) ●●●
1284 indifferent ( He seemed indifferent to the outcome of the match. ) ●●●
1285 ashamed ( She felt ashamed of her behavior at the party. ) ●●●
1286 bold ( His bold decision to start his own business paid off. ) ●●●
1287 ridiculous ( The idea of flying cars once seemed ridiculous, but not anymore. ) ●●●
1288 ugly ( The old building had an ugly exterior but a charming interior. ) ●●●
1289 pale ( She turned pale with shock upon hearing the news. ) ●●●
1290 male ( The male lion guards the pride while the females hunt. ) ●●●
1291 manual ( The manual for the new device is easy to understand. ) ●●●
1292 mutual ( They share a mutual respect for each other’s skills. ) ●●●
1293 delicate ( The delicate flowers need extra care to thrive. ) ●●●
1294 deliberate ( His deliberate decision took everyone by surprise. ) ●●●
1295 gradual ( The gradual increase in temperature signals the arrival of spring. ) ●●●
1296 loose ( The shoelaces are loose; let me tie them for you. ) ●●●
1297 bitter ( The coffee tasted bitter, so she added some sugar. ) ●●●
1298 mild ( He prefers mild weather over extreme heat or cold. ) ●●●
1299 dense ( The dense forest was difficult to navigate. ) ●●●
1300 tense ( The atmosphere in the courtroom was extremely tense. ) ●●●
1301 conceive ( She was able to conceive a brilliant idea for the project. ) ●●●
1302 confess ( He confessed that he had forgotten to complete the assignment. ) ●●●
1303 conform ( All employees are required to conform to the company’s rules. ) ●●●
1304 offend ( His comments offended several people in the audience. ) ●●●
1305 envy ( She couldn’t help but envy her friend’s success. ) ●●●
1306 boast ( He boasted about his achievements during the meeting. ) ●●●
1307 dare ( She dared to speak up against unfair treatment. ) ●●●
1308 confine ( The injured bird was confined to a small cage for safety. ) ●●●
1309 contradict ( His actions contradict his previous statements. ) ●●●
1310 compensate ( The company compensated the employees for their overtime work. ) ●●●
1311 coincide ( The festival coincides with the holiday weekend this year. ) ●●●
1312 assure ( I assure you that the project will be completed on time. ) ●●●
1313 attain ( She attained her goal of becoming a professional musician. ) ●●●
1314 inquire ( He inquired about the availability of rooms at the hotel. ) ●●●
1315 invade ( The army invaded the enemy territory during the war. ) ●●●
1316 conquer ( The explorers conquered new lands in search of resources. ) ●●●
1317 persist ( Despite the challenges, she persisted in her efforts. ) ●●●
1318 last ( The storm lasted for several hours, causing widespread damage. ) ●●●
1319 surrender ( The soldiers surrendered when they ran out of supplies. ) ●●●
1320 betray ( He betrayed his friend’s trust by revealing their secret. ) ●●●
1321 strain ( She strained her back while lifting a heavy box. ) ●●●
1322 refrain ( Please refrain from making loud noises during the performance. ) ●●●
1323 scatter ( The wind scattered the leaves across the lawn. ) ●●●
1324 spill ( He accidentally spilled his coffee on the table. ) ●●●
1325 prevail ( Justice prevailed, and the innocent man was set free. ) ●●●
1326 starve ( Many families starved during the famine. ) ●●●
1327 digest ( She took some time to digest the information she had just received. ) ●●●
1328 disguise ( The spy disguised himself as a local worker to gather information. ) ●●●
1329 strip ( They stripped the old paint off the walls before repainting. ) ●●●
1330 scratch ( The cat scratched the sofa while playing. ) ●●●
1331 bathe ( She bathed in the clear, refreshing waters of the stream. ) ●●●
1332 soak ( The laundry soaked in water for an hour before being washed. ) ●●●
1333 stir ( He stirred the soup to mix the ingredients evenly. ) ●●●
1334 wind ( The trail winds through the dense forest for miles. ) ●●●
1335 heal ( The wound will heal over time with proper care. ) ●●●
1336 knit ( She knitted a warm scarf for the winter. ) ●●●
1337 sew ( He learned to sew a button back onto his shirt. ) ●●●
1338 dye ( They dyed the fabric in bright colors for the festival. ) ●●●
1339 beg ( The homeless man begged for food on the street corner. ) ●●●
1340 pray ( She prayed for her family’s safety during the storm. ) ●●●
1341 congratulate ( I’d like to congratulate you on your outstanding performance. ) ●●●
1342 summit ( The climbers reached the summit after days of effort. ) ●●●
1343 mayor ( The mayor attended the opening ceremony of the new park. ) ●●●
1344 secretary ( The secretary prepared the documents for the board meeting. ) ●●●
1345 council ( The council voted to approve the new community project. ) ●●●
1346 panel ( A panel of experts discussed the future of renewable energy. ) ●●●
1347 jury ( The jury deliberated for hours before reaching a verdict. ) ●●●
1348 quarrel ( The siblings often quarrel over trivial matters. ) ●●●
1349 divorce ( They decided to file for divorce after years of unhappiness. ) ●●●
1350 thief ( The thief was caught by the police while attempting to escape. ) ●●●
1351 refuge ( The refugees found refuge in a safe shelter provided by the organization. ) ●●●
1352 mercy ( The judge showed mercy and reduced the defendant’s sentence. ) ●●●
1353 caution ( Proceed with caution when walking on icy roads. ) ●●●
1354 pity ( She felt pity for the stray dog wandering the streets. ) ●●●
1355 sorrow ( The family expressed deep sorrow at the loss of their loved one. ) ●●●
1356 grief ( He struggled to cope with the grief of losing his best friend. ) ●●●
1357 despair ( Despite her despair, she managed to find hope and keep going. ) ●●●
1358 suicide ( The hotline provides support to individuals struggling with thoughts of suicide. ) ●●●
1359 ambulance ( The ambulance arrived quickly to take the injured to the hospital. ) ●●●
1360 funeral ( Many people attended the funeral to pay their respects. ) ●●●
1361 grave ( The grave of the famous poet is visited by admirers from around the world. ) ●●●
1362 virtue ( Patience is a virtue that often leads to success. ) ●●●
1363 legend ( According to the legend, the treasure is hidden on the island. ) ●●●
1364 prestige ( Winning the award brought great prestige to the university. ) ●●●
1365 glory ( The team fought with determination to achieve glory in the final match. ) ●●●
1366 dignity ( She handled the difficult situation with grace and dignity. ) ●●●
1367 worship ( They gathered at the temple to worship and offer prayers. ) ●●●
1368 criterion ( The main criterion for selection is relevant experience. ) ●●●
1369 consent ( The students must obtain parental consent for the field trip. ) ●●●
1370 triumph ( His triumph in the competition was celebrated by the entire town. ) ●●●
1371 circulation ( Good circulation is vital for maintaining a healthy body. ) ●●●
1372 merit ( This proposal has great merit and deserves serious consideration. ) ●●●
1373 appetite ( After the long hike, he had a huge appetite for dinner. ) ●●●
1374 nutrition ( Proper nutrition is essential for a child’s growth and development. ) ●●●
1375 decay ( The old building showed signs of decay after decades of neglect. ) ●●●
1376 atom ( Every object in the universe is made up of atoms. ) ●●●
1377 boom ( The tech industry is experiencing a significant boom in innovation. ) ●●●
1378 valid ( Your passport must be valid for at least six months to travel abroad. ) ●●●
1379 due ( The assignment is due next Friday, so please plan accordingly. ) ●●●
1380 vacant ( The apartment has been vacant since the previous tenants moved out. ) ●●●
1381 bare ( The tree stood bare after all its leaves had fallen. ) ●●●
1382 naked ( The walls looked bare and naked without any paintings. ) ●●●
1383 obscure ( The meaning of the ancient text is obscure and difficult to interpret. ) ●●●
1384 peculiar ( There was something peculiar about the way he acted that day. ) ●●●
1385 tidy ( She keeps her desk neat and tidy at all times. ) ●●●
1386 minute ( He noticed a minute detail that others had overlooked. ) ●●●
1387 vague ( Her answer was vague, leaving us unsure of what she meant. ) ●●●
1388 steep ( The mountain trail was steep and challenging to climb. ) ●●●
1389 humid ( The weather in the rainforest is hot and humid throughout the year. ) ●●●
1390 earnest ( He made an earnest effort to resolve the misunderstanding. ) ●●●
1391 absurd ( The idea seemed absurd at first but turned out to be effective. ) ●●●
1392 hostile ( The hostile tone of the conversation made everyone uncomfortable. ) ●●●
1393 idle ( The factory was idle during the holiday season. ) ●●●
1394 jealous ( She felt jealous of her friend’s recent achievements. ) ●●●
1395 loyal ( Dogs are known to be loyal companions to their owners. ) ●●●
1396 supreme ( He holds a supreme position of authority in the organization. ) ●●●
1397 infinite ( The possibilities for innovation in this field are infinite. ) ●●●
1398 static ( The design remained static despite suggestions for improvement. ) ●●●
1399 thorough ( A thorough review of the data is necessary before making a decision. ) ●●●
1400 immense ( The immense size of the canyon left the tourists in awe. ) ●●●
英熟語練習(標準:英検2級・日東駒専レベル)
<練習問題>の(●●●)は1語
Unit01「同じ形で意味が異なる」熟語
(前置詞だけではイメージし難いため、型ごとに覚える)
<練習問題>
【(動詞) + up with】型
1 be (●●●) up with ~ (~にうんざりだ)
2 (●●●) up with ~ (~と別れる)
3 (●●●) up with ~ (~に追いつく)
4 (●●●) up with ~ (最終的に~になる)
5 (●●●) up with ~ (~についていく)
6 (●●●) up with ~ (~と会う(予定通り))
7 (●●●) up with ~ (~を我慢する)
【(動詞) + off】型
1 (●●●) out of ~ (~を使い果たす)
2 (●●●) out ~ (~であることがわかる/なる)
3 (●●●) out ~ (うまくいく/解決する)
4 (●●●) out ~ (~を見つけ出す/知る)
【(動詞) + off】型
1 (●●●) off ~ (離陸する/急に成功する
2 (●●●) off ~ (爆発する/鳴る/腐る)
3 (●●●) off ~ ( 延期する )
【(動詞) + on】型
1 (●●●) on with ~ (~とうまくやっていく)
2 (●●●) on ~ (続ける)
3 (●●●) on ~ (~を当てにする/頼る)
【(動詞) + down】型
1 (●●●) down ~ (故障する/(人が)取り乱す )
2 (●●●) down ~ (落ち着く)
【(動詞) + over】型
1 (●●●) over ~ (~を乗り越える/回復する)
2 (●●● ) over ~ (~をよく考える)
【(動詞) + in】型
1 (●●●) in ~ (屈する/譲る)
2 (●●●) in ~ (記入する)
Uni02「動詞でイメージできる」熟語
(動詞のイメージ+前置詞の向きでニュアンスを意識)
<up=上昇・完了、out=外・完全、downは=低下・制御>
<練習問題>
blow「吹く・爆発する」
1 blow (●●●) (爆発する/激怒する)
2 blow (●●●) (吹き飛ばす/感動させる)
drop「落とす」
1 drop (●●●) of ( を脱落する/中退する )
2 drop (●●●) ( 立ち寄る )
fade「薄れる・消える」
1 fade (●●●) (徐々に消える)
pass「通る・渡す」
1 pass (●●●) (受け継ぐ)
show「見せる」
1 show (●●●) (現れる/姿を見せる)
sign「署名する」
1 sign (●●●) for (に登録する)
throw「投げる」
1 throw (●●●) (投げ捨てる/追い出す)
2 throw (●●●) (吐く)
watch「見る・注意する」
1 watch (●●●) (気をつける)
turn「回る・向きを変える」
1 turn (●●●) (電気をつける/消す)
2 turn (●●●) (現れる/音量を上げる)
give「与える」
1 give (●●●) (あきらめる)
2 give (●●●) (屈する)
break「壊す」
1 break (●●●) (勃発する(戦争・火事など))
2 break (●●●) (故障する/取り乱す)
pick「拾う・選ぶ」
1 pick (●●●) (拾う/迎えに行く/習得する)
run「走る」
1 run (●●●) (偶然出会う/衝突する)
2 run (●●●) of (~を使い果たす)
call「呼ぶ」
1 call (●●●) (中止する)
2 call (●●●) (~を求める)
Unit03「前置詞・副詞が全体の意味を決定」熟語
(動詞だけでは予測し難く前置詞や副詞のニュアンス意識)
<練習問題>
【down】(減少・拒否・記録のイメージ)
1 (●●●) down (~を下げる、落とす)
2 (●●●) down on (削減する)
3 (●●●) down (拒否する)
4 (●●● ) down (書き留める)
【up】(増加・完了・強調など)
1 (●●● ) up (元気づける/元気になる)
2 (●●●) up (使い果たす)
3 ( ●●● ) up (正装する/着飾る)
【out】(外に出る・完全に・除外)
1 (●●●) out (除外する/省く)
2 (●●●) out (火・明かりを消す)
3 (●●●) out (目立つ)
4 (●●●) out (解決する/理解する)
【on】(継続・接触・集中)
1 (●●●) on (続ける)
2 (●●●) on~ing (~し続ける)
3 on ( ●●● ) (連続して)
4 ( ●●● ) on (続く/起こる)
【for】(方向・目的・対象)
1 (●●●) for (好む/世話をする)
2 (●●●) for (~を切望する)
3 (●●●) for (要求する)
4 (●●●) for (探す)
【from】(分離・原因・防止)
1 be (●●●) from (~がない)
2 (●●●) A from~ing (Aが~するのを防ぐ)
3 (●●●) A from B (AとBを区別する)
【to / with / at】などの他パターン
1 (●●●) up to (を尊敬する)
2 (●●●) down on (を見下す)
3 (●●●) along with (とうまくやっていく)
4 (●●●) with (に同意する)
5 (●●●) at (を目指す)
6 (●●●) at (を笑う)
「be + 過去分詞 + 前置詞」型
1 be known (●●●) (で知られている)
2 be made ( ●●● ) (でできている<形が残る>)
3 be worn ( ●●● ) (疲れ切っている )
4 be concerned ( ●●● ) (を心配している)
Unit04「文法構造=タイプ別」熟語
(類似表現との区別や文法的誤用の防止を意識)
<練習問題>
【他動詞+名詞型】(名詞を目的語にとる)
1 (●●●) sense (意味をなす)
2 (●●●) care (気をつける/用心する)
3 (●●●) a look (見てみる)
4 (●●●) a hand (手を貸す)
5 (●●●) in touch (連絡を取り続ける)
6 (●●●) a decision (決定する)
7 (●●●) part (in) (参加する)
8 (●●●) sight of (見失う)
9 (●●●) harm (害を及ぼす)
10 (●●●) one’s word (約束を守る)
11 (●●●) an effort (努力する)
12 (●●●) room (空ける)
13 (●●●) a deep breath (深呼吸する)
【自動詞型熟語】(目的語を取らず動詞的機能)
1 come (●●●) (話題などが出る)
2 turn (●●●) (生じる)
3 show (●●●) (現れる)
4 go (●●●) ((時が)過ぎる)
5 run (●●●) of (尽きる)
6 break (●●●) ( (戦争・火事などが)起こる)
7 get (●●●) (なんとかやっていく)
8 come (●●●) (一緒に行く/進行する)
9 go (●●●) (前進する)
【前置詞+名詞(+前置詞)型】(形容詞や副詞句)
1 (●●●) a loss (途方に暮れて)
2 at any (●●●) (どんな犠牲を払っても)
3 at (●●●) (すぐに/同時に)
4 by (●●●) (暗記して)
5 by no (●●●) (決して~ない)
6 in a (●●●) (急いで)
7 in (●●●) (困っている)
8 in the (●●●) (邪魔になって)
9 in (●●●) (それに対して)
10 in (●●●) of (~を担当して)
11 in (●●●) of (~の観点から)
12 on (●●●) (わざと)
13 under (●●●) (管理下にある)
14 (●●●) schedule (予定より遅れて)
15 in (●●●) of (~に賛成して)
【副詞句型】(文修飾、副詞として働く表現)
1 (●●●) first (初めは)
2 (●●●) the meantime (その間に)
3 (●●●) now on (これからは)
4 at (●●●) (多くても)
5 at (●●●) (少なくとも)
6 in the (●●●) (結局は)
7 (●●●) in a while (たまに)
8 (●●●) to now (今までのところ)
9 (●●●) and over (何度も繰り返して)
10 (●●●) away (すぐに)
11 so (●●●) (これまでのところ)
12for (●●●) (永久に)
13 (●●●) and there (あちこちで)
14 in (●●●) (一般に)
15 in (●●●) (要するに)
【be+形容詞+前置詞型】(状態や感情・判断)
1 be (●●●) of~ (~を恐れている)
2 be (●●●) of~ (~に気づいている)
3 be (●●●) of~ (~する能力がある)
4 be (●●●) of~ (~が好きである)
5 be (●●●) of~ (~でいっぱいである)
6 be tired (●●●) ~ (~にうんざりしている)
7 be surprised (●●●) ~ (~に驚いている)
8 be different (●●●) ~ (~と異なっている)
9 be responsible (●●●) ~ (~に責任がある)
10 be familiar (●●●) ~ (~に詳しい)
【名詞 + of型】(~の〜/〜に関する〜)
1 a (●●●) of~ (~の不足)
2 a (●●●) of~ (さまざまな~)
3 (●●●) number of~ (多くの~)
4 an increase (●●●) ~ (~における増加)
5 an increase (●●●) ~ (~の増加)
6 the (●●●) of~ (~の原因)
7 the (●●●) of~on… (~の…への影響)
8 (●●●) number of~ (~の数)
9 a photo (●●●) ~ (~の写真)
10 a member (●●●) ~ (~の一員)
11 a (●●●) of~ (~の兆候)
12 a (●●●) of~ (~の一部/1つ)
英文法
英文法を習得するためには、段階的に理解を深めていくことが効果的です。以下に、初心者から上級者までの英文法理解のステップを示します。特に受験英語や大学入試を意識した内容にしています。
1️⃣ 基礎理解(文の仕組みを知る)
英文の基本構造を理解する。
・品詞の理解(名詞・動詞・形容詞・副詞など)
・文の要素(主語・動詞・目的語・補語・修飾語)
・基本文型(SV/SVO/SVC/SVOO/SVOC)
・be動詞と一般動詞の使い分け
・時制(現在・過去・未来)
理解チェック:
・“She is a teacher.” の文型は?
・“I gave him a book.” は第何文型?
2️⃣ 基本文法の習得(文法ルールを身につける)
正しい英文を作るための文法ルールを覚える。
・助動詞(can, will, must など)
・不定詞・動名詞
・比較(原級・比較級・最上級)
・受動態
・接続詞(and, but, because, if など)
理解チェック:
・“He must have gone there.” の意味と文法構造は?
・“She is taller than I.” はなぜ “me” じゃないの?
3️⃣ 応用文法の理解(読解・作文への応用)
英文法を意識して長文読解や英作文で使えるようにする。
・関係詞(who, which, that, whose など)
・仮定法(If I were, If I had, would など)
・分詞構文
・倒置・強調構文
・名詞節・副詞節・形容詞節
理解チェック:
・“If I had studied harder, I would have passed.” はどういう意味?
・“The man talking to Mary is my uncle.” の “talking” は何?
4️⃣ 実践・運用力の強化(問題演習・実際の使用)
文法知識を意識しなくても使えるスキルにする。
方法:
・文法問題の演習(4択、整序、誤文訂正など)
・英文法を使った短文作成・瞬間英作文
・長文問題で文法を意識しながら読む
・英作文で「自分で文法を選ぶ」練習
5️⃣ 定着と深化(アウトプットとフィードバック)
自分の弱点を見つけて修正し知識を定着させる。
方法:
・模試・過去問を解いて文法知識を実戦で確認
・解説を読み、自分のミスを記録(文法ノートの作成)
・人に教える/説明することで定着を図る
アドバイス:
✅ 1️⃣〜2️⃣までは 反復と暗記 が大切。
✅ 3️⃣以降は文脈での理解 と 運用力 を重視。
✅ 苦手な文法分野はリスト化して「復習リスト」を作ると効率的。
- 文法問題
- 文法問題(解説)
第1章 文の種類
001 平叙文/肯定文と否定文
次の文を否定文にしなさい。
1) I am a student at this school.
2) He knows your sister very well.
3) I will be at home this evening.
002 Yes/No 疑問文 / 疑問詞を使った疑問文
( )に適語を入れなさい。
1) “( ) you like pop music? “Yes, I do.”
2) “( ) he angry last night? “No, he wasn’t.”
3) “( ) broke the glass?” “I did.”
4) “( ) are you going?” “To the city hall.”
003 命令文 / 感嘆文
日本語の意味に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) この花を摘んではいけません。
( ) pick these flowers.
2) 図書館の中では静かにしなさい。
( ) quiet in the library.
3) あの先生は話すのがなんて速いんだろう!
( ) fast that teacher speaks!
4) これはなんて簡単な問題なんだろう!
( ) ( ) easy problem ( ) ( )!
004 選択疑問文 / 命令文の様々な形
( )に適語を入れなさい。
1) “Who called me up, Jane ( ) Cathy?” “Cathy did.”
2) ( ) go to a movie, shall we?
第2章 動詞と文型
005 自動詞と他動詞
太字の動詞に注意して、それぞれの文を日本語に直しなさい。
1) A big car stopped in front of my house.
2) The driver stopped the car.
3) Don’t play on the street.
4) Let’s play tennis after school.
006 述語動詞
( )内の動詞を適切な形に変えなさい。
1) Kate is a student and (study) Japanese every day.
2) Last Sunday, my father (cut) some branches off the tree.
3) I (go) to my uncle’s log cabin with my brother last summer.
007 SV / SVC /SVO
太字の語が、補語、目的語のどちらであるか答えなさい。
1) Did you get my e-mail?
2) The teacher got angry with him?
3) We became friends at university.
4) He has a lot of friends all over the world.
008 SVOO
次の文中の目的語を指摘しなさい。
1) Ms.Kim teaches us math.
2) He gave me some magazines.
3) I got a letter from him.
009 SVOC
次の文を日本語に直しなさい。
1) We call the dog Max.
2) Our coach made her the team’s captain.
3) You will find this book easy.
010 SVO+to / for 〜
与えられた前置詞を用いて、SVOの文に書き換えなさい。
1) Mr. Evans teaches us English. (to)
2) I’ll buy you lunch. (for)
3) I chose her a nice dress. (for)
4) Please show me the photo. (to)
011 There+be動詞
( )の中から、適当なものを選びなさい。
1) There (is/are) a ball in the box.
2) There (was/were) many students in the station.
3) There is (a/the) book on the desk.
012 注意すべき自動詞と他動詞
次の文の誤りを訂正して、正しい英文にしなさい。(誤りはそれぞれ1カ所ある)。
1) He entered into the room.
2) When I opened the door, two men approached to me.
3) He agreed me on that point.
013 群動詞 / SVCで用いられる動詞
( )に入れるのにもっとも適切な語を、下から1つずつ選びなさい。
1) His story may ( ) strange, but it is true.
2) Your dream will soon ( ) true.
3) You must ( ) quiet in the library.
4) These roses ( ) sweet.
[ come / keep / sound / smell ]
014 SVOの文型で注意すべき目的語/ SVOOの文型で用いられる動詞
( )に適語をいれなさい。ただし、何も入れる必要のない場合は×を入れること。
1) Maggie taught herself ( ) French.
2) Tom made a house ( ) the dog.
3) Please bring me ( ) the dog.
4) He sold his CD player ( ) me for six thousand yen.
015 SVOCの文型で用いられる動詞
太字の語に注意をして、それぞれの文を日本語に直しなさい。
1) Please get me the dictionary on the desk.
2) I’ll get supper ready as soon as possible.
3) We left her a lot of work.
4) Don’t leave the door open, please.
第3章 動詞と時制
016 現在形
( )内の動詞を現在形か進行形にしなさい。
1) This orange (taste) bad; it (be) not good to eat.
2) Mary (play) a piece by Bach on the piano now; she (like) music very much.
3) The sun (rise) in the east and (set) in the west.
4) My sister usually (wear) contact lenses, but she (wear) glasses today.
017 過去形・過去進行形
( )内の動詞を適切な形に変えなさい。
1) I wanted to be a sailor when I (be) a boy.
2) My father often (tell) me interesting stories in my childhood.
3) He ran to the station and (catch) the last train.
4) My mother (watch) TV when I came home.
018 未来形・未来進行形
日本語に合うように、( )内に適語を入れなさい。
1) 「熱い、手をやけどしちゃった!」「僕が氷を取ってきてあげるよ!」
“Ouch! I burned my hand!” “I ( ) get some ice for you!”
2) この8月にスペインに引っ越すので、スペイン語を覚える必要があります。
I need to learn Spanish because I ( ) ( ) ( ) move to Spain this August.
3) 明日の今ごろは、彼らはパーティをしているでしょう。
At this time tomorrow they ( ) ( ) having a party.
019 時や条件を表す接続詞の後で用いる現在形
次の文の( )内の動詞を正しい形に直しなさい。
1) I’ll finish my home work before my sister (come) back.
2) I’ll give him this CD if he (want) it.
3) Don’t get off the bus till it (stop).
020 進行形の注意すべき用法
次の文を日本語に直しなさい。
1) It’s getting dark. Let’s go home.
2) I was leaving my house when the telephone rang.
3) That teacher is constantly forgetting his student’s names.
021 未来を表す様々な表現
( )に適語を入れなさい。
1) My sister ( ) to be married next week.
2) They were ( ) to leave their house when it began to rain.
3) Sam ( ) leaving Japan at the end of this month.
4) I was on the ( ) ( ) going to bed when he called me.
第4章 完了形
022 現在完了形の形と働き / 過去形と現在完了形
次の文の( )内の動詞を、現在完了形にしなさい。
1) I (finish) my work. So, I can go shopping.
2) Cindy (lose) her watch. She is going to buy a new one today.
023 「完了・結果」「経験」「継続」を表す現在完了形 / 「動作の継続」を表す現在完了進行形
日本語の意味に合うように( )に適語を入れなさい。
1) 私はまだクリスマスカードを書いていません。
I ( ) not ( ) my Christmas cards yet.
2) 私は彼からメールを受け取りました。
I ( ) ( ) an e-mail from him.
3) 今までに外国へ行ったことがありますか?
( ) you ( ) been abroad?
4) 日本に来てどのくらいになりますか?
How ( ) have you ( ) in Japan?
5) 1週間雨が降り続いています。
It ( ) ( ) raining ( ) a week.
024 現在完了と時を表す副詞
次の文の下線部を訂正して、正しい英文にしなさい。
1) I’ve left my bag in the train yesterday.
2) Recently more and more people begin to use smartphones.
3) My sister has been ill in bed yesterday.
025「完了・結果」「経験」「継続」を表す過去完了形 / 「動作の継続」を表す過去完了進行形 / 2つの出来事の時間的な前後関係を表す過去完了形
( )内の語句のうち、正しいほうを選びなさい。
1) The last bus (has already left / had already left) when I reached the bus stop.
2) I (have been / had been) abroad three times before I was twenty.
3) Judy (has been living / had been living) in this country since last year. She’ll go back home in March.
4) He (was reading / had been reading) the novel for two hours before I called him.
5) I lost the watch which my uncle (bought / had bought) for me.
026「完了・結果」「経験」「継続」を表す未来完了形
次の文の下線部を訂正して、正しい英文にしなさい。
1) I finished my homework by the time the TV program begins.
2) I will see the movie five times if I go to see it again.
3) Jack has been sick in bed for two weeks by tomorrow.
027「今」に視点を置かない現在完了形
( )内のうち、正しいほうを選びなさい。
1) The game will begin when the players (have arrived / will have arrived).
2) Please wait here until I (have come / will have come).
3) Don’t drive a car when you (haven’t had / will haven’t had) enough sleep.
第5章 助動詞
028「能力・可能」を表すcan / be able to
( )内から正しいほうを選びなさい。
1) I (can / be able to) help you.
2) I (could / was able to) reserve two seats for the concert.
3) You will (can / be able to) ride a bicycle soon.
4) I (could / couldn’t) find the house key this morning.
029「許可・依頼」を表すcan
canに注意して、次の文を日本語に直しなさい。
1) Can I ask you a question?
2) You can use my bike if you need it.
3) Can you tell me the way to the station?
030「許可」を表すmay
mayに注意して、次の文を日本語に直しなさい。
1) “May I ask you a personal question?” “Sure.”
2) Students may not use these computers.
3) You may leave the classroom after the bell rings.
031「義務・必要」を表すmust / have to
must, have to に注意して、次の文を日本語に直しなさい。
1) I must get more exercise.
2) She had to get up early this morning.
3) You must not play video games all day long.
4) You don’t have to attend the meeting.
032「義務・当然の行動を表すshould / ought to /「忠告」を表すhad better
日本語に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) 今すぐ病院へ行くべきです。
You ( ) go to the hospital right now.
2) 先生に助言を求めたほうがいいな。
I ( ) better ask the teacher for advice.
3) 親にそんな口のきき方をすべきではない。
You ought ( ) ( ) speak to your parents like that.
4) あの失敗のことは考えるなよ。
You had ( ) ( ) think about that mistake.
033 can / could / may / might / will / would
助動詞に注意して、次の文を日本語に直しなさい。
1) Winter in Tokyo can be very cold.
2) You may feel some shaking when the plane takes off.
3) That will be his house. I can see his car in the garages.
034 must / can’t / should / ought to
助動詞に注意して、次の文を日本語に直しなさい。
1) This watch must be your father’s.
2) This cannot be the right bus. It’s going south.
3) He should win the race.
4) He ought to be tired after the tennis practice.
035「意志」・「習慣」を表すwill / would
will, wouldに注意して、次の文を日本語に直しなさい。
1) My father would often play catch with me.
2) When she was a little girl, she wouldn’t touch any animals.
3) I will solve this problem by myself.
4) My dog likes running in the field, but today she won’t get out of the house.
036「依頼」を表すwill / would / 相手の意向を尋ねるshall
will, shallに注意して、次の文を日本語に直しなさい。
1) Will you drive me home?
2) Shall I give you the concert ticket?
3) Shall we watch the baseball game on TV?
037 need・used toの用法
日本語の意味に合うように、( )内に適切な助動詞を下から選んで入れなさい。ただし、同じものを2度使わないこと。
1) 部屋をそうじする必要はありません。もう私がやりましたから。
You ( ) clean the room. I’ve already cleaned it.
2) 私が子供のころ、父はとてもがんこでした。
My father ( ) be very stubborn when I was a child.
3) スペインに住んでいたころはよく美術館に行ったものだ。
I ( ) often visit museums when I lived in Spain.
[used to / would / needn’t]
038「過去のことに関する推量」表す〈助動詞+have+過去分詞〉
( )内の語句のうち、正しいほうを選びなさい。
1) A: I missed the TV program last night.
B: My brother (may record / may have recorded) it.
2) A: They’re very late.
B: Yes, they (cannot / must) have lost their way; they didn’t have a map.
3) She (cannot / must) have won the game; she looked very sad.
039「過去の行為に対する非難や後悔」を表す〈助動詞+have+過去分詞〉
助動詞に注意して、次の文を日本語に直しなさい。
1) He should have gone to the doctor earlier.
2) You ought to have taken my advice.
3) I need not have got up early this morning.
040 may / mightを含む慣用表現
助動詞に注意して、次の文を日本語に直しなさい。
1) Jim would rather go by train than fly.
2) I would like to read your poems.
3) She may well be right.
4) We can’t find a taxi on this street. We might as well walk.
041 that節で用いられるshouldの用法
日本語の意味に合うように、( )内に適語を入れなさい。
1) 彼女があの光景を見てびっくりするのも当然だよ。
It’s ( ) that she ( ) be surprised at that sight.
2) 歯医者に行く必要があるよ。
It is ( ) that you ( ) see a dentist.
3) 彼はその会議を延期することを要求した。
He ( ) that the meeting ( ) be postponed.
第6章 受動態
042 受動態の基本形
( )内の動詞を適切な形にしなさい。
1) This window (break) by Jim yesterday.
2) These pictures (taken) by my wife last year.
3) This skirt (make) by my mother.
4) Magazines (sell) at the convenience store.
043 受動態の様々な形(助動詞使用・進行形・完了形)
( )内の動詞を適切な形にしなさい。
1) The wall will (paint) next week.
2) My car (fix) now.
3) The store (close) since last week.
4) Rare animals can (see) in the forest.
044 受動態の様々な形(否定文)
日本語に合うように、( )内に適語を入れなさい。
1) この写真は私の兄が写したものではありません。
This picture ( ) ( ) ( ) by my brother.
2) この箱は開けてはいけません。
This box must ( ) ( ) ( ).
045 受動態の様々な形(Yes/No疑問文 / 疑問詞を使った疑問文)
日本語の意味に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) この化石はあなたのお父さんによって発見されたのですか?
( ) this fossil ( ) by your father?
2) この鳥はどこでつかまえられたのですか?
( ) ( ) this bird ( )?
3) ラジオはだれによって発明されたのですか?
( ) was the radio ( ) ( )?
046 語順に注意する受動態
( )内の動詞を適切な形にしなさい。
1) The actress (ask) a lot of questions by the reporter yesterday.
2) He (call) Ken by everyone now.
3) The news (tell) to her by her aunt last night.
047 群動詞の受動態
( )内の群動詞を適切な形にしなさい。
1) The experiment (carry out) by the students last month.
2) The typhoon was approaching, so the game (put off).
3) When I was a child, a party (look forward to) by everybody.
048 say, believeなどの受動態
次の文を日本語に直しなさい。
1) It is known that she is an excellent pianist.
2) It was said that he was a son of a well-known actor.
049 受動態で表す動作と状態 / getを使った受動態
次の文を日本語に直しなさい。
1) The gate is already closed.
2) The gate is usually closed at five.
3) My glasses got broken while I was playing soccer.
050 注意すべき受動態の表現(前置詞に注意/心理状態を表す受動態)
日本語の意味に合うように、( )内に適語を入れなさい。
1) 彼はそのニュースを聞いてがっかりした。
He ( ) ( ) at the news.
2) 彼女は新しい仕事に満足している。
She ( ) ( ) with her new job.
3) 彼の祖父は戦争で命を落とした。、
His grandfather ( ) ( ) in the war.
第7章 不定詞
051 不定詞の名詞的用法
次の日本語の部分を不定詞を用いて英語にしなさい。
1) His ambition is (パイロットになること).
2) It is not easy(このレースに勝つこと).
3) Why did you decide(先生になること)?
052 不定詞の形容詞的用法
日本語に合うように、与えられた語句を並びかえて、英文を完成させなさい。
1) その老人には世話をしてくれる人が必要だ。
The old man needs (him / to / someone/ look after).
2) 私には今読む本がない。
I have (books / read / to / no) now.
3) 父はチェスをしてくれる人を見つけた。
My father found (with / play / someone / chess / to).
4) 彼女は上野駅で私と待ち合わせるという約束を破った。
She broke (meet / her promise / to / me) at Ueno Station.
053 不定詞の副詞的用法
次の文を日本語に直しなさい。
1) I went to the theater to buy a ticket.
2) My mother was very glad to receive a letter from you.
3) You were lucky to see the famous actor.
4) The bird flew away, never to return.
054 SVO+to不定詞
日本語の意味に合うように、与えられた語句を並べかえて、英文を完成させなさい。
1) 私の父は私がその自転車を買うことを許してくれた。
My father allowed (buy / me / the bicycle / to).
2) 警察は群衆を強制的にその広場から出させた。
The police forced (the square / the crowd / leave / to)
3) 彼は私に休みをとるように勧めた。
He advised (take / a / me / to / day off).
055 不定詞の意味上の主語
不定詞の意味上の主語を指摘して、全文を日本語に直しなさい。
1) It is difficult for me to solve the problem.
2) It was a mistake for the government to carry out the plan.
3) I want my father to stop drinking so much.
056 不定詞の否定語(副詞)の位置
日本語に合うように、与えられた語句を並べかえて、英文を完成させなさい。
1) 医者は私の父にたばこを吸わないようにと警告した。
The doctor warned (smoke / not / my father / to).
2) 姉は決して間食しないことにしている。
My sister makes it a rule (never / eat / to) between meals.
057 使役動詞・知覚動詞を使った表現
( )内の語句のうち、正しい方を選びなさい。
1) Let me (try / to try) it again.
2) I heard someone (shout / to shout) in the distance.
3) The boy was made (turn / to turn) off the TV by his mother.
4) I noticed a tall man (enter / to enter) the building.
5) I’ll get my father (buy / to buy) a new computer.
058 不定詞のさまざまな形
各組の文がほぼ同じ意味になるように、( )に適語を入れなさい。
1) It seems that you are interested in my success story.
You ( ) ( ) ( ) ( ) in my success story.
2) It seems that he told a lie.
He ( ) ( ) ( ) ( ) a lie.
3) It seems that the baby in that car is crying.
The baby in that car ( ) ( ) ( ) ( ).
4) I don’t want anyone to do it so carelessly.
I don’t want it ( ) ( ) ( ) so carelessly.
059 自動詞+to不定詞(happen/prove/turn/come/get+to不定詞)
日本語の意味に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) 私はたまたまその歌手のとなりに座った。
I ( ) ( ) ( ) next to the singer.
2) その絵はにせものであることがわかった。
The painting ( ) ( ) ( ) be a fake.
3) どうやって彼女と知り合いになったのですか。
How did you ( ) ( ) know her?
060 自動詞+to不定詞(be to不定詞)
次の文を日本語に直しなさい。
1) We are to meet at the art museum tomorrow.
2) Not an animal was to be seen in the desert.
3) You are to return the book to me by tomorrow.
061 不定詞の注意すべき用法(難易を表す形容詞+to 不定詞 / too … to不定詞 / … enough to不定詞 / so … as to不定詞 / so as to不定詞 / in order to不定詞)
日本語の意味に合うように、あたえられた語句を並べかえて、英文を完成させなさい。
1) 彼女とうまくやっていくのは難しい。
She is (hard / get along / to) with.
2) そのかばんは片手で運ぶには重ずぎる
The bag is (carry / too / to / heavy) in one hand.
3) 彼女はその講義を理解することができるくらいには賢かった。
She was (enough / understand / to / smart) the lecture.
4) その若い男の人は、勇敢にもおぼれている子供を救った。
The young man was (as / brave / so / save / to) the drowning child.
5) 私のいとこはその資格を取るために一生懸命勉強した。
My cousin studied hard (order / get / in / to / the license).
062 不定詞の注意すべき用法(疑問詞+to不定詞 / 独立不定詞 / 代不定詞)
日本語の意味に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) 今日何をすべきか教えてください。
Tell us ( ) ( ) do today.
2) どうやったらその計画を実行できるかが問題だ。
( ) ( ) put the plan into practice is the question.
3) 言うまでもないことだが、健康は富に勝る。
( ) ( ) ( ), health is above wealth.
4) 「このかばんを運ぶのを手伝っていただけますか。」「もちろん、よろこんで。」
“Could you help me with this bag?” “Sure, I’d be happy ( ).”
第8章 動名詞
063 動名詞の働き
( )内の動詞を適切な形にしなさい。
1) (Make) model cars is my hobby.
2) One American tradition is (eat) turkey on Thanksgiving Day.
3) I enjoy (read) books in the library.
4) Mike is fond of (watch) horror movies.
064 動名詞の意味上の主語と否定語の位置
日本語の意味に合うように、( )内に適合を入れなさい。
1) 私の母は、私の兄が写真家として働いていることを自慢に思っている。
My mother is proud of ( ) ( ) ( ) as a photographer.
2) あなたが私の部屋でたばこを吸うのが嫌です。
I don’t like ( ) ( ) in my room.
3) 私は食事の作法を知らないことに恥じ入っています。
I am ashamed of ( ) ( ) table manners.
065 動名詞のさまざまな形
日本語の意味に合うように、( )に適合を入れなさい。
1) 私は父に怒られることを恐れていました。
I was afraid of ( ) ( ) by my father.
2) ジェーンはその花びんを割ったことを認めました。
Jane admitted of ( ) ( ) the vase.
3) 私はその芝居の第一幕を見逃したことを後悔しています。
I regret ( ) the first act of the play.
066 動名詞を使った重要表現
日本語の意味に合うように、( )に適合を入れなさい。
1) 私は通信販売のカタログが届くのを楽しみに待っている。
I’m ( ) ( ) ( ) receiving the mail-order catalogue.
2) 私が勝ったという事実は否定できない。
( ) ( ) ( ) denying the fact that I was the winner.
3) 私はコーヒーを飲みたい気がする。
I ( ) ( ) ( ) a cup of coffee.
067 動名詞と不定詞(動名詞を目的語にする他動詞 / 不定詞を目的語にする他動詞)
( )内の語句のうち、正しいほうを選びなささい。
1) Have you considered (moving / to move) out of this country?
2) Sorry. I didn’t mean (offending / to offend) you.
3) He refused (to come / coming) with us.
4) May I suggest (taking / to take) a vote on this matter?
068 動名詞と不定詞(目的語が動名詞と不定詞で意味が異なる他動詞 / 目的語が動名詞でも不定詞でもよい他動詞 / 動名詞と不定詞の使い分けに注意すべき表現)
日本語の意味に合うように、( )内の語句のうち、正しいほうを選びなさい。
1) 間違いを見つけてみなさい。
Try (finding / to find) the error.
2) ジムは試しにベッドのかわりにふとんで寝てみた。
Jim tried (to sleep / sleeping) on a futon instead of a bed.
3) もう雨はやみましたか?
Have it stopped (raining / to rain) yet?
第9章 分詞
069 名詞を修飾する分詞(限定用法)
( )内の動詞を適切な分詞の形に変えなさい。
1) She was shocked at the (break) guitar.
2) There is a cat (sleep) on the roof.
3) This is a picture (paint) by Picasso.
4) She received (disappoint) news.
070 補語になる分詞(叙述用法) (SV+分詞)
( )内の動詞を適切な分詞の形に変えなさい。
1) She kept (cry) in front of her mother’s grave.
2) The treasure lay (hide) in the cave.
3) We stood (talk) for about an hour.
071 補語になる分詞(叙述用法) (SVO+分詞)
( )内の動詞を適切な分詞の形に変えなさい。
1) When I came home, I found my wife (sleep) on the sofa.
2) Don’t leave the door (unlock).
3) I want this problem (solve) by tomorrow.
072 have+O+分詞
日本語の意味に合うように、( )に適合を入れなさい。
1) 彼は自分の犬を浜辺で走らせておいた。
He ( ) his dog ( ) on the beach.
2) 私はローマでパスポートを盗まれた。
I ( ) my passport ( ) in Rome.
3) 私は昨日、自転車を修理してもらった。
I ( ) my bicycle ( ) yesterday.
073 see+O+分詞
日本語の意味に合うように、( )内に適語を入れなさい。
1) 私は人ごみの中で自分の名前が呼ばれるのを聞いた。
I ( ) my name ( ) in the crowd.
2) パットは、女の子が川で泳いでいるのを見た。
Pat ( ) a girl ( ) in the river.
3) 私はだれかがどあをノックしているのを聞いた。
I ( ) someone ( ) on the door.
074 分詞構文 (分詞構文の働き / 分詞構文が表す内容)
次の文を日本語に直しなさい。
1) Hiking in the forest, we came across a bear.
2) Having nothing to do, I went to bed early.
3) I drive to the office every morning listening to the radio.
4) He managed to solve the problem, supported by his classmates.
075 分詞構文 (否定の位置)
指定された動詞を使って、日本語の意味に合うように( )に適語を入れなさい。
1) 時間がなかったので、今朝は新聞を読まなかった。(have)
( ) ( ), I didn’t read the newspaper this morning.
2) 私の忠告に従わなかったので、息子はかぜをひいた。(take)
( ) ( ) my advice, my son caught a cold.
076 分詞構文の応用 (分詞構文のさまざまな形)
日本語に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) お金を全部使ってしまったので、彼女は渋谷から家まで歩いた。
( ) ( ) all her money, she walked home from Shibuya.
2) サラダと一緒に食べると、このパスタはおいしい。
This pasta is delicious ( ) ( ) with a salad.
077 分詞構文の応用 (独立分詞構文)
次の文を日本語に直しなさい。
1) It being very hot last night, I couldn’t sleep well.
2) Generally speaking, Japanese people work hard.
3) Judging from her elegant dress, she must be going to the party.
078 付帯状況を表すwith+(代)名詞+分詞
日本語の意味に合うように、与えられた語句を並びかえて、英文を完成させなさい。ただし、不要な語が1語ある。
1) 彼は目を閉じたまま、いすに座っていた。
He was sitting in the chair ( his eyes / closed / with / closing ).
2) 彼はエンジンをかけたまま車から出た。
He got out of the car ( run / with / the engine / running ).
079 分詞を使った表現
日本語の意味に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) ビンの中に牛乳はほとんど残っていなかった。
There ( ) little milk ( ) in the bottle.
2) 日曜日にはよく川に釣りに行った。
I went ( ) ( ) the river on Sundays.
3) 彼の家は、わけなく見つかった。
We ( ) no trouble ( ) his house.
第10章 比較級
080 原級を使った比較
次の文を日本語にしなさい。
1) This camera is as small as that one.
2) Jenny has three times as many as books as Tom
3) I cannot read English as fast as you.
4) Write your name as nearly as you can.
081 比較級を使った比較
日本語に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) 私の弟は私よりも上手に絵を描きます。
My brother draws pictures ( ) ( ) me.
2) 私の家はその野球選手の家よりもずっと小さい。
My house is ( ) ( ) ( ) the baseball player’s house.
3) この問題はその問題ほど難しくない。
This question is ( ) hard ( ) that one.
082 最上級を使った比較
日本語の意味に合うように、与えられた語句を並びかえて文を完成させなさい。
1) これはロンドンでもっとも古い教会です。
This is ( the / London / church / in / oldest).
2) ここはこの町でもっともよいフランス料理店の1つです。
This is ( French restaurants / of / the / best / one ) in this town.
3) メルボルンはオーストラリアで2番目に大きな都市です。
Melbourne is ( in / largest / the / city / second ) Australia.
4) 彼はこの劇団で抜群にうまい役者です。
He ( best / is / by far / actor / the ) in this theater company.
083 原級・比較級を使って最上級の意味を表す
次の文と同じ意味になるように、原級と比較級を用いた3つの文をつくりなさい。
Ted is the tallest boy in this class.
084 原級を用いたさまざまな表現
日本語の意味に合うように、与えられた語句を並べかえて英文を完成させなさい。
1) この本は歴史に関するエッセイというよりは、むしろ小説だ。
This book is ( a historical essay / not so / as / a novel / much ).
2) その事故で100人もの人がけがをした。
( one hundred / as / as / people / many ) got injured in the accident.
3) 彼はあいかわらずだれにでも友好的だ。
He is ( friendly / as / as / to / everyone ) ever.
4) その仕事は終わったも同然だ。
The work is ( finished / good / as / as ).
085 比較級を用いたさまざまな表現(1)
次の文を日本語に直しなさい。
1) She bought the cheaper of the two sweaters.
2) I like her all the better for her kindness.
3) It is getting warmer and warmer.
4) The more he practiced, the better he played the piano.
086 比較級を用いたさまざまな表現(2)
次の文を日本語に直しなさい。
1) I don’t want to read the novel, still less buy it.
2) This computer is technically inferior to that model.
3) She wanted to receive a higher education.
4) You ought to know better than to play with fire.
087 noを使った比較表現
次の文を日本語に直しなさい。
1) This car is no less fast than that one.
2) He speaks no less than five languages.
3) There were no more than three passengers on the bus.
088 最上級を用いたさまざまな表現
次の文を日本語に直しなさい。
1) The fastest train cannot reach Osaka before noon.
2) This lake is deepest here..
3) I have at most twenty minutes to solve this problem.
4) You should be back by eight o’clock at the latest.
第11章 関係詞
089 whoとwhich
次の文の( )に適切な関係代名詞を入れなさい。
1) I know a man ( ) has ten cats in his house.
2) I visited a church ( ) was built about 200 years ago.
090 whomとwhich
次の文の( )に適切な関係代名詞を入れなさい。
1) She’s talking with the boy ( ) lives next door.
2) That is the woman ( ) I saw in the restaurant yesterday.
3) The ring ( ) my wife liked best was very expensive.
091 whose
次の文の( )に適切な関係代名詞を入れなさい。
1) I have a friend ( ) is a lawyer.
2) This is the woman ( ) purse has been stolen.
3) I know a musician ( ) son became the number-one hit this year.
4) The bicycle ( ) front tire is flat is mine.
092 that
( )内の関係代名詞から、適切でないものを一つずつ選びなさい。
1) This is a letter from a friend ( who / that / whose ) lives in Ireland.
2) Did you buy the CD ( who / which / that ) Jack recommended to us?
3) He is the man ( whose / that ) daughter is a famous painter.
093 前置詞と関係代名詞
( )に適切な関係代名詞を入れなさい。
1) I found a box in ( ) there were some pretty dolls.
2) This is the cafeteria in ( ) I met my husband for the first time.
3) I know the girl with ( ) you were talking.
094 what
日本語の意味に合うように、whatを使って英文を完成させなさい。
1) それは私の言ったことではない。
That is not ( ).
2) 君にはちょっと休息が必要だ。
( ) is some rest.
3) 私にとって難しいことは、コンピュータの操作のしかただ。
( ) for me is how to operate a computer.
095 関係代名詞の継続用法
次の文を日本語に直しなさい。
1) He has a daughter, who lives in London.
2) We went to the party, which was boring.
3) He said Nicky had bought a diamond ring, which was true.
4) He passed the entrance examination, which surprised all his friends.
096 関係副詞 (where, when, why, how)
次の( )に適切な関係副詞を入れなさい。ただし、where, when, why, howを一度ずつ使うこと。
1) Chicago is a city ( ) it is very cold in winter.
2) I can’t think of any reason ( ) they gave up the plan.
3) There are times ( ) everyone needs to be alone.
4) This is ( ) I finished the work in one day.
097 関係副詞の継続用法
次の文を日本語に直しなさい。
1) He was taken to the police station, where he told the truth.
2) Someone broke into the house in the middle of the night, when the alarm rang.
098 複合関係詞
日本語の意味に合うように、( )に適切な関係詞を入れなさい。
1) この事故に責任のある人はだれでも処罰されるだろう。
( ) is responsible for this accident will be punished.
2) どこでも好きなところに座りなさい。
Sit ( ) you want.
3) ぼくは消しゴムを2つ持っている。どちらでも好きなほうを使っていいよ。
I have two erasers. You use ( ) you like.
099「譲歩」を表す複合関係詞
日本語の意味に合うように、( )に適切な関係詞を入れなさい。
1) 何が起ころうとも、私のことをあてにしていいよ。
( ) happens, you may count on me.
2) だれが会いに来ても、私は外出中だと伝えてください。
( ) comes to see me, tell them I’m out.
3) どこにいようとも、私はいつもあなたのことを思っています。
( ) I am, I am always thinking of you.
4) 私たちの犬はどんな遠くまで行っても、必ず家に帰ってくる。
( ) far our dog goes, he always comes home.
100 関係代名詞の働きをするasとthan
( )にasかthanを入れなさい。
1) These books are written in such easy English ( ) beginners can understand.
2) There were more people at the party ( ) I expected.
101 関係代名詞のさまざまな用法
次の文を日本語に直しなさい。
1) In England there are many sayings the meanings of which I can’t understand.
2) While I was in Paris, I got to know a lot of people, most of whom were Japanese.
3) He is trying to make a list of all the songs which he thinks are popular among young people.
4) His success is an example of what is called the American Dream.
5) She is not what she was ten years ago.
6) Facts are to the scientist what words are to the poet.
102 関係形容詞
次の文を日本語に直しなさい。
1) I gave the child what little money I had with me.
2) Lend me what magazines you have about diving.
3) The doctor told her to take a few days’ rest, which advice she didn’t follow.
第12章 仮定法
103 ifを使った仮定法 (直接法と仮定法/仮定法過去/仮定法過去完了/主節時制相違)
日本語の意味に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) 明日晴れたら、ピクニックに行きます。
If it ( ) fine tomorrow, we’ll go on a picnic.
2) 彼女の電話番号を知っていたら、電話するんだが。
If I ( ) her phone number, I ( ) call her.
3) もし、宇宙人と話すとしたら何を言う?
What ( ) you say if you ( ) with an alien?
4) もし私がお金持ちだったら、そのお屋敷が買えるのに。
If I ( ) rich, I ( ) buy the mansion.
5) もし、君がもう少し注意深ければ、そんな間違いはしなかっただろうに。
If you ( ) ( ) a little more careful, you ( ) not ( ) ( ) such a mistake.
6) もっと早起きしていたら、彼女は学校に間に合っただろうに。
She ( ) ( ) ( ) in time for school if she ( ) ( ) up earlier.
7) もしその電車に間に合っていれば、私は、そのパーティーに出席しているのに。
If I ( ) ( ) the train, I ( ) ( ) present at the party.
104 wishやas ifの後の仮定法
日本語の意味に合うように、( )内の語を適切な形に変えなさい。
1) 彼の自宅の住所を知っていればなあ。
I wish I ( know) his home address.
2) 彼女は私にうそをつかなければよかったのに。
I wish she ( not tell ) a lie to me.
3) 彼女は、彼といっしょにいることができたらと思った。
She (wish) she could stay with him.
4) 君はまるでスターであるかのようにふるまう。
You behave as if you (are) a star.
5) 彼女はまるで私に以前一度も会ったことがないかのような顔つきだった。
She looked as though she (has) never (met) me before.
105 未来のことを表す仮定法
次の文を日本語に直しなさい。
1) What would happen if he were to tell others about our secret?
2) If you should be unable to come, please let me know soon.
106 ifが出てこない仮定法
日本語の意味に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) その本が日本語で書かれていたら、私は楽に読めただろうに。
( ) the book ( ) ( ) in Japanese, I would have read it easily.
2) もしも私が遅れるようなことがあれば、待たずに出発してください。
( ) I be late, please start without me.
3) もう少し暖かければ、散歩に出かけるのだが。
( ) it a little warmer, we would go out for a walk.
4) 彼が踊っているのを見れば、君は笑い出すだろう。
( ) see him dancing, you would burst out laughing.
5) コンピュータがなければ、彼はまったく仕事ができないでしょう。
( ) ( ) the computer, he couldn’t do his work at all.
6) もう少し運があれば、彼女は試合に勝つことができただろうに。
( ) a little more luck, she could have won the game.
7) スパイだったら、本当の名前を言うことはないだろう。
A secret agent ( ) never tell you his real name.
8) 2年前だったら、あなたのプロポーズに応じていたことでしょう。
Two years ago, I ( ) ( ) accepted your proposal.
107 仮定法を使った慣用表現
次の文を日本語に直しなさい。
1) If it were not for air, nothing could live on the earth.
2) If it had not been for your help, we couldn’t have finished the job.
3) It’s about time you started working
4) If only I had seen the film!
108 仮定法を使ったていねいな表現
次の文を日本語に直しなさい。
1) Would it be rude if I opened the present now?
2) Would you mind if I smoked here?
3) I was wondering if you could pass me the sugar.
第13章 疑問詞と疑問文
109 疑問代名詞
( )に入れるのに適切な疑問詞を下から選びなさい。
1) “( ) are you thinking about? “Well, nothing in particular.”
2) “( ) is this new car? “It’s John’s.”
3) “( ) did he take to the zoo?” “He took his son there.”
4) “( ) of these T-shirts do you want?” “The blue one.”
5) “( ) went to the party with her?” “Her father did.”
[ Who / Whose / Whom / What / Which]
110 疑問形容詞
疑問詞に対する答えとして適切なものをA)〜D)の中から一つずつ選びなさい。
1) Whose camera is this?
2) What kind of car did you buy?
3) What color do you like?
4) Which shirt do you like?
A) The red one in the middle.
B) I like green.
C) It’s my sister’s.
D) A compact.
111 疑問副詞
( )に適切な疑問詞を入れなさい。
1) “( ) are you going?” “To the park.”
2) “( ) did he change his mind?” “Because his mother gave him some good advice.”
3) “( ) much did you pay for the book?” “Fifteen dollars.”
4) “( ) will you be back?” “At ten.”
5) “( ) was the show?” “Oh, it was great.”
112 疑問詞と前置詞
日本語の意味に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) だれを待っているの?
( ) are you waiting ( )?
2) だれにその小包を送るつもりなのですか?
( ) are you going to send the parcel ( )?
113 間接疑問
次の疑問文を、指定された書き出しに続く間接疑問文にしなさい。
1) Why did ‘t you come? (You must tell me …)
2) What kind of music do you like? (I want to know …)
3) When is she going to leave? (The problem is …)
114 否定疑問文
日本語の意味に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) 「あなたはあのバンドのメンバーではないのですか。」「メンバーですよ。」
“( ) you a member of that band?” “( ), I am.”
2) 「その場所に行かなかったの?」「行かなかったよ。」
“( ) ( ) visit that place?” “( ), I didn’t.”
3) 「彼女は日本語を話せないの?」「いいや、話せるよ。」
“( ) ( ) speak Japanese?” “( ), she ( ).”
115 疑問文への答え方
疑問文に対する答えとして適切なものをA)からD)から1つずつ選びなさい。
1) What do you think this is?
2) Do you know what this is?
3) Do you mind if I smoke here?
4) Can I use your bathroom?
A) Sure. Go ahead.
B) It’s a kind of toy.
C) No. I have no idea.
D) No, I don’t mind.
116 付加疑問文
( )に適語を入れて、付加疑問文を作りなさい。
1) These flowers smell sweet, ( ) ( )?
2) There is no one in the room, ( ) ( )?
3) You’ve already made up your mind, ( ) ( )?
117 修辞疑問文/平叙文疑問文/聞き返し疑問文/応答疑問文
日本語の意味に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) そんなことをしてなんの役に立つんだろうか。
( ) is the use of doing such a thing?
2) 「専攻は哲学です。」「何を専攻しているって?」
“I’m majoring in philosophy.” “ You’re majoring in ( )?”
3) 「ジャックとべティが結婚したんだってさ。」「へえ、そうなの。」
“Jack and Betty got married.” “Oh, ( ) they?”
118 疑問文の慣用表現
日本語の意味に合うように、( )の語句を並べかえて英文を完成させなさい。
1) 何のためにここに来たの?
What ( come / you / for / here / did )?
2) 明日の天気はどうなりそうですか。
What’s ( like / to / going / be / the weather ) tomorrow?
3) どうして彼女の家に行ったのですか。
( went / come / to / how / you ) her house?
4) イタリア料理の店で夕食を食べるのはどうですか。
( eating / how / dinner / about ) at an Italian restaurant?
第14章 否定
119 not / never / no
日本語の意味に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) ティムは兄からではなく、いとこから手紙を受け取った。
Tim received a letter from his cousin, ( ) from his brother.
2) 私には衣類を洗たくする時間がない。
I have ( ) time to wash my clothes.
3) だれもこの絵には興味をもたないだろう。
( ) will be interested in this picture.
4) 私は彼にうそをつくなと言った。
I told him ( ) to tell a lie.
5) 私は決して朝食を食べない。
I ( ) eat breakfast.
120 否定語の位置
次の文を否定文にしなさい。
1) I think he is a good violinist.
2) I hope she will accept his offer.
121 節の代わりをするnot
日本語の意味に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) 「明日は雨が降るだろうか。」「降らないといいね。」
“Will it rain tomorrow?” “I ( ) ( ).”
2) 「彼はよくなるだろうか。」「よくならないとおもうよ。」
“ Will he get well?” “I’m ( ) ( ).”
122 準否定語
( )内から正しいほうを選びなさい。
1) He ( hardly / seldom) goes out on Sundays.
2) I could ( hardly / seldom ) understand the lecture.
3) They had ( few / little ) snow in Osaka.
4) He is a man of ( few / little ) words.
123 部分否定・二重否定
次の文を日本語に直しなさい。
1) Not all of the members attended the meeting.
2) None of the members attended the meeting.
3) He doesn’t always buy that weekly magazine.
4) I’m not quite satisfied with your plan.
5) It’s not impossible to swim across this river.
124 否定の慣用表現
日本語の意味に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) 彼のおかしな髪型を見て、笑わずにはいられなかった。
I ( ) ( ) laughing at his funny hairstyle.
2) 海で泳ぐ時はいくら注してもしすぎることはない。
You ( ) be ( ) careful when you swim in the sea.
3) 健康を損なって初めてそのありがたさがわかる。
We ( ) appreciate the blessing of health ( ) we lose it.
4) 私が食卓につくとすぐに電話が鳴った。
I had ( ) sat down at the table ( ) the telephone rang.
5) 彼は1日中テレビばかり見ている。
He does ( ) ( ) ( ) TV all day long.
125 否定語を使わない否定表現
日本語の意味に合うように、( )の語句を並べかえて英文を完成させなさい。
1) 彼はあまりに眠かったので、宿題ができなかった。
He was ( sleepy / do / too / to ) his homework.
2) 彼女は決して約束を破るような人間ではないでしょう。
She would be the ( person / break / to / last / her promise ).
3) 彼の話は決して退屈ではなかった。
His story ( but / was / anything / boring ).
4) 彼の新しい小説は、とてもじゃないがおもしろいとは言えない。
His new novel ( from / is / far / interesting ).
5) その町を訪れる時は、私は必ず彼と会います。
I ( meet / to / fail / him / never ) when I visit that town.
第15章 話法
126 直接話法と間接話法の形
日本語の意味に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) 彼はその時、次のコンサートの準備をしていると言った。
He ( ) me that ( ) ( ) preparing for his next concert ( ).
2) 私の母は、その前の日に私のスニーカーを洗ったと、私に言った。
My mother told me that ( ) ( ) washed ( ) sneakers the day before.
3) ジョンは、彼の娘が次の日、空港で私たちを出迎えると言った。
John said that ( ) daughter ( ) meet us at the airport the ( ) day.
127 平叙文以外の間接話法 (疑問詞疑問文・Yes/No疑問文・命令文)
日本語の意味に合うように、( )に適語をいれなさい。
1) 彼は私に、私がそのロックグループのファンなのかと尋ねた。
He asked me ( ) ( ) ( ) a fun of the rock group.
2) その少年は私に、どこでその本を見つけることができるのかと尋ねた。
The boy ( ) me where I ( ) find the book.
3) その女性は息子に、彼はどうしてそんなことを言ったのかと尋ねた。
The woman ( ) her son ( ) ( ) ( ) said such a thing.
4) 彼は息子に新聞を持ってくるように言った。
He ( ) his son ( ) ( ) ( ) the newspaper.
5) 先生は少年たちにホールで走らないようにと言った。
The teacher ( ) the boys ( ) ( ) ( ) in the hall.
6) 彼女は私にいっしょに来るように頼んだ。
She ( ) me ( ) ( ) ( ) ( ).
128 提案文・勧誘文・感嘆文
日本語の意味に合うように、( )に適語をいれなさい。
1) 彼は私に、その辞書を買うように助言した。
He ( ) ( ) ( ) buy that dictionary.
2) 彼は弟にキャッチボールをやろうと提案した。
He ( ) to his brother that they play catch.
3) 彼女は、私のバイクはなんてうるさいのかと文句を言った。
She ( ) ( ) how noisy my motorcycle was.
4) 少年たちは、勝ったと喜んで叫んだ。
The boys cried out in ( ) they ( ) ( ).
129 従属節を含む文 / and, butなどで結ばれた文 / 種類の異なる文
次の文を間接話法で表現しなさい。
1) Bill said, “I don’t know how the accident will affect the economy.”
2) Betty said to me, “I have a headache, but I will go to the movie with you.”
3) I said to the salesperson, “I like this type of shirt. Do you have a large size?”
第16章 名詞構文・無生物主語
130 名詞構文
次の文を日本語に直しなさい。
1) We got to the station before the arrival of her train.
2) She denied her knowledge of the fact.
3) I understood her anxiety about her grandmother’s heart operation.
4) Let’s have a walk in the park.
5) My father is a fast walker.
131 無生物主語
日本語の意味に合うように、( )の語句を並べかえて英文を完成させなさい。
1) あなたは、どうして彼があのレスラーを負かすことができると思ったのですか。
( made / think / what / you ) he could defeat that wrestler?
2) 急用のため、昨日は来れなかった。
( from / kept / me / urgent business ) coming yesterday.
3) このグラフから、物価の急騰は明らかです。
( a sharp rise / the / shows / graph ) in prices.
4) 彼女の表情から、そのプレゼントが気に入っていないことがわかった。
( she / her expression / that / showed ) was not pleased with the present.
5) 数分歩くと、私たちは湖に出た。
( brought / a few minutes’ walk / to / us ) the lake.
第17章 強調・倒置・挿入・省略・同格
132 特定の語句をつけ加える強調 / 同じ語の繰り返しによる強調
日本語の意味に合うように、( )に適切な語句を与えられた語群から選んで入れなさい。
1) 私はたしかにメアリーにスカーフをあげました。
I ( ) give a scarf to Mary.
2) いったい全体どうしてそんなことをしているんだい?
Why ( ) are you doing such a thing?
3) 私たちがトーナメントで優勝する可能性は少しもないだろう。
There will be no chance ( ) of our winning the tournament.
4) 彼は同じジョークを何度も何度も言う。
He tells the same jokes ( ).
[ did / whatever / on earth / again and again ]
133 強調構文
次の文を強調構文を使って、( )内の語句を強調する英文に書き換えなさい。
Beth teaches music at the university.
1) (Beth)
2) (music)
3) (at the university)
134 関係詞などを使った強調
日本語の意味に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) 彼に欠けているのは、知識ではなく経験だ。
( ) he is lack in ( ) not knowledge but experience.
2) このボタンを押すだけでいいのです。
( ) you have to do ( ) ( ) this button.
135 倒置
( )の語句をならべかえて英文を完成させなさい。
1) Never ( failed / I / have / to watch the TV program ).
2) No ( he / other mistake / did / make ).
3) Away ( the bank robber / ran ).
4) Amazing ( the show / was / at the Mirage Hotel in Las Vegas ).
136 挿入
次の文を日本語に直しなさい。
1) The concert was, in the end, called off.
2) The book, to my surprise, sold well also in Japan.
3) This experiment, I’m afraid, is a failure.
137 省略
次の文で省略できる部分を指摘しなさい。
1) Mr. Jones wasn’t angry, but Ms. Smith was angry.
2) You can eat this pudding if you want to eat it.
3) Did you visit Hollywood while you were traveling in the United States?
138 同格
次の文を日本語に直しなさい。
1) Carter, a friend of mine, graduated from Oxford University.
2) My son is pleased with his name of Daisuke.
3) We heard the news that a thief had broken into Bill’s house.
第18章 名詞
139 普通名詞・集合名詞・物質名詞・抽象名詞・固有名詞の用法
( )内の語句のうち、正しいほうを選びなさい。
1) (A freedom / Freedom) is as important as equality.
2) (Wine is / Wines are) made from grapes.
3) The Japanese are (a hardworking people / hardworking peoples).
4) He drank (three cups of coffee / three cup of coffees).
5) You must write in (ink / an ink), not with (pencil / a pencil).
140 数えられない名詞を普通名詞として使う
( )内の語句のうち、正しいほうを選びなさい。
1) I will never forget your many (kindness / kindnesses).
2) You must not throw (stone/stones) in the park.
3) I want to be (Edison/an Edison).
4) The bus (fare/fee) is 210 yen.
141 規則変化・不規則変化
次の名詞の複数形を書きなさい。
1) pencil 2) city 3) foot 4) woman
5) Japanese 6) passer-by 7) box 8) child
142 複数形の意味と用法
下線の語句の意味に注意して、次の文を日本語に直しなさい。
1) It is bad manners to make a noise when you eat soup.
2) We got to know each other during our college days.
3) I changed trains for Nara at Kyoto.
143 所有格・B of Aの形を用いて所有を表す
次の文の必要な語を所有格に直して、正しい英文にしなさい。
1) I borrowed Henry motorcycle yesterday.
2) It is ten minutes walk to the museum.
3) My sister sometimes stays at our grandmother.
第19章 冠詞
144 冠詞の働き
次の文の( )に適切な冠詞を入れなさい。無冠詞にするのが正しいときには×を入れなさい。
1) There is ( ) apple on the table.
2) I ate a slice of cake. ( ) cake was delicious.
3) All living things live in ( ) nature.
4) My daughter went to ( ) bed at ten last night.
145 不定冠詞の用法
必要なところにaまたはanを入れて、正しい英文にしなさい。
1) I bought mountain bike yesterday.
2) There are 60 minutes in hour.
3) My father works five days week.
146 定冠詞の用法
必要なところにtheを入れて、正しい英文にしなさい。
1) Do you mind if I open window?
2) We are paid by week.
3) Can you play guitar?
4) I want to travel around world some day.
147 無冠詞になる場合
文中の不要な冠詞に×をつけなさい。
1) He filled the glass with the milk.
2) She went to the post office by a bicycle.
3) We don’t have to go to the school on Sundays.
4) Let’s play the baseball in the park.
148 冠詞の位置
必要なところにa / an / theのいずれかを入れて、正しい英文にしなさい。
1) What nice handkerchief you have!
2) I have never seen so big airplane.
3) She gave me such interesting book.
4) Has he spent all money I gave to him?
第20章 代名詞
149 人称代名詞(格変化/ばくぜんと「人々」を指すyou/they/we / 所有代名詞)
次の文の太字を適切な代名詞に変えなさい。
1) I bought a pair of shoes for my son. My son was pleased with them.
2) Mike and I are good friends. Mike and I made the model plane in two days.
3) Your room is as large as my room.
4) I borrowed a bicycle from Bob. Bob’s bicycle was nice.
150 人称代名詞(再帰代名詞の再帰用法 / 強調用法)
日本語の意味に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) あなた自身が私にそう言ったのよ。
You told me so ( ).
2) 私たちはパーティーで楽しく過ごした。
We enjoyed ( ) at the party.
151 itの用法
次の文の下線部のitが指している語句を答えなさい。
1) I have lost my handkerchief. I bought it only yesterday.
2) It is difficult to win the race.
3) I think it necessary that you should do the homework by yourself.
152 指示代名詞
次の文を日本語に直しなさい。
1) The city library is a long way from here. That is the problem.
2) The population of China is much larger than that of Japan.
153 不定代名詞(one / another / the other / others)
( )内の語句のうち、正しいほうを選びなさい。
1) “Do you have a red pen?” “Yes, I have (it / one).
2) I have this kind of wallet. Please show me (another / other).
3) Hold the racket in one hand and the ball in (another / the other).
4) We have four children. One is a college student, and (others / the others) are high school students.
154 不定代名詞(some / any)
( )内にsomeかanyのいずれかを入れて、英文を完成させなさい。
1) If there is ( ) milk left, could I drink ( )?
2) I’d like ( ) information about the trip.
3) I haven’t met ( ) of her family yet.
155 不定代名詞(both / either / neither/ all / none / each / someone / everything)
( )内の語のうち、正しいほうを選びなさい。
1) I have two pretty birds and I like (all / both) of them.
2) (No / None) of the ten girls watched the TV drama last night.
3) My uncle gave candies to (each / every) of us.
4) I have (everything / something) to do today.
第21章 形容詞
156 形容詞の用法
( )内の語句のうち、正しいほうを選びなさい。
1) China has ( a large population / large a population ).
2) Please give me ( hot something / something hot ) to drink.
3) Look at the ( sleeping / sleep ) baby.
4) They caught the bear ( alive / live ).
5) My son was taller than all the ( boys present / present boys ).
157 分詞形容詞
( )内の語のうち、正しいほうを選びなさい。
1) It’s so ( bored / boring ) to spend the weekend alone.
2) We were very ( shocked / shocking ) to hear the news.
158 主語に注意すべき形容詞 / 可能性・確実性を表す形容詞 / such
( )内の語句のうち、正しいほうを選びなさい。
1) He is ( likely / possible ) to succeed as a singer.
2) It is ( sad / sorry ) to see him resign.
3) It is ( sure / certain ) that he will win the election.
4) We can’t stay home on ( a such nice day / such a nice day ).
159 数量を表す形容詞
( )内の語句のうち、正しいほうを選びなさい。
1) Taking too ( much / many ) salt is not good for your health.
2) She had ( a few / a little ) friends in New York City.
3) This town doesn’t have ( few / many ) parks.
第22章 副詞
160「様態」「場所」「時」「頻度」「程度」を表す副詞
( )内の語句のうち、正しいほうを選びなさい。
1) Bob opened ( carefully the box / the box carefully ).
2) She ( almost / always ) goes to school by bicycle.
3) I’m going to live ( in Paris next year / next year in Paris).
4) My sister is traveling ( in abroad / abroad ) now.
161 文を修飾する副詞
副詞が何を修飾しているのか考え、次の文を日本語に直しなさい。
1) She lives happily with her grandchildren.
2) Happily, the typhoon didn’t approach Japan.
162 注意すべき副詞の形と意味
( )内の語句のうち、正しいほうを選びなさい。
1) Mayumi is sometimes ( late / lately ) for school.
2) I can ( hard / hardly ) believe the news.
3) The boy ( near / nearly ) fell into the river.
163 very/much/ago/before/already/yet/still/too/either/neither
( )内の語のうち、適切なほうを選びなさい。
1) I met him two weeks ( ago / before ).
2) This is a ( very / much ) interesting novel.
3) She didn’t go to the party, and I didn’t, ( too / either ).
4) I haven’t received the card ( yet / already ).
164 so
日本語の意味に合うように、与えられた語句を並べかえなさい。
1) 「ナンシーはパーティーに来るの?」「ええ、たぶん。」
“Is Nancy coming to the party?” “( so / guess / I ).”
2) 私は昨日学校に遅刻したが、兄もそうだった。
I was late for school yesterday, and ( my brother / was / so ).
165 2つの文の論理関係を表す副詞
( )内の語のうち、正しいほうを選びなさい。
1) Let’s take a taxi. It’s getting dark. ( Besides / Nonetheless ), it’s starting to rain.
2) I tried hard to solve the problem. ( However / Therefore ), I couldn’t.
第23章 前置詞
166 at / in / on
( )内の前置詞から、正しいものを選びなさい。
1) I saw your father standing ( at / in / on ) the bus stop.
2) I usually get up ( at / in / on ) ten ( at / in / on ) Sundays.
167 from / to / for
日本語の意味に合うように、( )に適切な前置詞を入れなさい。
1) 私たちはパリからロンドンまで飛行機で飛んだ。
We took the plane ( ) Paris ( ) London.
2) 私はジュリアのためにダイヤモンドの指輪を買った。
I bought a diamond ring ( ) Julia.
3) 冬休みのあいだにこの本を読んでみたら?
Why don’t you read this book ( ) winter vacation?
168 of / by / until / with
日本語の意味に合うように、( )に適切な前置詞を入れなさい。
1) 彼は18歳で両親から独立した。
He became independent ( ) his parents at the age of eighteen.
2) 突然、知らない人から話しかけられた。
Suddenly, I was spoken to ( ) a stranger.
3) 父は8時には家に帰っているでしょう。
My father will come home ( ) eight o’clock.
4) トムはナイフでそのロープを切った。
Tom cut the rope ( ) a knife.
169 about / after / before / along / across / through / around / in front of / behind / opposite / into / out of / onto / over / under / above / below / between / among
日本語の意味に合うように、( )に適切な前置詞を入れなさい。
1) この川は森を抜けて、海へ注いでいます。
This river runs ( ) the forest and flows into the sea.
2) その家の裏には、きれいな庭があった。
There was a beautiful garden ( ) the house.
3) マイクの点数は平均より下だった。
Mike’s score was ( ) average.
4) 子どもたちがウサギのまわりに集まった。
The children gathered ( ) the rabbit.
5) 私は松林の中に小さな小屋を見つけた。
I found a small cabin ( ) the pine trees.
170 群前置詞
日本語の意味に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) 病気のため、彼は旅行をキャンセルしなければならなかった。
He had to cancel the trip ( ) ( ) ill health.
2) 家にいないで、外に出よう。
Let’s go out ( ) ( ) staying home.
第24章 接続詞
171 等位接続詞の用法(and, but, or, nor, so, for)
日本語に合うように、( )内のうち、正しいほうを選びなさい。
1) 彼は野球選手であるだけではなく、フットボールの選手でもある。
He is not only a baseball player ( and / but ) also a football player.
2) 寒くなってきた。それで私たちは家に帰った。
It was getting colder, (so / for) we went home.
3) パーティーにいったほうがいいよ。そうしないと彼女に会う機会を逃してしまう。
You should go to the party, ( and / or ) you will miss the chance to see her.
4) 私の兄も私も早起きだ。
Bothe my brother ( and / nor ) I are early risers.
5) 私は有名でないし、なりたいとも思わない。
I’m not famous, ( and / nor ) do I wish to be.
172 名詞節を導く従属接続詞の用法
1) 困ったことに、ジムは飛行機での旅行が好きではないんだ。
The problem is ( ) Jim doesn’t like traveling by air.
2) 彼が明日映画を見に行くかどうか知っていますか。
Do you know ( ) he is going to see a movie tomorrow?
3) 私は娘が入試に合格したという知らせを受け取った。
I received the news ( ) my daughter had passed the entrance exam.
4) ゲーリーがその申し出を受けるかどうかは定かではない。
It is uncertain ( ) Gary will take the offer.
173 副詞節を導く従属接続詞の用法
( )内の語句のうち、正しいほうを選びなさい。
1) My mother was very delighted ( when / while ) I gave her a present.
2) I’ll wait here ( by the time / until) school is over.
3) I will fix the roof ( in case / for fear ) we have heavy rain.
4) It was ( so / such ) a nice day that we decided to go for a drive.
5) My father doesn’t use taxis ( if / unless ) it is absolutely necessary.
6) (Although / Because ) we did our best, we lost the game.
第1章 文の種類(解説)
001 平叙文/肯定文と否定文
次の文を否定文にしなさい。
1) I am a student at this school.
I am not a student at this school.
(= I’m not a student at this school.)
※「否定の短縮形」
・are not → aren’t
・is not → isn’t
・was not → wasn’t
・were not → weren’t
・do not → don’t
・does not → doesn’t
・did not → didn’t
・cannot → can’t
・could not → couldn’t
・will not → won’t
・would not → wouldn’t
・should not → shouldn’t
・must not → mustn’t
※「主語+be動詞の短縮形」
・I am → I’m
・we are → we’re
・you are → you’re
・he is → he’s
・she is → she’s
・it is → it’s
・they are → they’re
2) He knows your sister very well.
He does not know your sister very well.
(= He doesn’t know your sister very well.)
3) I will be at home this evening.
I will not be at home this evening.
(= I won’t be at home this evening.)
002 Yes/No 疑問文 / 疑問詞を使った疑問文
( )に適語を入れなさい。
1) “(Do) you like pop music? “Yes, I do.”
2) “(Was) he angry last night? “No, he wasn’t.”
3) “(Who) broke the glass?” “I did.”
※「だれが」のように疑問詞が主語になる場合は〈疑問詞+動詞〉という語順になる。
・Who made you angry? (何が君を怒らせたんだい?)
4) “(Where) are you going?” “To the city hall.”
※疑問詞が主語でない場合は〈疑問詞+be動詞/助動詞+主語〉という語順になる。
003 命令文 / 感嘆文
日本語の意味に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) この花を摘んではいけません。
(Don’t) pick these flowers.
※「〜するな」という禁止の意味を表すには、〈Don’t[Do not]+動詞の原形〉を用いる。
Never mind. (気にするなよ。)のようにNeverを用いることもある。
2) 図書館の中では静かにしなさい。
(Be) quiet in the library.
3) あの先生は話すのがなんて速いんだろう!
(How) fast that teacher speaks!
※副詞の意味を強調したいときは、〈How+副詞+主語+動詞〉という語順にする。
また、感嘆文では、〈主語+動詞〉を省略することもある。
・How strange! (変だな!)
4) これはなんて簡単な問題なんだろう!
(What) (an) easy problem (this) (is)!
※〈形容詞+名詞〉の意味を強調して強い感情を表すときは、〈What (a/an)+形容詞+名詞+主語+動詞〉という語順にする。
また、感嘆文では、〈主語+動詞〉を省略することもある。
・What a nice day! (なんてすてきな日なんだろう!
また、whatで始まる感嘆文では、形容詞が入らないこともある。
・What a surprise! (びっくりしたな!)
004 選択疑問文 / 命令文の様々な形
( )に適語を入れなさい。
1) “Who called me up, Jane (or) Cathy?” “Cathy did.”
※「Aですか、それともBですか」と、相手に複数の選択肢の中から選択することを求める場合には、”…A or B?”の形を用いる。
疑問詞のwhichを用いて「どちらですかと尋ねることもできる。
・Which are you looking for? (どちらを探していますか?)
Whichを使った疑問文には次のような形もある。
・Which is your coat? (どちらがあなたのコートですか。)
・Which book do you want? (どちらの本がほしいですか。)
2) (Let’s) go to a movie, shall we?
※〈Let’s+動詞の原形〉で、「〜しよう」という提案・勧誘を表す。これにshall we?を付け加えると、ややていねいなニュアンスがでる。誘いに応じるときはYes, let’s., 断るときはNo, let’s not.と答える。
Let’s…の否定形は、Let’s not…が用いられ、「〜しないようにしよう」という意味を表す。
・Let’s not talk about it. (そのことを話すのはやめよう。)
第2章 動詞と文型(解説)
005 自動詞と他動詞
下線を引いた動詞に注意して、それぞれの文を日本語に直しなさい。
1) A big car stopped in front of my house.
(大きな車が私の家の前で止まった。)
※主語のA big carについて「止まった」ことを表している。この場合の動詞stopは「止まる」という意味で使われている。このように、主語と動詞の組み合わせで意味を表す動詞は自動詞。
自動詞として用いられる動詞 (go, die, fall, happen, wait)
2) The driver stopped the car.
(運転手が車を止めた。)
※stopの後ろにthe carを続けて、「車を止める」という意味を表している。このように、動詞の働きを受ける名詞を後に続けて意味を表す動詞が他動詞。stop the carのthe carのように、動詞の後に続ける名詞のことを目的語と呼ぶ。
他動詞として用いられる動詞 (bring, find, like)
3) Don’t play on the street.
(通りで遊んではいけません。)
※playは自動詞と他動詞の両方で用いられる動詞。ここでは、「遊ぶ」という意味の自動詞。
4) Let’s play tennis after school.
(放課後、テニスをしましょう。)
※playは自動詞と他動詞の両方で用いられる動詞。ここではテニスを「する」という意味の他動詞。
また、自動詞と他動詞で形が異なるものもある。
・lie(横たわる)[自動詞]— lay(〜を横たえる)[他動詞]
・rise(上がる)[自動詞]— raise(上げる)[他動詞]
006 述語動詞
( )内の動詞を適切な形に変えなさい。
1) Kate is a student and (studies) Japanese every day.
※現在のことを表している文で、主語が3人称単数の場合は、述語動詞に3単元のsをつける。
2) Last Sunday, my father (cut) some branches off the tree.
※「先週の土曜日」という過去のことを表しているのでcutの過去形cutを使用する。
3) I (went) to my uncle’s log cabin with my brother last summer.
※「昨年の夏」という過去のことを表しているのでgoの過去形wentを使用する。
007 SV / SVC /SVO
太字の語が、補語、目的語のどちらであるか答えなさい。
1) Did you get my e-mail? 目的語
※You got my e-mail. の疑問文。
S V O (S≠O)
2) The teacher got angry with him. 補語
※The teacher got angry with him.
S V C (S=C)
3) We became friends at university. 補語
※We became friends at university.
S V C (S=C)
4) He has a lot of friends all over the world. 目的語
※He has a lot of friends all over the world.
S V O (S≠O)
008 SVOO
次の文中の目的語を指摘しなさい。
1) Ms. Kim teaches us math.
※Ms. Kim teaches us math.
S V O ≠ O
(人) (物)
teach A B (AにBを教える)
2) He gave me some magazines.
※He gave me some magazines.
S V O ≠ O
(人) (物)
give A B (AにBをあげる)
3) I got a letter from him.
※I got a letter from him.
S V O (S≠O)
009 SVOC
次の文を日本語に直しなさい。
1) We call the dog Max.
(私達はその犬をマックスと呼んでいる。)
※We call the dog Max.
S V O = C (形容詞か名詞)
call A B (AをBと呼ぶ)
2) Our coach made her the team’s captain.
(私達のコーチは彼女をチームのキャプテンにした。)
※Our coach made her the team’s captain.
S V O = C (形容詞か名詞)
make A B (AをBにする)
3) You will find this book easy.
(この本はやさしいとあなたは思うでしょう。)
※You will find this book easy.
S V O = C (形容詞か名詞)
find A B (AがBだと思う)
010 SVO+to / for 〜
与えられた前置詞を用いて、SVOの文に書き換えなさい。
1) Mr. Evans teaches us English. (to)
Mr. Evans teaches English to us.
2) I’ll buy you lunch. (for)
I’ll buy lunch for you.
※〈buy A lunch〉Aに昼食をおごる
3) I chose her a nice dress. (for)
I chose a nice dress for her.
※〈choose A B〉AにBを選んであげる
4) Please show me the photo. (to)
Please show the photo to me.
※〈show A B〉AにBを見せる
011 There+be動詞
( )の中から、適当なものを選びなさい。
1) There (is) a ball in the box.
※〈There+be動詞…〉という表現では、be動詞の後の名詞が単数か複数かでbe動詞の形を変える。また、be動詞以外の自動詞を使って、〈There VS…〉の文を作ることができる。
〈There VS…〉の文を作ることができる自動詞 (exist, live, come, arrive, happen)
・Once upon a time, there lived a very happy prince. (昔々とても幸せな王子様が住んでいました。)
2) There (were) many students in the station.
3) There is (a) book on the desk.
012 注意すべき自動詞と他動詞
次の文の誤りを訂正して、正しい英文にしなさい。(誤りはそれぞれ1カ所ある)。
1) He entered into the room.
He entered the room. (彼は部屋に入った。)
※自動詞と間違えやすい他動詞 (discuss, approach, resemble, enter, oppose attend)
2) When I opened the door, two men approached to me.
When I opened the door, two men approached me.
(私がドアを開けた時、二人の男が私に近づいてきた。)
3) He agreed me on that point.
He agreed with me on that point.(彼はその点で私に同意した。)
※ 他動詞と間違いやすい自動詞
(agree with, agree to, complain to, complain about, apologize for, apologize to)
・He’ll agree to our proposal. (彼は私たちの申し出に同意するだろう。)
・My mother complained to me about my grades.
(私の母は、私に成績のことで文句を言った。)
・He didn’t apologize for his behavior.
(彼は自分のふるまいのことで謝らなかった。)
・You should apologize to her.(あなたは彼女に謝るべきです。)
013 群動詞 / SVCで用いられる動詞
( )に入れるのにもっとも適切な語を、下から1つずつ選びなさい。
1) His story may (sound) strange, but it is true.
※(彼の話は奇妙に聞こえるかもしれないが、それは本当である。)
①「~の感じがする」を表す動詞 (feel, smell, taste, look, sound)
・This milk tastes sour.(この牛乳はすっぱい味がする。)
②「~に思われる」を表す動詞 (seem, appear)
・He appeared a normal person.(彼はふつうの人のように思われた。)
2) Your dream will soon (come) true.
※(あなたの夢はすぐにかなうでしょう。)
「~になる」を表す動詞 (become, get, grow, turn)
・The sky turned gray.(空が暗くなった。)
・The meat in the refrigerator went bad.(冷蔵庫の肉が腐った。)
3) You must (keep) quiet in the library.
※(あなたは図書館でずっと静かにしていなければならない。)
「~である、~のままである」を表す動詞 (be, keep, like, remain, stay)
・His death remains a mystery. (彼の死は謎のままである。)
4) These roses (smell ) sweet.
(これらのバラは甘い香りがする。)
014 SVOの文型で注意すべき目的語/ SVOOの文型で用いられる動詞
( )に適語をいれなさい。ただし、何も入れる必要のない場合は×を入れること。
1) Maggie taught herself (×) French.
※(マギーは独学でフランス語を勉強した。)
SVOOで用いられる動詞
① give型(「相手の元に何かを届かせる」タイプ:SVOに変換する場合は前置詞にtoを使う)
(give, lend, show, hand, offer, pass, pay, sell, send, teach, tell)
② buy型(「相手のために何かをする」タイプ:SVOに変換する場合は前置詞にforを使う)
(buy, find, cook, make, choose, get, leave, play, sing)
SVOOで注意すべき動詞
① askを用いてSVOOからSVOに変換する場合は、前置詞ofを用いる。
Can I ask you a favor? お願いがあるのですが。)
Can I ask a favor of you?
② SVOOを<SVO+to/for+相手>に書き換えられない動詞
cost, take, save, envy
This watch cost me 7,500 yen.(この腕時計は7,500円かかりました。)
The journey took us three days.(私たちはその旅に3日を要した。)
2) Tom made a house (for) the dog.
※ (トムはその犬のために家を作ってあげた。)
= Tom made the dog a house.
3) Please bring me (×) the dog.
※ (私にその犬を持ってきてください。)
Bringは、「相手の元に何かを届かせる」という意味合いでも、「相手のために何かを持ってくる」という意味合いでも用いることができる。
= Please bring the dog to me.
= Please bring the dog for me.
4) He sold his CD player (to) me for six thousand yen.
※(彼は彼のCDプレーヤーをを私に6千円で売ってくれた。)
=He sold me his CD player for six thousand yen.
015 SVOCの文型で用いられる動詞
下線をを引いた語に注意をして、それぞれの文を日本語に直しなさい。
1) Please get me the dictionary on the desk.
机の上の辞書を私に持ってきてください。
※上記はSVOO
2) I’ll get supper ready as soon as possible.
できるだけ早く夕食の準備をします。
※ SVOCで用いられる動詞
① make型:「OをCにする」(Oの状態について述べる)
make, get, keep, leave, paint, bake, cut, dye
・ Mick painted it black.(ミックはそれを黒く塗った。)
② call型:「OをCと呼ぶ」(Oの名や役職などについて述べる)
call, elect, name
③ think型:「OをCと考える」(Oについての認識を述べる)
think, believe, find, consider
3) We left her a lot of work.
私達は彼女にたくさんの仕事を残した。
※上記はSVOO
4) Don’t leave the door open, please.
どうか、ドアをあけたままにしないでください。
第3章 動詞と時制(解説)
016 現在形
( )内の動詞を現在形か進行形にしなさい。
1) This orange (tastes) bad; it (is) not good to eat.
※一般動詞の現在形は、動詞の原形と同じ形。主語が3人称単数の場合は、原形に-sまたは-esをつける。動詞には状態を表す状態動詞と動作を表す動作動詞がある。tasteは状態動詞。
状態動詞の種類
① 心理を表す動詞 (like, love, hate, hope, want, think, believe, know, understand, remember, forget)
② 知覚・感覚を表す動詞 (see, look at, hear, listen to, feel, smell, taste)
③ その他の状態を表す動詞 (be, remain, have, own, belong to, contain, exist, resemble)
2) Mary (is playing) a piece by Bach on the piano now; she (likes) music very much.
※現在進行形は、今まさにしている途中の動作を表す事ができる。また、ある期間にわたって、繰り返している動作や、し続けている動作を表すこともある。
3) The sun (rises) in the east and (sets) in the west.
※現在形は、過去・現在・未来を通じて変化のない事実を表す事ができる。
4) My sister usually (wears) contact lenses, but she (is wearing) glasses today.
※上記文では、現在形のwearsは「ふだんくり返ししていること」を表し、現在進行形のis wearingは「(ふだんとは違って)今まさにしていること」を表している。
017 過去形・過去進行形
( )内の動詞を適切な形に変えなさい。
1) I wanted to be a sailor when I (was) a boy.
※過去のある時期に存在した状態を表現する場合には、状態動詞の過去形を用いる。
2) My father often (told) me interesting stories in my childhood.
※動作動詞の過去形は、過去に繰り返し行われた動作を表すこともできる。
3) He ran to the station and (caught) the last train.
※過去のある時に1回行われた動作を表すことも、過去形の場合は可能である。
4) My mother (was watching) TV when I came home.
※過去進行形は「過去のある時」にしている最中だった動作を表す。したがって、「過去のある時」がいつなのか、文脈上明確になっていなければならない。上記文ではwhen I came homeが「過去のある時」にあたる。
018 未来形・未来進行形
日本語に合うように、( )内に適語を入れなさい。
1) 「熱い、手をやけどしちゃった!」「僕が氷を取ってきてあげるよ!」
“Ouch! I burned my hand!” “I (will) get some ice for you!”
※〈will+動詞の原形〉には、単純未来と意思未来がある。上記は主語の意思を表す意思未来。単純未来とは、話し手や主語の意思とは関係なく、自然のなりゆきで起こるであろうことを表す。(It will rain tomorrow.)
2) この8月にスペインに引っ越すので、スペイン語を覚える必要があります。
I need to learn Spanish because I (am) (going) (to) move to Spain this August.
※〈be going to +動詞の原形〉は話す前からすでにするつもりでいたことを表すのに用いられる。また、「起こりそうな兆候を推測」する場合にも使う。(It’s going to rain.)
3) 明日の今ごろは、彼らはパーティをしているでしょう。
At this time tomorrow they (will) (be) having a party.
※〈will be+動詞のing形〉は、「今」から未来のある時を予測したとき、その時に「行われている最中」であると思われる動作を表す。また、「(何らかの都合で)未来のある時にする予定に決まっている動作」を表すこともある。(This train will soon be arriving at Mizue station.) どちらも主語の意思と関係ないことについて使うのがふつう。
019 時や条件を表す接続詞の後で用いる現在形
次の文の( )内の動詞を正しい形に直しなさい。
1) I’ll finish my home work before my sister (comes) back.
※主節が未来を表す場合、beforeのような「時」を表す接続詞の後に続く節の中で、「実際に成り立つ」と考えられることを扱う際には、動詞は単純な現在形にする。未来のことであっても「実際にあること」と考えて現在形で表す。この場合の従属節は、副詞節となる。「時」を表す接続詞 (when, before, after, until[till], by the time, as soon as) しかしながら、従属節で今から未来のことを推測する場合には、willが必要となり、名詞節となる。
・Tell me when she will come back. (名詞節) (彼女がいつ戻ってくるのか教えてください。)
・Tell me when she comes back. (副詞節) (彼女が戻ってきたら教えてください。)
2) I’ll give him this CD if he (wants) it.
※主節が未来を表す場合、ifのような「条件」を表す接続詞の後に続く節の中では、「実際に成り立つ」と考えられることを扱うことになるので、動詞は単純な現在形にする。未来のことであっても「実際にあること」と考えて現在形で表す。「条件」を表す接続詞 (if, unless) しかしながら従属節で、今から未来のことを推測する場合には、willが必要となり、名詞節となる。
・I wonder if it will rain tomorrow. (名詞節) (明日雨が降るかなぁ。)
・I’ll stay home if it rains tomorrow. (副詞節) (明日雨が降れば家にいます。)
また、if 節の中で、相手に対する依頼を表す場合や、2・3人称の主語で強い意思を表す場合にはwill必要。
・I’ll be happy if you will make a speech at the conference.
(あなたが会議でスピーチをしてくださるなら嬉しいのですが。)
・If you will go out in this storm, I won’t stop you.
(この嵐の中をどうしても出かけるつもりなら、止めません。)
また、過去のある時点から見た未来を表す場合、時や条件を表す副詞節であれば、過去形を使うことになる。
He decided to wait at the station until his wife came.
3) Don’t get off the bus till it (stops).
020 進行形の注意すべき用法
次の文を日本語に直しなさい。
1) It’s getting dark. Let’s go home.
(暗くなってきました。家に帰りましょう。)
※何らかの変化を含む動詞を進行形にすると、「変化している途中」を表すことになる。
変化を含む動詞 (die, stop, get, become, grow)
2) I was leaving my house when the telephone rang.
(電話が鳴った時、私は家を出ようとしていました。)
※過去のある時点でそうなるだろうと思ったことを表すために過去進行形が使われる。
3) That teacher is constantly forgetting his student’s names.
(あの先生はいつも、生徒達の名前を忘れてばかりいます。)
※現在進行形が、always, constantlyなどの頻度を表す副詞(句)を伴うと、その動作がしばしば反復されることを表す。
021 未来を表す様々な表現
( )に適語を入れなさい。
1) My sister (is) to be married next week.
※〈be to 不定詞〉「〜することになっている」
2) They were (about) to leave their house when it began to rain.
※〈be about to+動詞の原形〉「まさに〜しようとしている」
3) Sam (is) leaving Japan at the end of this month.
※未来の予定を表す時に現在進行形がよく使われる。この場合、未来の行動に向けて、今、心構えをしていたり、具体的な準備をしているという内容が含まれる。
4) I was on the (point) (of) going to bed when he called me.
※〈be on the point of+動詞のing〉「まさに〜しようとしている」
第4章 完了形(解説)
022 現在完了形の形と働き / 過去形と現在完了形
次の文の( )内の動詞を、現在完了形にしなさい。
1) I (have finished) my work. So, I can go shopping.
(仕事を終えました。ですので、買い物に行くことができます。)
※過去に仕事を終え、現在も仕事が終わっている状態にある。
2) Cindy (has lost) her watch. She is going to buy a new one today.
(シンディーは自分の腕時計をなくしてしまった。彼女は新しいのを買うつもりです。)
※過去に腕時計をなくしてしまい、現在もなくした状態にある。
参考: 現在では、おもにアメリカ英語で、現在完了形を使うべきところで過去形を使うことがある。だからと言って、むやみに過去形を使うことはせず、現在完了形と過去形を使い分けるようにしましょう。
023 「完了・結果」「経験」「継続」を表す現在完了形 / 「動作の継続」を表す現在完了進行形
日本語の意味に合うように( )に適語を入れなさい。
1) 私はまだクリスマスカードを書いていません。
I (have) not (written) my Christmas cards yet.
※現在完了の「完了・結果」を表す用法では上記のyet([否定文で]まだ…ない, [疑問文]もう…したか)や、already,(すでに), just(…したばかり), now(経った今)といった副詞を伴うことが多い。
〈現在形で現在完了形の意味を表すことのできる動詞〉
hear, forget, find, understand
・I hear you quit your job. (あなたが仕事をやめたって聞いたんだけど。)
(=I have heard you quit your job.)
・I forget her name. (彼女の名前を忘れた。)
(=I have forgotten her name.)
〈be動詞+自動詞の過去分詞〉で「結果」を表す動詞 (ただし、文章体)
go, come, fall, finish
・All my money is gone. (有り金が全部なくなった。[→今はお金がない])
(= All my money has gone.)
・Spring is come. (春が来た。[→今は春だ])
(= Spring has come.)
2) 私は彼からメールを受け取りました。
I (have) (received) an e-mail from him.
3) 今までに外国へ行ったことがありますか?
(Have) you (ever) been abroad?
※現在完了の「経験」を表す用法では、上記のever([疑問文で]今までに)やbefore(以前に), never(1度も〜ない), often(しばしば), once(1度), twice(2度), many times(何度も)のような回数や頻度を表す副詞(句)を伴うのがふつう。
〈have beenとhave gone〉
・He has been to Thailand. (彼はタイに行ったことがある。) [経験]
・He has gone to Thailand. (彼はタイに行ってしまった。[今はここにいない])[完了・結果]
・I have just been to the supermarket.
(たった今、スーパーマーケットに行ってきたところだ。[→もう買い物を終えて戻ってきた])[完了・結果]
〈never, everを過去形とともに用いて「経験」を表す〉
・I never went to such a beautiful island before.
(あんなに美しい島にはこれまで1度も行ったことがない。)
(= I have never been to such a beautiful island before.)
・Did you ever see such a beautiful sunset?
(こんなに美しい夕焼けを今まで見たことがありますか?)
(= Have you ever seen such a beautiful sunset?)
4) 日本に来てどのくらいになりますか?
How (long) have you (been) in Japan?
※現在完了の「継続」用法では、上記のHow long…?(どのくらいのあいだ…?)やalways(ずっと/前々から), for(〜のあいだ), since(〜以来)の様な表現を用いて表すのがふつう。
5) 1週間雨が降り続いています。
It (has) (been) raining (for) a week.
※「(今まで)ずっと〜し続けている」という動作の継続を表す場合に、現在完了進行形を用いる。現在完了形の「継続」用法との意味の違いは、たいがい、無視できるほどわずかである。とはいえ、一般に、長期にわたって安定した状態を表す場合には、現在完了形が好まれる。動詞には下記の動作動詞が用いられる。
learn, study, rain, snow, sleep, stay, play, wait, work
・We have studied English for five years.
・We have been studying English for five years.
(私たちは5年間英語の勉強をしています。)
また、現在完了進行形は継続していた動作自体は少し前に終わったものの、その動作の「余韻」がその時点で色濃く残っている時にも使われる。
・I’m very tired. I’ve been running. (とても疲れているんだ。ずっと走っていたからね。)
024 現在完了と時を表す副詞
次の文の下線部を訂正して、正しい英文にしなさい。
1) I’ve left my bag in the train yesterday.
I left my bag in the train yesterday.
(私は、昨日、自分のカバンを電車におき忘れました。)
※〈現在完了形とともに使うことのできない表現の例〉
yesterday, last night[week/month/year], then, just now, …ago, when I was…, When…?, What time…?, in 1972, on July 4 など。
〈現在完了形とともに使うことができる表現の例〉
before, ever, lately, just, now, today, recently, so far, this week[month/year], for the last[past] …days, for…, since… など。
・Have you written a letter to him this month? (今月、彼に手紙を書きましたか?)
2) Recently more and more people begin to use smartphones.
Recently more and more people have begun to use smartphones.
(最近、ますます多くの人々がスマートフォンを使い始めています。)
※〈「最近」を表す表現と時制: lately, recently〉
lately: 現在完了形で用いるのがふつう。
recently: 現在完了形と過去形で用いる。
nowadays, these days: 現在形と現在進行形で用いる。
・They got married recently. (彼らは最近結婚した。)
・Many people nowadays travel abroad. (最近は海外旅行をする人が多い。)
3) My sister has been ill in bed yesterday.
My sister was ill in bed yesterday.
025「完了・結果」「経験」「継続」を表す過去完了形 / 「動作の継続」を表す過去完了進行形 / 2つの出来事の時間的な前後関係を表す過去完了形
( )内の語句のうち、正しいほうを選びなさい。
1) The last bus (had already left) when I reached the bus stop.
(私がバス停に到着した時には、最終バスはすでに出発してしまっていた。)
※過去完了形の「完了・結果」用法。
2) I (had been) abroad three times before I was twenty.
(私は、20歳になる前に海外へ3度行ったことがあった。)
※過去完了形の「経験」用法。
3) Judy (has been living ) in this country since last year. She’ll go back home in March.
(ジュディは昨年からずっとこの国に住んでいます。彼女は3月に帰国します。)
※現在完了進行形の「動作の継続」用法。
4) He (had been reading) the novel for two hours before I called him.
(私が彼に電話する前の2時間、彼はずっと小説を読んでいた。)
※過去完了進行形の「動作の継続」用法
〈継続していた動作自体は少し前に終わったものの、その動作の「余韻」がその時点で色濃く残っている時にも使われる。〉
・I was very tired because I had been working too hard.
(あまりにも懸命に働いていたので、私はとても疲れていた。)
5) I lost the watch which my uncle (had bought) for me.
(私はおじさんが買ってくれた腕時計をなくした。)
※過去完了の「大過去」用法。過去に起こった2つの出来事について、実際に起こった順序とは逆の順序で述べる場合、時間的に前に起こった出来事を過去完了に用いる。
上記文では、「買った」のは「なくした」時よりも前のことであるが、英文では先にlostがあるため、「買った」をhad boughtと過去完了形にして、2つの出来事の時間的な前後関係を明確にしている。
〈2つの出来事をどちらも過去形で表す場合〉
起こった通りの順序で述べる場合
・My uncle bought a watch for me and I lost it.
(おじさんが私に時計を買ってくれたのだが、私はそれをなくした。)
beforeやafterがついていたり、文脈から時間の前後関係が明らかにわかる場合
・I went to the park after I finished [had finished] my home work.
(私は宿題を終えた後、公園に行った。)
・I visited the town I lived [had lived] in when I was a boy.
〈過去完了形で実現されなかった期待を表す動詞〉
expect, hope, intend, want, thinkなど、期待や願望を表す動詞が過去完了形でもちいられると、それが実現されなかったことを表すことができる。
・I had expected you to come. (君にきてほしかった(のに来なかった)。)
026「完了・結果」「経験」「継続」を表す未来完了形
次の文の下線部を訂正して、正しい英文にしなさい。
1) I finished my homework by the time the TV program begins.
I will have finished my homework by the time the TV program begins.
(そのテレビ番組が始まる頃までには、私は宿題を終えてしまっているでしょう。)
※未来完了形の「完了・結果」用法
2) I will see the movie five times if I go to see it again.
I will have seen the movie five times if I go to see it again.
(もう1回見たら、私はその映画を5回見たことになる。)
※未来完了形の「経験」用法
3) Jack has been sick in bed for two weeks by tomorrow.
Jack will have been sick in bed for two weeks by tomorrow.
(明日でジャックは2週間病気で寝ていることになる。)
※未来完了形の「継続」用法
「動作の継続」は未来完了進行形で表す。
・Next year, I will have been working at the company for 30 years.
(来年で、私はこの会社に30年間勤め続けたことになる。)
027「今」に視点を置かない現在完了形
( )内のうち、正しいほうを選びなさい。
1) The game will begin when the players (have arrived).
(その選手たちが到着したら、その試合は始まるでしょう。)
※現在完了形は、「今」という時点から離れて、「未来に実際にあると想定すべきこと」を表す時に用いられることもある。上記では、「選手たちが到着した状況」を思い浮かべ、「それ以前に起きていたことやしていたこと」とつながっているので、完了形を用いて表現できる。
2) Please wait here until I (have come).
(私が来るまでここで待っていてください。)
3) Don’t drive a car when you (haven’t had) enough sleep.
(十分な睡眠をとっていない時に、車の運転をしてはいけない。)
※現在完了形は、「今」という時点から離れて、「一般論」を表す時に用いられることもある。上記の場合は、「(話している)今」の状況に限らず、いつでも成り立つ「一般的な事実」を扱っている。「睡眠不足の時に車を運転してはいけない」というのは、「今」だけに限らない一般論である。
第5章 助動詞(解説)
028「能力・可能」を表すcan / be able to
( )内から正しいほうを選びなさい。
① I (can) help you.
※ (私はあなたを助けることができる。)
上記のように、canは「~することができる」という、現在の能力を表す場合にもちいられる。canの代わりにbe able toを用いてI am able to help youと言うこともできるが、canを使うのがふつう。willのような助動詞がある場合にI will be ableto help you.というふうにbe able toを使う。
② I (was able to) reserve two seats for the concert.
※ (私はそのコンサートの2席を予約することができた。)
上記文のように、「~することが(実際に)できた」という過去に実行したことを表す時には、was able toを用い、couldを用いることはできない。
〈couldとwas able to 違い〉
・「能力があって、実際のその動作を行った」という、過去の1回の動作[行為]を表す場合: was able to
・ 単に「そうする能力があった」ということを表す場合: couldかwas able to
She could [was able to] speak French.
(彼女はフランス語を話すことができた)
・ 動作[行為]が達成できなかった場合(否定文): couldn’tかwasn’t able to
I couldn’t [wasn’t able to] reserve two seats for the concert.
(私はそのコンサートの2席を予約することができなかった。)
③ You will (be able to) ride a bicycle soon.
※ (あなたはすぐに自転車に乗ることができるでしょう。)
上記文のようにwillのような助動詞がある場合はbe able toを使う。
④ I (couldn’t) find the house key this morning.
※ (私は、今朝、家のカギを見つけることができなかった。)
上記文を肯定文にした場合、2)の解説により、couldを使用することはできず、was able toのみの使用になる。
029「許可・依頼」を表すcan
canに注意して、次の文を日本語に直しなさい。
1) Can I ask you a question?
(質問してもいいですか?)
※ 「~してもいいですか」と相手の許可を求める場合は、Can I…?を用いることができる。Could I…?を使うと、Can I…?よりもていねいな言い方になる。
・Could I use your phone?(電話をお借りしてもよろしいですか?)
〈Can I…?への答え方〉
・「はい、どうぞ」: of course (you can). / Yes, please (do). / Sure.
・「しないでください」: I’m afraid you can’t. / I’m sorry, you can’t.
〈申し出「~しましょうか」や依頼「~をください」の用法〉
・ Can I carry your bag? (かばんを運びましょうか?
・ Can I have a newspaper, please? (新聞をください。)
2) You can use my bike if you need it.
(必要なら私の自転車を使ってもいいですよ。)
※ 「~してもよい」という許可を表すのに、口語では上記のようにcanがよく用いられる。「~してはいけない」という不許可を表すときは、can’t[cannot]を用いることができる。
3) Can you tell me the way to the station?
(駅までの道を教えてくれませんか?)
※ Can you …?は「~してくれませんか?」という依頼の意味を表す。Could you…?を使うと、よりていねいな言い方になる。Possiblyを使って、Could you possiblyとすると、さらにていねいな依頼を表すことができる。
・ Can you lend me another fifty dollars?
(もう10ドル、貸し手くれませんか?)
・ Could you lend me another fifty dollars?
(もう10ドル、貸していただけないでしょうか?)
・ Could you possibly lend me another fifty dollars?
(もう10ドル、なんとか貸していただけないでしょうか?)
030「許可」を表すmay
mayに注意して、次の文を日本語に直しなさい。
1) “May I ask you a personal question?” “Sure.”
(「個人的な質問をしてもよろしいですか?」「どうぞ。」)
※ 「~してもよろしいですか」と相手の許可を求める場合には、May I…?を用いることができる。ただし、これはやや堅苦しい言い方なので、Can I… ?が使われることのほうが多い。
2) Students may not use these computers.
(学生はこれらのコンピュータを使ってはいけない。)
※ may notは「~してはいけない」という不許可を表す。強く禁止するときにはmust notを用いる。
3) You may leave the classroom after the bell rings.
(ベルが鳴った後なら、教室を出てもかまわない。)
※ You may…は上の立場の人が許可を与える言い方。したがって、May I…?に対するYes, you may.という返答は、こどもや下の立場の人に許可する感じを与える。
〈May I…?への答え方〉
・「はい、どうぞ」: of course (you can). / Yes, please (do). / Sure.
・「しないでください」: I’m afraid you can’t. / I’m sorry, you can’t.
031「義務・必要」を表すmust / have to
must, have to に注意して、次の文を日本語に直しなさい。
1) I must get more exercise.
もっと運動をしなくちゃ。
※ mustは「〜しなければならない」という現在(あるいは未来)の義務や必要を表す。また、上記や下記の文のように、mustは話し手の決意を表すこともある。
・ I must go on a diet. (私はダイエットをしなければならない。)
2) She had to get up early this morning.
彼女は今朝、早起きしなければならなかった。
※ 過去の義務や必要を表したい場合には、上記のようにhad toを使う。未来の義務や必要を表す場合は、will have toを使う。
・ You’ll have to replace this light bulb.
(この電球を取り替えなければならないでしょう。)
〈must / have toを使った文の疑問文〉
・ Must I apologize to him? (私が彼に謝らなければならないの?)
= Do I have to apologize to him?
〈have toと同じ意味のhave got to〉
口語では、have toとほぼ同じ意味でhave got toという形が用いられる。haveが
省略形(‘ve)になることも多い。have gotは〈have+過去分詞〉という形であるが、
完了形の意味を表すわけではない。
・You’ve got to be more patient, Mary.
(メアリー、もっとがまん強くないといけないよ。)
〈強い勧めを表すmust〉
You must … の形で「ぜひ…してね」という意味の強い勧めや勧誘を表すことがある。この表現は親しい人に対して使われる。
・ You must visit Kyoto when you come to Japan.
(日本に来たら京都にはぜひ行ってね。)
・ You must come and visit me.
(ぜひ遊びに来てくださいね。)
3) You must not play video games all day long.
一日中テレビゲームをしてはいけません。
※ must notは「〜してはいけない」という禁止を表す。
4) You don’t have to attend the meeting.
その会議に出る必要はないよ。
※ don’t have toは「〜しなくてもよい、する必要はない」という不必要を表す。
・ She doesn’t have to take the test.
(彼女はそのテストを受ける必要はありません。)
032「義務・当然の行動を表すshould / ought to /「忠告」を表すhad better
日本語に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) 今すぐ病院へ行くべきです。
You (should) go to the hospital right now.
※ shouldは上記のように「~すべきだ」という義務や当然の行動を表す。
2) 先生に助言を求めたほうがいいな。
I (had) better ask the teacher for advice.
※ 〈had better+動詞の原型〉で「~したほうがいい/~しなければいけない/~しなさい」という意味を表す。
3) 親にそんな口のきき方をすべきではない。
You ought (not) (to) speak to your parents like that.
※ shouldとほぼ同じ意味でought toを使うことができ、否定形はought not toという語順。
4) あの失敗のことは考えるなよ。
You had (better) (not) think about that mistake.
※ had betterの否定形はhad better notという語順。
033 can / could / may / might / will / would
助動詞に注意して、次の文を日本語に直しなさい。
1) Winter in Tokyo can be very cold.
東京の冬はとても寒いことがある。
※ 上記ではcanを使って、「ありうる」という可能性があることを表している。Canは「論理的にそういうことがありうる」という可能性を表す。「そういうことがあるかもしれない」と話し手が思っていることを表すときはcouldを使う。また、canが疑問文で用いられると、強い疑問を表す場合がある。この場合、驚きや不信感を示唆することが多い。
・Can his story be true? (彼の話が真実だなんて、ありうるだろうか。)
2) You may feel some shaking when the plane takes off.
飛行機が離陸する時、いくらか揺れを感じるかもしれません。
※ mayは「〜かもしれない」という推量を表す。mightもほぼ同じ意味で使われることが多いが、mightを使うとmayよりもやや可能性が低いことを表すことができる。
3) That will be his house. I can see his car in the garages.
あれが彼の家だろう。彼の車が車庫の中にあるのが見えるから。
※ 「たぶん〜だろう」という話し手の推測を表すときに、willやwouldを使う。wouldを使うと、willよりも控え目でていねいな言い方になり、willよりも自身のなさを表すこともある。
〈注意〉可能性や推量を表すcould/might/wouldは形は過去形だが、過去のことを表しているのではない。
034 must / can’t / should / ought to
助動詞に注意して、次の文を日本語に直しなさい。
1) This watch must be your father’s.
この腕時計は君のお父さんのものに違いない。
※ 上記のように「〜に違いない」と話し手が確信していることを表すときに、mustを使う。
2) This cannot be the right bus. It’s going south.
これが正しいバスのはずがない。南に向かっているもの。
※ 上記のように「〜のはずがない」と話し手が思っている場合はcan’t[cannot]を使う。この意味では、must notは使わない。また、can’tの代わりにcouldn’tを使うこともできる。
・ She couldn’t be over forty years old. (彼女が40歳を超えているはずがない。
〈参考〉have to [have got to]も「〜に違いない」の意味で使える。
・ You’ve got to be kidding. (冗談でしょ。)
3) He should win the race.
彼はきっとそのレースに勝つだろう。
※ 「〜のはずだ/きっと〜だ」という意味でshouldを用いることがある。
4) He ought to be tired after the tennis practice.
テニスの練習の後なので、きっと彼は疲れているはずだ。
※ ought toはshouldとほぼ同じ意味を表す。
〈参考〉mustは「絶対そうだ」、shouldは「きっとそうだ」、mayは「そうかもしれない」というニュアンス。mustは間違いなくそうだと思っている場合、shouldはそうでない可能性もある場合、mayはどちらかわからない場合に使う。
035「意志」・「習慣」を表すwill / would
will, wouldに注意して、次の文を日本語に直しなさい。
1) My father would often play catch with me.
父は私とキャッチボールをすることがよくあった。
※ 「よく〜したものだった」という過去の習慣や繰り返される動作を表すには上記のようにwouldを用いる。この用法では、動作が繰り返されることを示すために、oftenやsometimesなどの頻度を表す副詞を伴うことが多い。「よく〜する」という現在の習慣や繰り返される動作を表す場合はwillを使う。
〈参考〉used toも過去の習慣を表す。
2) When she was a little girl, she wouldn’t touch any animals.
彼女が小さかたころ、どんな動物にもさわろうとはしなかった。
※ 上記のようにwould not[wouldn’t]を使うと、「どうしても〜しとうとしなかった」という過去における拒絶を表すことができる。
3) I will solve this problem by myself.
私はこの問題を独力で解きます。
※ 「〜する/〜するつもりだ」という主語の意志を表すときは、willを用いる。また、「どうしても〜しようとする/必ず〜する」という主語の強い意志を表す場合にも、willを使う。この場合、wouldを使えば過去における強い意志を表すことになる。この場合は短縮形(I’llなど)は使わない。
・He will[would] have his own way in everything.
(彼は何でも自分の思いどおりにしようとする[した]。)
4) My dog likes running in the field, but today she won’t get out of the house.
私の犬は野原を走るのが好きなのに、今日は家のそとに出ようとしない。
※ 現在における拒絶を表す場合にはwill not[won’t]を使う。
〈習性・傾向を表すwill〉
「〜するものだ」という主語の習性や傾向をwillで表すことができる。一般的なこと、物質の性質や習性、傾向を表すときに使う。
・ Teenagers will not do as they are told.
(10代の子は言われたとおりにはしないものだ。)
・Gasoline will float on water.
(ガソリンは水に浮くものだ。)
036「依頼」を表すwill / would / 相手の意向を尋ねるshall
will, shallに注意して、次の文を日本語に直しなさい。
1) Will you drive me home?
私を家まで車で送ってくれませんか。
※ 「〜してくれませんか」という意味で、相手の意志を尋ねたり、依頼をする場合に、上記のようにWill you …?という形を用いる。Would you …?を用いると「〜していただけませんか」というややていねいな依頼になる。なお、依頼を表す場合はCan[Could] you …?を用いることも多い。
〈参考〉依頼を表す文でpleaseを用いると、よりていねいな表現になる。
・Will you please close the window?
・Can you close the window, please?
〈参考〉「〜しませんか」という意味で、相手に何かを勧める場合に、Will you …?
やWon’t you …?を用いることがある。
・ Will you try my chocolate cake?
(私の作ったチョコレートケーキを食べてみませんか。)
・ Won’t you have a seat? (お座りになってください。)
2) Shall I give you the concert ticket?
そのコンサートの切符をあげましょうか。
※ 上記のように「〜しましょうか」と、自分が何かをすることを相手に申し出る場合には、Shall I …?を用いる。
〈参考〉Do you want me to …?も同じ意味でよく使われる。
・ Do you want me to give Jim a call?
(あなたは私に、ジムに電話をかけてほしいですか。→ジムに電話をかけましょうか。)
3) Shall we watch the baseball game on TV?
その野球の試合をテレビで見ませんか[見ましょうよ]。
※上記のように「〜しましょうよ」と、相手といっしょに何かをすることを提案する場合には、Shall we …?を用いる。
037 need・used toの用法
日本語の意味に合うように、( )内に適切な助動詞を下から選んで入れなさい。ただし、同じものを2度使わないこと。
1) 部屋をそうじする必要はありません。もう私がやりましたから。
You (needn’t) clean the room. I’ve already cleaned it.
※ needは「〜する必要がある」という意味で、おもに上記のような否定文や疑問文で用いられる。needを助動詞として使うとややかたい表現になるため、ふつうは動詞として使う。
〈注意〉needの使い方
① 肯定文では一般動詞として〈need to do〉の形で「〜する必要がある」という意味。
・He needs to have a haircut. (彼は散髪する必要がある。)
・ “Do we need to pay for the tickets in cash?” “No, you don’t need to.”
(「チケット代を現金で払う必要がありますか。」「いいえ、その必要はあ
りません。」)
② 助動詞needには過去形がないので過去のことを述べるときは一般動詞として用いる。
・ She needed to change trains at Shinjuku.
(彼女は新宿で電車を乗り換える必要があった。)
・ Did you need to show them your ID card?
(あなたは彼らに身分証明書を見せる必要がありましたか。)
・ I didn’t need to give a speech at the meeting.
(会合でスピーチをする必要はなかった。)
2) 私が子供のころ、父はとてもがんこでした。
My father (used to) be very stubborn when I was a child.
※ 上記のように、used toは「(今はそうではないが)以前は〜であった」という過去の状態を表す。また、「(今はそうではないが)以前はよく〜したものだった」という過去の習慣的行為も表すことができる。
・ I used to go to a gym after work, but now I don’t.
(以前は仕事の後にジムに行ったものだが、今は行かない。)
3) スペインに住んでいたころはよく美術館に行ったものだ。
I (would) often visit museums when I lived in Spain.
※ 〈used toとwouldの違い〉
used toとwouldはどちらも過去の習慣を表すが、used toは過去と現在を対比して、今では成り立たなくなってしまった過去の事実を述べる。一方、wouldは話し手が個人的に過去を回想するという意味合いが強く、現在との対比は特に意識されない。
・ I used to go to the movies every Sunday, but now I don’t.
(日曜日にはいつも映画を見に行ったものだが、今は行かない。)
・ I would often go to the movies when I was young.
(若いころはよく映画を見に行ったものだ。)
〈dareを使った慣用表現〉
How dare you …? 「よくもまあ…できるものだ」
・ How dare you tell such a lie to me?
(私に向かってよくもまあそんなうそがつけるものだ。)
I dare say[I daresay]…「おそらく…だろう」
・ I dare say[I daresay] prices will rise.
(おそらく物価は上がるだろう。)
〈参考〉dare(〜する勇気がある/思い切って〜する)はneedと同様に、助動詞としても、一般動詞としても使われる。
・ I dare not[daren’t] express my true feelings.
(私には自分の本当の気持ちを表現する勇気がない。)
・ Dare you propose to her? (彼女にプロポーズする勇気はありますか。)
dareは否定文と疑問文において用いられることが多い。ただし口語では以下のような表現を用いるのがふつう。
・ I am afraid to express my true feelings.
・ Do you have the courage to propose to her?
肯定文では、一般動詞として〈dare to do〉の形で用いることが多い。
・ The climbers dare to climb Mt. Everest in winter.
(登山家たちは、思い切って冬にエベレスト山に登ろうとしている。
・ You must dare to do what is right.
(正しいことをする勇気がなければなりません。)
助動詞dareには過去形がある。
・ He dared not mention the subject again.
(彼にはその話題をふたたび口に出す勇気がなかった。)
〈be supposed toの使い方〉
shouldと同じような意味で使われるbe supposed toという表現がある。
〈be supposed to+動詞の原形〉
・ You’re supposed to come to school at eight.
(学校には8時に来ることなっている→来なければならない。)
・ You’re not supposed to take pictures here.
(ここでは写真をとってはいけません。)
be supposed toを使うのは、そのようにする取り決めができているような場合や、社会的にすべきことを述べる場合である。
038「過去のことに関する推量」表す〈助動詞+have+過去分詞〉
( )内の語句のうち、正しいほうを選びなさい。
1) A: I missed the TV program last night. (昨夜、そのテレビ番組を見逃した。)
B: My brother (may have recorded) it.(私の弟が録画したかもしれない。)
※ 〈may have+過去分詞〉は、上記のように「〜したかもしれない/〜だったかもしれない」という意味を表す。mightを使って〈might have+過去分詞〉としてもほぼ同じ意味を表す。
2) A: They’re very late. (彼らはとても遅い。)
B: Yes, they (must) have lost their way; they didn’t have a map.
(ええ、道に迷ったに違いない。地図を持っていなかったから。)
※ 〈must have+過去分詞〉は、「〜したに違いない/〜だったに違いない」という意味で過去のことに関して確信していることを表す。
3) She (cannot) have won the game; she looked very sad.
(彼女はその試合に勝ったはずがない。とても悲しそうだったから。)
※ 〈cannot have+過去分詞〉は、上記のように「〜したはずがない/〜だったはずがない」という意味を表す。〈couldn’t have+過去分詞〉を使うこともできる。
039「過去の行為に対する非難や後悔」を表す〈助動詞+have+過去分詞〉
助動詞に注意して、次の文を日本語に直しなさい。
1) He should have gone to the doctor earlier.
彼はもっと早く医者に行くべきだったのに。
※ 〈should have+過去分詞〉は「〜すべきだったのに(実際はしなかった)」という意味で、過去において実行されなかったことに対する非難や後悔の気持ちを表す。また、「(きっと)〜したはずだ」という意味も表す。
・ The game should have started at noon.
(正午にはその試合は始まっていたはずだ。)
〈注意〉〈should not have+過去分詞〉は「〜すべきではなかったのに(実際はしてしまった)」という意味
・ We should not have turned left at the last corner.
(先ほどの角を左に曲がるべきではなかったのに。)
2) You ought to have taken my advice.
君は私の忠告を聞くべきだったのに。
※ 〈ought to have+過去分詞〉も〈should have+過去分詞〉ほぼ同じ意味を表す。
〈注意〉〈ought not to have+過去分詞〉も〈should not have+過去分詞〉とほぼ同じ意味を表す。
3) I need not have got up early this morning.
今朝早く起きる必要はなかったんだ。
※ 〈need not[needn’t] have+過去分詞〉は、「〜する必要はなかったのに(実際にはしてしまった)」という意味を表す。
〈注意〉〈didn’t need to do〉との意味の違い
・ You need not have come.
(君は来る必要はなかったのに[実際は来てしまった]。)
・ You didn’t need to come.
(君は来る必要はなかった[実際に来たかどうかはわからない]。)
040 may / mightを含む慣用表現
助動詞に注意して、次の文を日本語に直しなさい。
1) Jim would rather go by train than fly.
ジムは、飛行機で行くよりはむしろ列車で行きたがっている。
※ would rather doは「(むしろ)〜したい」という意味を表す。上記のように、than …が続くと、「…するよりは〜したい」という意味になる。
2) I would like to read your poems.
私はあなたの詩を読みたい。
※ would like to doは「〜したいと思うのですが」というていねいな申し出や希望を表す。want to doよりもていねいでひかえめな言い方である。
3) She may well be right.
彼女はたぶん正しいだろう。
※ may well …は「たぶん〜だろう」というmayよりも確信度の高い推量の意味。
〈参考〉may wellを「〜するのも当然だ/〜するのももっともだ」という意味で使
うこともある。どちらの意味になるかは、文脈から判断する。
・ You may well be angry with your brother.
(君が弟に腹を立てているのももっともだ。)
なお、might well …でmay well …と同じような意味を表すこともできる。
・ She might well complain of her boss.
(彼女が上司について文句を言うのももっともだ。)
4) We can’t find a taxi on this street. We might as well walk.
この通りではタクシーが見つからない。歩いたほうがよさそうだ。
※ might as well …は「〜したほうがいいのでは」という意味になる。「したくないならしなくてもいいけど、したほうがいいと思うよ。」というニュアンス。
〈参考〉might as wellは「助言」を表す表現なので、「忠告を」を表すhad betterとは意味合いに違いがある。
この表現ではmight の代わりにmayを使ってmay as wellとすることもできる。また、may as well … as 〜は「〜するより…するほうがよい」という意味になる。might as well … as〜は「〜するのは…するようなものだ」という意味(現実性がうすい)。
・ You may as well do your homework now as do it later.
(宿題をあとでするよりも、今したほうがいいよ。)
・ You might as well throwing your money as buying such a thing.
(あんなものを買うなんて、お金を捨てるようなものだよ。)
〈参考〉文語では〈May+主語+動詞の原形〉の形で、「どうか〜でありますように」という祈願を表す。
May you find happiness! (ご多幸をお祈りします!)
041 that節で用いられるshouldの用法
日本語の意味に合うように、( )内に適語を入れなさい。
1) 彼女があの光景を見てびっくりするのも当然だよ。
It’s (natural) that she (should) be surprised at that sight.
※ 〈It is+形容詞+that S should+動詞の原形〉という形で、当然・驚き・善悪などの話し手の感情や判断を表す。この形では次のような形容詞や、a pity(残念なこと)のような名詞が用いられる。
natural(当然の), right(正しい), strange(不思議な), surprising(驚くべき), wrong(悪い), a pity(残念なこと)
〈注意〉shouldを用いない場合
shouldを用いずに表すこともできるがその場合は動詞を適切な形に変える。
・ It is natural that she gets angry. (彼女が怒るのも当然だ。)
・ It is strange that he said so. (彼がそう言ったとは不思議だ。)
that以下で話者の主観が入らない事実を述べる場合にはshouldは用いない。
・ It is natural that babies cry. (赤ちゃんが泣くのは当然だ。)
([赤ちゃんは泣くものだ]というだれもが認める事実について述べている。)
〈It is … that S should have+過去分詞〉「~したなんて・・・だ」
過去のことについて「~したなんて・・・だ」と述べる場合には、that節中に〈should have+過去分詞〉の形を用いる。
・ It is strange that they should have canceled the concert.
(彼らがコンサートをキャンセルしたなんて不思議なことだ。)
2) 歯医者に行く必要があるよ。
It is (necessary) that you (should) see a dentist.
※ 〈It is +形容詞+that S should+動詞の原形〉で、必要・緊急などの意味を表す。この形で用いられるおもな形容詞は以下のとおり。
important(重要な), necessary(必要な), essential(必要不可欠な),
desirable(望ましい), urgent(緊急の)
〈注意〉should を用いずに、動詞の原形を用いる場合
アメリカ英語では、この形のthat節でshouldを用いずに、〈動詞の原形〉を用い
ることが多い。
・ It is important that you be sincere.(誠実であることは重要だ。)
また、動詞の原形ではなく、主語に合わせて動詞の形を変えることもある。
・ It is important that she goes there.(彼女がそこに行くことが重要だ。)
3) 彼はその会議を延期することを要求した。
He (insisted) that the meeting (should) be postponed.
※ 提案・要求・決定などを表す動詞に続くthat節ではshouldが用いられる。この構文で用いられるおもな動詞は以下のとおり。
advise(忠告する), decide(決定する), demand(要求する), insist(要求する),
order(命令する), propose(提案する), recommend勧める),
request(要求する), suggest(提案する)
Shouldを用いずに、〈動詞の原形〉を用いることも多い。
・ She suggested that we share the cost of the meal.
(彼女は食事代を割りかんにしようと提案した。)
〈参考〉that節で用いる動詞の原形を「仮定法現在」と呼ぶこともある。
〈shouldのその他の用法〉
① 疑問詞を含む疑問文でshouldを用いると、「いったい~、どうして~」という「意外・驚き・いらだち」などの感情を表す。
・ Why should anyone want to hurt you?
(いったいだれがあなたを傷つけたいなんて思うだろうか。)
[この文の場合は「そんなことを思うわけがない」という意味合いをもつ。]
② Lestなどで始まる副詞節で用いる。文語的な表現で、アメリカ英語ではshouldを用いずに、動詞の原形を用いることが多い。
・ Keep quiet lest you should wake the baby.
(赤ちゃんを起こさないように静かにしていなさい。)
③ I should say …のようにshouldを用いると、確信がない場合のためらいの気持ちや、ていねいでひかえめな気持ちを表すことがある。
・ I should say there were about 100 students in the hall.
(ホールにはおよそ100人の学生がいたと思いますよ。)
第6章 受動態(解説)
042 受動態の基本形
( )内の動詞を適切な形にしなさい。
1) This window (was broken) by Jim yesterday.
※ (この窓は昨日ジムによって壊された。)
上記の文は「壊す」という行為を受ける「される側」のThis windowを主語にした文。「壊される」という意味にするために、〈be動詞+過去分詞〉という受動態を使ってwas brokenとしている。「する側」のJimはbyの後に続ける。
2) These pictures (were taken) by my wife last year.
※ (これらの写真は昨年、私の妻によって写された。)
3) This skirt (was made) by my mother.
※ (このスカートは私の母によって作られた。)
4) Magazines (are[were] sold) at the convenience store.
※ (雑誌はコンビニで売られている[た]。)
上記のように、動作をする側がはっきりしていて、あえて表す必要がない場合に、受動態が使われる。また、下記のように「動作をする側がだれ[何]なのかがはっきりわからない場合にも受動態が使われる。
・This temple was built about 500 years ago.
(この寺は約500年前に建てられた。)
〈注意〉by…のない受動態が多い:動作をする側を表すby…は必ずなければなら
ないものではない。むしろby…がない文のほうが多い。また、する側がwe, you, theyなど、特定の人を指さない場合、受動態ではこれをby…の形で表現しない。
043 受動態の基本形 / 受動態の様々な形(助動詞使用・進行形・完了形)
( )内の動詞を適切な形にしなさい。
1) The wall will (be painted) next week.
※ (来週、この壁は塗られるでしょう。)
能動態と同じように、受動態でも助動詞を用いることがある。その際は、will be paintedのように、〈助動詞+be+過去分詞〉という形になる。「~されるだろう」のように、未来のことを受動態で表すときは、〈will be+過去分詞〉という形にする。be going toを受動態の文で使うと、次のようになる。
・His new book is going to be published next week.
(彼の新しい本が来週、出版されることになっている。)
2) My car (is being fixed) now.
※ (私の車は今修理されているところです。)
「~されているところだ」のように、主語が何らかの動作を受けている途中であることを表すときは、受動態を進行形にする。
進行形は〈be動詞+動詞のing形〉で表すので、進行形の受動態は、〈be動詞+過去分詞〉のbe動詞をbeingにして、〈be動詞+being+過去分詞〉という形になる。
・My brother was being scolded by my mother when I came home.
(私が家に帰ってきた時、弟は母にしかられていた。)
3) The store (has been closed) since last week.
※ (その店は先週から閉まっている。)
完了形の意味を受動態で表したいときは、has been closedのように〈have/has/had been+過去分詞〉の形で表す。上記文では、「ずっと閉まっている」という意味を表している。
・The thief had already been arrested when we arrived there.
(私たちがそこに着いた時には、泥棒はすでに逮捕されていた。)
4) Rare animals can (see be seen) in the forest.
※ (珍しい動物がその森で見られる。)
能動態と同じように、受動態でも助動詞を用いることがある。その際は、can be seenのように、〈助動詞+be+過去分詞〉という形になる。
044 受動態の様々な形(否定文)
日本語に合うように、( )内に適語を入れなさい。
1) この写真は私の兄が写したものではありません。
This picture (was) (not) (taken) by my brother.
※ 受動態の否定文は、上記のように〈be動詞+not+過去分詞〉という形で表す。
2) この箱は開けてはいけません。
This box must (not) (be) (opened).
※ 上記のように助動詞を使った受動態の否定文の場合には〈助動詞+not be+過去分詞〉の形になる。
〈受動態の否定文では準否定語もnotと同じ位置に置く〉
never(一度も~ない)や、hardly(ほとんど~ない)もnotと同じ位置で使うことができる。
・She was never allowed to go out at night.
(彼女は夜間に外出することを一度も許してもらえなかった。)
・This kind of custom would hardly be accepted in Japan.
(この種の習慣は日本でほとんど受け入れられないだろう。)
045 受動態の様々な形(Yes/No疑問文 / 疑問詞を使った疑問文)
日本語の意味に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) この化石はあなたのお父さんによって発見されたのですか?
(Was) this fossil (discovered) by your father?
※ 受動態のYes/No疑問文は、be動詞を文頭に出した〈be動詞+主語+過去分詞…?〉という形にする。助動詞を使う場合は、次のように助動詞を文頭に出すことになる。
・Will this door be painted tomorrow?
(このドアは明日ペンキを塗られるのですか。)
2) この鳥はどこでつかまえられたのですか?
(Where) (was) this bird (caught)?
※ 上記のwhereやwhenのような疑問副詞を使って、「いつ」「どこ」のように尋ねる場合は、疑問詞の後に〈be動詞+主語+過去分詞〉を続ける。
・When was this bridge built? (この橋はいつ造られたのですか)
3) ラジオはだれによって発明されたのですか?
(Who) was the radio (invented) (by)?
※ 「だれによって」のように、「する側」がだれ[何]なのかを尋ねるときは上記のようになる。
また、〈by+疑問詞〉をセットで文頭に出すこともできる。ただし、この形は文章体。
・By who was the radio invented?
〈参考〉次の文でも、疑問詞は前置詞の目的語の働きをしている。
・What is this tool used for? (この道具は何のために使われるのですか。)
046 語順に注意する受動態
( )内の動詞を適切な形にしなさい。
1) The actress (was asked) a lot of questions by the reporter yesterday.
※ (その女優は昨日、記者によってたくさんの質問をされた。)
上記では「尋ねる相手」の女優を主語にして、「尋ねられる」を表すwas askedを続け、その後に「尋ねられたこと」であるa lot of questionsを直接続けている。the reporterを主語にして能動態の文を作ると、次のようなSVOOの文になる。
・The reporter asked the actress a lot of questions.
2) He (is called) Ken by everyone now.
※ (彼は今、みんなにケンと呼ばれている。)
callは「相手を~と呼ぶ」という意味で使うことができる。「呼ぶ相手」を主語にすると、上記のような受動態の文を作ることができる。主語の後に「呼ばれている」を表すis calledを続け、その後に主語について述べる語(補語)を続ける。
everyoneを主語にして能動態の文を作ると、次のようなSVOCの文になる。
・Everyone calls him Ken now.
主語について説明する語について尋ねる疑問文は次のようになる。
・What is he called by everyone? (彼はみんなに何と呼ばれているの。)
3) The news (was told) to her by her aunt last night.
※ (その知らせは昨夜、彼女のおばによって彼女に告げられた。)
tellやsendのような「相手に物や情報をなどを届かせる」ことを表すgive型の動詞を使うと、上記文のような「物や情報」を主語にした受動態の文と下記のような「相手」を主語にした受動態の文を作ることができる。
・She was told the news by her aunt last night.
また、her auntを主語にして能動態の文を作ると、次のようなSVOOの文およびSVOの文になる。
・Her aunt told her the news last night.
・Her aunt told the news to her last night.
SVOの文において、前置詞は、give型の動詞であればtoを、buy型の動詞であれば、for を用いる。
give型: give, lend , show, hand, offer, pass, pay sell, send, teach, tell
buy型: buy, find , cook ,make, choose, get, leave, play, sing
・This apartment was found for me by my uncle.
(このアパートは、おじが私のために見つけてくれた。)
Toは人称代名詞が続く場合には省略することもある。ただしforを省略することはできない。
・This watch was given (to) me by my father.
(この腕時計は父さんがぼくにくれたんだ。)
〈注意〉buy型の動詞を使った受動態
buy型の動詞は、「相手」を主語にした受動態の文を作ることはできない。
・My mother made me a new dress. (母は私に新しいドレスを作ってくれた。)
→○A new dress was made for me by my mother.
→×I was made a new dress by my mother.
〈参考〉buyは例外的に2種類の受動態を作ることが可能。「買い与える」という
giveの意味合いが含まれる場合である。
・He bought me a nice pair of shoes. (彼は私にすてきな靴を買ってくれた。)
→○A nice pair of shoes was bought for me by him.
→△I was bought a nice pair of shoes by him. [ただし、この形はあまり使われない]
047 群動詞の受動態
( )内の群動詞を適切な形にしなさい。
1) The experiment (was carried out) by the students last month.
※ (実験は先月、生徒達によって実行された。)
複数の単語からなる群動詞は、まとめて1つの動詞とみなして受動態にする。上記文では、carry out~(~を実行する)を〈be動詞+過去分詞〉の形にしたため、was carried outとなっている。the studentsを主語にすると、The students carried out the experiment last month.という能動態の文ができる。
2) The typhoon was approaching, so the game (was put off).
※ (台風が近づいてきたので、その試合は延期された。)
3) When I was a child, a party (was looked forward to) by everybody.
※ (私が子供のころ、パーティーはみんなに楽しみにされていた。)
048 say, believeなどの受動態
次の文を日本語に直しなさい。
1) It is known that she is an excellent pianist.
彼女はすばらしいピアニストとして知られている。
※ say, believe, expect, know, thinkなど「言う」「考える/思う」といった意味をもつ動詞は、目的語にthat節を伴う場合、上記文のように主語にitを用いた受動態の文を作ることができる。
2) It was said that he was a son of a well-known actor.
彼は有名な俳優の息子だと言われていた。
※ 上記文はThey said that he was a son of a well-known actor.という能動態の文を作ることができる。itを主語にしてまでわざわざ受動態を作るのは、「ばくぜんとした人々」を指すtheyを主語にするのが好ましくないと感じられたり、theyがほかのだれかをさしているように見えて誤解を与えかねない場合などである。
〈参考〉that節の主語を文の主語にして、He was said to be a son of a well-known actor.という文を作ることもできる。
049 受動態で表す動作と状態 / getを使った受動態
次の文を日本語に直しなさい。
1) The gate is already closed.
その門はもう閉まっています。
※ 同じ動詞でも〈be動詞+過去分詞〉という形の受動態を使って、「~される」という「動作・変化」の意味と、「~されている」という「状態」の意味の両方を表す場合がる。上記文では「閉まっている」という「状態」を表す。どちらの意味で使われているかは文の内容や文脈から判断しなければならない。
2) The gate is usually closed at five.
その門はふつう、5時に閉まります。
※ 上記文では、「閉められる」という「動作」を表す。
3) My glasses got broken while I was playing soccer.
サッカーをしていた時に、私のメガネが壊れた。
※ 上記文のように、受動態を作るのに、be動詞の代わりにgetを使うことがある。getを使うのは、「~になった」のように変化を表す場合。
〈参考〉dress(~に服を着せる)のように、〈be動詞+過去分詞〉の形で状態を表し、〈get+過去分詞〉の形で動作を表すという具合に、両者を区別して使う動詞もある。
・She was dressed in red. (彼女は赤い服を着ていた。)
・She got dressed quickly. (彼女はすばやく服を着た。)
050 注意すべき受動態の表現(前置詞に注意/心理状態を表す受動態)
日本語の意味に合うように、( )内に適語を入れなさい。
1) 彼はそのニュースを聞いてがっかりした。
He (was) (disappointed) at the news.
※ 英語では、感情や心理状態を表す動詞の大部分は、「だれか(目的語)」をある心理状態にさせる」という意味の他動詞であるため、「~な気持ちになる」という意味を表すには、「~な気持ちにさせられる」という受動態で表す必要がある。
be surprised at[by]~(~に驚く)
be excited at[about]~(~に興奮している)
be satisfied with[at/about]~(~に満足する)
be disappointed at[about/in/with]~ (~にがっかりする)
be confused with[at/about]~(~に混乱する)
be shocked at[about]~(~にショックを受ける)
2) 彼女は新しい仕事に満足している。
She (is) (satisfied) with her new job.
3) 彼の祖父は戦争で命を落とした。
His grandfather (was) (killed) in the war.
※ 英語の受動態は、常に「られる」という日本語と対応しているわけではない。日本語では「ている」で表す表現を、英語では受動態で表すことがある。
・Helen is married to an artist. (ヘレンは芸術家と結婚している。)
・William was born and raised in New York.
(ウィリアムはニューヨークで生まれ育った。)
・Please be seated. (座ってください。)
〈受動態と間違えやすい表現〉
英語の自動詞の中には、受動態の形をとっているわけではないのに、日本語で考えると受動的な意味を表すものもある。
・Our new products are selling very well.
(我が社の新製品はとてもよく売れている。)
・This tough steak doesn’t cut easily.
(このかたいステーキはなかなか切れない。)
・Red wine stains don’t wash out easily.
(赤ワインのしみは、洗っても簡単には落ちません。)
・Your paper reads like a novel.
(あなたの論文は小説のように読める。)
第7章 不定詞(解説)
051 不定詞の名詞的用法
次の日本語の部分を不定詞を用いて英語にしなさい。
1) His ambition is (パイロットになること).
His ambition is to become a pilot.
※ (彼の野望はパイロットになることです。)
上記ではbe動詞の直後にto becomeという不定詞が続き、to became a
pilotが主語のHis ambitionの説明をしている。主語の内容を説明するのが補語な
ので、この不定詞は補語ということになる。不定詞は〈to+動詞の原形〉という形
で名詞の働きをすることができる。上記のように補語として使ったり、次のように
主語として使うこともできる。ただし、現代英語では不定詞を主語の位置におくこ
とはあまり見られない。
・To own a house is a dream of many Japanese.
(家を持つことは多くの日本人の夢だ。)
2) It is not easy(このレースに勝つこと).
It is not easy to win this race.
※ (このレースに勝つことは容易ではない。)
不定詞が主語になる場合は、上記のように形式主語のitを使ってIt is … という文の骨組みをまず見せ、その後に真の主語である不定詞を続けることが多い。
3) Why did you decide(先生になること)?
Why did you decide to become a teacher?
※ (なぜ君は先生になる決心をしたのですか?)
上記では他動詞のdecideの直後にto become a teacherという不定詞が続いている。このように、不定詞が名詞の働きをして他動詞の目的語になることもある。
なお、SVOCのOが不定詞の場合は、次のように形式目的語のitを使う。
・Sam finds it easy to make friends.
(サムは友人をつくることは簡単だと思っている。)
Sam finds it easyという文の骨組みをまず見せ、その後に真の目的語である不定詞を続けることになる。
052 不定詞の形容詞的用法
日本語に合うように、与えられた語句を並びかえて、英文を完成させなさい。
1) その老人には世話をしてくれる人が必要だ。
The old man needs (someone to look after him).
※ 上記のto look after himは直前の名詞someoneを修飾している。この文ではsomeoneはlook after himの主語の働きをしている。
2) 私には今読む本がない。
I have (no books to read) now.
※ 上記ではto readがno booksを修飾している。この文ではno booksはreadの目的語の働きをしている。
3) 父はチェスをしてくれる人を見つけた。
My father found (someone to play chess with).
※ 上記ではto play chess withがsomeoneを修飾している。この場合は、someoneは前置詞withの目的語の働きをしている。
〈参考〉修飾される名詞が前置詞の目的語の働きをする場合、その前置詞が省かれることもある。ただし、それは前置詞を省略しても文意に誤解が生じない場合である。
・I don’t have enough money to buy those shoes (with).
(その靴を買うのに十分なお金を持っていない。)
〈不定詞が「実際に起こったこと」を表す〉
文脈によっては、名詞を修飾する不定詞が「これからのこと」ではなく、「実際に起こったこと」を表す場合もある。
・They were the first men to land on the moon.
(彼らは初めて月に降り立った男たちだった。)
名詞を修飾する不定詞が「実際に起こったこと」を表す場合は、原則的に次の3つの条件を満たしている。
① 過去の事柄を述べた文の中で不定詞が使われている。
② 修飾される名詞が不定詞の主語の働きをしている。
③ 修飾される名詞にlast, onlyや、first, secondなどの助数詞、あるいは形容詞の最上級がついている。
4) 彼女は上野駅で私と待ち合わせるという約束を破った。
She broke (her promise to meet me) at Ueno Station.
※ 上記では、不定詞の直前にある名詞her promise(彼女の約束)がどういうものかを、to meet meという不定詞が説明している。このように、不定詞が直前の具体的な内容を説明することがある。この場合、Her promise is to meet me.という文をつくることができ、直前の名詞と不定詞の関係は「同格」と呼ばれる。
〈不定詞と同格の関係にできる名詞〉
① decision など(←decide toのような不定詞を目的語にする他動詞から派生した名詞が多い)
・We were surprised at her decision to become an actress.
(私たちは、女優になるという彼女の決心に驚いた。)
② ability など(←be able toのような不定詞を伴う形容詞から派生した名詞が多い)
・Whales have the ability to communicate with each other.
(クジラにはお互いに意思を伝え合うという能力がある。)
③ time, wayなど一部の限られた名詞
・It’s time to go.(もう行く時間だよ。)
・What is the best way to prevent cancer?
(ガンを予防するもっともよい方法は何ですか?)
053 不定詞の副詞的用法
次の文を日本語に直しなさい。
1) I went to the theater to buy a ticket.
私はチケットを買うために劇場に行った。
※ 上記文は、I went to the theater(私は劇場に行った)という行為の「目的」を、to buy a ticketという不定詞で表している。「目的」を表す不定詞は、直前にin orderやso asを加えてin order to buy …やso as to buy …とすることもある。
2) My mother was very glad to receive a letter from you.
私の母はあなたからの手紙を受け取ってとても喜んだ。
※ 上記文では、gladという形容詞にto receive a letter from youという不定詞が結びついて、「~して喜んだ」という意味になっている。このように、不定詞は感情を表す形容詞や動詞と結びつき、「感情の原因」を表すことができる。この場合、不定詞は「~して」と訳せることが多い。
・Jake was surprised to hear the news.
(ジェイクはその知らせを聞いて驚いた。)
3) You were lucky to see the famous actor.
その有名な俳優に会えるとは、あなたは幸運だった。
※ 上記文では、you were luckyと話し手が判断した根拠を、to see the famous actorで示している。このように、話し手の判断を示す表現と結びついて、不定詞がその判断の根拠を表すことがある。話し手の判断は、上記文でのlucky(幸運な)のような人物評価を表す形容詞で示される。判断の根拠を表す不定詞は、「~するとは」と訳せることが多い。
kindやcarelessのような人物評価を表す形容詞が判断の根拠を表す不定詞を伴う場合、次のように〈It is[was]+形容詞+of+人+to不定詞〉「~するとは〈人〉は…だ[だった]」という形にすることができる。
・It is kind of you to help me. (手伝ってくださるなんて、ご親切ですね。)
・It was careless of you to make such a mistake.
(そんな間違いをするなんて、君は不注意だったね。)
〈人物評価を表す形容詞〉
kind/good/nice(親切な)
polite(ていねいな)
rude(無礼な)
brave(勇敢な)
smart/clever/wise(賢明な)
foolish/silly/stupid(愚かな)
careless(不注意な)
〈参考〉〈It is[was]+形容詞+of+人+to不定詞〉が感嘆文になると、it is はふつ
う省略される。
・How brave (it is) of you to save the child from the fire!
(子どもを火事から助けたなんて、君はなんて勇敢なんだ!)
4) The bird flew away, never to return.
その鳥は飛び去って、二度と戻ってくることはなかった。
※ 上記文は、The bird flew away(その鳥が飛び去った)の後に、不定詞のnever to returnを続けて、「飛び去った、そして二度と戻ってこなかった」という意味を表している。この不定詞は、何かをした結果どうなったのか、という「結果」を表している。また、結果を表す不定詞の前にneverを入れて〈~, never to不定詞〉という形にすると「~, そして二度と…しなかった」という意味を表すことができる。(neverの前にコンマを入れることが多い)
〈成長して~になる〉
次のように、成長して何かになったことを表すときにも不定詞を使うことができる。
・He grew up to be a professional soccer player.
(彼は成長してプロのサッカー選手になった。)
〈only to 不定詞〉
結果を表す不定詞の前にonlyを入れて〈~, only to不定詞〉とすると「~、しかし結局…しただけのことだった」という意味になる。(onlyの前にコンマを入れることが多い)
・We ran to the store, only to find it closed.
(私たちは店まで走ったが、閉まっていることがわかっただけだった。)
ただし、不定詞の前にonlyが置かれていれば、必ず「結果」を表すというわけではない。次のように「目的」を表すこともある。
・He bought an expensive car only to please her.
(彼は、彼女を喜ばせるためだけに、高価な車を買った。)
〈直前の形容詞を修飾する不定詞〉
不定詞の副詞的用法には、直前の形容詞を修飾する用法もある。
・The older managers were slow to accept the new technology.
(年配の経営者たちは、新しい技術を受け入れるのが遅かった。)
054 SVO+to不定詞
日本語の意味に合うように、与えられた語句を並べかえて、英文を完成させなさい。
1) 私の父は私がその自転車を買うことを許してくれた。
My father allowed (me to buy the bicycle).
※ 上記の〈allow+O+to不定詞〉は「Oが~するのを許す」という意味になる。相手が何かを実行することを表す「Oに~させる」という意味を表している。
〈allowと同じ使い方をする動詞〉
allow(~するのを許す/許可する)
cause((結果的に)~させる)
compel(無理やり~させる)
enable(~することを可能にする)
force(無理やり~させる)
get(~してもらう)
permit(~するのを許す/許可する)
2) 警察は群衆を強制的にその広場から出させた。
The police forced (the crowd to leave the square).
3) 彼は私に休みをとるように勧めた。
He advised (me to take a day off).
※ 〈advise+O+to不定詞〉の形で、「Oに~するように勧める」という命令や依頼を表している。
〈adviseと同じ使い方をする動詞〉
tell(~するように言う/命令する)
advise(~するように勧める/忠告する)
ask(~するように頼む)
warn(~するように警告する/注意する)
〈その他のSVO+to不定詞で使う動詞〉
want(~してほしい)
expect/prefer(~することを望む)
persuade(説得して~させる)
remind(~することを思い出させる/気づかせる)
〈注意〉〈SVO+to不定詞〉では使えない動詞→that節を使う
suggest(提案する)
hope(望む)
・I suggest that you should stay at that hotel.
(そのホテルに泊まることをお勧めします。)
「~だと思う」の意味の動詞が〈SVO+to不定詞〉で使われる場合
believe, consider, thinkなど、「~だと思う」の意味の動詞は〈SVO+to be+補語〉の形をとれるものが多い。
・I believe him to be a genius.(私は彼が天才だと思う。)
(= I believe that he is a genius.)
know(~だと考える)
understand(~だと了解する)
feel(~だと感じる)
find(~だとわかる)
055 不定詞の意味上の主語
不定詞の意味上の主語を指摘して、全文を日本語に直しなさい。
1) It is difficult for me to solve the problem.
me 私がその問題を解くのは難しい。
※ 上記文では、「私がその問題を解く」という意味になるように、for meで、不定詞to solveの意味上の主語を示している。このように、不定詞の意味上の主語を示す必要がある場合は、不定詞の直前にfor~を置き、〈for~+to不定詞〉の形にする。この場合、for の後の(代)名詞が不定詞の意味上の主語である。forの後には名詞や目的格の代名詞を置き、主格の代名詞は置けないことに注意。
〈注意〉人物評価を表す形容詞と不定詞の意味上の主語
〈It is+形容詞+of+人+to不定詞〉の形をとる場合は、to不定詞の意味
上の主語はof の後の「人」である。
・It is kind of you to help me.
(手伝ってくださるなんて、あなたはご親切ですね。)
2) It was a mistake for the government to carry out the plan.
the government 政府がその計画を実行したのは誤りでした。
3) I want my father to stop drinking so much.
my father 私は父に(お酒を)飲みすぎるのをやめてほしい。
※ 上記文では、stop (やめる)するのは、want の目的語のmy fatherである。このように〈SVO+to不定詞〉の文では、動詞の目的語が不定詞の意味上の主語になる。
ただし、次の文のように、文の主語が不定詞の意味上の主語になる場合もある。
・He promised me to send a postcard from Hawaii.
(彼は私に、ハワイからはがきを送ると約束した。)
[はがきを送るのは「私」ではなく、主語の「彼」である。]
056 不定詞の否定語(副詞)の位置
日本語に合うように、与えられた語句を並べかえて、英文を完成させなさい。
1) 医者は私の父にたばこを吸わないようにと警告した。
The doctor warned (my father not to smoke).
※ 不定詞を否定するnot やneverなどの副詞は、toの直前に置く。上記文では、notが直後の不定詞to smokeを否定して、「たばこを吸わない」という意味になる。
〈注意〉目的を表す不定詞の否定形
「~しないように」という否定の意味にする場合は、〈in order not+to不定詞/so as not+to不定詞〉を用いる。〈not+to不定詞〉だけで目的を表すことはほとんどない。
・I studied hard in order not to fail the exam.
(試験に落第しないように、がんばって勉強した。)
2) 姉は決して間食しないことにしている。
My sister makes it a rule (never to eat) between meals.
057 使役動詞・知覚動詞を使った表現
( )内の語句のうち、正しい方を選びなさい。
1) Let me (try) it again.
※ (もう一度、それを私に試させて。)
上記は、let me tryで「私に試させる」という意味になる。〈let+O+動詞の原形〉は、「Oが~することを許す/許可する」という意味を表す。このようにmake, let, haveは目的語の後にto不定詞ではなく、動詞の原形を置く。この形をとるmake([無理やり]~させる), let, have(~してもらう/させる)は使役動詞と呼ばれ〈使役動詞+O+動詞の原形〉の形になる。
・My mother made me wait outside the store.
(母は私をその店の外で待たせた。)
・He had the doctor look at his leg.
(彼はその医者に足を見てもらった。)
〈参考〉〈Let me[us]+動詞の原形〉は、文脈によっては「~しよう」という申し出
を表すこともある。ただし、let’sの場合は勧誘の意味だけ。
・Let me give you a hand.(お手伝いしましょう。)
・Let’s go at once.(今すぐ行きましょう。)
〈参考〉〈have+O+動詞の原形〉は、相手にそうしてもらえるのが当然というよう
な行為に対して使う。「目上の人に何かを無償でしてもらう」という場合に
は使わない。
〈参考〉helpは〈help+O+to不定詞/動詞の原形〉
「Oが~するのを手伝う」という意味で、目的語の後にto不定詞と動詞
の原形のどちらを置いてもよい。
・Can you help me (to) put up the tent?
(私がテントを張るのを手伝ってくれませんか。)
2) I heard someone (shout) in the distance.
※ (私は誰かが遠くで叫ぶのを聞いた。)
see, hear, feelのような知覚を表す動詞は、目的語の後に動詞の原形を置いて「Oが~するのを見る/聞く/感じる」という意味を表すことができる。この形をとる動詞は知覚動詞と呼ばれ、〈知覚動詞+O+動詞の原形〉という形で使う。
〈他の知覚動詞〉
notice(気づく), observe(気づく), watch(見守る), listen to(聞く), look at(見る)など。
3) The boy was made (to turn) off the TV by his mother.
※ (その少年は母にテレビを消させられた。)
makeを受動態にして「~させられた」という意味を表すときは、動詞の原形ではなく、to不定詞が使われる。
seeやhearを受動態にして「~するのを見られた/聞かれた」という意味を表すときにも動詞の原形ではなく、to不定詞が使われる。
なお、使役動詞のletとhaveおよび知覚動詞のfeel, notice, watch, listen to, look atは、ふつうは受動態にしない。
4) I noticed a tall man (enter) the building.
※ (私は背の高い男がその建物に入るのに気付いた。)
5) I’ll get my father (to buy) a new computer.
※ (私は、父に新しいコンピューターを買ってもらいます。)
getを使って〈have+O+動詞の原形〉と同じような意味を表すことができる。getを使うのは相手を説得して何かをしてもらうような場合で、〈get+O+to不定詞〉の形になることに注意。
058 不定詞のさまざまな形
各組の文がほぼ同じ意味になるように、( )に適語を入れなさい。
1) It seems that you are interested in my success story.
You (seem) (to) (be) (interested) in my success story.
※ 君は僕の成功話に興味があるようだね。
「Sは~のようだ/Sは~らしい」は、〈S seem+to不定詞〉や〈S appear+to不定詞〉で表現できる。(apperはどちらかというと客観的な状況を表す場合に用いられるのがふつう。) これは、何かを見た時点でのその様子を表す表現である。上記では、「君は僕の成功話に興味があるようだ」と今のことを述べている。またthat節を使った表現にする場合はIt seems that … で表す。このitは「ばくぜんとした状況」を表す。なお、seem to be / appear to beのto beは省略できることが多い。
・The children seemed[appeared] happy.(子供たちは幸せそうでした。)
ただし、to beの後に置かれる表現が程度の差を問題としない場合は、to beの省略はできない。
・He seems to be a teacher.(彼は先生のようだ。)
・He seems (to be) a good teacher.(彼はよい先生のようだ。)
[どのような先生かという程度を表しているのでto beを省略できる。]
2) It seems that he told a lie.
He (seems) (to) (have) (told) a lie.
※ (彼は嘘をついたらしい。)
上記のIt seems that … の文では、that節の中の動詞は過去形である。これをseem
toの文にする場合、述語動詞のseemが表す時よりも以前のことは〈to have+過去
分詞〉で表す。上記文では、彼が嘘をついたのは、seemが表す時よりも前のこと
である。
また、「彼は嘘をついたらしかった。」という文にする場合は次のようになる。
・He seemed to have told a lie.
不定詞がto have told a lieになっているので、「彼が嘘をついた」のは、seemedが
表す時よりも以前のことになる。したがって、It seemed that … の文にすると、told
は次のように過去完了形となる。
・It seemed that he had told a lie.
〈to have+過去分詞〉が現在完了形に相当する内容を表す場合
〈to have+過去分詞〉で表現される事柄が現在とつながりをもっているときには、
〈to have+過去分詞〉が現在完了形に相当する内容を表す。
・These tourists seem to have lost their way.
(= It seems that these tourists have lost their way.)
(この観光客たちは道に迷ってしまった。)
〈S is said to不定詞〉で「Sは~だと言われている」を表す。
〈It is said that …〉で、「…だと言われている」という意味を表す。このthat節の主語を文の主語にして〈S is said to不定詞〉とすると、「Sは~だと言われている」という意味を表すことができる。
・His mother is said to be an actress.(彼の母は女優だと言われています。)
「Sは~だったと言われている」という以前のことを表すときは、完了形の不定詞を使って、〈S is said to have+過去分詞〉とする。
・His mother is said to have been an actress.
(彼の母親は女優だったと言われています。)
3) It seems that the baby in that car is crying.
The baby in that car (seems) (to) (be) (crying).
※ (あの車の中の赤ちゃんが泣いているようです。)
進行形に相当する内容を不定詞で表現する場合には、上記のように〈to be+-ing〉
の形を使う。〈seem to be+-ing〉で「~しているようだ」という意味を表す。
4) I don’t want anyone to do it so carelessly.
I don’t want it (to) (be) (done) so carelessly.
※ (私はそれを不注意にしてほしくない。)
受動態を不定詞で表現するときには、上記のように〈to be+過去分詞〉の形にする。
〈want to be+過去分詞〉で「~されたい」という意味を表している。
059 自動詞+to不定詞(happen/prove/turn/come/get+to不定詞)
日本語の意味に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) 私はたまたまその歌手のとなりに座った。
I (happened) (to) (sit) next to the singer.
※ 〈S happen+to不定詞〉で「Sが偶然~する/たまたま~する」の意味となる。
また、〈S happen+to不定詞〉は、〈It happens that …〉という形を使って次のよ
うに表すことができる。
・It happens that I sit next to the singer.
2) その絵はにせものであることがわかった。
The painting (turned) (out) (to) be a fake.
※ 〈S turn out+to be〉(=〈S prove+to be〉)で「Sは…だとわかる/判明する」という意味になる。このto beは省略することが多い。
また〈S turn out+to不定詞〉は、〈It turns out that …〉という形を使って次のよ
うに表すことができる。
・It turns out that the painting was fake.
3) どうやって彼女と知り合いになったのですか。
How did you (come[get]) (to) know her?
※ 〈come+to不定詞〉、〈get+to不定詞〉で「~するようになる」の意味になる。comeの代わりにbecomeを使うことはできない。come to/get toの後にはlikeやknowのような状態動詞を続ける。
060 自動詞+to不定詞(be to不定詞)
次の文を日本語に直しなさい。
1) We are to meet at the art museum tomorrow.
明日私たちは美術館で会うことになっています。
※ be toは助動詞と同じような働きをし、一般に〈be to不定詞〉と呼ばれ、おもな意味は3つ(①予定「~することになっている」②義務・命令「~すべきである/~しなければならない」③可能「~できる」)。上記は「~することになっている/~する予定だ」の意味で「予定」を表す。
〈参考〉〈be to不定詞〉には次のような用例もある。
・He was never to return to his hometown.
(彼は二度と故郷に帰ることはなかった。)[運命]
・If you are to pass the exam, you’d better study hard.
(その試験に受かりたいのなら、必死で勉強しなさい。)[意図]
意図を表すのはこの文のように条件を表す文で使われる場合である。
2) Not an animal was to be seen in the desert.
その砂漠では動物は一匹も見かけなかった。
※ 上記の〈be to不定詞〉は「~できる」の意味で、「可能」を表す。ただし、この意味になるのは否定の内容の文で、不定詞が〈to be+過去分詞〉の形になっている場合である。
3) You are to return the book to me by tomorrow.
あなたはその本を明日までに私に返すべきだ。
※ 上記の〈be to不定詞〉は「~すべきである/~しなければならない」の意味で、「義務・命令」を表す。
061 不定詞の注意すべき用法(難易を表す形容詞+to 不定詞 / too … to不定詞 / … enough to不定詞 / so … as to不定詞 / so as to不定詞 / in order to不定詞)
日本語の意味に合うように、あたえられた語句を並べかえて、英文を完成させなさい。
1) 彼女とうまくやっていくのは難しい。
She is (hard to get along) with.
※ 〈S is+形容詞+to不定詞〉の形で、主語に対する話し手の評価を表すことができる。上記文の場合は、「彼女」について「うまくやっていくのが難しい」と述べている。ここでは、主語のSheはto get alongの後の前置詞withの目的語の働きをしている。このような意味になるのは、形容詞がおもに難易などを表す場合である。
〈難易などを表す形容詞〉
easy(簡単な)
difficult / hard(難しい)
impossible(不可能な)
dangerous(危険な)
comfortable(快適な)
また、上記文は、形式主語を使って次のように表現できる。
・It is hard to get along with her.
2) そのかばんは片手で運ぶには重ずぎる
The bag is (too heavy to carry) in one hand.
(= The bag is so heavy that I can’t carry it in one hand.)
※ 〈too+形容詞/副詞+to不定詞〉は「~するには…すぎる」という意味。
3) 彼女はその講義を理解することができるくらいには賢かった。
She was (smart enough to understand) the lecture.
(= She was so smart that she understood the lecture.)
※ 〈形容詞/副詞+enough to不定詞〉で「~するのにちょうど必要なだけ…/~するのに十分…」という意味を表す。〈so … that+肯定文〉で表現することができる。ただし、次のような場合はできない。
・He is old enough to buy alcohol.(彼はお酒を買うことのできる年齢だ。)
→×He is so old that he can buy alcohol.
He is so oldとすると、「彼はとても年をとっている」という意味を表すことに
なる。
〈参考〉enoughとto不定詞のあいだに不定詞の意味上の主語が入ることもある。
・This problem is easy enough for me to solve.
(この問題はぼくが解けるほど簡単だ。)
4) その若い男の人は、勇敢にもおぼれている子供を救った。
The young man was (so brave as to save) the drowning child.
※ 〈so+形容詞/副詞+as to不定詞〉は、〈… enough to不定詞〉同様、「~するほど…」を表現できる。ただし、この表現ではsoの直後に形容詞や副詞を置く。この表現はややかための文体である。
5) 私のいとこはその資格を取るために一生懸命勉強した。
My cousin studied hard (in order to get the license).
※ 不定詞が「目的」を表すことをはっきりと示すために、上記のような〈in order to不定詞〉や〈so as to不定詞〉が使われる。
「~しないように」という否定の意味を表すときには、〈in order not to
不定詞〉や〈so as not to不定詞〉が使われる。
062 不定詞の注意すべき用法(疑問詞+to不定詞 / 独立不定詞 / 代不定詞)
日本語の意味に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) 今日何をすべきか教えてください。
Tell us (what) (to) do today.
※ 〈疑問詞+to不定詞〉は「疑問詞の意味+~すべきか[できるのか]」という意味になる。上記のwhat to doは「何をすべきか」という意味。
how to
You should teach your children how to swim.
(あなたは自分の子供たちに泳ぎ方を教えるべきです。)
who to
I thought about who to invite to the party.
(私はパーティーにだれを招待すべきか考えた。)
what to
I don’t know what to do next.
(私は次に何をすればよいのかわからない。)
where to
Do you know where to buy the tickets?
(チケットをどこで買えばよいかご存知ですか?)
when to
Ask your teacher when to start.
(いつ出発すればよいか、先生に尋ねなさい。)
〈whether to不定詞〉
疑問詞の代わりに「~かどうか」の意味のwhetherが使われることもある。
・I can’t decide whether to accept his request.
(彼の要求に応じるべきかどうか決心がつかない。)
2) どうやったらその計画を実行できるかが問題だ。
(How) (to) put the plan into practice is the question.
※ 上記のhow to … は「どのように…すべきか」の意味。
3) 言うまでもないことだが、健康は富に勝る。
(Needless) (to) (say), health is above wealth.
※ 独立不定詞慣用句に使われる不定詞の表現
needless to say(言うまでもないことだが)
to tell the truth(実を言えば)
strange to say(奇妙なことに/不思議な話だが)
to be honest(正直に言って/正直なところ)
so to speak(いわば)
to be frank (with you)(率直に言うと)
to be brief(手短に言えば/要するに)
to begin with(まず第一に)
to make matters worse(なお悪いことには/なお困ったことには)
to say nothing of ~(~は言うまでもなく)
not to say~(~とは言えないまでも)
to be sure(確かに)
4) 「このかばんを運ぶのを手伝っていただけますか。」「もちろん、よろこんで。」
“Could you help me with this bag?” “Sure, I’d be happy (to).”
※ 上記文では、前の発言に出てきたhelp me with this bagを受けて変換されるべきhelp you with this bagが後の発言のtoの後で省略されている。このようにto不定詞のtoの後では、反復を避けるために前に出てきた動詞を省略することがある。このtoは代不定詞と呼ばれる。
ただし、be動詞の場合にはtoだけでなく、to beを残す。
・He is not a good actor, and he doesn’t even try to be.
(彼はよい俳優ではないし、そうなろうとすらしていない。)
第8章 動名詞(解説)
063 動名詞の働き
( )内の動詞を適切な形にしなさい。
1) (Making) model cars is my hobby.
※ (模型の車を作ることが僕の趣味です。)
上記文では、文頭にMaking model carsというing形を使った句がある。この後にis my hobbyと続くので、Making model carsは主語の働きをしていると考えられる。
2) One American tradition is (eating) turkey on Thanksgiving Day.
※ (あるアメリカの伝統は感謝祭に七面鳥を食べることです。)
上記の主語はOne American tradition(あるアメリカの伝統)で、それがどういうものかを、動詞のing形を使ったeating turkey(七面鳥を食べる)で表している。主語がどういうものかを説明するのは補語の役割なので、このeating turkeyは補語ということになる。
〈動名詞と不定詞の表す意味〉
動名詞は「習慣的行為や一般論」を表すことができる。一方、不定詞には、「…したい/…すべき/…できる」という「実行への希望・意志」などが含まれる。すべてが、このようなパターンにあてはまるわけではないが、一般的なに動名詞・不定詞がこのように使われるということは覚えておくとよい。
〈動名詞が主語の場合に、形式主語のitを使うこともある〉
・It is enjoyable living by the sea. (海の近くで生活するのは楽しい。)
この例文ではItは形式主語で、living by the seaが真の主語になっている。実際にそこに住んでいるような場合は、このように動名詞を使う。
3) I enjoy (reading) books in the library.
※ (私は図書館で本を読むのが好きです。)
上記文のreading booksは動詞のenjoyの直後に置かれ、enjoyの目的語となっている。このように、動名詞は他動詞の目的語になることもできる。
〈動名詞が目的語の場合に、形式目的語を使うこともある〉
・I found it comfortable lying on the grass.
(芝生の上で横になるのは気持ちのいいものだと思った。)
この文では、itはfoundの形式目的語で、lying … が真の目的語。実際にやってみてそう思ったような場合は、このように動名詞を使う。
〈need –ing / want -ing〉
・This shirt needs washing. (このシャツは洗濯をしなければならない。)
・These shoes want polishing.(この靴はみがかなければならない。)
この場合のing形は名詞と考えればよい。need washingであれば「洗濯の必要がある」という意味で、need a washという名詞を使った表現と同じような意味を表しているのである。同じ内容を不定詞を使って表す場合には、〈need to be+過去分詞〉という受動態にする必要がある。
・This shirt needs to be washed.
・These shoes need to be polished.
4) Mike is fond of (watching) horror movies.
※ (マイクはホラー映画を見るのが好きです。)
上記文では、前置詞ofの直後にwatching horror moviesというing形が続いている。前置詞の直後には名詞が来るので、このbakingは、名詞の働きをする動名詞である。このように、動名詞は前置詞の目的語として使うこともできる。
064 動名詞の意味上の主語と否定語の位置
日本語の意味に合うように、( )内に適合を入れなさい。
1) 私の母は、私の兄が写真家として働いていることを自慢に思っている。
My mother is proud of (my) (brother’s[brother]) (working) as a photographer.
※ 上記文では、名詞my brother’sがworkingの意味上の主語になっている。名詞の場合は所有格かそのままの形で動名詞の前に置く(無生物主語の場合はそのままの形がふつう。
2) あなたが私の部屋でたばこを吸うのが嫌です。
I don’t like (your[you]) (smoking) in my room.
※ 上記文では、動名詞smokingの直前に置かれた所有格の代名詞yourが意味上の主語。your smokingで「あなたがたばこを吸うこと」という意味になる。意味上の主語を示さないと、たばこを吸うのは文の主語の「私」になってしまう。意味上の主語が代名詞の場合、他動詞の後では目的格が自然に感じられるので、目的格になることも多い。
3) 私は食事の作法を知らないことに恥じ入っています。
I am ashamed of (not) (knowing) table manners.
※ 動名詞を否定するnotやneverなどの副詞は、動名詞の直前に置く。この文では「テーブルマナーを知らないこと」を表すために、not knowing table mannersという形になっている。
065 動名詞のさまざまな形
日本語の意味に合うように、( )に適合を入れなさい。
1) 私は父に怒られることを恐れていました。
I was afraid of (being) (scolded) by my father.
※ 動名詞を受動態で表現するときには〈being+過去分詞〉の形にする。上記文では、being scolded(怒られること)という受動態の動名詞が前置詞ofの目的語になっている。scold me(私を怒る)のmeが文の主語になっているので、「怒られる」という受動態の表現にする必要がある。
2) ジェーンはその花びんを割ったことを認めました。
Jane admitted (having) (broken) the vase.
※ 述語動詞が表す時よりも以前のことを動名詞で表すときは、〈having+過去分詞〉という形にする。that節を使って次のように表現することもできる。
・Jane admitted that he had broken the vase.
3) 私はその芝居の第一幕を見逃したことを後悔しています。
I regret (missing) the first act of the play.
※ 文脈から時の関係が明らかな場合は、完了形の動名詞を使わなくてもよい。
・He remembered meeting her once before.
(彼は以前に一度会ったことを覚えていた。)
・The man admitted stealing her purse
(その男は彼女のハンドバッグを盗んだことを認めた。)
〈この形で使うことのできる動詞〉
remember(覚えている)
admit(認める)
deny(拒否する)
regret(後悔する)
066 動名詞を使った重要表現
日本語の意味に合うように、( )に適合を入れなさい。
1) 私は通信販売のカタログが届くのを楽しみに待っている。
I’m (looking) (forward) (to) receiving the mail-order catalogue.
※ look forward to –ingは「~することを楽しみに待つ」という意味。この表現では、toにつられて動詞の原形を続けないように注意。be used to –ing / be accustomed to -ing(「~することに慣れている」)も同様に注意。
・The boy is used to making his own breakfast.
(その男の子は、自分で朝食を作ることに慣れている。)
2) 私が勝ったという事実は否定できない。
(There) (is) (no) denying the fact that I was the winner.
※ there is no –ingは「~できない」という意味。
3) 私はコーヒーを飲みたい気がする。
I (feel) (like) (drinking) a cup of coffee.
※ feel like –ingは「~したい気がする」という意味。
〈動名詞を使った慣用表現〉
It is no use[good] –ing 「~してもむだだ」
・It is no use[good] worrying about the past.
(過去のことをくよくよしてもむだだよ。)
Would you mind –ing? 「~していただけませんか?」
・Would you mind repeating that?(もう一度言っていただけませんか)
Would you mind my[me] –ing? 「~してもかまいませんか」
・Would you mind my sitting here?(ここに座ってもかまいませんか)
keep[prevent/stop] O from –ing 「Oが~するのを防ぐ/妨げる」
・The doctors tried to keep[prevent/stop] the virus from spreading.
(医師たちはそのウイルスがまん延するのを防ごうとした。)
worth –ing 「~する価値がある/~するに値する」
・The museum is worth visiting.(その美術館は、訪れる価値がある。)
How about –ing? 「~するのはどうですか」
・How about going for a swim?(泳ぎにいきませんか。)
on –ing 「~と同時に/~するとすぐに」
・On seeing the man’s faced, she panicked.
(その男の顔を見たとたん、彼女はうろたえた。)
in –ing 「~しているあいだに/~する時に」
・I slipped in getting off the train.(電車を降りる時にすべった。)
〈参考〉〈動名詞+名詞〉で「~するための…」という意味を表す
sleeping car(寝台車)
waiting room(待合室)
dining room(食堂)
frying pan(フライパン)
067 動名詞と不定詞(動名詞を目的語にする他動詞 / 不定詞を目的語にする他動詞)
( )内の語句のうち、正しいほうを選びなささい。
1) Have you considered (moving) out of this country?
※ (あなたはこの国から出て行くことをよく考えたことがありますか)
consider –ing は「~することをよく考える」という意味。
〈動名詞を目的語にする他動詞〉不定詞を目的語にすることはできない。
admit(認める)
avoid(避ける)
deny(否定する)
enjoy(楽しむ)
escape(避ける、免れる)
finish(終える)
imagine(想像する)
mind(いやがる)
miss(しそこなう)
practice(練習する)
quit(やめる)
stop(やめる)
suggest(提案する)
give up(あきらめる)
put off(延期する)
2) Sorry. I didn’t mean (to offend) you.
※ (すみません。私はあなたを怒らせるつもりはありませんでした。)
mean to不定詞は「~するつもりである」という意味。
〈不定詞を目的語にする他動詞〉動名詞を目的語にすることはできない。
care(したいと思う)
decide(決心する)
desire(強く望む)
expect(するつもりである)
hope(したいと思う)
manage(どうにか~する)
offer(しようと申し出る)
pretend(ふりをする)
promise(約束する)
refuse(拒む)
want(したいと思う)
wish(したいと思う)
3) He refused (to come) with us.
※ (彼は私たちと来ることを拒んだ。)
refuse to不定詞は「~することを拒む」という意味。refuseは動名詞を目的語にすることはできない。
4) May I suggest (taking) a vote on this matter?
※ (この件については投票で決めることを提案してもよろしいですか。)
suggest –ing は「~することを提案する」という意味。suggestは不定詞を目的語にすることはできない。
068 動名詞と不定詞 (目的語が動名詞と不定詞で意味が異なる他動詞 / 目的語が動名詞でも不定詞でもよい他動詞 / 動名詞と不定詞の使い分けに注意すべき表現)
日本語の意味に合うように、( )内の語句のうち、正しいほうを選びなさい。
1) 間違いを見つけてみなさい。
Try (to find) the error.
※ 上記文のtry to不定詞は「~しようと試みる/努力する」という意味。try –ing にすると「(試しに)~してみる」という意味で「実際にやってみること」を表す。
2) ジムは試しにベッドのかわりにふとんで寝てみた。
Jim tried (sleeping) on a futon instead of a bed.
※ 上記文のtry –ing は「(試しに)~してみる」という意味で「実際にやってみること」を表す。
〈目的語が動名詞と不定詞で意味が異なる他動詞〉
forget
forget –ing 「~したことを忘れる」
forget to不定詞「~し忘れる」
・I’ll never forget meeting her.(彼女に会ったことは決して忘れません。)
・Don’t forget to meet her.(彼女に会うのを忘れないでね。)
remember
remember –ing「~したことを覚えている」
remember to 不定詞「~することを覚えている/~忘れずに~する」
・Do you remember locking the door?
(ドアのカギをかけたことを覚えていますか)
・Please remember to lock the door.
(ドアのカギをかけるのをおぼえておいてね。)
regret
regret –ing「~したことを後悔する」
regret to不定詞「~残念ながら~しなければならない」
・I regret rejecting your offer.
(私はあなたの申し出を断ったことを後悔しています。)
・I regret to say that we must reject your offer.
(残念ながら、あなたの申し出をお断りしなければなりません。)
〈目的語が動名詞でも不定詞でもよい他動詞〉
begin(始める)
cease(やめる)
continue(続ける)
hate(嫌う)
intend(するつもりである)
like(好む)
love(大好きである)
neglect(しない/し忘れる)
start(始める)
3) もう雨はやみましたか?
Have it stopped (raining) yet?
※ 上記のstop –ingは「~するのをやめる」という意味。一方、stop to不定詞という表現は、「~するためにそれまでしていたことをやめる/~するために立ち止まる/立ち止まって~する」という意味になる。この場合のstopは自動詞で、to不定詞は副詞的用法である。
・He stopped taking pictures.(彼は写真を撮るのをやめた。)
・He stopped to take pictures.(彼は写真を撮るために立ち止まった。)
〈動名詞と不定詞の使い分けに注意すべき表現〉
① be anxious
be anxious about –ing「~を心配している/不安に思って入る」
be anxious to不定詞「~するこを切望している」
・I am anxious about traveling alone.
(私はひとりで旅行することを不安に思っている。)
・I’m very anxious to travel alone.
(私はひとりで旅行に行きたいのです。)
② go on
go on –ing「~し続ける」
go on to不定詞「続けて~する/次に~する」
・They went on arguing until 2 a.m.
(彼らは朝の2時まで議論を続けた。)
・He went on to explain how to use the machine.
(彼は、次にその機械の使い方を説明した。)
③ be sure[certain]
be sure of –ing 「(主語)は~を確信している」
be sure to不定詞「(主語)はきっと~する/~するのは確実である」
・Roland is sure of being accepted by that school.
(ローランドはあの学校に入学できると確信している。)
・Roland is sure to pass the test; he has been studying for weeks.
(ローランドが試験に合格するのは確実だ。何週間もずっと勉強してき
たんだから。)
第9章 分詞(解説)
069 名詞を修飾する分詞(限定用法)
( )内の動詞を適切な分詞の形に変えなさい。
1) She was shocked at the (broken) guitar.
※ (彼女は壊れたギターにショックを受けた。)
上記文のbrokenはguitarを修飾している。このように、分詞は名詞を修飾し、その意味を限定することができる。これを分詞の限定用法と呼ぶ。上記文のように、名詞を修飾する1語の分詞は、修飾する名詞の直前に置くことができる。この場合、修飾する名詞は分詞の意味上の主語となり、過去分詞は受動の意味を表し、次のような現在分詞は能動の意味を表す。
・Someone is in that burning house! (だれかがあの燃えている家の中にいるぞ。)
上記の2文からは次のような文を作ることができる。
The guitar was broken.
That house is burning.
2) There is a cat (sleeping) on the roof.
※ (屋根の上で寝ている猫がいる。)
上記文ではsleeping on the roofが直前の名詞a catを修飾している。この場合も、分詞は名詞を修飾し、その意味を限定することができる。これも限定用法である。分詞には上記文のような現在分詞と次のような過去分詞がある。
・The picture painted by a little girl won the contest.
(小さな少女によって描かれた絵が、コンテストで優勝した。)
上記の2文からは、次のような文を作ることができる。(分詞に修飾される名詞は、その分詞の意味上の主語)
A cat is sleeping on the roof.
The picture was painted by a little girl.
3) This is a picture (painted) by Picasso.
※ (これはピカソによって描かれた絵です。)
4) She received (disappointing) news.
※ (彼女はがっかりさせるような知らせを受けた。)
分詞の中には、動詞としての性質が薄れ、形容詞として使われているものが多くある。上記のdisappointingはdisappointの現在分詞形で、disappointは「(人)をがっかりさせる」という意味の他動詞である。したがって、disappointingは「(人)をがっかりさせる」という能動の意味をもつことになる。また、次の文のように過去分詞形のdisappointedは「がっかりさせられた(人) (→がっかりした(人))」という受動の意味をもつことになる。
・I saw a lot of disappointed supporters.
(私はたくさんのがっかりしたサポーターを見かけた。)
「がっかりしているサポーター」という日本語からdisappointing supportersとしてしまいがちだが、これだと「(人)をがっかりさせる観客」という意味になってしまう。
〈参考〉〈分詞+名詞〉には、日常的によく使われるものがある。日本語化していて聞いたことのある表現も多いはずだが、カタカナ語と英語の違いに注意。
boiled egg (ゆで卵)
fried chicken(フライドチキン)
iced tea(アイスティー)
stained glass(ステンドグラス)
smoked salmon(スモークサーモン)
boiling water(熱湯)
frozen food(冷凍食品)
rising sun(日の出)
used car(中古車)
070 補語になる分詞(叙述用法) (SV+分詞)
( )内の動詞を適切な分詞の形に変えなさい。
1) She kept (crying) in front of her mother’s grave.
※ (彼女は母の墓の前で泣き続けていた。)
上記文では、keptが術後動詞であり、cryingがSVCの文型の補語として用いられ、「泣き続けた」という動作の継続を表している。このように分詞が補語として用いられることを、叙述用法と呼ぶ。SVCの文型では「Sは〜だ」というS is Cの関係が成り立つので、上記文の術後動詞をbe動詞に置き換えてみると、次のようになる。
She was crying in front of her mother’s grave.
また、現在分詞が能動の意味を表すのに対して、下記のように過去分詞は受動の意味を表す。
・His eyes remain closed. (彼の目は閉じられたままだ。)
2) The treasure lay (hidden) in the cave.
※ (宝物は洞くつに潜んでいた。)
上記文のような過去分詞の場合は「〜されて」と訳すことができる。主語がどのような状態なのかを表す表現。現在分詞の場合は「〜しながら/〜して」と訳すことができる。
〈分詞を伴う自動詞〉
walk, sit, come, lie
・They walked laughing into the room.
(彼らは笑いながらその部屋に入っていった。)
・The teacher sat surrounded by his students.
(その先生は生徒たちに囲まれて座っていた。)
〈参考〉この表現では、動詞と分詞のあいだに場所を表す表現が入ることがある。
・The teacher sat on the floor surrounded by his students.
(その先生は生徒たちに囲まれて床に座っていた。)
〈注意〉go –ingの意味
go shopping(買い物をしに行く)のように「〜しに行く」という意味で使うことが多い
3) We stood (talking) for about an hour.
※ (私たちは1時間くらい話しながら立っていた。)
071 補語になる分詞(叙述用法) (SVO+分詞)
( )内の動詞を適切な分詞の形に変えなさい。
1) When I came home, I found my wife (sleeping) on the sofa.
※ (私は帰宅した時、妻がソファで寝ているのを見つけた。)
findはSVOCの文型で用いられ、「OがCであるのを見つける」という意味を表すことができる。SVOCの場合は、OとCのあいだに「Oは〜だ」というO is Cの関係が成り立つ。したがって、上記文では、My wife was sleeping.という文を作ることができる。現在分詞のsleepingは能動の意味を表している。
2) Don’t leave the door (unlocked).
※ (ドアの鍵を開けっ放しにしておくな。)
leaveはSVOCの文型で用いられ、「OをCの状態にしておく」という意味を表すことができる。SVOCの場合は、OとCのあいだに「Oは〜だ」というO is Cの関係が成り立つ。したがって、上記文では、The door is unlocked..という文を作ることができる。過去分詞のunlockedは受動の意味を表している。
3) I want this problem (solved) by tomorrow.
※ (私はこの問題を明日までに解決してほしい。)
wantはSVOCの文型で用いられ、「OをCの状態にしてほしい」という意味を表すことができる。SVOCの場合は、OとCのあいだに「Oは〜だ」というO is Cの関係が成り立つ。したがって、上記文では、This problem is solved.という文を作ることができる。過去分詞のsolvedは受動の意味を表している。
072 have+O+分詞
日本語の意味に合うように、( )に適合を入れなさい。
1) 彼は自分の犬を浜辺で走らせておいた。
He (had) his dog (running) on the beach.
※ 〈have / get+O+現在分詞〉の形で、「Oを〜させる/させておく」という意味を表すことができる。
〈参考〉haveはある状態への変化や継続を表すときに、getはある状態までもって
いくことを表すときに使う。
・The comedian had the people laughing.
(そのコメディアンは人々を笑わせた。)
・He got the machine working.
(彼はその機会を動かした。)
〈参考〉〈have+O+動詞の原型〉は「Oに〜させる / してもらう」という意味。(不
定詞の使役動詞)完結した動作を表すときに使う。
・He had the dog run on the beach.
(彼は自分の犬に浜辺で走ってもらった。)
2) 私はローマでパスポートを盗まれた。
I (had[got]) my passport (stolen) in Rome.
※ 〈have / get+O+過去分詞〉の形で、「Oを〜してもらう/Oを〜される」という意味を表すことができる。上記文はやってほしいことでないので、「パスポートを盗まれた」のような意味になる。やってほしいことであれば、次のように「髪を切ってもらった」のような意味になる。このような用法のhaveとgetも使役動詞とよぶ。
・I had my hair cut at a famous beauty salon.
(私は有名な美容室で髪を切ってもらった。)
また、次のように「Oを〜し終える」という意味を表すこともできる。この場合は、自分で何かをやり遂げることを表す。
・Have your essay finished by tomorrow!
(作文を明日までに書き上げてしまいなさい!)
〈参考〉次のように偶然や不注意による被害を表すときはgetが用いられる。
・I got my fingers caught in the train doors.
(私は電車のドアに指をはさまれた。)
〈make+O+過去分詞〉の表現
makeも過去分詞を伴うことがある。〈make+O+過去分詞〉で「Oを〜されるようにする」の意味。ただし、過去分詞が形容詞化している場合を除くと、次のような慣用的な表現に限られると考えてよい。
make oneself understood (自分の意思を伝える)
make oneself heard (自分の声を聞かせる)
・Can you make yourself understood in English?
(あなたは英語で自分の意思を伝えられますか。)
3) 私は昨日、自転車を修理してもらった。
I (had[got]) my bicycle (repaired[fixed]) yesterday.
073 see+O+分詞
日本語の意味に合うように、( )内に適語を入れなさい。
1) 私は人ごみの中で自分の名前が呼ばれるのを聞いた。
I (heard) my name (called) in the crowd.
※ 〈hear+O+過去分詞〉は、「Oが〜されるの聞く」という意味を表す。この形で使えるのはsee, look at, hear, listen to, feelなど、「見る」「聞く」「感じる」という意味を表す動詞で、これらは知覚動詞と呼ばれる。次のような〈hear+O+現在分詞〉は、「Oが〜しているの聞く」という意味を表す。
I heard someone calling my name in the crowd.
(私は人ごみの中でだれかが自分の名前を呼んでいるのを聞いた。)
2) パットは、女の子が川で泳いでいるのを見た。
Pat (saw) a girl (swimming) in the river.
※ 〈see+O+現在分詞〉は、「Oが〜しているのを見る」という意味。。
3) 私はだれかがどあをノックしているのを聞いた。
I (heard) someone (knocking) on the door.
※ 〈hear+O+現在分詞〉は、「Oが〜しているの聞く」という意味。
074 分詞構文 (分詞構文の働き / 分詞構文が表す内容)
次の文を日本語に直しなさい。
1) Hiking in the forest, we came across a bear.
森の中をハイキングしている時、私たちはクマに出くわした。
※ 上記文でHiking in the forestが表すのは、「森の中をハイキングしている時」であると考えられる。このように、分詞構文を使って「〜している時/〜しているあいだ」という何をしている時のことなのかを表すことができる。このよう場合、whenやwhileのような接続詞を使って次のように表現することができる。
While we were hiking in the forest, we came across a bear.
2) Having nothing to do, I went to bed early.
何もすることがなかったので、私は早く寝た。
※ 上記文では、I went to bed early (私は早く寝た)という理由を、「何もすることがなかった」と説明している。「原因や理由」を表す分詞構文はふつう文頭に置かれる。このように「原因や理由」を表す場合は、because, since, asなどの接続詞を使って表現することができる。
Since I had nothing to do, I went to bed early.
〈参考〉過去分詞を使った分詞構文では、過去分詞の前にbeingが置かれ、〈being+過去分詞〉の形になることがある。この場合、分詞構文はふつう「原因・理由」をあらわす。
Written in simple English, this book is easy to understand.
(= Being written in simple English, this book is easy to understand.)
(簡単な英語で書かれているので、この本は理解しやすい。)
〈注意〉分詞構文は次のように、「時」と「原因・理由」のどちらを表しているのか、その文だけでは判断できないことも多い。
Seeing the storm clouds, they turned back.
(あらしの雲を見て、彼らは引き返した。)
〈参考〉分詞構文が「条件」を表すこともある。ただし、あまり用いられない。
・Turning left after the bank, you will see our house on the right.
= If you turn left after the bank, you will see our house on the right.
(銀行の先を左に曲がると、右手に私たちの家が見えます。
3) I drive to the office every morning listening to the radio.
私は毎朝、ラジオを聞きながら車で会社に行く。
※ 上記文では、「私が毎朝車で会社に行く」時に「ラジオを聞いている」という状況表している。このように、分詞構文を使ってその時していることを表すことができる。その時の状況を表す用法は「付帯状況」と呼ばれ、分詞構文の中ではもっとも頻度が高い。
4) He managed to solve the problem, supported by his classmates.
彼はクラスメイトに助けられて、その問題をなんとか解決した。
※ 上記文ではHe managed to solve the problemという文の後にsupported by his classmatesという過去分詞に導かれた句を置いて、「クラスメイトに助けられて」という情報を加えている。分詞構文では、分詞の意味上の主語は、文の主語と同じになるのが原則。上記文では、He was supported by his classmates.という文を作ることができる。また、「原因や理由」を表す分詞構文はふつう文頭に置かれるが上記文のように、分詞句が文末に置かれる場合、コンマを使うことがある。また、次のように分詞が主語の直後に置かれることもある。
・Mary, shocked at the news, couldn’t speak a word.
(メアリーは、その知らせに驚いて、一言も話せなかった。)
〈注意〉分詞構文の使用
分詞構文が会話で使われることはあまりない。むやみに分詞構文を使わないようにしよう。
075 分詞構文 (否定の位置)
指定された動詞を使って、日本語の意味に合うように( )に適語を入れなさい。
1) 時間がなかったので、今朝は新聞を読まなかった。(have)
(Not) (having) time, I didn’t read the newspaper this morning.
※ 上記文のNot havingのように、分詞を否定するnotやneverなどは分詞の直前に置く。
2) 私の忠告に従わなかったので、息子はかぜをひいた。(take)
(Not) (taking) my advice, my son caught a cold.
076 分詞構文の応用 (分詞構文のさまざまな形)
日本語に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) お金を全部使ってしまったので、彼女は渋谷から家まで歩いた。
(Having) (spent) all her money, she walked home from Shibuya.
※ 文の術後動詞の表す時よりも以前のことを分詞構文で表現する場合は、分詞を〈having+過去分詞〉の形にする。上記文では、「歩いた」というwalkedが表す時よりも以前に「使った」ことから、分詞がhaving spentになる。この文を接続詞を使って表現すれば、次のようになる。
Because she had spent all her money, she walked home from Shibuya.
2) サラダと一緒に食べると、このパスタはおいしい。
This pasta is delicious (when) (eaten) with a salad.
※ 分詞構文の意味を明確にするために、分詞の前に接続詞を置くことがある。上記文では、whenを置くことで「時」を表すことを明確にしている。分詞の前に置かれる接続詞はwhenやwhileが多い。この文のwhen eatenのような場合は〈主語+be動詞〉の省略と考えることができる場合もある。
This pasta is delicious when it is eaten with a salad.
〈参考〉afterやbeforeに-ingが続く場合は、前置詞の後に動名詞が続いた形と考えればよい。
After finishing his homework, he played the video game.
(宿題を終えた後、彼はテレビゲームをした。)
〈「譲歩」を表す分詞構文〉
分詞構文が「譲歩」を表すことがある。その場合は分詞の前にalthoughやthoughのような「譲歩」の接続詞がついていたり、主節にstillのような「逆説」を表す副詞があることが多い。
・Although impressing the interviewer, he couldn’t get a job.
(面接担当者にはよい印象を与えたが、彼はその仕事を得ることができなかった。)
・Accepting that he may be right, I still don’t like his idea.
(彼が正しいかもしれないということは認めるが、それでも私は彼の考えが気に入らない。)
077 分詞構文の応用 (独立分詞構文)
次の文を日本語に直しなさい。
1) It being very hot last night, I couldn’t sleep well.
昨夜はとても暑かったので、よく眠れなかった。
※ 分詞構文では、分詞の意味上の主語は文の主語と一致しているのが原則である。しかし、上記の文のように、実際の英文では、分詞の意味上の主語が文の主語と一致していないこともある。このような分詞構文を、独立分詞構文と呼ぶ。分詞の意味上の主語が文の主語と異なる場合は、分詞の直前に意味上の主語を置く。上記文ではbeingの直前にあるItが意味上の主語になっている。接続詞を使って表現すれば次のようになる。
Because it was very hot last night, I couldn’t sleep well.
〈注意〉〈There + be動詞 …〉の構文を分詞構文にする場合
・There being …またはThere having been …となる。これはかなりかための文章体の表現
・There being no bridge, we had to swim across the river.
(橋がなかったので、私たちは泳いでその川を渡らなければならなかった。)
2) Generally speaking, Japanese people work hard.
一般的に言って、日本人は熱心に働く。
※ Generally speakingは「一般的に言って」という意味で、分詞の意味上の主語を明示しない慣用表現。厳密に言えば、分詞の意味上の主語は「不特定の人々」や「話者」ということになるが意味上の主語を気にする必要はない。
〈分詞構文の慣用表現〉
frankly speaking (率直に言って)
speaking[talking] of … (…と言えば)
generally speaking (一般的に)
strictly speaking (厳密に言えば)
judging from … (…から判断すると)
3) Judging from her elegant dress, she must be going to the party.
彼女の上品なドレスから判断すると、彼女はそのパーティーに行くところであるにちがいない。
※ Judging from … は「…から判断すると」という意味で分詞の意味上の主語を明示しない慣用表現。
078 付帯状況を表すwith+(代)名詞+分詞
日本語の意味に合うように、与えられた語句を並びかえて、英文を完成させなさい。ただし、不要な語が1語ある。
1) 彼は目を閉じたまま、いすに座っていた。
He was sitting in the chair (with his eyes closed).
※ 主節で表していることと同時に起こっている事柄を補足的に説明するときに、〈with + (代)名詞 + 分詞〉の形が使われることがある。この場合、(代)名詞は分詞の意味上の主語になる。上記文では、過去分詞closedを使って、with以下にはHis eyes were closed.という受動態の文に相当する内容が表されるようにする。つまり、上記文では、「彼がいすに座っていて、(それと同時に)彼の目は閉じられていた」という状況が表現されている。
2) 彼はエンジンをかけたまま車から出た。
He got out of the car (with the engine running ).
※ 上記文では、with the engine runningが「彼が車から出た」様子を補足して説明している。ここでは現在分詞を使ってthe engine was runningという能動態の文に相当する内容が表されるようにする。つまり、上記文では、「彼が車から出て、(それと同時に)エンジンがかかっていた」という状況が表現されている。
〈付帯状況を表す場合に用いられるwith〉
withを使って付帯状況を表す場合、分詞の代わりに、形容詞、副詞、前置詞句が使われることも多い。この場合も〈with+(代)名詞+形容詞/副詞/前置詞句〉の形になり、(代)名詞抜きでは使えないことに注意。
・Some people sleep with their eyes open.
(目をあけたまま眠る人もいる。)[openは形容詞]
・Did you interview her with the tape recorder on?
(テープレコーダーのスイッチを入れて、彼女にインタビューをしましたか。)[onは副詞]
・He apologized for his mistake with tears in his eyes.
(彼は目に涙を浮かべて自分の間違いを謝罪した。)[in his eyesは前置詞句]
079 分詞を使った表現
日本語の意味に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) ビンの中に牛乳はほとんど残っていなかった。
There (was) little milk (left) in the bottle.
※ 何かの存在を伝えるときには〈There+be動詞+名詞〉の形を使う。この名詞の後に分詞を続けると、それがどういう状況にあるのかを表すことができる。上記文の場合は、little milkの後にleftを続けて、「ほとんど残されていない」という状況を表している。名詞と分詞で表す動作が上記文のように「〜される」という受動の関係なら〈There+be動詞+名詞+過去分詞〉、次のように「〜する」という能動の関係なら〈There+be動詞+名詞+現在分詞〉となる。
・There’s a car coming. (車が来るよ。)
2) 日曜日にはよく川に釣りに行った。
I went (fishing) (in) the river on Sundays.
※ スポーツやレジャーなどについて「〜しに行く」と言うときは、上記文のようにgo –ing という形を使う。
go fishing (釣りに行く)
go climbing (山登りに行く)
go swimming (泳ぎに行く)
go skating (スケートをしに行く)
go skiing (スキーをしに行く)
go shopping (買い物に行く)
〈注意〉go –ingの後の前置詞
go-ingの後ろに「場所」を表す〈前置詞+名詞〉を置く場合、 用いる前置詞を間違えないように注意する。この前置詞は-ingになっている動詞とのつながりで決まる。
go shopping in Ginza (銀座に買い物に行く)
go skating on the lake (湖にスケートをしに行く)
go swimming in the river (川へ泳ぎに行く)
go skiing at Hakuba (白馬にスキーをしに行く)
〈go –ingが表す2つの意味〉
go-ingの後に、その活動が行われる場所を続けると、「〈場所〉に〜をしに行く」という意味になる。
・I’m going to go skiing at Hakuba. (白馬にスキーをしに行くつもりだ。)
この場合の「〜に」は〈場所〉を表すatを用い、〈到達点〉を表すtoは用いない。Toを用いると「〈場所〉まで〜しながら行く」という意味になってしまう。
・They went talking loudly to the station.
(彼らは駅まで大きな声で話しながら行った。)
3) 彼の家は、わけなく見つかった。
We (had) no trouble (finding) his house.
※ 上記はhave trouble –ing「〜するのに苦労する」という意味を表すらわす。ほかにも、次のような表現がある。(ing形の前に前置詞inを入れることもある。)
be busy [in] –ing「〜するのに忙しい」
・We are very busy [in] preparing for the party.
(私たちはパーティーの準備でとても忙しい。)
spend+時間+[in] -ing「〜して〈時間〉を過ごす」
・I spent a lot of time [in] watching TV last night.
(昨夜はテレビを見て長時間過ごしてしまった。)
第10章 比較級(解説)
080 原級を使った比較
次の文を日本語にしなさい。
1) This camera is as small as that one.
このカメラはあのカメラと同じくらいの小ささだ。
※ asの後では、なくても誤解が生じないものは省略できる。上記文でthat oneの後のisが省略されている。This camera is as small as that one (is).
また、asの後が代名詞1語になる場合には、それが主語であっても目的格が使わ
れることが多い。
・My sister is as tall as me.
(私の姉は私と同じくらいの身長です。)
〈as nice a person as の語順〉
原級を使った比較では、比較の軸になるのが名詞を伴う形容詞のこともある。この場合、a nice personのようにa/anがつくと、次のような語順になる。
・He is as nice a person as his father.
(彼は、彼の父親と同じくらい、いい人です。)
a nice personの形容詞niceが、副詞as に引っ張られる形でその直後に置かれ、〈as+形容詞+a/an+名詞〉の語順になっている。×as a nice person as~とするのは誤り。
2) Jenny has three times as many books as Tom
ジェニーはトムの3倍の数の本を持っている。
※ 上記文のように「持っている本の数」について比較したい場合には、as … asのあいだにmany booksを入れて、〈数量を表す形容詞+名詞〉の組み合わせで使わなくてはならない。また、2人の人(2つの物事)をくらべて、一方がもう一方のX倍あるという場合、as … as の前に倍数を置いて表す。上記は倍数を使った文。倍数はX timesで表すので3倍の場合はthree timesとなる。2倍の場合はtwice、1.5倍なら、one and a half timesとなる。
また、次のように、一方がもう一方のX分のYであることを表す場合は、as … asの前に分数を置いて表す。「2分の1」の場合にはhalfを、「4分の1」の場合にはa[one] quarterを使う。
・That room is half as large as this one.
(あの部屋はこの部屋の半分の大きさだ。)
・This bridge is one-third as long as that one.
(この橋はあの橋の3分の1の長さです。)
〈名詞を使って「~のX倍の…だ」を表す〉
length(長さ), size(大きさ/体積)height(高さ), depth(深さ)などの名詞を使ってX倍の差があることを表現することもできる。
・His second novel is three times the length of his first one.
= His second novel is three times as long as his first one.
(彼の2作目の小説は、1作目の3倍の長さです。)
・This box is a[one] quarter the size of that one.
= This box is a[one] quarter as large as that one.
(この箱はあの箱の4分の1の大きさです。)
3) I cannot read English as fast as you.
私はあなたほど速く英語を読めません。
※ as … asを使った比較の文をnotで否定すると、「~ほど…ではない」という意味になり、比べる相手と「同じくらいではない」ことを表す。上記文ではyouの後のcanが省略されている。I cannot read English as fast as you (can).
なお、否定文では原級の前にはsoを使ってもよい。
I cannot read English so fast as you (can).
4) Write your name as nearly as you can.
できるだけきちんと名前を書きなさい。
※ 「できるだけ…」という意味はas … as possibleか、as … as S canという形で表す。(Sはその動作をする人)。
081 比較級を使った比較
日本語に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) 私の弟は私よりも上手に絵を描きます。
My brother draws pictures (better) (than) me.
2) 私の家はその野球選手の家よりもずっと小さい。
My house is (much) (smaller) (than) the baseball player’s house.
※ 比較されている2者のあいだの差が大きいことを表したい場合は、比較級の前にmuchやfar, a lotなどを置く。〈much[far]+比較級+than~〉で、「~よりもずっと[はるかに]…」となる。
逆に、差が小さいことを表すには、〈a little[a bit]+比較級+than~〉「~よりも少し…」などを用いる。
・His grades were a little[a bit] better than mine.
(彼の成績は私の成績より少しよかった。)
また、数の多さにについて比べる〈more+名詞の複数形+than~〉という表現では、muchを使わず、manyを用いて差の大きさを表す。
・My brother has many more T-shirts than me.
(弟は僕よりもかなり多くのTシャツを持っている。)
[×much more T-shirtsとはしない]
〈evenやstillを使って「さらにいっそう…」を表す〉
〈even[still]+比較級+than~〉で「~よりもさらにいっそう…」を表す。
・His new car is even[still] bigger than mine.
(彼の新しい車は私のよりもさらに大きい。)
この文は、「私の車も割と大きい車だが、彼の新しい車はそれよりもさらに大きい」という意味合いになる。
また、比較されている2者のあいだの差を具体的に表すには、次のthree yearsyoungerのように、数を使った表現を比較級の前に置く。
・Sue is three years younger than Tim.
(スーはティムより3歳年下だ。)
= Sue is younger than Tim by three years.
[2つの差をbyを使って数値で表すこともある。]
〈比較級を使った比較の文で、倍数を使って差を明示する〉
〈比較級+than~〉でも、倍数や分数の表現を使うことができる。ただし、twiceは比較級を使った文で用いることはできない。
・This computer can work two and a half times faster than that one.
= This computer can work two and a half times as fast as that one.
(このコンピュータはあのコンピュータより、2.5倍速く動く。)
3) この問題はその問題ほど難しくない。
This question is (less) hard (than) that one.
※ 「~ほど…でない」のように、形容詞や副詞の表す程度が比べる相手より低いことを表すときに、〈less+形容詞/副詞+than~〉を使う。lessの後には原級を置く。〈less … than~〉は、〈not as[so] … as~〉とほぼ同じ意味を表す。ただし、〈less … than~〉よりも〈not as[so] … as~〉を使うことのほうが多い。
This question is not as[so] hard as that one.
= That question is harder than this one. [That questionのほうを主語にして]
= This question is easier than that one.
[文意によっては、lessの後の形容詞や副詞の反意語の比較級を使うことが可能な場合もある。]
〈比較の対象をはっきりと表す〉
・He looks much younger than he really is.
(彼は実際の年齢よりずっと若く見える。)
この文では、「彼のみかけ(he looks)」の年齢と、「本当の(he really is)」年齢とを比べている。比較の文では何と何を比較しているのかをはっきりとらえることが大切。
・You can find a good job more easily in a big city than in a small town.
(小さな町よりも大都市のほうがいい仕事が簡単に見つかる。)
この文では、「いい仕事を見つけるのはどちらが簡単(more easily)か」という点について、in a big cityとin a small townという2つの場所を表す副詞句(前置詞+名詞)を比べているので、thanの後のin を省略することはできない。
・The climate of Japan is much milder than that of Iceland.
(日本の気候はアイスランドの気候よりもずっと温暖だ。)
この文では、「日本の気候」と「アイスランドの気候」をくらべている。thatは代名詞で、the climateを受けている。この場合の「アイスランドという国」との比較ではないので、than Icelandとはしない。
〈比較級を使った比較の文で、thanが省略される場合〉
・Why don’t you use a sharper knife?
(もっとよく切れるナイフをつかったらどうなの?)
「(今使っているナイフよりも)もっとよく切れるナイフを使う」ことを勧めている文である。このように何と比較しているのが明らかな場合には、than以下は省略される。
・I have to practice basketball harder this year.
(今年はバスケットボールをもっとがんばって練習しなければならない。)
「以前に比べて/今までよりも」という意味で過去との比較をする場合も、わざわざ言わなくても意味が通じるので、than以下は省略される。
082 最上級を使った比較
日本語の意味に合うように、与えられた語句を並びかえて文を完成させなさい。
1) これはロンドンでもっとも古い教会です。
This is (the oldest church in London).
※ 上記文のように、名詞を修飾する形容詞の最上級を使う場合は、その前にtheを置く。名詞が続いてなくても、形容詞の後に名詞を補うことができれば、theを使う。
・Chris is the richest (person) in the town. (クリスは町で一番のお金持ちだ。)
副詞の最上級の場合は、次のようにtheを置かないことが多い。
・He swims fastest of us all. (彼は私たちの中でもっとも速く泳ぐ。)
〈in … と of …〉
最上級の文では、比較する範囲や対象は〈in+名詞(代名詞)〉か〈of+名詞(代名詞)〉の形で表すことが多い。
inを使うのは上記文のin Londonや次のin this schoolやin my familyのように、比べる相手がその中に入っているような場合。(inは容器に入っているイメージ)
・He is the fastest sprinter in this school.
(彼はこの学校でもっとも速い短距離走者です。)
・I am the tallest in my family.
(私は家族の中で一番背が高い。)
ofを使うのは、上記文のof us allや次のof the threeのように、比べる相手を並べて個別に意識している場合。(ofは個々を意識するイメージ)
・He is the tallest of the three. (彼はその3人の中で一番背が高い。)
2) ここはこの町でもっともよいフランス料理店の1つです。
This is (one of the best French restaurants) in this town.
※ 「もっとも…なものの1つ」と言う時に、〈one of the+形容詞の最上級+複数形の名詞〉という形を使う。
3) メルボルンはオーストラリアで2番目に大きな都市です。
Melbourne is (the second largest city in) Australia.
※ 「一番」であることを示すには最上級を使えばいいが、「2番目に…な〜」を表す場合には〈the second+形容詞の最上級+単数形の名詞〉という表現を使う。secondの代わりにthirdを使えば「3番目に…な〜」となるし、fourthを使えば「4番目に…な〜」という意味になる。
・This is the third most popular song in the hit chart this week.
(これは、今週のヒットチャートで第3位の歌です。)
また、「もっとも…でない/一番…でない」の意味で、形容詞や副詞の表す程度が最も低いことを表すには次のように〈the least+形容詞/副詞〉を使う。
・This is the least expensive computer in this store.
(これがこの店でもっとも高くないコンピュータです。)
4) 彼はこの劇団で抜群にうまい役者です。
He (is by far the best actor) in this theater company.
※ 最上級が表す意味に「はるかに/断然」という意味を加えるときは、by far, muchなどを使う。この文のようにtheが付いているときは、theの前に置く。
次のように、veryを形容詞の前に置くことで「まさに…な」という意味を表すことができる。この場合は、〈the very+形容詞の最上級(+名詞)〉の語順になる。
・He is the very best player on[in] this team.
(彼はこのチームでまさに最高の選手です。)
〈比較の範囲を関係代名詞を使って表す〉
最上級の文で、比較する範囲や対象を関係詞節で表すこともできる。関係詞節には〈経験〉の意味の完了形が用いられ、「これまで〜した中でもっとも…な」という意味になる。
・This is the most interesting book (that) I have ever read.
(これは私が今まで読んだ中でもっともおもしろい本です。)
083 原級・比較級を使って最上級の意味を表す
次の文と同じ意味になるように、原級と比較級を用いた3つの文をつくりなさい。
Ted is the tallest boy in this class.
(テッドはこのクラスの中で一番背の高い少年です。)
=①No (other) boy in this class is as[so] tall as Ted.
(テッドほど背の高い少年はこのクラスの中にはいない。)
※ 〈No (other)+単数形の名詞〉を主語にして、「〜ほど…なものはない」という意味を表すことができる。この文ではno (other) boy in this classとTedが「背の高さ」の点で同じくらいであることを示している「テッドと同じくらいの少年はいない」ということなので、「テッドがもっとも背が高い」となる。
また、次のようにany other boyを先に置くとanyが出てきた瞬間に強い肯定と感じ,その後にnotが来ると論理的混乱を引き起こすため、このような使い方は避ける。
× Any other boy in this class is not as[so] tall as Ted.
◯ Not any No boy in this class is as[so] tall as Ted.
=②No (other) boy in this class is taller than Ted.
(テッドより背の高い少年はこのクラスの中にいない。)
※ 上記文では、no (other) boy in this classと、thanの後ろのTedを、比較級を用いて比べている。「テッドより背の高い少年は居ない」ということなので、「テッドがもっとも背が高い」ということになる。
〈参考〉比較級を使うこの表現は、「それよりも上のものはない」ということを表す。
したがって、「同程度のものがある」可能性も残される。
また、次のようにany other boyを先に置くとanyが出てきた瞬間に強い肯定と感じ,その後にnotが来ると論理的混乱を引き起こすため、このような使い方は避ける。
× Any other boy in this class is not taller than Ted.
◯ Not any No boy in this class is taller than Ted
=③Ted is taller than any other boy in this class.
(テッドはこのクラスの他のどの少年よりも背が高い。)
※ 比較級を使った比較表現のthanの後ろに〈any other+単数形の名詞〉を置くと、「ほかのどの〜よりも…」という「一番…」の意味を表すことになる。上記文では、Tedとany other boyを比べている。「テッドはこのクラスの他のどの少年よりも背が高い。」→「テッドはもっとも背が高い。」となる。
〈注意〉nothing, anythingを用いて最上級の意味を表す
「少年」のような具体的な名詞ではなく、一般の「もの」や「こと」を対象にして上にあげたような最上級に相当する表現を使う場合には、〈no other+単数形の名詞〉の代わりにnothing (else)を、また〈any other+単数形の名詞〉の代わりにanything elseを使う。
Nothing (else) is as[so] precious as time.
Nothing (else) is more precious than time.
Time is more precious than anything else.
(時間よりも貴重なものはない。)
〈注意〉nobody, no one, anybody, anyoneを用いて最上級の意味を表す
「もの」や「こと」ではなく、一般の「ひと」を対象にして最上級に相当する表現を使う場合には、nothing (else)の代わりにnobody no oneを、また、anything elseの代わりにanybody [anyone] elseを使う。
Nobody (else) in her school is as[so] tall as her.
No one (else) in her school is taller than her.
(彼女の学校で、彼女よりも背の高い人は1人もいない。)
She is taller than anyone else in her school.
(彼女は、彼女の学校のほかのだれよりも背が高い。)
084 原級を用いたさまざまな表現
日本語の意味に合うように、与えられた語句を並べかえて英文を完成させなさい。
1) この本は歴史に関するエッセイというよりは、むしろ小説だ。
This book is (not so much a historical essay as a novel).
※ ある物事や人について、2つの要素のうちどちらがより強く備わっているかを述べる場合、〈not so much A as B〉という表現が用いられる。「AというよりはむしろB」という意味になる。
〈not so much A as Bの同意表現〉
① not A so much as Bという語順も可能。
=The book is not a historical essay so much as a novel.
② B rather than A / rather B than A
=The book is a novel rather than a historical essay.
=The book is rather a novel than a historical essay.
③ more (of) B than A
=The book is more (of) a novel than a historical essay
〈not so much as+動詞の原形〉「〜さえしない」
The old man did not so much as apologize to me.
(その老人は私にあやまりさえしなかった。)
= The old man did not even apologize to me.
〈without so much as + -ing〉「〜さえしないで/〜なしで」
He left me without so much as saying thanks.
(彼は礼も言わずに私のもとから立ち去った。)
2) その事故で100人もの人がけがをした。
(As many as one hundred people) got injured in the accident.
※ 〈as many / much as + 数詞〉「〜もの」(= no less than + 数詞)は、数や量がかなり多いことを表す表現。数の多さを表す場合にはmanyを、量の場合は次のようにmuchを使う。
・I paid as much as 250 dollars for this sweater.
(このセーターに250ドルも出した。)
= I paid no less than 250 dollars for this sweater.
〈as + 形容詞/副詞 + as〜〉の表現
manyやmuchの代わりにさまざまな形容詞や副詞を使った〈as + 形容詞/副詞 + as〜〉で次のような意味を表すことができる。
・Radio broadcasting started as early as 1920.
(ラジオ放送は早くも1920年に始まった。)[1920年がかなり早いと思っている]
・He goes fishing as often as three times a week.
(彼は週に3回もつりに行く。)[週3回はかなり多いと思っている]
〈as many / much〜〉「それと同数/量の〜」
・The tour group visited five cities as many days.
(そのツアーの団体は、5日間で5つの都市を回った。)
この文では、先にfive citiesという数の表現が出ているので、as many days「それと同じ日数」と言えば、「5日間」を意味することになる。
・I’ll have 200 grams of ham salad and as much mashed potatoes.
(ハムサラダを200グラムと、マッシュポテトも同じ量ください。
3) 彼はあいかわらずだれにでも友好的だ。
He is (is as friendly to everyone as ) ever.
※ as … as everは「これまでと同じくらい…」ということなので、「あいかわらず…」という意味になる。
〈as … as ever lived〉「きわめて…」
次のように「これまで存在したどんな偉大な俳優と比べても劣らない」ことを表すため、「きわめて偉大な俳優」ということになる。
・He is as great an actor as ever lived.
(彼はきわめて偉大な俳優です。)
〈as … as any +単数形の名詞〉「きわめて…」
次のように「私が知っているどんな正直な男と比べても劣らない」ことを表すため、「きわめて正直な男」ということになる。
・He is as honest as any man I know.
(彼はきわめて正直な男です。)
4) その仕事は終わったも同然だ。
The work is (as good as finished).
※ 〈as good as〜〉は「ほとんど〜と同じ」という意味。上記文は「実質的に仕事が終わったのと同じ程度→終わったも同然」であることを意味している。
・This house is as good as new. (この家は新築同然です。)
なお、as good as〜はふつうの比較表現でも使われ、「〜と同じくらいよい」という意味を表す。
・His car is as good as mine. (彼の車は私のと同じくらいよい。)
085 比較級を用いたさまざまな表現(1)
次の文を日本語に直しなさい。
1) She bought the cheaper of the two sweaters.
彼女はその2枚のセーターのうちの安いほうを買った。
※ 「(3つ以上の中で)もっとも…」と言う場合には次のように最上級を使うが、比べるものが2つの場合には、上記文のように〈the+比較級+of the two〜〉という形を使う。 the cheaperおよびthe cheapestの後にはsweaterが省略されているので比較級・最上級の前にtheが必要となる。
She bought the cheapest of the three sweaters.
(彼女は3枚のセーターのうち、一番安いのを買った。)
2) I like her all the better for her kindness.
彼女は親切なので、私は彼女のことがますます好きだ。
※ 〈all the+比較級〉で「それだけ…/ますます…」という意味を表し、その後に続くfor … やbecause … で述べている理由によって、比較級で表されたことの程度がいっそう増していることを示す。上記文は、「彼女が親切である」という理由によって、もともと私たちが抱いている「彼女に対する好意」が、よりいっそう増していることを意味している。上記文のようにforを使う場合は後ろに名詞(句)を置く。
次の文では、「子どもがいる」という理由によって、彼女がよりいっそう懸命に働いていることを述べている。次のように、becauseを使う場合には後ろに節を置く。
・She works all the harder because she has a child.
(彼女には子どもがいるので、それだけいっそう一生懸命働くのです。)
〈参考〉比較級の前についているtheは副詞で、「それだけ…/ますます…」とい
う意味を表すので、〈all the+比較級〉のallは〈the+比較級〉を強調する
働きをしており、省略することもある。
〈none the+比較級〜〉
比較級にnoやnoneなどの否定語がつくと、比較級によって意味される「差」が存在しないことになる。したがって、〈none the+比較級〜〉は、「〜という理由では程度に何の変化も生じない」→「〜だからといってそれだけ…というわけではない/〜だからといって少しも…でない」という意味になる。なお、〈none the+比較級〜〉も理由を表す〈for+名詞(句)〉や〈because+節〉を伴うことが多い。
・He worked none the harder because he became a father.
(彼は父親になったとうことで、一生懸命に働くことはなかった。)
〈none the less(〜)〉「(〜であるが)それでもやはり/それでもなお」
・We respect him none the less for his faults.
(彼には欠点があるが、それでもやはり私たちは彼を尊敬している。)
欠点によって私たちの彼に対する敬意が減ることはなく、欠点があってもなくても、彼をまったく同じように尊敬しているという意味。
3) It is getting warmer and warmer.
だんだん暖かくなってきている。
※ 形容詞や副詞の比較級をandを使って繰り返すと、「ますます…」という意味になり、程度が次第に増していくことを表す。-er型の比較級は、上記文のwarmer and warmerのようにandで結ぶだけでよいが、more型の場合には、次のように〈more and more+原級〉という形になる。
・It’s becoming more and more important to understand English.
(英語がわかるということが、ますます重要になっている。)
More and more people are traveling abroad these days.
(最近、ますます多くの人が海外旅行に出かけている。)[moreはmanyの比較級]
〈less and less …〉「ますます…でなくなる」(程度が徐々に減っていくことを示す)
・During the match, the boxer became less and less aggressive.
(試合中、そのボクサーはしだいに攻撃的でなくなっていった。)
4) The more he practiced, the better he played the piano.
たくさん練習すればするほど、彼はますますピアノが上手になった。
※ 〈the+比較級+SV …, the+比較級+SV〜〉は「…すればするほど、ますます〜」の意味。関連し合った2つの動作や状態が、互いに比例関係を保ちながら、程度を増したり減じたりしていく場合に使われる。
・The more I study, the more I know. (学べば学ぶほど、それだけ知識が増える。)
・The older my dog gets, the fatter he gets.
(私の犬は年をとればとるほど、ますます太っていく。)
なお、次のようにSVがit isの場合は省略されることがある。
・The sooner you see a doctor, the better (it is).
(医者に診てもらうのは、早ければ早いほどいいよ。)
〈形容詞の比較級+名詞〉の場合
・The more time you have, the more work you can do.
(時間があればあるほど、たくさんの仕事ができる。)
この場合、形容詞と名詞を切り離して×The more you have time, … のようにしてはならない
〈参考〉時間の経過に伴う変化を表す場合には、接続詞as (〜につれて)をつかっ
て書き換えることができる。
・The longer I waited, the less patient I became.
(長く待てば待つほど、私はいらいらしてきた。)
・As I waited longer and longer, I became less (and less) patient.
(長く待つにつれて、私はますますいらいらしてきた。)
086 比較級を用いたさまざまな表現(2)
次の文を日本語に直しなさい。
1) I don’t want to read the novel, still less buy it.
私はその小説を読みたくないし、ましてや買いたいとは思わない。
※ much[still] less … は、否定文の直後に続けて、「なおさら…でない/まして…でない」という意味を表す。上記文では、「小説を読みたくない」という内容を受け、「小説を買いたいなどとなおさら思うわけがない」と述べている。
2) This computer is technically inferior to that model.
このコンピュータは、あのモデルよりも技術的に劣っている。
※ 比較の意味を含む形容詞や動詞の中には、比較の対象を表すのにthanではなく、toを用いるものがある
上記文のinferiorのように、語尾が-iorで終わる形容詞は、比較の意味を含んでいるものが多い。このような形容詞は比較の対象をtoを使って表す。
inferior to〜 (〜より劣った)
superior to〜 (〜より優れた)
senior to〜 (〜の上役の/〜の先輩の)
junior to〜 (〜より地位の低い/〜の後輩の)
次のように、動詞prefer (形容詞のpreferable, 名詞形のpreference)も、to〜を使ってprefer A to Bで「BよりもAを好む」という意味になる。
・I prefer playing sports to watching them.
(スポーツは見るよりもするほうが好きだ。)
〈参考〉年上/年下をsenior/juniorで表現するときは、ふつう、名詞のsenior/junior
を使い、「〜よりも」は所有格の(代)名詞で表す。one’s juniorで「〜よりも年下の人」の意味になる。
・He is my senior by six years. (彼は私より6歳上だ。)
・She is one year my junior. (彼女は私より1歳年下だ。)
3) She wanted to receive a higher education.
彼女は高等教育を受けたがっていた。
※ 具体的な比較の対象をもたず、全体を2つに分けてどちらにあるのかを表す比較級の用法(絶対比較級)。
higher education (高いほうの教育→高等教育)
the upper class (全体の中で上のほうの階級→上流階級)
the lower animals (動物全体で低いほうの動物→下等動物)
the younger generation (全体で若いほうの世代→若い世代の人たち)
〈具体的な比較対象をもたない最上級(絶対最上級)〉
「全体の中で最高の部類に属する」という意味で最上級を使う場合がある(絶対最上級と呼ぶ)。
〈a most+形容詞+名詞の単数形〉、〈most+形容詞+名詞の複数形〉の形で、いずれも〈very+形容詞+名詞〉よりもやや強くひびく強意表現となる。
a most kind person (とっても親切な人)
most interesting books (とってもおもしろい本)
-er, -est型の比較変化をする語でも、most … という形で用いる点に注意。
4) You ought to know better than to play with fire.
火遊びをするような愚か者であってはならない。
※ know better than to do は「〜するほど愚かではない/〜しないくらい分別はある」という意味。thanの後にはto不定詞が来ることに注意。
〈more or less〉
① 「多かれ少なかれ/ある程度は/いくぶん」
・Our guess was more or less correct.
(私たちの推測は、多かれ少なかれ正しかった。)
② 「およそ/だいたい」
・The cap will cost 20 dollars, more or less.
(その帽子はだいたい20ドルはするでしょう。)
・We came to more or less the same conclusion.
(私たちはだいたい同じ結論に達した。)
③ 「事実上/実質的に/〜も同然」
She has more or less retired.
(彼女は隠退したも同然だ。)
〈sooner or later〉「遅かれ早かれ/いつかは」
・Sooner or later you will find a good solution.
(遅かれ早かれ、よい解決策が見つかるよ。)
087 noを使った比較表現
次の文を日本語に直しなさい。
1) This car is no less fast than that one.
この車はあの車と同じくらい速い。
※ 〈no less … than〜〉は「〜と同じように…である/〜に劣らず…である」で肯定の意味。
・Relaxing is no less important than working (is).
(リラックスすることは、仕事をするのと同じように大切なことだ。)
・Julia can no less sail a yacht than Steve (can).
(スティーブがヨットを走らせることができるのと同じように、ジュリアもヨットを走らせることができる。)
〈no more… than 〜〉は「〜と同じように…でない」で否定の意味。
・Sleeping too much is no more healthy than eating too much (is).
(寝過ぎは、食べ過ぎと同じように、健康によくない。)
・He is no more a genius than I am
(私が天才でないのと同じで、彼は天才ではない。)
〈参考〉no more … than〜の代わりに、not any more … than〜やnot … any more
than〜が使われることもある。
・He is not any more popular than you are.
(彼は君(が人気ないのと)同様に人気がない。)
2) He speaks no less than five languages.
彼は5カ国後も話す。
※ 〈no less than+数詞〉は、「〜ほども多く」という意味で、数量が多いことを強調する。as many/much as〜とほぼ同じ意味。
= He speaks as many as five languages.
・She paid me no less than 30,000 yen for the work.
(彼女はその仕事に対して、私に30,000円も払ってくれた。)
=She paid me as much as 30,000 yen for the work.
〈not less than+数詞〉は、「少なくとも〜」という意味で、数量の下限を表す。at leastとほぼ同じ意味。
・The cost will be not less than 20,000 yen.
(その費用は、少なくとも20,000円になるでしょう。)
= The cost will be at least 20,000 yen.
〈no less thanが「少なくとも〜」という意味で使われることも多い。〉
= The cost will no less than 20,000 yen.
〈参考〉lessはlittleの比較級なので、数を表す場合はfewerを使うのが正式な用法。
しかし、数についていうときもno less thanやnot less thanを使うことが多い。
・He has no fewer[less] than 200 CDs.
(彼は200枚ものCDをもっている。)
3) There were no more than three passengers on the bus.
バスにはたった3人しか乗客がいなかった。
※ 〈no more than+数詞〉は、「(ほんの)〜しか/(わずか)〜にすぎない」という意味で、数量が少ないことを強調する。only〜やas little/few as〜を使ってほぼ同じ意味を表すことができる。
= There were only[as few as] three passengers on the bus.
〈not more than+数詞〉は、「〜よりも多くない/(多くて)せいぜい〜」という意味で、数量の上限を表す。at mostとほぼ同じ意味。
・There were not more than three passengers on the bus.
(バスにはせいぜい3人しか乗客がいなかった。)
= There were at most three passengers on the bus.
〈no more thanが「せいぜい〜」の意味で使われることも多い〉
= There were no more than three passengers on the bus.
〈参考〉more than〜は「〜を超える/〜を上回る」という意味。
・There were more than twenty people in the theater.
(その劇場には、20人を超える人がいた。)
088 最上級を用いたさまざまな表現
次の文を日本語に直しなさい。
1) The fastest train cannot reach Osaka before noon.
もっとも速い列車でさえ正午前に大阪には着けない。
※ 主語に形容詞の最上級がついている場合、「もっとも…な〜でさえ/どんなに…な〜でさえ」という意味合いを含むことがある。この場合は、主語がふつうしないはずの内容を述べることになる。上記文であれば、「もっとも速い列車」と「正午前に大阪に付けない」という組み合わせから、「もっとも速い列車でさえ正午前に大阪には着けない」という意味にとらえる必要が出てくるのである。
2) This lake is deepest here.
この湖は、ここが一番深い。
※ 上記文は、ほかの湖との比較をしているのではなく、同じ湖の中で一番深い地点はどこかを述べている。この場合は、deepestの後ろには名詞を補うことができないので、theをつけることはできない。
下記文では、「この湖」を日本のほかの湖と比べて「一番深い」とのべている。日本で一番深い湖はどの湖か特定できるので、定冠詞のtheが必要となる。この場合は、the deepest lakeと考えることができる。
・This lake is the deepest in Japan.
(この湖は日本で一番深い。)
3) I have at most twenty minutes to solve this problem.
その問題を解くのに、せいぜい20分しかない。
※ at (the) mostは「最大でも〜/せいぜい〜」という意味で、後に続く内容 (たいていは数値を含んでいる) を最大として、「それと同じか、それよりも少ない」ことを表している。
at (the) leastは「最小でも〜/少なくとも〜」という意味で、後に続く内容 (たいていは数値を含んでいる) を最小として、「それと同じか、それよりも多い」ことを表している。
4) You should be back by eight o’clock at the latest.
遅くとも8時までには戻ってきなさい。
※ at the latest 「遅くても」
at (the) earliest 「早くても」
at one’s best 「最高の状態の」
・People are at their best when they are under pressure.
(人々は、プレッシャーの下にあるとき、もっとちからを発揮する。)
at (the) best 「最高でも」
・The small factory can produce 30 cars a month at (the) best.
(その小さな工場は、最高でも1カ月に30台の車しか生産できない。)
at (the) worst 「最悪でも」
・Our team will get third prize, at (the) worst.
(私たちのチームは、いくら悪くても3位にはなるだろう。)
第11章 関係詞(解説)
089 whoとwhich
次の文の( )に適切な関係代名詞を入れなさい。
1) I know a man (who) has ten cats in his house.
※ (私は家で10匹の猫を飼っている男の人を知っている。)
上記文では、a manがどういう男の人であるかをwho has ten cats in his houseで説明している。[a man←he has ten cats in his house]を関係代名詞を使って表したものが、a man who has ten cats in his houseである。この文では、関係代名詞whoはhasの主語の働きをしている。このように、関係詞節中の動詞に対して関係代名詞が主語として働く場合は、主格の関係代名詞が使われる。上記文では、先行詞(a man)が人なのでwhoが使われている。
2) I visited a church (which) was built about 200 years ago.
※ (私はおよそ200年前に建てられた教会を訪れた。)
上記文では先行詞がa church。関係詞節中の動詞に対して関係代名詞が主語として働く場合は、主格の関係代名詞が使われる。上記文では、先行詞(a churc)が人以外のものなので、関係代名詞はwhichが使われる。
090 whomとwhich
次の文の( )に適切な関係代名詞を入れなさい。
1) She’s talking with the boy (who) lives next door.
※ (彼女は隣に住んでいる少年と話している。)
上記文は、the boyが先行詞。関係詞節中の動詞に対して関係代名詞が主語として働く場合は、主格の関係代名詞が使われる。上記文では、先行詞(the boy)が人なのでwhoが使われている。
2) That is the woman (whom) I saw in the restaurant yesterday.
※ (あれは私が昨日レストランで見た女性です。)
上記文は、the womanが先行詞。whom I saw in the restaurant yesterdayの部分が関係詞節で、whomはsawの目的語の働きをしている([the woman←I saw her in the restaurant yesterday])。このように、関係代名詞が関係詞節の中にある動詞の目的語として働く場合は、目的格の関係代名詞が使われる。上記文では、先行詞(the woman)が人なので、関係代名詞はwhomが使われている。
なお、whomという形は文章体であり、目的語の働きをする場合でもwhoが用いられることが多い。
= That is the woman who I saw in the restaurant yesterday.
また、目的格の関係代名詞は省略されることが多い。
= That is the woman I saw in the restaurant yesterday.
〈目的格以外の関係代名詞の省略〉
① There is a woman outside (who) says she’s your cousin.
(あなたのいとこだと言う女性が外にいますよ。)
There is[are] … やHere is[are] …の文に続く〈名詞〉を関係代名詞が修飾してい
る場合は、主格の関係代名詞でも省略されることがある。
② This is the only bow tie (that) there is in this store.
(これが、当店にありますただ1つのちょうネクタイです。)
関係代名詞の直後にthere is[are]で始まる節が続いている場合は、関係代名詞は省
略されるのがふつうである。
③ He is not the great singer (that) he once was.
(彼は、かつてそうだったような偉大な歌手ではない。)
関係代名詞thatがbe動詞の補語となっている場合には、関係代名詞は省略され
ることがある。この例文では、thatはwasの補語の役割をしている。
3) The ring (which) my wife liked best was very expensive.
※ (私の妻が一番気に入った指輪はとても値段が高かった。)
上記文は、the ringが先行詞。関係代名詞が関係詞節の中にある動詞の目的語として働く場合は、目的格の関係代名詞が使われる。上記文では、先行詞(the ring)が人以外のものなので、関係代名詞はwhichが使われている。先行詞が人以外の場合は、主格も目的格も同じ形である。
091 whose
次の文の( )に適切な関係代名詞を入れなさい。
1) I have a friend (who) is a lawyer.
※ (私には弁護士の友達がいる。)
上記文は、a friendが先行詞。関係詞節中の動詞に対して関係代名詞が主語として働く場合は、主格の関係代名詞が使われる。上記文では、先行詞(a friendが人なのでwhoが使われている。
2) This is the woman (whose) purse has been stolen.
※ (こちらが財布を盗まれた女性です。)
上記文では、関係代名詞が「その人の」という所有の意味を表している。([the woman←her purse has been stolen])。このように、所有格の代名詞の意味を表す場合には、所有格の関係代名詞を使うことになる。上記文では、先行詞(the woman)が人である。所有格の関係代名詞は先行詞にかかわらずwhoseを使う。
3) I know a musician (whose) son became the number-one hit this year.
※ (私は息子が今年一番ヒットしたミュージシャンを知っている。)
上記文では、関係代名詞が「その人の」という所有の意味を表している。([a musician←his son became the number one hit this year])。このように、所有格の代名詞の意味を表す場合には、所有格の関係代名詞を使うことになる。上記文では、先行詞(a musician)が人である。所有格の関係代名詞は先行詞にかかわらずwhoseを使う。
4) The bicycle (whose) front tire is flat is mine.
※ (前輪がパンクしている自転車は私のものです。)
上記文では、関係代名詞が「その人の」という所有の意味を表している。([The bicycle
←it’s front tire is flat])。このように、所有格の代名詞の意味を表す場合には、所
有格の関係代名詞を使うことになる。上記文では、先行詞(The bicycle)が人以外の
ものである。所有格の関係代名詞は先行詞にかかわらずwhoseを使う
〈関係代名詞のwhoseの代わりに用いられる表現〉
物に対してwhoseを用いる表現はぎこちなく聞こえるので、関係代名詞を使わず、
次のような表現をすることが多い。
・The house with a green roof is mine.
(緑の屋根の家が私の家です。)
= The house whose roof is green is mine.
= The house the roof of which is green is mine.
092 that
( )内の関係代名詞から、適切でないものを一つずつ選びなさい。
1) This is a letter from a friend (who[that]) lives in Ireland.
適切でないもの: whose
※ (これはアイルランドに住んでいる友人からの手紙です。)
関係代名詞のthatは、whichの代わりによく使われるが、who, who(m)の代わりに使うこともできる。上記文の先行詞はa friend。関係代名詞whoもしくはその代わりにthatを使うことができる。
2) Did you buy the CD (which[that]) Jack recommended to us?
適切でないもの: who
※ (君はジャックが私たちに勧めてくれたCDを買いましたか?)
上記文の先行詞はthe CD。関係代名詞whichもしくはその代わりにthatを使うことができる。なお、目的格のthatも省略されることが多い。
= Did you buy the CD Jack recommended to us?
3) He is the man (whose) daughter is a famous painter.
適切でないもの: that
※ (彼は娘が有名な画家である男の人を知っている。)
thatは所有格として働くことはできないので、whoseの代わりに使うことは不可。
〈関係代名詞のthatがよく使われる場合〉
次のような場合にはthatが使われることが多い。
① 先行詞が人以外のもので、the first(最初の)、the second(2番目の)、the last(最後の)、the very(まさにその)、〈the+最上級〉(もっとも~な)、the same(同じ)、the only(唯一の)などの特定の1つのものであることを表す修飾語を伴う場合。
・This is the only suit that I have.
(これが、私が持っている唯一のスーツです。)
② 先行詞がall, every, any, noなどの「すべて」「まったく~ない」といった意味を表す修飾語を伴う場合。
・Running the marathon took all the strength that she had.
(マラソンをすることは、彼女がもっているすべての力を必要とした。)
③ 〈人+人以外のもの〉が先行詞となっている場合。
・He talked about the people and the things that had fascinated him during his trip.
(彼は、旅行中に自分の興味を引いた人々や物事の話をした。)
④ 疑問詞whoの直後に関係代名詞節が続く場合。
・Who that has seen the Pyramids can forget their beauty?
(ピラミッドを見たことがある人で、その美しさを忘れる人がいる
だろうか。)
この英文では、疑問詞whoが関係代名詞の先行詞となっている。
⑤ 先行詞が人の性質や状態を表していて、関係代名詞が関係代名詞節で補語となっている場合。
・He is not the man that he was ten years ago.
(彼は10年前の彼とは違う。)
この場合、関係代名詞thatは関係代名詞節で補語となっていて、the
manが先行詞である。the man that he was ten years ago(彼が10
年前にそうであった人)のthe manは、人そのものというよりも、10
年前の彼の人柄・性質を表している。
093 前置詞と関係代名詞
( )に適切な関係代名詞を入れなさい。
1) I found a box in (which) there were some pretty dolls.
※ (私はいくつかのかわいい人形が入っている箱を見つけた。)
上記文ではa boxが先行詞で、in which there were some pretty dollsの部分が関係詞節になっている。このwhichは直前の前置詞inの目的語の働きをしている。このように、関係代名詞が前置詞の目的語になっている場合、その前置詞も一緒に関係詞節の先頭に置くことができる。こちらは、there were some pretty dolls in a boxと考えればよい([a box←there were some pretty dolls in a box])。この場合、関係代名詞を省略することはできない。
なお、前置詞が関係詞節の後ろに残った場合、関係代名詞にはthatを用いることができる。さらにこの関係代名詞は省略されることが多い。
= I found a box which[that] there were some pretty dolls in.
= I found a box there were some pretty dolls in.
〈注意〉thatは前置詞の後に置けない
関係代名詞のthatはwhomやwhichとは違い、前置詞の直前に置くことは不可。
×I found a box in that there were some pretty dolls.
〈注意〉群動詞の前置詞は関係代名詞の前に出さない
群動詞は、〈動詞+前置詞〉のようなひとまとまりの形で意味を表すので、前置詞を切り離して関係代名詞の前に出すことはしない。
My mother found the key (which[that]) I had been looking for.
(私が探していたカギを、母が見つけた。)
×My mother found the key for which I had been looking.
2) This is the cafeteria in (which) I met my husband for the first time.
※ (これは私が初めて夫に出会ったカフェです。)
3) I know the girl with (whom) you were talking.
※ (私はあなたが話してい少女を知っています。)
上記文ではthe girlが先行詞で、with whom you were talkingの部分が関係詞節に
なっている。このwhomは直前の前置詞withの目的語の働きをしている。この場
合、whomを先行詞に置き換えて、you were talking with the girlと考えるとわか
りやすい。また、上記文のように、関係代名詞が前置詞の目的語になっている場合、
その前置詞も一緒に関係詞節の先頭に置くことができる。この場合、whoやthat
を使うことはできず、関係代名詞を省略することもできない。
× I know the girl with (who[that]) you were talking.
口語体 ○ I know the girl you were talking with.
○ I know the girl who[that] you were talking with.
○ I know the girl whom you were talking with.
文章体 ○ I know the girl with whom you were talking.
094 what
日本語の意味に合うように、whatを使って英文を完成させなさい。
1) それは私の言ったことではない。
That is not (what I said).
※ 関係代名詞whatは「~すること[もの]」という意味を表し、先行詞なしで使う。whatの導く節は名詞節で、文全体の主語や目的語、補語になる。
上記文では、whatの導く関係詞節what I saidが文の補語になっている。whatは関係詞節の中で名詞として働くので、関係詞節の中では、上記文のように補語になったり、主語や目的語になったりする。
2) 君にはちょっと休息が必要だ。
(What you need) is some rest.
※ 上記文では、whatの導く関係詞節What you needが文の主語になっている。whatは関係詞節の中で名詞として働くので、関係詞節の中では、上記文のように目的語になったり、主語や補語になったりする。
3) 私にとって難しいことは、コンピュータの操作のしかただ。
(What is difficult) for me is how to operate a computer.
※ 上記文では、whatの導く関係詞節What is difficult for meが文の主語になっている。whatは関係詞節の中で名詞として働くので、関係詞節の中では、上記文のように主語になったり、目的語や補語になったりする。
095 関係代名詞の継続用法
次の文を日本語に直しなさい。
1) He has a daughter, who lives in London.
彼には娘が1人いて、彼女はロンドンに住んでいる。
※ 上記文は関係代名詞の前にコンマ(,)がある継続用法である。こちらの文では、He has a daughter. と言うだけで娘がいることがわかる。コンマ以下の関係詞節では、「彼女はロンドンに住んでいる」という補足説明をしているのである。
一方、コンマのない限定用法と区別するには、先行詞についてきちんと説明してどういうものか限定する必要があるのか、特に限定する必要はなく補足説明でよいのかを考えるとよい。
A) He has a daughter who lives in London.
(彼には、ロンドンに住んでいる1人の娘がいる。) [限定用法]
B) He has a daughter, who lives in London.
(彼には娘が1人いて、彼女はロンドンに住んでいる。)[継続用法]
限定用法
A)では先行詞a daughterが、「ロンドンに住んでいる」という内容で限定されている。この文では、彼の娘たちのうち1人がロンドンに住んでいることになるので、ロンドンに住んでいない娘がほかにいる可能性が残る。
継続用法
B)ではコンマの前で「彼には1人の娘がいる」と内容が完結していて、その娘に
ついて「ロンドンに住んでいる」という説明がつけ加えられている。したがって、彼には1人しか娘がいないことになる。
〈thatは継続用法には用いない〉thatはコンマの後ろには置けない
○ I bought a cell phone, which can also work as a digital camera.
(私は携帯電話を買ったが、それはデジタルカメラとしても使える。)
× I bought a cell phone, that can also work as a digital camera.
〈先行詞と関係詞〉
「唯一のもの」を表す固有名詞などは、限定用法の関係代名詞の先行詞にはならない。
・Do you know of Chopin, who is a world-famous composer?
(世界的に有名な作曲家であるショパンをあなたは知っていますか。)
Chopinは個人名なので、関係代名詞をつなげる場合は、コンマをその前に
置いて継続用法にする。
・My wife, who lives in Paris, has sent me a letter.
(私の妻はパリに住んでいるのですが、その妻から手紙が来たところです。)
「私の妻」は特定の人物なので、関係代名詞で修飾する場合はコンマを置く。
My wife who lives in Paris has sent me a letter.のように限定用法にしてし
まうと、「私には複数の妻がいて、その中のパリに住んでいる妻から手紙が
来た」という意味になってしまう。
・This book, whose author is a woman of eighty, is very amusing.
(この本は、著者は80歳の女性だが、とてもおもしろい。)
この場合、This bookは特定の本を指しているので、whose … eightyの部分
をコンマなしでつなげることはできない。
2) We went to the party, which was boring.
私たちはそのパーティに行ったが、つまらなかった。
※ 継続用法は、文脈によってさまざまな意味合いで使われることがあり、接続詞を使って書き換えることができる場合もある。
上記文は、私たちが行ったthe partyについて、「しかし、それは~」という意味で情報をつけ加えるために使われており、but it was boringとすることができる。
3) He said Nicky had bought a diamond ring, which was true.
彼はニッキーがダイヤの指輪を買ったと言ったが、それは本当だった。
※ 継続用法のwhichは、名詞や名詞句を先行詞とするばかりでなく、直前の文の内容全体や、その分中の一部の語句や節を先行詞とすることがある。whichの後ろに述べられている説明の内容から、何に関する説明なのかを考えて、先行詞をみきわめるようにしましょう。
上記文では、which was true(それは本当だった)という関係詞節の意味から考え
ると、whichの先行詞はNicky had bought a diamond ringという節だとわかる。
4) He passed the entrance examination, which surprised all his friends.
彼は入学試験に合格したが、それは彼の友人たちみんなを驚かせた。
※ 上記文では、which surprised all his friends(彼の友人たちみんなを驚かせた)から考えると、主節(He passed the entrance examination)の内容全体が先行詞となっていることがわかる。
096 関係副詞 (where, when, why, how)
次の( )に適切な関係副詞を入れなさい。ただし、where, when, why, howを一度ずつ使うこと。
1) Chicago is a city (where) it is very cold in winter.
※ (シカゴは冬がとても寒い都市です。)
関係副詞のwhereは、「その場所で[に]~する」という意味の節を作り、その節の中で副詞の働きをする。上記文では、a cityがどういう都市なのかを、where it is very cold in winterで説明している([a city←it is very cold there in winter]。) したがって、a cityがwhereの先行詞である。
また、関係代名詞を使って次のようにすることもできる。
= Chicago is a city in which it is very cold in winter.
= Chicago is a city (which) it is very cold in in winter.
〈whereかwhichか〉
関係詞節の中でwhereは場所を表す副詞の役割をし、関係代名詞は節の主語や目的語のような名詞的要素になる代名詞の役割をする。先行詞によって関係詞の使い分けをするわけではない。
次の2つの文で、関係詞の働きを考えてみよう。
・Do you know the country where Christopher was born?
(クリストファーが生まれた国を知っていますか。)
↑Christopher was born in the country.
・Do you know the country which Christopher visited?
(クリストファーが訪れた国を知っていますか。)
↑Christopher visited the country.
O(目的語)
2つ目の例にあるとおり、先行詞のthe countryが場所を表す語句だからといって、それだけで自動的に関係副詞whereが使われるわけではない。関係詞節の中で副詞の働きをするのか、名詞の働きをするのかで使い分けよう。
〈先行詞なしで用いられる関係副詞where〉
whereは先行詞なしで、「~する場所」という意味の名詞節を導くこともできる。この場合、whereはthe place whereと同じ意味を表している。
・This is where the old ferry used to go across.
(ここは昔、古いフェリーボートが行き来していたところだ。)
〈関係副詞whereの先行詞〉
whereは場所を表す語のほかに、場合・状況・立場などを表す語、case(場合), point(点), situation(状況)などを先行詞とすることもある。
・These are the cases where this rule does not apply.
(これらは、この規則が当てはまらない場合である。)
= These are the cases which this rule does not apply in.
〈参考〉先行詞がplaceかsomewhereのような-whereのつく語の場合、thatを
関係副詞として用いたり、関係副詞を省略することができる。
Do you know anywhere (that) I can find a taxi?
(タクシーを見つけられる場所をご存じですか。)
2) I can’t think of any reason (why) they gave up the plan.
※ (私は彼らがその計画をあきらめた理由について何も考えられない。)
関係副詞のwhyは「~する(理由)」という意味の節を作り、a/the reasonを先行詞とする。上記文は、any reasonを先行詞としたany reason why … という形で、「…する理由」という意味を表している。
次のように、先行詞のthe reasonが省略された形もよく用いられる。
・I really like sweets. That is (the reason) why my teeth are bad.
(私は本当に甘いものが好きです。そういうわけで歯が悪いのです。)
なお、This[That] is why … は、一種の提携表現と考えて、「こういう[そういう]わけで…」と訳せばよい。また、関係副詞を使わずに、a/the reason … という形で「…する理由」という意味を表し、the reason thatに置き換えることもできる。
= That is the reason that my teeth are bad.
〈参考〉関係副詞のwhyの代わりにfor whichを用いることもできるが、あまり使
われない。
3) There are times (when) everyone needs to be alone.
※ (すべての人が1人になることを必要とする時がある。)
関係副詞のwhenは「その時〜する」という意味の節を作る。上記文ではtimesが先行詞となっていて、関係代名詞を使って表すと、次のようになる。
There are times in which everyone needs to be alone.
〈注意〉whenと〈前置詞+which〉
関係副詞のwhenはon[at/in] whichなどで書き換えられる。Whereと同様に、先行詞と関係詞節内の動詞との関係を考えて適切な前置詞を使うこと。
・Tuesday is the day when the garbage truck comes.
(火曜日は、ゴミ収集のトラックが来る日だ。)
→ Tuesday is the day on which the garbage truck comes.
The garbage truck comes on Tuesday.という表現ができることを確認しよう。
また、関係副詞のwhenの代わりに、thatを関係副詞として用いることができる。また、関係副詞のwhenやthatは省略されることが多い
= Tuesday is the day (when[that]) the garbage truck comes.
〈先行詞なしで用いられる関係副詞when〉
whenは先行詞なしで、「〜する時」という意味の名詞節を導くこともできる。この場合、whenはthe time whenの意味を表している。
・Late spring is when the rainy season begins here.
(晩春は、この地域で雨季が始まる時である。)
〈先行詞と関係副詞whenが離れる場合〉
次の文のように、先行詞と関係副詞のwhenが離れることもある。この場合はwhenを省略することはできない。
・The day will soon come when we can enjoy space travel.
(宇宙旅行を楽しむことのできるような時代がもうすぐやってくるでしょう。)
4) This is (how) I finished the work in one day.
※ (このようにして、私は1日で仕事を終えた。)
関係副詞のhowは、上記文のようにThis[That] is how … (これが[それが]…するやり方[方法]だ)の形で使われることが多い。
なお、「…するやり方[方法]」は、the way (in which)…で表現することもできる。また、the way that … という形もあり、このthatはin whichと同様の意味を表す関係副詞として使われ、省略することもできる。
・Could you tell me the way (in which[that]) I can get a discount?
(割引を受けられる方法を教えてくれませんか?)
〈注意〉× the way how … という形は使われない
097 関係副詞の継続用法
次の文を日本語に直しなさい。
1) He was taken to the police station, where he told the truth.
彼は警察署に連れて行かれ、そこで本当のことを話した。
※ 関係副詞のwhereは継続用法で使うことができる。どういう意味で使われるのかは、関係代名詞の場合と同じように、文脈から考えることになる。上記文は、「そしてその場所で…(= and there)」という意味になる。
2) Someone broke into the house in the middle of the night, when the alarm rang.
真夜中に何者かがその家に侵入し、その時、警報が鳴った。
※ 関係副詞のwhenは継続用法で使うことができる。どういう意味で使われるのかは、関係代名詞の場合と同じように、文脈から考えることになる。上記文は、「そしてその時…(= and then)」という意味になる。
なお、whyとhowには継続用法はない。
また、継続用法の関係副詞節は、関係代名詞節同様、文中に挿入されることがある。
Last Monday, when we went surging, was a national holiday.
(この前の月曜日に私たちはサーフィンに出かけたが、その日は国民の祝日だった。)
098 複合関係詞
日本語の意味に合うように、( )に適切な関係詞を入れなさい。
1) この事故に責任のある人はだれでも処罰されるだろう。
(Whoever) is responsible for this accident will be punished.
※ whoeverは「~する人はだれでも」という意味の名詞節を作る。
上記文では、whoever is responsible for this accidentという名詞節が主語で、whoeverは関係詞節の主語になっている。
〈参考〉whoeverが関係詞節の中で目的語になる場合はwhomeverとなる場合には
whoeverを用いることが多い。
You may invite whoever[whomever] you like.
(だれでも好きな人を紹介していいよ。)
また、複合関係代名詞のwhoeverはanyoneの先行詞とwhoの関係代名詞を使っ
て書き換えることもできる。
The club admits whoever pays the entry fee.
(そのクラブは入会金を払う人ならだれでも入会を認めている。)
= The club admits anyone who pays the entry fee.
2) どこでも好きなところに座りなさい。
Sit (wherever) you want.
※ whereverは「~するところならどこでも」という意味の副詞節を作る。
また、wheneverは「~する時ならいつでも/~する時はいつも」という意味の副詞
節を作る。また、複合関係副詞をany time, every time, any placeで書き換えることもできる。
・On holidays, we can get up whenever we want to.
(休日には、いつでも好きな時に起きることができる。)
= On holidays, we can get up at any time (when) we want to.
・I visit my uncle whenever I go to Osaka.
(大阪に行く時はいつも、おじのところを訪れる。)
= I visit my uncle every time (that) I go to Osaka.
・Put the table wherever you like.
(そのテーブルを君の好きな場所に置きなさい。)
= Put the table in any place (that) you like.
3) ぼくは消しゴムを2つ持っている。どちらでも好きなほうを使っていいよ。
I have two erasers. You use (whichever) you like.
※ whicheverは「~するものはどれ[どちら]でも」という意味の名詞節を作る。上記文のwhichever you likeという名詞節がuseの目的語で、whicheverは関係詞節の中ではlikeの目的語になっている。また、whateverは「~するものは何でも」という意味の名詞節を作る。whicheverはいくつかの選択肢がある場合に使用し、whateverは特に選択肢が前提にあるわけではない場合に使用する。
〈参考〉whicheverとwhateverは直後に名詞を置いて形容詞的に用いることができる。
・You can have whichever book you like.
(どの[どちらの]本でも好きなほうをあげるよ。)
また、複合関係代名詞whicheverやwhateverは、any one, anythingの先行詞とthatの関係代名詞を使って書き換えることもできる。その場合、whichever=any one[ones] that, whatever=anything thatとなる。
・Help yourself to whichever you want.
(どれでもほしいものを自由に取って食べてね。)
= Help yourself to any oneones you want.
・You can order whatever you like.
(好きなものを何でも注文していいよ。)
= You can order anything (that) you like.
099「譲歩」を表す複合関係詞
日本語の意味に合うように、( )に適切な関係詞を入れなさい。
1) 何が起ころうとも、私のことをあてにしていいよ。
(Whatever) happens, you may count on me.
※ whateverは、「譲歩」の意味を表すことがある。その場合は「何が[を]~しようとも」という意味で、副詞節を作る。一方、「~なら何でも」という意味のwhateverは次のように名詞節を作る。
・You can order whatever you like.
(好きなものを何でも注文していいよ。)
また、複合関係詞のwhatever, whicheverが譲歩の意味を表す場合に限り、whatever = no matter what …, whichever = no matter which …で書き換えることができる。
Whatever happens, you may count on me.
= No matter what happens, you may count on me.
Whichever you take, please return it tomorrow.
(どれを持っていっても、明日返してね。)
= No matter which you take, please return it tomorrow.
〈参考〉文章体では、whoever, whichever, whateverによる譲歩を表す副詞節中
の動詞にmayをつけることがある。また、whicheverやwhateverの直後に名詞が続いて形容詞的に用いられることがある。
・Whichever way you may go, you will have to cross the rever.
(どちらの道を行くにしても、川を渡らなければならないだろう。)
2) だれが会いに来ても、私は外出中だと伝えてください。
(Whoever) comes to see me, tell them I’m out.
※ whoeverは、「譲歩」の意味を表すことがある。その場合は「だれが]~しようとも」という意味で、副詞節を作る。また、複合関係詞のwhoeverが譲歩の意味を表す場合に限り、no matter who…で書き換えることができる。
= No matter who comes to see me, tell them I’m out.
3) どこにいようとも、私はいつもあなたのことを思っています。
(Wherever) I am, I am always thinking of you.
※ wherever, wheneverは、「譲歩」の意味を表すことがある。その場合はwhereverは「どこで[へ]~しようとも」という意味になり、wheneverは「いつ~しようとも」という意味になる。譲歩を表すかどうかは文脈で判断する。また、複合関係詞wherever, wheneverが譲歩の意味を表す場合に限り、wherever = no matter where, whenever = no matter whenで書き換えることができる。
・Wherever I am, I am always thinking of you.
= No matter where I am, I am always thinking of you.
・You will be welcomed whenever you com.
(君がいつ来ようと、歓迎するよ。)
= You will be welcomed no matter when you come.
〈参考〉文章体では、wherever, whenever, howeverによる譲歩を表す副詞節中の
動詞にmayをつけることがある。
・You will be welcomed whenever you may com.
4) 私たちの犬はどんな遠くまで行っても、必ず家に帰ってくる。
(However) far our dog goes, he always comes home.
※ howeverは、形容詞や副詞の前で使い、「どれほど~でも」という「譲歩」の意味を表す。また、Howeverが譲歩の意味を表す場合に限り、however = no matter howで書き換えることができる。また、上記文は〈however+副詞〉の形。〈however+形容詞〉は次のようになる。
・However tiered she is, she always smiles.
(どんなに疲れていても、彼女は笑顔を絶やさない。)
〈注意〉however+SV
howeverの直後に形容詞や副詞が続かないでSVが続く場合は、「どんなふうに~しても」とか「~するどんなやり方でも」というin whatever wayの意味になる。
・However you look at it, it’s a stupid thing to do.
(どんなふうに考えてみても、それをするのはばかげているよ。)
・You can do it however you like.
(君が好きなどんなやり方ででも、それをやっていい。)
100 関係代名詞の働きをするasとthan
( )にasかthanを入れなさい。
1) These books are written in such easy English (as) beginners can understand.
※ (これらの本は初心者が理解できるような簡単な英語で書かれている。)
asは関係代名詞のように、節の中で主語、補語、目的語の働きをすることがある。上記文のasは、as beginners can understandの目的語の働きをしている。このasは、such … as~(~するような…)やthe same … as~(~するのと同じ…)という表現で使われる。
・This is the same jacket as was worn by the actor in the movie.
(これはその映画でその俳優が着ていたのと同じジャケットだ。)
・America is not the same country as it used to be.
(アメリカは昔と同じような国ではない。)
・I want to paint such pictures as I see in museums.
(私は美術館で見るような絵を描きたい。)
また、次のように、asがwhichのように直前の節全体を先行詞とする関係代名詞のように使われることもある。また、このasは、節の中のknowの目的語の働きをしている。(関係代名詞の働きをするasが節全体を先行詞とするとき、先行詞となる節よりも前に置かれることがある。)
・Oil and water do not mix, as we all know.
(みんなが知っているように、油と水は混ざらない。)
= As we all know, oil and water do not mix.
2) There were more people at the party (than) I expected.
※ (そのパーチィーには私が期待していた以上に多くの人がいた。)
thanは、関係代名詞と同じように、後に続く節の中で主語や目的語の働きをすることがある。この文では、thanがexpectedの目的語の働きをしている。
You have more money than is necessary.
(君は必要以上にお金をもっている。)[thanはisの主語の働き]
また、butも関係代名詞の働きをすることがある。butは、否定を伴った語句を先行詞として、否定の意味を表す関係代名詞のように使われることがあるが、あまり用いられない文章体の表現。
・There was no one but thought he was guilty.
(彼が有罪だと思わなかった人はだれもいなかった。)
= There was no one that didn’t think he was guilty.
101 関係代名詞のさまざまな用法
次の文を日本語に直しなさい。
1) In English there are many sayings the meanings of which I can’t understand.
英語には、私には意味が理解できないことわざがたくさんある。
※ 先行詞が人以外のものの場合は、所有格の関係代名詞としてwhoseのほかに、of whichという形も使われる。上記文では、of which … understandの部分が関係詞節である。[many sayings ← I can’t understand the meanings of many sayings] のof many sayingsがof whichとなって、of whichで修飾される名詞を前にもってきて〈the+名詞+of which〉という形にしている。
また、of whichで修飾される名詞(the meanings)を後ろにもっていき、of whichを節の頭に置くこともできる。
= In England there are many sayings of which I can’t understand the
meanings.
whoseを使って書き換えると次のようになる。(of whichを使った所有格は文章体なので、whoseを使って表現するのがふつう。)
= In England there are many sayings whose meanings I can’t understand.
〈複雑な構造の関係詞節〉
・We came to a cave at the entrance of which was a dead bear.
(私たちはほら穴に着いたが、その入り口にはで死んだくまがいた。)
このof whichは所有格の関係代名詞で、the entranceにつながっている。先行詞はa caveなので、the entrance of a cave(そのほら穴の入り口)となる。これに前置詞atがついて、at the entrance of which(そのほら穴の入り口に)という場所を表す副詞句が作られているのである。
つまり、この文は次の2つの文から成り立っていることになる。
We came to a cave.
At the entrance of the cave was a dead bear. [倒置文]
(= A dead bear was at the entrance of the cave.)
このような複雑な構造の関係代名詞の場合は、whichを先行詞と置き換えて、関係代名詞節の部分の構造を確認するとわかりやすくなる。
2) While I was in Paris, I got to know a lot of people, most of whom were Japanese.
パリにいるあいだ、私はたくさんの人と知り合いになったが、そのほとんどは日本人だった。
※ 上記文では、関係代名詞がmost of whomという形で使われる。mostやall, some, many, bothのような数量を表す表現にof whichやof whomが続き、継続用法で使われると、「そのうちの~」という意味を表す。したがってmost of whomは「そのうちの~」という意味を表す。したがってmost of whomは「そのうちの大部分」という意味になる。上記文では、a lot of peopleが先行詞なので、most of whomは「たくさんのひとの大部分」という意味を表している。また、most of whomの3語で主語の働きをしている。
・I couldn’t understand her massage, most of which was in French.
(私は彼女の伝言が理解できなかった。その大半がフランス語でかかれていたのだ。)
3) He is trying to make a list of all the songs which he thinks are popular among young people.
彼は若い人たちのあいだで人気があると思うすべての歌の一覧表を作ろうとしている。
※ 関係代名詞の後にほかの節(SV)が続いて、〈関係代名詞+SV+V…〉という形になる場合がある。この場合は、関係代名詞の直後のSVをカッコに入れて考える。
上記文ではいったんhe thinksをはずして、all the songs which are popular among young peopleとする。これにhe thinksの意味を加えて、「若い人たちのあいだで人気があると思うすべての歌」とすればよい。この形の文はhe thinks they are popularのtheyが関係代名詞whichとなり、節の頭に移動したと考えらる。
all the list which he thinks (they) are popular
このように使われる表現には、he thinksのほか、he believes、he is sureなどがある。
・The woman who I thought was her sister was actually her mother.
(私が彼女の姉だと思った女性は、実は彼女の母親だった。)
・Greg is a man who I know is capable of wining.
(グレッグは、勝利する能力があると私にはわかっている男だ。)
4) His success is an example of what is called the American Dream.
彼の成功は、いわゆるアメリカンドリームの一例だ。
※ what is called …は、「いわゆる…/世間で言う…」という意味を表す。なお、what you/we/they call … という形でも使われる。
5) She is not what she was ten years ago.
今の彼女は10年前の彼女とは違う。
※ what S was[used to] は、「かつてのS/昔のS」という意味になる。what S is (today)だと「現在のS」という意味になる。
・His father made him what he is today.
(彼の父が、彼を今日の彼にした。)
・He is completely different from what he used to be.
(彼は昔の彼とはまったく違う。→彼はまったく人がかわってしまった。)
〈参考〉what S hasは、「Sが持っているもの」という意味から「Sの財産」という意味でも使われる。
・A man’s happiness does not depend on what he has.
(人の幸福はその人の財産で決まるわけではない。)
6) Facts are to the scientist what words are to the poet.
真実と科学者の関係はことばと詩の関係と同じだ。
※ A is to B what C is to Dは「AのBに対する関係はCのDに対する関係に等しい」という意味。
また、what is moreは「そのうえ」という意味で、一般に、〈what is +比較級〉という形で、「さらに~なことに」という意味になる。この形の表現としてはほかに次のようなものがある。
what is worse (さらに悪いことに)
what is more surprising(さらに驚くべきことに)
what is more important(さらに重要なことに)
・He plays the piano, and what is more, he sings very well.
(彼はピアノを弾き、そのうえとても上手に歌う。)
・She lost her way, and what was worse, she had no map.
(彼女は道に迷った。さらに悪いことに、彼女は地図を持っていなかった。)
また、what with A and (what with) Bは、「AやらBやらで/AとかBとかのために」という理由を表す。
・What with working and housekeeping, I’m very busy.
(仕事やら家事やらで、私は大変忙しい。)
102 関係形容詞
次の文を日本語に直しなさい。
1) I gave the child what little money I had with me.
私は少ないけれども持っていたお金をすべてその子どもに与えた。
※ 関係詞whatは、〈what+名詞〉の形で使われることがある。この場合、whatは直後の名詞を修飾する形容詞として働くので、関係形容詞と呼ばれる。〈what+名詞〉は〈all the +名詞+that … 〉と同じ意味を表し、「…するすべての~」と訳すことができる。上記文では、what little money I had with me = all the little money that I had with meであり、「私がわずかながら持っていたすべてのお金」という意味になる。
・I gave him what help I could give.
(私は、できる限りの援助を彼に与えた。)
2) Lend me what magazines you have about diving.
君の持っている、ダイビングに関する雑誌を全部私に貸して。
※ = Lend me all the magazines that you have about diving.
3) The doctor told her to take a few days’ rest, which advice she didn’t follow.
その医師は数日休養をするようにと彼女に言ったが、その助言に彼女は従わなかった。
※ 継続用法のwhichは、関係形容詞として使うことがある。上記文のように〈, which+名詞〉という形で用いられると、「そしてその〈名詞〉を[は/が]」という意味になる。
・The men wore kilts, which clothing I thought very interesting.
(その男たちはキルトをはいていたが、その服はとてもおもしろいと思った。)
また、関係代名詞のwhichが〈, 前置詞+which+名詞〉という形でもちいられることもある。in which caseで「そしてその場合には~」という意味を表す。
・We may miss the train, in which case we’ll be late for the appointment.
(私たちはその列車に乗り遅れるかもしれない。そしてその場合は約束に遅れるだろう。)
〈参考〉関係形容詞は現代英語ではあまり見られない。
第12章 仮定法(解説)
103 ifを使った仮定法 (直接法と仮定法/仮定法過去/仮定法過去完了/主節時制相違)
日本語の意味に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) 明日晴れたら、ピクニックに行きます。
If it (is) fine tomorrow, we’ll go on a picnic.
※ 上記文の「明日晴れる」という内容は現実に起こる可能性があること。このように現実のことや現実に起こる可能性のあることを表す動詞の形を直接法と呼び、if節の中では動詞の現在形を使う。
2) 彼女の電話番号を知っていたら、電話するんだが。
If I (knew) her phone number, I (would) call her.
※ 上記文の「電話番号を知っていたら」は現実とは違うこと。このように現実とは違うことを表す動詞の形を仮定法と呼ぶ。仮定法で過去形を使った場合には、現在の事実と違うと思っている事柄を表すことになる。これを仮定法過去と呼ぶ。if節(条件節)の動詞及び主節の助動詞に過去「形」を使用して〈今〉のことを表す点に注意。動詞の形がそのまま話題になっている時を表しているわけではない。
主節で使われる助動詞は主にwouldであり、「…だろうに」という意味。ただし、「…かもしれない」という意味を含めたいときにはmightが用いられ、「…できる」という意味を含めたいときにはcouldが用いられる。
上記文の裏には、「彼女の電話番号を知らないから電話しない( = I don’t know her phone number, so I won’t call her.)」という現在の事実が隠れていることになる。
3) もし、宇宙人と話すとしたら何を言う?
What (would) you say if you (talked[spoke]) with an alien?
※ 仮定法過去は、現実に起こる可能性のないことを表すときにも用いられる。上記文は、「宇宙人と話すことなどありそうもないが、もし話すことでもあれば」という話し手の判断が込められている。
4) もし私がお金持ちだったら、そのお屋敷が買えるのに。
If I (were[was]) rich, I (could[should]) buy the mansion.
※ 上記文では主語がIであるにもかかわらず、if節(条件節)の中でwereが使われている。仮定法では、主語の人称や数に関係なく、be動詞にはwereを使うことができる。口語では、主語が1人称単数および3人称単数の場合、wasも使われる。また、主語が1人称のときにはshouldも使うことができる。
5) もし、君がもう少し注意深ければ、そんな間違いはしなかっただろうに。
If you (had) (been) a little more careful, you (would) not (have) (made) such a mistake.
※ 仮定法で過去完了を使った場合には、過去の事実とは違うと思っている事柄を表すことになる。これを仮定法過去完了と呼ぶ。この場合も、仮定法過去と同様、動詞の「形」と、「表す時」にはズレがあることに注意。上記文の裏には、「注意深くなかったので間違いをした」という過去の事実が隠れていることになる。
6) もっと早起きしていたら、彼女は学校に間に合っただろうに。
She (would) (have) (been) in time for school if she (had) (got[gotten]) up earlier.
7) もしその電車に間に合っていれば、私は、そのパーティーに出席しているのに。
If I (had) (caught) the train, I (would) (be) present at the party.
※ 上記文では、「もしその電車に間に合っていれば」は過去のことを指すので、if節では、〈過去の事実に反する仮定〉としてhad caughtという仮定法過去完了を使用する。それに対して、主節の「そのパーティーに出席しているのに」は〈現在の事実に反する仮定〉なので、would beという仮定法過去の場合の形が使われる。〉
104 wishやas ifの後の仮定法
日本語の意味に合うように、( )内の語を適切な形に変えなさい。
1) 彼の自宅の住所を知っていればなあ。
I wish I (knew) his home address.
※ wishに続く節の内容は、実現できそうもない願望を表す。現在の事実とは違うと思っている事柄を表すときには仮定法過去が用いられる。
〈注意〉wishに続く節のbe動詞はwere。ただし、口語では1人称単数・3人称単
数のときにwasを使うこともある。
・I wish she was[were] here. (彼女がここにいてくれたらなあ。)
2) 彼女は私にうそをつかなければよかったのに。
I wish she (had not told) a lie to me.
※ 過去の事実とは違うと思っている事柄をを表すときには仮定法過去完了が用いられる。
3) 彼女は、彼といっしょにいることができればと思った。
She (wished) she could stay with him.
※ 上記文では、「〜できればと思った」ということなので、wishしている時点は過去と判断できるのでwishedと過去形にする。そしてwishが現在形か過去形かということとは無関係に、「願っている時」と同時であれば、wishに続く節は上記文のように過去形(could stay)を使う。それよりも前のことであれば、次のように過去完了形を使う。
・She wished she could have stayed with him.
(彼女は彼といっしょにいることができていたならばと思った。)
・She wishes she could have stayed with him.
(彼女は彼といっしょにいることができていたならばと思う。)
〈wishの後で使われる助動詞〉
withに続く節では、couldやwouldが使われることもある。
① I wish I could play the guitar as well as you.
(君と同じくらいギターがうまく弾けたらなあ。)
② I wish my father would give up smoking.
(父がタバコをやめてくれたらなあ。)
couldの場合は「~できる」という意味を、wouldの場合は「~するつもりだ/~する予定だ/~してくれる」という意味を表す。
このような過去形の助動詞は、意味上必要なときにだけに用いる。ifを使った「もし~なら、…だろうに」の「…だろうに」の部分とは違って、過去形の助動詞を絶対に用いなければならないということはない。
4) 君はまるでスターであるかのようにふるまう。
You behave as if you (were) a star.
※ as ifに導かれる節でも、事実とは異なる空想を表す場合に、仮定法が使われる。上記文では、現在の事実とは違うと思っていることなので、仮定法過去が用いられている。
〈参考〉as ifに続く節で使われるbe動詞は、口語では、1人称単数・3人称単数の
ときにはwasも使われる。
5) 彼女はまるで私に以前一度も会ったことがないかのような顔つきだった。
She looked as though she (had) never (met) me before.
※ as if の代わりにas thoughを使っても同じ意味が表せる。
wishの後の仮定法の表現と同様に、as if[though]の後に置かれる仮定法も、主節の
述語動詞が表す時点と同時のことであれば過去形を使い、それよりも前のことであ
れば過去完了形を使う。述語動詞が現在形か過去形かということとは無関係である。
・She looks as if[though] she had never met me before.
(彼女はまるで私に一度もあったことがないかのような顔つきだ。)
・He talks as if he were an expert in economics.
(彼はまるで経済学の専門家であるかのように話す。)
・He talked as if he were an expert in economics.
(彼はまるで経済学の専門家であるかのように話した。)
述語動詞が過去形になっていても、述語動詞が示すのと同じ時点のことであれば、仮定法過去(were)が使われていることを確認しよう。
〈as if の後には直説法もくる〉
話し手が事実だろうと判断していることを表す場合、as if の後には直説法が使われる。
・You talk as if you’re angry.
(怒っているみたいな口ぶりだね。)
[You are angry.だろうと話し手は判断している]
・You talk as if you were angry.
(まるで怒っているみたいな口ぶりだね。)
[You aren’t angry.だろうと話し手は判断している。]
〈as if の後にto不定詞を置くこともある〉
・Her guest suddenly stood up as if to leave.
(彼女の客は、立ち去ろうとするかのように突然立ち上がった。)
105 未来のことを表す仮定法
次の文を日本語に直しなさい。
1) What would happen if he were to tell others about our secret?
もし彼がほかの人たちに私たちの秘密を話すようなことがあれば、どんなことがおこるだろう。
※ if節の中でwere to を使うと、未来の事柄についての仮定を表すことになる。その際、どれくらい実現の可能性があるかについては、発言内容や文脈から判断する。上記文の場合は、「もし~するようなことがあれば」という、ありそうもない未来を表している。
また、「仮に~すれば」というような、実現の可能性のある仮定を表すこともできる。
・If you were to give her a bunch of roses she would be pleased.
(仮に君が彼女にバラの花束を贈ってあげるなら、彼女は喜ぶだろう。)
このwere to は〈be to 不定詞〉の過去形であり、〈be to 不定詞〉がもつ未来のニュアンスを引き継いでいる。(→T-127)
・The President is to visit China next week.
(大統領は来週中国を訪問する予定です。)
〈注意〉wereの代わりにwasも使われる。
口語では、主語が1人称単数および3人称単数の場合、wereの代わりにwasが使われることもある。
・If he was to fail again, his boss might fire him.
(もし彼がまた失敗したら、彼の上司はかれをくびにするかもしれない。)
2) If you should be unable to come, please let me know soon.
もし来れなくなったら、すぐに知らせてください。
※ if節で使われるshouldは「実現の可能性が低い」という話し手の判断を表す。まったく不可能なことを表すときには、shouldは使えない。また、if S should~の表現に限って、上記文のように主節が命令文になることもある。
また、if S should~の表現に限って、主節の助動詞が過去形にならないこともある。
If our teacher should find out about your cheating, he will[would] punish you.
(もし先生が万が君のカンニングのことを知ったら、君を罰するぞ。)
106 ifが出てこない仮定法
日本語の意味に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) その本が日本語で書かれていたら、私は楽に読めただろうに。
(Had) the book (been) (written) in Japanese, I would have read it easily.
※ 仮定法のif節のifを省略すると、後ろのSVは倒置され、疑問文と同じ語順になる。これは、文章体の表現である。ifを補うと、上記文は次のようになる。
= If the book had been written in Japanese, I would have read it easily.
〈注意〉ifの省略は、実際にはwere / had / shouldが文頭に出る倒置でしか行われない。
2) もしも私が遅れるようなことがあれば、待たずに出発してください。
(Should) I be late, please start without me.
※ 仮定法ifの省略による倒置文。
= If I should be late, please start without me.
3) もう少し暖かければ、散歩に出かけるのだが。
(Were) it a little warmer, we would go out for a walk.
※ 仮定法ifの省略による倒置文。
= If it were a little warmer, we would go out for a walk.
4) 彼が踊っているのを見れば、君は笑い出すだろう。
(To) see him dancing, you would burst out laughing.
※ to不定詞も、if節の代わりになる。上記文は次のように書き換えることができる。
= If you saw him dancing, you would burst out laughing.
〈参考〉分詞構文がif節の代わりになることもある。(→T-168)
・Living in this country, she would have lived a happy life.
(この国で暮らしていたら、彼女は幸せな生活を送ったことだろう。)
・Born in the United States, he might have been elected President.
(合衆国に生まれていたら、彼は大統領に選ばれていただろう。)
また、接続詞のSupposing~がif節の内容を表すこともある。
5) コンピュータがなければ、彼はまったく仕事ができないでしょう。
(But) (for) the computer, he couldn’t do his work at all.
※ but for~とwithout for~は「~がなければ/~がなかったら」という意味を表す。but for~は文章体の表現。if it were not for~でも表現できる。
= Without for the computer, he couldn’t do his work at all.
= If it were not for the computer, he couldn’t do his work at all.
〈注意〉but for やwithoutの後には名詞的な語句が置かれ、節を置くことはできない。
〈注意〉but for~ やwithout~の部分には動詞が出てこないので、いつのことをいっているかは、ふつうは主節の動詞から判断する。
〈otherwise〉
「そうでなければ」という意味を表すotherwiseは、直前で述べられている事実と反対の仮定を表し、1語でif節と同じ内容を表す。
・I know he is innocent; otherwise I wouldn’t try to save him.
(彼が潔白だと私にはわかっている。そうでなければ彼を救おうとはしない
だろう。)
= If I didn’t know he is innocent, I wouldn’t try to save him.
・We stopped talking; otherwise our teacher would have scolded us.
(私たちはしゃべるのをやめた。そうでなければ先生は私たちをしかっただ
ろう。)
= If we had not stopped talking, our teacher would have scolded us.
6) もう少し運があれば、彼女は試合に勝つことができただろうに。
(With) a little more luck, she could have won the game.
※ with~はwithout~の逆で、「~があれば/~があったら」という意味を表す。ifを使って次のように表すことができる。
= If she had had a little more luck, she could have won the game.
〈注意〉with~の表現の場合も、いつのことを言っているかは主節の動詞から判断。
7) スパイだったら、本当の名前を言うことはないだろう。
A secret agent (would) never tell you his real name
※ 文の内容から主語のA secret agentに「スパイだったら」という仮定の意味が込
められていることがわかるため、仮定法での主節に用いる助動詞を使用する。
8) 2年前だったら、あなたのプロポーズに応じていたことでしょう。
Two years ago, I (would) (have) accepted your proposal.
※ 文の内容から副詞句のtwo year agoに「2年前だったら」という意味が込められて
いることがわかるため、仮定法での主節に用いる助動詞を使用する。
107 仮定法を使った慣用表現
次の文を日本語に直しなさい。
1) If it were not for air, nothing could live on the earth.
もし空気がなければ、地球上では何も生きられないだろう。
※ 「もし~がなければ」という意味で、現在の事実に反する仮定の場合はif it were not for~を用いる。but for~/ without~でも表現できる。なお、この表現に対応する肯定文は存在しない(×if it were for)。また、if it were not for~ではif を省略することができる。その場合は倒置が起こることに注意。
= Were it not for air, nothing could live on the earth.
2) If it had not been for your help, we couldn’t have finished the job.
もしあなたの手助けがなかったなら、私たちはその仕事を終わらせることはできなかっただろう。
※ 過去の事実に反する仮定の場合はif it had not been for~を用いる。but for~/ without~でも表現できる。なお、この表現に対応する肯定文は存在しない(×if it had been for)。また、if it had not been for~ではif を省略することができる。その場合は倒置が起こることに注意。
= Had it not been for your help, we couldn’t have finished the job.
3) It’s about time you started working
そろそろ、仕事を始めてもいいころだよ。
※ 〈it’s time+仮定法過去〉で「もう~してもよいころだ」という意味になる。timeの前にhighをつけると「とっくに~する時間だ」、aboutをつけると「そろそろ~する時間だ」という意味を示すことができる。it’s timeに節を続ける場合は必ず仮定法過去を使う。また、it’s timeの後の節では助動詞は使わない。
・It’s past midnight. It’s high time the children went to bed.
(もう夜の12時を過ぎた。子供はとっくに寝る時間だよ。)
〈注意〉to不定詞を使って、ほぼ同じ内容を表現できる。
= It’s about time for you to start working.
4) If only I had seen the film!
その映画を見てさえいたらなあ。
※ if only~は「~でありさえすれば」という意味でI wishとほぼ同じ意味で用いられる。if onlyは間接話法では使えない。
○ He seid, “If only she were here.”
(彼は「彼女がここにいさえすればなあ」といった。)
×He said that if only she were here.
108 仮定法を使ったていねいな表現
次の文を日本語に直しなさい。
1) Would it be rude if I opened the present now?
今プレゼントを開けたら失礼でしょうか。
※ 上記文のように相手の許可を求める場合に仮定法(would)を使うとていねいな表現となる。
・Would it be all right if I sat here?
(ここに座ってもよろしいですか?)
また、次のように相手に何かをしてほしいときにもていねいな表現となる。
・It would be nice if you could help me with my luggage.
(私の荷物を運ぶのを手伝っていただけると助かるのですが。)
2) Would you mind if I smoked here?
ここでタバコを吸ってもよろしいでしょうか?
※ Would you mind if I+動詞の過去形?で「~してもよろしいでしょうか」の意味。動名詞を使用して下記のように書き換えることもできる。
= Would you mind my smoking here?
またwould ratherの後で仮定法を使うと、遠回しな表現となり、ていねいさが出る。
・I’d[would] rather you didn’t smoke here.
(ここではタバコを吸わないでいただきたいのですが。)
3) I was wondering if you could pass me the sugar.
お砂糖をこちらに回していただけないでしょうか。
※ I wonder if you can pass me the sugar.というと、「砂糖をこちらにまわしてくれるかな」のような直接的な依頼表現となる。これをI wonder if you could pass me the sugar.とすると、少していねいな依頼になる。さらに、wonderを過去形にすると、より遠回しな表現となり、ていねいさが増す。上記文のwas wonderingのように、進行形を使うことで、さらにていねいな表現にすることができる。
wonderのほか、thinkやhopeも、同じような表現を使うことができる。
・Do you think you could help me move this weekend?
(今週末の、私の引っ越しを手伝ってもらえませんか。)
第13章 疑問詞と疑問文(解説)
109 疑問代名詞
( )に入れるのに適切な疑問詞を下から選びなさい。
1) “(What) are you thinking about? “Well, nothing in particular.”
※ (「君は何について考えているの。」「いや、特に何も。」
尋ねたい事柄が「物事」という名詞の場合は疑問代名詞のwhat(何)を用いる。このwhatは「人」にも用いられる。
2) “(Whose) is this new car? “It’s John’s.”
※ (「この新車はだれの?。」「ジョンのです。」)
「だれのもの?」と尋ねる場合には、whoの所有格であるwhoseを用いる。
3) “(Who[Whom]) did he take to the zoo?” “He took his son there.”
※ (「彼はだれを動物園に連れて行ったの?」「彼の息子だよ。」)
動詞の目的語になる「人」について「だれを?」と尋ねる場合には、whomを用いる。ただし口語では、whomの代わりにwhoを用いるのがふつう。
また、動詞の目的語が「物事」の場合には、次のようにwhatを用いる。
・“What do you have for breakfast?” “I usually have toast.”
(「朝食には何を食べますか?」「たいてい、トーストです。」)
4) “(Which) of these T-shirts do you want?” “The blue one.”
※ (「これらのTシャツの中でどれが欲しい?」「青色の。」)
「人」や「物事」について、「この中でどれ?」のように、限られた選択肢から選ぶ場合にはwhichを用いる。
〈参考〉選択肢が限られている場合でも、whoを用いることができる。
・Who won the race, John or Paul?
(ジョンとポールのどちらがそのレースに勝ったの?)
ただし、次のようにof …が後に続く場合にはwhichを用いる。
・Which of these singers do you like best?
(この中のどの歌手が一番好きですか。)
5) “(Who) went to the party with her?” “Her father did.”
※ (「だれが彼女とパーティーの行ったの?」「彼女はのお父さんだよ。」)
「人」について「だれなのか」を尋ねたい場合には、上記文のようにwhoを用いる。
110 疑問形容詞
疑問詞に対する答えとして適切なものをA)〜D)の中から一つずつ選びなさい。
1) Whose camera is this?
C) It’s my sister’s.
※ (これはだれのカメラ?C) 僕の妹のだよ。)
上記文のように「だれの…?」と尋ねるときにはwhoseを用いる。所有格の代名詞はmy sister’s camera(僕の妹のカメラ)のように後ろに名詞を伴って用いられるので、「だれのカメラ」と言いたいときはwhose cameraとすれば良い。whoseは〈whose+名詞〉の形で用いることが多い。
2) What kind of car did you buy?
D) A compact.
※ (君はどんな種類の車を買ったの? D) 小型車。)
what kind of …は「どんな(種類の)…?」という意味を表し、ものの種類を尋ねたい場合に用いる。
3) What color do you like?
B) I like green.
※ (どんな色が好き?B) 緑が好き。)
What do you like?(何が好き?)という質問だと答えにとまどってしまうが、上記文のような質問なら、話が色に限られるので答えやすい。このように〈what+名詞〉で、「どんな…?」という意味を表すことができる。
4) Which shirt do you like?
A) The red one in the middle.
※ (どのシャツがいいですか?A)真ん中の赤いの。)
いくつかの選択肢がある中で、どれかを知りたいときにはwhichを使って上記文のように言う。〈which+名詞〉で「どの…?」という意味を表す。
111 疑問副詞
( )に適切な疑問詞を入れなさい。
1) “(Where) are you going?” “To the park.”
※ (「どこに行くの?」「公園に。」)
「どこ?」と場所を尋ねる場合には上記文のようにwhereを用いる。
2) “(Why) did he change his mind?” “Because his mother gave him some good advice.”
※ (「なぜ、彼は気持ちが変わったの?」「彼のお母さんが彼にいくつか良い忠告をしたからだよ。」)
「なぜ?」と理由を尋ねる場合には上記文のようにwhyを用いる。
3) “(How) much did you pay for the book?” “Fifteen dollars.”
※ (「その本にいくら払ったの?」「15ドル。」
量について尋ねるときは、how much(どのくらいの量?)を使う。
また、数について尋ねるときは、how many(どのくらいの数?)を使う。
“How many CDs do you have?” “Over a hundred.”
(「どのくらいのCDを持っているの?」「100枚以上はあるよ。」)
〈howのさまざまな使い方〉
方法を尋ねる「どのように?」
・“How do you go to school?” “By bus.”
(「どうやって通学していますか。」「バスで。」)
・“How do you spell ‘giraffe’?” “G-I-R-A-F-F-E.”
(「giraffe(キリン)はどのようにつづりますか。」「G-I-R-A-F-F-Eです。」)
様子や状態を尋ねる「どんな具合[状態]?」
・“How do you feel?” “I feel fine.”
(「気分はどうですか?」「元気ですよ。」)
・“How was your meal?” “It was very good.”
(「食事はどうでしたか。」「とてもおいしかったです。」)
程度を尋ねる「どのくらい…なのか」(直後に形容詞や副詞を伴う)
・“How far is your house from the station.” “About two kilometers.”
(「あなたの家は、駅からどのくらいの距離がありますか。」「約2キロです。」)
・“How long did you wait there?” “For one hour.”
(「どのくらいそこで待っていたのですか。」「1時間です。」)
・“How soon can I have the book?” “In a week.”
(「いつごろからその本が手に入りますか。」「1週間後には。」)
〈Howを用いて相手の調子を尋ねる〉
友人や知人に出会った時、「調子はどう?」と尋ねることはよくあることだ。こういう場面で使える表現をいくつか覚えておこう。
・How are you? / How are you doing? / How’s it going? / How are things?
(調子はどう?)
・Pretty good. / Great.(とてもいいよ。)
・Not bad. / So-so.(まあまあだね。)
〈Whatを用いて相手の調子を尋ねる〉
・What’s up? / What’s going on? / What’s new? (何か変わったことは?)
・Not much. / Nothing, really. (相変わらずだね。)
4) “(When) will you be back?” “At ten.”
※ (「君はいつ戻る予定?」「10時に」)
「いつ?」と時を尋ねる場合には上記文のようにwhenを用いる。
5) “(How) was the show?” “Oh, it was great.”
※ (「そのショーはどうでしたか?」「素晴らしかった。」)
112 疑問詞と前置詞
日本語の意味に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) だれを待っているの?
(Who) are you waiting (for)?
※ 前置詞の後の名詞(前置詞の目的語)について尋ねる場合は、前置詞の目的語を疑問代名詞に置き換え、その疑問代名詞だけを文頭に出すのが一般的である。
上記文に対する返答として、例えば “I’m waiting for Jim.”(「ジムを待っている。」)などを想像すると、「ジム」にあたるのがだれなのかを尋ねようとしていることになる。「だれ?」を尋ねるときにはwhoを使うので、Who are you waiting for?となるのである。また、前置詞と疑問詞を〈前置詞+疑問詞〉の形でまとめて文頭に出すこともか可能である。(ただし、この形は口語ではあまり用いられない。)
= For whom are you waiting?
〈参考〉疑問代名詞whoの使い方には注意が必要。前置詞の目的語が疑問詞になる
ので、文法的にはwhomを用いるのが理屈に合っている。実際、For whom …?のように、前置詞を疑問詞の前に置く場合にはwhomを用いる。(×For who …?は不可)。しかし、前置詞と切り離されて疑問詞だけが文頭に出る場合にはwhoを用いるのが一般的である。
2) だれにその小包を送るつもりなのですか?
(Who) are you going to send the parcel (to)?
113 間接疑問
次の疑問文を、指定された書き出しに続く間接疑問文にしなさい。
1) Why did ‘t you come? (You must tell me …)
You must tell me why you didn’t come.
※ (あなたはなぜ来なかったかを私に伝えなければならない。)
上記文では、You must tell meの後にwhy you didn’t comeが続く。このwhy you didn’t comeはtellの目的語になっている。このように、文の一部として組み込まれた疑問文が間接疑問である。
間接疑問で注意すべき点は疑問詞の後の語順である。間接疑問は〈S+V〉という平叙文と同じ語順になるため、why didn’t you comeという疑問文の語順ではなく、why you didn’t comeという語順になる。
また、次のように疑問文の中に間接疑問が組み込まれている場合でも、間接疑問の部分は〈S+V〉の語順になる。
・Can you tell me why you didn’t come?
(なぜ来なかったか教えてくれませんか?)
なお、Who broke the window?のように主語が疑問詞になっている疑問文は、もともと〈S+V〉という平叙文と同じ語順になっているので、そのままの形で間接疑問として用いられる。
・I don’t know who broke the window.(だれが窓を割ったのか知りません。)
〈参考〉間接疑問の文中での働き
① 動詞の目的語
Do you want to know what I bought?
(私が何を買ったか知りたいですか?)
② 前置詞の目的語
I have no idea (of) who broke the computer.
(だれがコンピュータを壊したのか見当がつかない。)
この場合、前置詞ofは省略されることが多い。
③ 主語
When he left the house is not known.
(彼がいつ家を出たのかはわかっていない。)
④ 補語
The problem is how we will finish this job.
(問題は、どうやってこの仕事を終えるかということだ。)
2) What kind of music do you like? (I want to know …)
I want to know what kind of music you like.
※(私はあなたがどんな種類の音楽が好きなのか知りたい。)
3) When is she going to leave? (The problem is …)
The problem is when she is going to leave.
※ (問題は彼女がいつ去るつもりかということだ。)
114 否定疑問文
日本語の意味に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) 「あなたはあのバンドのメンバーではないのですか。」「メンバーですよ。」
“(Aren’t) you a member of that band?” “(Yes), I am.”
※ 上記文のような否定形の疑問文を否定疑問文と呼ぶ。否定疑問文は上記文のように、自分が思っていることを相手にもそうだと言わせたいような場面で用いられることがある。この場合、不可疑問文を使った文と同じ意味合いになる。
= You are a member of that band, aren’t you?
・“Isn’t it a lovely day?” “Yes, it is.”
(「すてきな日じゃない?」「うん、すてきなひだね。」)
・Don’t you like my new swimsuit?
(私の新しい水着はどう?)[「いいでしょう?」と相手に確認している]
〈参考〉notを次のような位置で使うこともある。
・Did you not meet Lisa yesterday?
(昨日、リサに会わなかったの?)
〈否定疑問文での答え方〉
日本語だと「はい/いいえ」の答えは相手の質問の形に合わせて変える。しかし、英語のYes/Noは、相手の質問の形にかかわらず、自分の答えが肯定の内容ならYesを用い、否定の内容ならNoを用いる。つまり、相手がDo you …?と尋ねても、Don’t you …?と尋ねても、返事は同じになる。
答え方 「知っている」「知らない」
Do you know this? → Yes, I do. No, I don’t.
Don’t you know this? → Yes, I do. No, I don’t.
2) 「その場所に行かなかったの?」「行かなかったよ。」
“(Didn’t) (you) visit that place?” “(No), I didn’t.”
※ 否定疑問文は、上記文のように、否定の意味で尋ねる場合に用いられる。Did you visit that place?であれば「その場所に行ったかどうか」をたずねているだけでだが、Didn’t you visit that place?は、相手が行かなかったことに気づいたときの質問ということになる。
3) 「彼女は日本語を話せないの?」「いいや、話せるよ。」
“(Can’t) (she) speak Japanese?” “(Yes), she (can).”
※ 当然そうだと思っていたのに「違うの?」と、驚きや意外な気持ちを表現する時に
否定疑問文を用いることもできる。
・Don’t you know this?(あなたはこれを知らないのですか?)
この疑問文は、「当然知っているはずなのに」という気持ちを表していると考えることができる。
115 疑問文への答え方
疑問文に対する答えとして適切なものをA)からD)から1つずつ選びなさい。
1) What do you think this is?
B) It’s a kind of toy.
※ (これは何だと思う?B)それはおもちゃの一種。)
「これは何だと思いますか?」と尋ねるときは、疑問詞のwhatを使って、上記文のような疑問文にする。疑問詞が文頭に置かれた疑問文なので、YesやNoで答えることはできない。
上記文のような「何[だれ]だと思いますか?」という意味の文では、疑問詞を文頭に出して〈疑問詞+do you think …?〉という形にする。また、thinkに続く部分は、平叙文の語順になることにも注意が必要。think以外にも、believe(信じる)やsuppose(想像する)などの動詞を用いる場合は同様の語順にする。
・When do you suppose he will propose to her?
(彼はいつ彼女にプロポーズすると思いますか。)
〈注意〉主語が疑問詞になっているパターンに注意
whatやwho, whichが、do you think[believe / suppose]に続く節の主語として働いている文では、do you think[believe / suppose]の後に(助)動詞が続く。
・Who do you think is the best player on our team?
(チームで一番いい選手はだれだと思いますか。)
・What do you think will be the most successful movie this year?
(今年もっとも成功する映画は何だと思いますか。)
・Which do you suppose is the better plan?
(どちらのほうがよい計画だと思いますか。)
2) Do you know what this is?
C) No, I have no idea.
※ (これが何だか知っていますか。B)いいえ、見当がつきません。)
上記文のような「これが何だか知っていますか?」という疑問文にはYes/Noで答えることになる。このように「何[だれ]だか知っていますか?」という意味の疑問文をつくる場合は〈Do you know+疑問詞…?〉の形を用い、文頭に疑問詞を置いてはならない。
3) Do you mind if I smoke here?
D) No, I don’t mind.
※ (ここでタバコを吸ってもいいかな。D)どうぞ。)
Do you mind … ?を文字どうおりに訳すと「あなたは…をいやがりますか?」となる。したがって、Yed, I do.で答えると「はい、いやです」という意味になってしまう。相手の依頼を引き受けたり、相手に許可を与えたりする場合には、Not at all. / Of course not. / Certainly not. / I don’t mind.といった否定の返事をしなければならない。
「やめてほしい」と言いたければ、I’d rather you didn’t.と言う。また、I’m sorry …とことばをにごしたり、I do mind.と強く言ったりすることもある。
〈参考〉会話の状況や、答え方の口調や表情で、Yes, certainly.のように、Yesを使って承諾を意味することもある。
〈参考〉Do you mind?は、相手に対して、「今していることをやめてほしい」という意味で用いられることがある。
・Do you mind? That’s my seat you’re sitting in.
(すみません。その席は私の席なんですが。)[→どいてほしい]
4) Can I use your bathroom?
A) Sure. Go ahead
※ (トイレを使ってもいいかな。A)もちろん。どうぞ。)
Can I … ?のような相手の許可を求める疑問文に答える場合、「いいですよ」と承諾するときには、
Sure. / Certainly. / OK. / Of course.
などが使える。
また、「だめだよ」と言いたいときには、
No, you can’t. / Sorry, you can’t.
などが使える。
なお、Can you … ?に対して「いやだ」と言うときには、
No, I can’t. / I’m afraid I can’t.
のように言う。
“Can you help me with my homework?” “No, I can’t.”
(「宿題手伝ってくれる?」「だめだよ。」)
〈haveとhave got〉
① “Do you have a credit card?” “Yes, I do. / No, I don’t.”
② “Have you got a credit card?” “Yes, I have. / No, I haven’t.”
いずれも「あなたはクレジットカードを持っていますか?」「はい、持っています。/いいえ、持っていません。」という意味である。
①は、もっとも一般的な表現。Have you a credit car?という形も可能であるが、現在ではhaveは一般動詞と考えるのがふつうで、疑問文をつくるときやそれに答えるときも、ほかの一般動詞と同じように用いる。
②のhave gotはhave got = haveと考えてよい。Haveが助動詞としてもちいられていることに注意。口語でよく用いられる表現である。
116 付加疑問文
( )に適語を入れて、付加疑問文を作りなさい。
1) These flowers smell sweet, (don’t) (they)?
※ (これらの花は甘い香りがしますよね。)
「~ですよね」と相手に同意を求めたり確認したりするときには、平叙文の後に短縮の疑問形を続ける。これを付加疑問文と呼ぶ。付加疑問文の形は〈助動詞/be動詞/+主語?〉で、主語はその文の主語を表す代名詞を使う。
肯定文の後には、上記文のように否定の付加疑問をつける。
・“It’s very hot today, isn’t it?” “Yes, it is.”
(「今日はとっても暑いよね。」「うん、暑いね。」)
・Your sister likes candy, doesn’t she?(君の妹はキャンディーが好きだよね。)
・They can run fast, can’t they?(彼らは早く走れるよね。)
一方、否定文の後には、次のように肯定の付加疑問をつける。
・“She doesn’t like coffee, does she?” “No, she doesn’t.”
(「彼女はコーヒーが好きじゃないよね。」「うん、好きじゃないね。」)
・You aren’t tired, are you?(疲れてはいませんよね。)
・They cannot run fast, can they?(彼らは早く走れませんよね。)
〈参考〉rightやOKを付加疑問のように使って相手に念を押すことも口語ではよ
くある。
・You know the truth, right?(君は本当のことを知ってるんでしょ?)
〈参考〉相手の同意を得たい場合には文尾を下がり調子(⤵)で言い、相手に確認
したい場合は、文尾を上がり調子(⤴)で言う。
〈注意〉付加疑問文の答え方
肯定文の答えにはYes, 否定文の答えにはNoを使って答える。
2) There is no one in the room, (is) (there)?
※ (部屋にはだれもいないですよね。)
上記文のようなThere is …の場合、付加疑問では主語の位置にはthereを入れる。また、この文はnoがあるので否定文である。したがって、付加疑問文は肯定の形を使う。littleなどの準否定語を使った文も否定文なので、付加疑問は肯定の形を使う。
・“There’s some juice in the fridge, isn’t there?” “Yes, there is.”
(「冷蔵庫にはまだジュースがあるよね?」「うん、あるよ。」
・“She never listens, does she?” “No, she never does.”
(「彼女ってまったく人の話を聞かないよね。」「ああ、まったくだ。」
3) You’ve already made up your mind, (haven’t) (you)?
※ (君はもう決心はついているんだよね。)
上記文のような完了形の場合、付加疑問ではhave[has/had]を使う。
117 修辞疑問文/平叙文疑問文/聞き返し疑問文/応答疑問文
日本語の意味に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) そんなことをしてなんの役に立つんだろうか。
(What) is the use of doing such a thing?
※ 疑問文の形をしているが、相手に答えを求めることを目的としない文を修辞疑問文と呼ぶ。肯定の修辞疑問文は否定の気持ちを、否定の疑問文は肯定の気持ちを表している。
・Who knows? (だれにわかるだろうか。→だれにもわからないよ。)
・What could be simpler than this?
(これ以上簡単なものが何かあるかい。→これが一番簡単だよ。)
・Who doesn’t love ice cream?(アイスクリームを嫌いな人なんていないよ。)
2) 「専攻は哲学です。」「何を専攻しているって?」
“I’m majoring in philosophy.” “ You’re majoring in (what)?”
※ 上記文のように、相手が言ったことの一部が聞き取れなかったり、理解できなかったときに、平叙文の語順のままで、わからなかった部分を疑問詞にして聞き返すことができる。また、相手が言ったことに対して、驚きや意外な気持ちを表すときにも用いることができる。
・“I’m sorry, Dad. I broke your …” “You broke my what?”
(「お父さんごめん。壊しちゃったんで。お父さんの…」「私の何を壊しただって?」)
・“I told him the truth.” “You told him what?”
(「彼に本当のことを言ったの。」「何を言ったって?」)
3) 「ジャックとべティが結婚したんだってさ。」「へえ、そうなの。」
“Jack and Betty got married.” “Oh, (did) they?”
※ 相手が言ったことにあいづちを打つ場合に、疑問文の形式を用いることがある。文の内容は相手が話したことのくり返しになるので、Are you?やDo you?など、疑問文であることを示す最低限の部分だけを用いる。
・“Ichiro hit a home run yesterday.” “Oh, did he?”
(「イチローが昨日ホームランを打ったんだ。」「へえ、そうなの。」)
・ “I’m not interested in video games.” “Aren’t you?”
(「テレビゲームには興味がないんだ。」「そうなんだ。」
118 疑問文の慣用表現
日本語の意味に合うように、( )の語句を並べかえて英文を完成させなさい。
1) 何のためにここに来たの?
What (did you come here for)?
※ 「何のために…?」と目的を尋ねるときに、What … for?という形を用いることもできる。また、単にWhat for?として、「どうして?」と尋ねることもある。
・“I must go back to my house.” “What for?”
(「家に帰らなきゃ。」「どうして?」)
2) 明日の天気はどうなりそうですか。
What’s (the weather going to be like) tomorrow?
※ 主語について「どのようであるか/何のようであるか」を尋ねる場合は、S is like … (Sは…のようだ)という文の「…」に相当する部分を聞けばよい。疑問代名詞のwhatを使って疑問文を作ると、What is S like?となる。この疑問文には、〈S is like+名詞〉(Sは~のようなものです)や〈S is +形容詞〉(Sは~です)などのように答えればよい。
・What is the food in Spain like?
(スペインの料理ってどのようなものですか?)
・“What is your father like?” “He is very kind.”
(「あなたのお父さんはどんな人」「とっても優しいの。」)
「Sは見た目はどんな感じですか。」「Sはどのように見えますか?」という意味の疑問文は、What does S look like? という形になる。
・What does the Sphinx look like?
(スフィンクスは見た目はどんな感じですか。)
〈注意〉WhatかHowか
Whatを用いるべきところで、「どのように」にひきずられて、Howを使ってしまうことがある。
・What is Cathy like? (キャシーはどんな人ですか。)
How is Cathy?(キャシーの調子はどうですか。)
How を用いてHow is Cathy?とするとキャシーの健康状態を尋ねていることになってしまう。人の性格や物の特徴を尋ねるときはWhat is S like?を使う。
〈What do you think? と How do you feel?〉
・What do you think about his novel?
(彼の小説についてどう思いますか。)[どういう考え(意見)か尋ねている]
・How do you feel about his novel?
(彼の小説についてどうお感じですか。)[どういう感じ(印象)か尋ねている]
3) どうして彼女の家に行ったのですか。
(How come you went to) her house?
※ 「どうして…?」と聞く場合に〈How come+S V?〉という形を使うことができる。how comeはwhyとほぼ同じ意味と考えてもよいが、疑問文の作り方に大きな違いがある。whyを用いて疑問文を作る場合は、後ろは疑問文の語順になるが、how comeの場合は後ろが平叙文の語順となる。
= Why did you go to her house?
4) イタリア料理の店で夕食を食べるのはどうですか。
(How about eating dinner) at an Italian restaurant?
※ 疑問文で提案や勧誘を表す表現。
① How[what] about …? 「…はいかがですか?」(相手に提案・推奨)
[aboutの後は名詞/代名詞/動名詞を置く]
・How[what] about going to the movies tonight?
(今夜、映画を見に行きませんか。)
・How about a cup of coffee?(コーヒーを1杯いかがですか。)
② What do you say to …?「…はいかがですか?」(相手の意向を尋ねる)
[toの後は名詞/代名詞/動名詞を置く]
・What do you say to renting a DVD?(DVDを借りませんか。)
③ Why don’t you +動詞 …?「…してはいかがですか?/…しましょうよ」(提案)
・Why don’t you get more exercise?(もっと運動したらどうですか。)
④ Why don’t we +動詞 …?「(一緒に)…しましょうよ」(提案)
・Why don’t we get more exercise?(もっと運動しましょうよ。)
⑤ Why not+動詞 …? 「…してはいかがですか?」「…しましょうよ」(提案)
・Why not just ignore her comment?
(彼女の発言は無視したらどうですか。)
〈Why not?「もちろん、いいよ」〉
・“Let’s turn on the air conditioner.” “Why not?”
(「エアコンのスイッチを入れようよ。」「もちろん、いいよ。」)
このWhy not?は「なぜいけないの?」→「もちろん、いいです。」という意味。相手からの依頼、提案などに答えるときに使う。
第14章 否定(解説)
119 not / never / no
日本語の意味に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) ティムは兄からではなく、いとこから手紙を受け取った。
Tim received a letter from his cousin, (not) from his brother.
※ 特定の語・句・節をnotで否定する場合には、否定する語・句・節の直前にnotを置く。
上記文は句を否定。語や節の否定は次のようになる
・David is Australian, not British.
(デイブはオーストラリア人で、イギリス人ではない。) [語の否定]
・She loves him not because he is handsome, but because he is warm-hearted.
(彼女は彼がハンサムだからではなく、心が温かいから愛しているのです)
[節の否定]
2) 私には衣類を洗たくする時間がない。
I have (no) time to wash my clothes.
※ noは上記文のように、名詞の前について「まったく~ない」「1人[1つ]も~ない」という強い否定を表す。no~はnot a~/ not any~という意味で、数えられる名詞にも数えられない名詞にも使うことができる。
数えられる名詞の場合は、次のように複数形、単数形のどちらにも使うことができる。
・There were no children in the park.
(公園には子どもが1人もいなかった。)
・There was no chair for me to sit on.
(私が座るいすが1つもなかった。)
〈参考〉There were no children in the park.では「ふつうは子どもたちが何人かいる」ような状況が考えられるのでchildrenという複数形が使われている。There was no chair for me to sit on.では自分が座るいすは1つあればよいのだから、単数形が使われていると考えればよい。
〈参考〉noは、「ゼロ」という意味の数や量を表す形容詞であると考えるとわかりやすい。
・He has made two major discoveries.
(彼はこれまでに2つの大きな発見をしている。)
・He has made no major discoveries.
(彼はこれまでゼロ個の大きな発見をしている。→大きな発見は1つもしていない。)
この2つの文におけるtwoとnoの使い方に注目すれば、noが数・量を表す形容詞であるという考え方が理解できるだろう。
3) だれもこの絵には興味をもたないだろう。
(Nobody) will be interested in this picture.
※ 主語にnoがつくと、主語が否定されるばかりでなく、結果的に文全体の内容が否定されることになる(全否定)。
・No students are allowed to enter this room
(いかなる学生もこの部屋に入ることは許されていない。)
nobody, nothingなども〈no+名詞〉と同じように考えるとよい。また、no oneはnobodyと同じ意味で使われ、単数扱いになる。
また、noは〈形容詞+名詞〉の前や、be動詞の補語となる名詞の前に置かれると、「決して~ない」という意味に強い否定を表す。
・Building a house is no simple task.
(家を建てるということは、決して簡単なことではない。)
・He is no genius.
(彼は決して天才なんかじゃない。)
4) 私は彼にうそをつくなと言った。
I told him (not) to tell a lie.
※ 上記文では、notがto tell a lieという句を否定している。ここでは、「(彼が)うそをつくこと」が否定されていることに注意。「私が彼に言った」ことは否定されていない。
〈notの位置と意味の違い〉
上記文のnotの位置を変えると、文全体が否定され、意味が変わる。
I told him not to tell a lie.
[to tell a lieを否定]
I did not tell him to tell a lie.
[述語動詞tellを否定]
(私は彼にうそをつくようにとは言わなかった。)
5) 私は決して朝食を食べない。
I (never) eat breakfast.
※ neverは「一度も~ない」という意味を表す。
〈注意〉neverの位置
be動詞以外の一般動詞を使う場合は、〈never+動詞〉の語順。
・It never snows on the island.(その島では決して雪が降らない。)
be動詞を使う場合は、〈be動詞+never〉の語順。
・Peter is never at home.(ピーターはいつも家にいない。)
助動詞が含まれる場合は、〈助動詞+never+動詞〉の語順。
・I will never ride a roller coaster again.
(もう二度とジェットコースターには乗らないよ。)
neverは「一度も[いつも]~ない」ことを表すので、経験の意味を表す完了形でよく使われる。
・I have never seen such a rude man.
(そんな失礼な男には今まで一度も会ったことがない。)
〈参考〉Have you ever been to Oslo?(オスロに行ったことがありますか。)と
いう疑問文に、「いいえ、一度もありません。」と答える場合は、No, I haven’t.かNo, I never have.という。このように、応答分などで本動詞が省略される場合には、neverは助動詞の前に置く。×No, I have never.とは言わない。
120 否定語の位置
次の文を否定文にしなさい。
1) I think he is a good violinist.
I don’t think he is a good violinist.
※ (彼は上手なバイオリン奏者だと思います。)
think, believe, supposeなどの主語の意思や判断を表す動詞の後ろにthat節や語句がある場合、そのthat節や語句を否定語にするのではなく、最初の動詞を否定することが多い。expect、imagineもこの形をとる。
・I don’t expect that he will accept my apology.
(彼が私の謝罪を受け入れるとは思っていません。)
seemもこの形で用いられることが多い。
・It doesn’t seem that he knows our secret.
(彼が私たちの秘密を知っているようには思えません。)
2) I hope she will accept his offer.
I hope she will not[won’t] accept his offer.
※ (彼女が彼の申し入れを受け入れないと思う。)
hope(〈好ましい事態を〉想定する、思う)、be afraid / fear(〈不都合[心配な事態]を〉想定する、思う)の場合は、動詞の後に続くthat節を否定形にする。
・I am afraid that she won’t be able to get here on time.
(彼女が時間通りにここに着くのは無理なんじゃないだろうか。)
〈notと副詞の位置〉
A) I just don’t like her. (私は彼女のことは全く好きではない。)
B) I don’t just like her. (私は彼女のことをどうしようもないくらい好きだ。)
A)の文では、just 「まったく、完全に」がdon’tという否定表現を修飾しているため、否定が強められる結果となている。
それに対して、B)の文では、否定語notがjust「ただ単に」を修飾しているため、「私は単に彼女のことを好きだというだけではない。」→「私は彼女をどうしようもないくらい好きだ。」という意味になっている。否定語と、just, simplyといった副詞との位置関係には注意しよう。
121 節の代わりをするnot
日本語の意味に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) 「明日は雨が降るだろうか。」「降らないといいね。」
“Will it rain tomorrow?” “I (hope) (not).”
※ 上記のI hope not.はI hope that it won’t rain tomorrow.と同じ意味を表す。このように、hopeやbe afraidの後ろには、節の代わりとしてnot 1語を置く。
2) 「彼はよくなるだろうか。」「よくならないとおもうよ。」
“ Will he get well?” “I’m (afraid) (not).”
※ 上記のI’m afraid not.はI’m afraid that he won’t get well.と同じ意味を表す。
that節を肯定の意味で受けたいのであれば、not ではなくsoを使う。
“Is it still raining?” “I’m afraid so.”
(「まだ雨が降っているのかな?」「うん、降っていると思うよ。」
〈注意〉afraidとnotの位置
I am not afraid.(私はこわがってなんかないぞ。)
I am afraid not.(残念ながら私はそうじゃないと思います。)
※ 〈soとnotの使い分け〉
soとnotのどちらかを使うかは、肯定の意味でのべるのか、否定の意味で述べるのかによって決まる。
“Is he coming to the party?”(彼はパーティーに来るの?)
という肯定の形での問いかけに対しても、
“Isn’t he coming to the party?”(彼はパーティーに来ないの?)
という否定の形での問いかけに対しても、「来る」と思えば
“Yes, I hope so.” や “Yes, I suppose so.”
などと答え、「来ない」と思えば
“No, I’m afraid not.” や “No, I suppose not.”
などと答えればよい。
122 準否定語
( )内から正しいほうを選びなさい。
1) He (seldom) goes out on Sundays.
※ (彼はめったに日曜日は出かけない。)
Rarely, seldomは、何かをする回数がほとんどないことを表す副詞で、動詞を修飾して「めったに~ない」という意味を表す。
・I rarely listen to classical music.
(私はめったにクラシック音楽を聴きません。)
〈注意〉hardly[scarcely] everも「めったに~ない」
hardly ever, scarcely everは頻度を表す。「一度でも」という意味のeverに「ほとんど~ない」という意味のhardlyやscarcelyがつくためである。
・I hardly[scarcely] ever eat breakfast.(私は朝食をめったに食べない。)
2) I could (hardly) understand the lecture.
※ (私はその講義がほとんど理解できなかった。)
hardly, scarcelyは、何かの〈程度〉がほとんどないことを表す副詞。動詞を修飾すると「ほとんど~しない」という意味になる。
・The injured child could scarcely walk.
(けがをしたその子どもは、ほとんど歩けなかった。)
3) They had (little) snow in Osaka.
※ (大阪では雪はほとんど降らなかった。)
littleは量がほとんどないことを表す形容詞。littleは名詞を修飾して「ほとんど~ない」という意味を表す。littleは数えられない名詞の前に置く。no(まったく~ない)がもつ否定の意味を弱めた表現である。
・I had little time to buy a present for her.
(彼女へのプレゼントを買う時間はほとんどなかった。)
〈注意〉a littleのようにaをつけると否定の意味が消え、「少しはある」という意味になる。
4) He is a man of (few) words.
※ (彼は口数の少ない男だ。)
fewは数がほとんどないことを表す形容詞。fewは名詞を修飾して「ほとんど~ない」という意味を表す。fewは数えられる名詞の前に置く。no(まったく~ない)がもつ否定の意味を弱めた表現である。
・Few students handed in the homework.
(宿題を提出した生徒はほとんどいなかった。)
〈注意〉a fewのようにaをつけると否定の意味が消え、「少しはある」という意味になる。
123 部分否定・二重否定
次の文を日本語に直しなさい。
1) Not all of the members attended the meeting.
会員の全員が会議に出席したというわけではなかった。
※ 上記文は、All of the members attended the meeting.という文の文頭にnotが置かれ、内容が否定されている。したがって、「会員の全員が会議に出席した」+「のではない」となって、「会員の全員が会議に出席したというわけではなかった」という意味になる。このような否定文を部分否定と呼ぶ。
〈注意〉notはallの前に置く
「全部が…というわけではない」という意味を表したい場合は、Not all …のように、allの前にnotを置く。notをallの後に置いて、All of the members didn’t attend …のようにすると、「全部が…ない」という意味にとられてしまうこともある。
2) None of the members attended the meeting.
会員はだれも会議に出席しなかった。
※ 上記文は、all of the membersのallの代わりにNoneがおかれている。Noneは「だれも[何も]ない」ことを表すので、「だれも会議に出席しなかった 」という文になる。すべてを否定していることになるので、この文は全否定と呼ばれる。
3) He doesn’t always buy that weekly magazine.
彼はいつもその週刊誌を買うとは限らない。
※ notの後に、allやalways, completelyのような「全体性」や「完全性」を表す表現を続けると、「全部ではない」「完全ではない」という意味の部分否定になる。「全部が~というわけではない」ということは、「一部には~でないものもある」という意味を表していることになる。
部分否定を作る語には、次のようなものがある。
all(すべて(の))
every(すべての)
always(いつも/つねに)
necessarily(必ず)
quite(まったく/完全に)
altogether(まったく)
completely(完全に)
entirely(完全に)
〈注意〉「あまり~でない」を表す場合
manyやmuchなど「数・量・程度の多さ」を表す語を含む文を否定すると、「あまり多くない」「それほどでもない」という意味を表すことになる。
・Not many people in this country go to other countries to find a job.
(外国に職を探しに行く人は、この国にはあまり多くはいない。)
veryやsoを使った文も否定文になると、「あまり~ではない」という意味になる。
・He doesn’t like Italian food very much.
(彼はイタリア料理はあまり好きではない。)
・I don’t see him so often these days.
(最近、彼とはそれほどひんぱんには会っていない。)
〈参考〉文によっては部分否定なのか全否定なのかがあいまいなものもある。
・I have not read all of these books.
この文の場合、notだけが強く発音されると「全部読んでいない」という全否定の意味にとれるし、notとallを同じように強く発音されれば、「全部読んだわけではない」という部分否定の意味にとれる。
4) I’m not quite satisfied with your plan.
私はあなたの計画に完全に満足しているわけではない。
5) It’s not impossible to swim across this river.
この川を泳いで渡ることは不可能ではない。
※ 1つの文の中で否定を表す語が2つ使われることを二重否定という。二重否定は、上記文の「不可能ではない」のように、結果的に肯定の意味を表すことになる。たいていの場合、単なる肯定文よりも、肯定の意味が強く響く表現となる。
= It is possible to swim across this river.
・He never visits us without bringing a gift.
(彼が私たちのところに訪ねてくる時には必ずおみやげを持ってきてくれる。)
・It’s not unusual for couples to quarrel.
(夫婦が口げんかをするのは珍しいことではない。)
〈注意〉否定語を2つ使ってはいけない場合
nobodyやnothingのような否定語は、notのような否定の副詞とともに用いることはできない。
Nobody hates him.(だれも彼のことを嫌いではない。)
×Nobody doesn’t hate him.
124 否定の慣用表現
日本語の意味に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) 彼のおかしな髪型を見て、笑わずにはいられなかった。
I (couldn’t) (help) laughing at his funny hairstyle.
※ cannot help –ingは「~しないではいられない」という意味。このhelpは「~を避ける」という意味で、cannot helpで「~を避けることができない」という意味を表している。
・It cannot be helped.(どうしようもない。)
〈参考〉〈cannot but+動詞の原形〉[文語] や〈cannot help but+動詞の原形〉[口語] も同じ意味を表す。
= I couldn’t help but laugh at his funny hairstyle.
2) 海で泳ぐ時はいくら注意してもしすぎることはない。
You (cannot) be (too) careful when you swim in the sea.
※ cannot … too~は「いくら~してもしすぎることはない」という意味。tooの後には形容詞や副詞を続ける。
・We cannot praise him too highly.
(彼のことはいくらほめてもほめすぎることはない。)
この表現は、enoughを使ってcannot … enoughとしても同じ内容を表すことがで
きる。enoughは修飾する形容詞や副詞の後に置く。
・I cannot see her often enough.
(彼女とは、どんなにひんぱんに会っても足りないくらいだよ。)
〈参考〉動詞の後にenoughを続けることもできる。
・I cannot apologize enough.
(いくら謝っても謝り足りない。)
3) 健康を損なって初めてそのありがたさがわかる。
We (don’t) appreciate the blessing of health (until) we lose it.
※ not … until~は「~までは…しない/~して初めて…する/~になってやっと…する」という意味。この表現は、It is … that~の強調構文で、〈not+until節〉を強調するパターンでも使われる。
= It is not until we lose our health that we appreciate the blessing of it.
〈参考〉Not untilを文頭に出す表現もある(ただしこれは文章体)。その場合「倒置」が起こることに注意
= Not until we lose our health do we appreciate the blessing of it.
4) 私が食卓につくとすぐに電話が鳴った。
I had (hardly[scarcely]) sat down at the table (when[before]) the telephone rang.
※ hardly[scarcely] … when[before]~は「…するとすぐに~/…するかしないかのうちに~」という意味。上記文のhad hardly sat のように、過去完了を使うことが多い。また、no sooner … than~で「…するとすぐに~」という意味を表すこともできる。
・He had no sooner stepped outside than it started to rain.
(彼が外に出るとすぐに雨が降り出した。)
〈参考〉HardlyやNo soonerを文頭に出す表現もある(ただしこれは文章体)。その場合「倒置」が起こることに注意
Hardly had I sat down at the table when the telephone rang.
No sooner had he steeped outside than it started to rain.
5) 彼は1日中テレビばかり見ている。
He does (nothing) (but) (watch) TV all day long.
※ 〈do nothing but+動詞の原形〉で「…してばかりいる」という意味。このbutは「…を除いて/…以外は」という意味。「…する以外は何もしない」と考えるとよい。butの後ろに動詞の原形を置くことに注意。
〈have no choice but+to不定詞〉は、「…するしかない」という意味を表す。
・I had no choice but to quit my job.
(私は仕事をやめるしかなかった。)
〈no longer …〉は「もはや…でない/もう…でない」という意味。not … any longer
も同じ意味を表す。
・He is no longer a strong wrestler.
(彼はもはや強いレスラーではない。)
・I can’t trust him any longer.
(私は、もはや彼のことを信じられない。)
125 否定語を使わない否定表現
日本語の意味に合うように、( )の語句を並べかえて英文を完成させなさい。
1) 彼はあまりに眠かったので、宿題ができなかった。
He was (too sleepy to do) his homework.
※ 〈too … to不定詞〉は「あまりに…なので~できない/~できないほど…だ/~するには…すぎる」という意味。
〈参考〉不定詞の前に〈for+名詞〉を置き、不定詞の意味上の主語を表すこともできる。
・This book was too boring for me to read through.
(この本は退屈すぎて私は最後まで読み通すことができなかった。)
〈参考〉too … to~を使った文を、so … that~を使って表すこともできる。その
場合、that以下が否定文になることに注意。
= He was so sleepy that he couldn’t do his homework.
2) 彼女は決して約束を破るような人間ではないでしょう。
She would be the (last person to break her promise).
※ 〈the last … to不定詞〉は「決して~しない…/もっとも~しそうにない…」という意味。「~するとしたら最後の…」ということ。
〈参考〉to不定詞の代わりに関係詞節が続く場合もある。
・He is the last person who I would want to talk about the matter.
(彼とだけはその件について話したくない。)
3) 彼の話は決して退屈ではなかった。
His story (was anything but boring).
※ anything but … は「決して…でない」という意味。anythingは「どれでも」、butは「…を除いて」という意味なので、「…を除いたどれでも」となる。この文では「退屈だけは違う」→「決して退屈でない」ということ。
4) 彼の新しい小説は、とてもじゃないがおもしろいとは言えない。
His new novel (is far from interesting).
※ far from …は「…からはほぼ遠い/少しも…ない/とても…とは言えない」という意味。be動詞を使う文で使われることが多く、fromの後に名詞や形容詞が続く。
free from … で「…をまぬがれている/…がない」という意味。「束縛するものがない」という意味合いなので、fromの後には意味的に「やっかいなもの」「不都合なもの」「苦痛」「心配」など、話し手が悪い印象をもっている名詞が来る。前置詞にofを使う場合もある。
・No animal can live free from danger.
(何の危険もなしに生きていける動物などいない。)
・No part of Tokyo is free of air pollution.
(東京はどこも空気が汚れている。)
〈beyondを使って否定を表す〉
・The view from the window was beautiful beyond belief.
(その窓からのながめは信じられないくらい美しかった。)
このbeyond … は「…できない」という意味を表す。beyond自体は前置詞で、「…を超えている」という意味。後ろに人がすることを表す名詞や代名詞を置くと「…できる範囲を超えている」→「…できない」という意味の慣用句となる。
また、beyondの代わりにaboveを用いることもある。
・He is above cheating on exams.
(彼は試験でカンニングをするような人ではない。)
beyond … を使った表現には次のようなものがある。
beyond description 「描写(できる範囲)をこえている」
→「筆舌に尽くしがたい」
beyond my reach「私の手の届く範囲を超えている」
→「私の手には負えない」
beyond my budget「私の予算(で支払える範囲)を超えている」
→「買えないほど高い」
5) その町を訪れる時は、私は必ず彼と会います。
I (never fail to meet him) when I visit that town.
※ 〈never fail to不定詞〉は「~しそこなうことがない/必ず~する」という意味になる。また、〈fail to不定詞〉は「~しそこなう/~できない」という意味。本来ならすべきことや、したいと思っていたことができなかった場合に使い。
・The alarm failed to ring.(目覚まし時計がならなかった。)
・Never fail to call me every day.(毎日必ず電話をしてね。)
〈注意〉一度だけのことにneverは使わない
neverは「一度も~ない」という意味なので、一度だけの動作について言う場合は、Don’t forget to … / Be sure to …などを使う。
・Don’t forget to call me tomorrow. (明日必ず電話をしてね。)
第15章 話法(解説)
126 直接話法と間接話法の形
日本語の意味に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) 彼はその時、次のコンサートの準備をしていると言った。
He (told) me that (he) (was) preparing for his next concert (then).
※ 上記文を直接法で表現するとHe said to me now, “I am preparing for my next concert.”となるが、上記文は間接話法を用いており、発言内容は現在から見た過去のこととして言い直されている。そのため、時制の一致によって動詞が過去形になっている。間接話法で用いられるthatは省略することができる。
〈時制の一致の基本〉
① 従属節が同じ時点のこと(単純形)
We think he is honest.(私たちは彼は正直だと思う。)
We thought he was honest.(私たちは彼は正直だと思った。)
② 従属節が同じ時点のこと(進行形・完了形)
I understood what he was saying.(彼が言っていることは理解できた。)
He knew she had been there.
(彼女がそこに行ったことがあることを彼は知っていた。)
③ 従属節が過去のこと
It seems that the toast was burnt.(トーストがこげたようだ。)
It seemed that the toast had been burnt.(トーストがこげたようだった。)
④ 従属節が未来のこと
I think she will come.(私は彼女は来るだろうと思う。)
I thought she would come.(私は彼女は来るだろうと思った。)
〈助動詞の過去形〉
① 過去形をもつ動詞
will → would, can → could, may → might, have to → had to など
主節の動詞が過去形の場合、同じ時点のことであれば従属節でもそれに合わせて過去形の助動詞を用いる。
I thought he could come.(私は彼が来ることができると思った。)
② 過去形をもたない助動詞
must, need, should, ought to, had better, used toなど
主節の動詞が過去形で、従属節で述べることが同じ過去のことでも助動詞の形は変わらない。
He said Lucy must be angry.
(彼はルーシーが怒っているに違いないと言った。)
I thought you should be more careful.
(私は君がもっと注意深くあるべきだと思った。)
〈人称代名詞〉
① 直接話法の文
He said to me then, “I am preparing for my next concert.”
(彼はその時「私は次のコンサートの準備をしている」と言った。)
「彼」の発言をそのまま引用しているのでIやmyは「彼」が「自分」のこと
を言っていることになる。
② 間接話法の文
He told me that he was preparing for his next concert then.
(彼はその時、次のコンサートの準備をしていると言った。)
「彼」の発言を、伝える人の視点で言い直している。したがって、発言内容
を表す文ではheやhisが使われている。
〈sayとtell〉
① say
He said (to me) then, “I am preparing for my next concert.”
= He said (to me) that that he was preparing for his next concert then.
said to me(私に言った)のように〈to+人〉を続けるか、話す相手を示さず
に使うことができる。直接話法ではsayを使うことが多い。間接話法で使う
こともできる。
② tell
He told me (that) he was preparing for his next concert then.
× He told that he was preparing for his next concert then.
tellは、told me(私に言った)のように、伝える相手をしめさなければならない。×He told that …とはできないことに注意。間接話法ではtellを使うことが多い。直接話法でも使うことができるが、あまり一般的ではない。
2) 私の母は、その前の日に私のスニーカーを洗ったと、私に言った。
My mother told me that (she) (had) washed (my) sneakers the day before.
※ 上記文を直接話法に書き換えると次のようになる。
My mother said to me, “I washed your sneakers yesterday.”
間接話法を用いるときは、だれかの発言を、伝える人の視点で言い直す。話し手の
視点が変わることによって、表し方が異なる語句がでてくる。時を表す表現、指示
語(this, theseなど)の表し方が直接法と間接法では異なることがある。
直接話法 間接話法
this that
these those
here there
today that day
yesterday the day before / the previous day
tomorrow the next day / the following day
now then
last night the night before / the previous night
next week the next week / the following week
… ago … before
状況によってはこの表のとおりにはならないこともある。
You said, “I’ll come back here by five.”
(君は「ぼくはここに5時までに戻る」と言ったよ。)
→You said that you would come back here by five.
(君は、自分がここに5時までに戻ると言ったよ。)
発言をした人と、伝える人のいる場所が同じであれば、直接話法でも、間接話法で
もhereはhereのままである。機械的に暗記したパターンにあてはめるのではなく、
場所、時間、人、ものを別の立場から表現する場合、どのように表現すれば適切な
のかをその状況から判断することが必要。
3) ジョンは、彼の娘が次の日、空港で私たちを出迎えると言った。
John said that (his) daughter (would) meet us at the airport the (next)
day.
※ 上記文を直接話法で表現すると次のようになる。
John said, “My daughter will meet us at the airport tomorrow.”
127 平叙文以外の間接話法 (疑問詞疑問文・Yes/No疑問文・命令文)
日本語の意味に合うように、( )に適語をいれなさい。
1) 彼は私に、私がそのロックグループのファンなのかと尋ねた。
He asked me (if[whether]) (I) (was) a fun of the rock group.
※ (→直接話法:He said to me, “Are you a fun of the rock group?”)
伝える発言が疑問詞のないYes/No疑問文の場合、間接話法にすると上記文のよう
に、〈ask(人)+if[whether]SV〉という形になる。ただし、伝える発言がorを用い
る疑問文の場合は、〈whether … or ~〉の形を用いる。
・She asked the clerk whether that sweater was knit by hand or by machine.
(彼女は店員に、そのセーターが手編みなのか機械編みなのか尋ねた。)
この文を直接法で表すと次のようになる。
・She said to the clerk, “Is this sweater by hand or by machine?”
(彼女は店員に「このセーターは手編み、それとも機械編み?」と言った。)
2) その少年は私に、どこでその本を見つけることができるのかと尋ねた。
The boy (asked) me where I (could) find the book.
※ (→直接話法:The boy said to me, “Where can you find the book?”)
伝える発言が疑問詞を用いた疑問文の場合、間接話法にすると上記のように、〈ask(人)+疑問詞+SV〉という形になる。ただし、疑問詞自体が主語として働いている場合は、〈ask(人)+疑問詞+V〉になる。
・My boss asked who had called him up that morning.
(私の上司は、だれがその朝彼に電話したのか尋ねた。)
この文を直接話法で表すと次のようになる。
・My boss said, “Who called me up this morning?”
(私の上司は「だれが今朝私に電話したんだ?」と言った。)
3) その女性は息子に、彼はどうしてそんなことを言ったのかと尋ねた。
The woman (asked) her son (why) (he) (had) said such a thing.
※ (→直接話法:The woman said to her son, “Why did you say such a thing?)
4) 彼は息子に新聞を持ってくるように言った。
He (told[ordered]) his son (to) (bring) (him) the newspaper.
※ (→直接話法:He said to his son, “Bring me the newspaper.”)
伝える発言が命令文の場合、間接話法にすると上記文のように、〈tell+人+to do〉という形になる。話す相手に行動を求める発言なので、that節ではなくto不定詞を使って、「~するように」という意味にする。
5) 先生は少年たちにホールで走らないようにと言った。
The teacher (told[ordered]) the boys (not) (to) (run) in the hall.
※ (→直接話法:The teacher said to the boys, “Don’t run in the hall.”)
間接話法で「…するな」という禁止を表す命令文は次のようになる。
・My father told me not to give up my dream.
(父は私に、夢をあきらめないように言った。)
〈参考〉命令文のニュアンスによっては、orderやcommandなどのより強い命令
を表す動詞をtellの代わりに使うことができる。
My father ordered me to go out.
(父はぼくに、出ていくように命じた。)
6) 彼女は私にいっしょに来るように頼んだ。
She (asked) me (to) (come) (with) (her).
※ (→直接話法:She said to me, “Please come with me.”)
伝える相手が、相手に何かを依頼するような命令文の場合は、間接話法にする際にask(頼む)を用いて〈ask+人+to do〉という形にする。
・The receptionist asked me to call back after lunch.
(受付係は私に、昼食後に電話をかけ直すように頼んだ。)
この文を直接話法で表すと次のようになる。
・The receptionist said to me, “Please call back after lunch.”
(受付係は私に「昼食後に電話をかけ直してください。」と言った。)
発言がWould you … ?などを使ったていねいな依頼の場合も同様に〈ask+人+to do〉を用いる。
・A woman asked me to tell her the way to the station.
(ある女性が私に、駅への道を教えてほしいと頼んだ。)
・A woman said to me, “Would you tell me the way to the station?”
(ある女性が私に「駅への道を教えていただけませんか。」と言った。)
128 提案文・勧誘文・感嘆文
日本語の意味に合うように、( )に適語をいれなさい。
1) 彼は私に、その辞書を買うように助言した。
He (advised) (me) (to) buy that dictionary.
※ (→直接話法:He said to me, “You should buy this dictionary.”)
伝える発言が、相手に何かを提案したり忠告したりする文であれば、間接話法では上記文のようにadviseを用いて〈advise+人+to do〉の形を用いる。このように、相手の行動を促すような内容のときは、to不定詞を使うのがふつう。
2) 彼は弟にキャッチボールをやろうと提案した。
He (suggested) (to) his brother that (they) (play) catch.
※ (→直接話法:He said to his brother, “Let’s play catch.”)
伝える発言が、Let’s do … / Shall we do …?などの勧誘を表す文の場合は、間接話法では〈suggest (to+人) that S (should) do … 〉の形を用いる。この場合thatは省略しないのがふつう。suggestはto不定詞を続けることはできない。suggestの後のthat節では、〈should+動詞の原形〉か〈動詞の原形〉を使う。
・She suggested to me that we (should) go out for a walk.
(彼女は私に、散歩に出かけることを提案した。)
この文を直接話法で表すと次のようになる。
・She said to me, “Let’s go out for a walk.”
(彼女は私に「散歩に出かけましょう」と言った。)
なお、suggestの代わりにpropose(to+人)(提案する)を使うことも多い。〈suggest to+人〉〈propose to+人〉の形に注意。
He proposed to me that we discuss it later.
(彼は私に、それを後で議論することを提案した。)
3) 彼女は、私のバイクはなんてうるさいのかと文句を言った。
She (complained) (about) how noisy my motorcycle was.
※ (→直接話法: She said to me, “How noisy your motorcycle is!”)
伝える発言が、上記直接話法のHow noisy your motorcycle is!のような感嘆文の場合、間接話法ではその内容に合った動詞を使う。上記文では、「文句を言っている」ことがわかるので、complain(不満を言う)を使っている。
4) 少年たちは、勝ったと喜んで叫んだ。
The boys cried out in (joy) that they (had) (won).
※ (→直接話法:The boys said loudly, “We won!”)
間接話法では、上記文のように内容に合った動詞を使う。cry (out) (叫ぶ), exclaim
(叫ぶ)などの動詞を使ったり、in joy (喜んで), with regret (後悔して), in anger (怒
って)などの副詞(句)を用いて感情を表現することもできる。一定の形にこだわるよ
りも、もとの文のニュアンスを損なわない工夫をすることが大切である。
・He shouted in anger that he had been cheated.
(彼はだまされていた、と怒って叫んだ。)
129 従属節を含む文 / and, butなどで結ばれた文 / 種類の異なる文
次の文を間接話法で表現しなさい。
1) Bill said, “I don’t know how the accident will affect the economy.”
(ビルは「その事故がどのように経済に影響を与えるのかわからない」と言った。)
→Bill said (that) he didn’t know how the accident would affect the economy.
(ビルは、その事故が経済にどのような影響を与えるのかわからないと言った。)
※ 伝える発言が、接続詞や関係詞を使った節を含む場合、従属節(名詞節、形容詞節、副詞節)の動詞も適切な形にする。上記の間接話法文の場合は、過去の時点から見た未来のことになるので、the accident would affectとwouldを使っている。
2) Betty said to me, “I have a headache, but I will go to the movie with you.”
(べティは私に「私は頭痛がするけど、あなたと映画に行きます」と言った。)
→Betty told me (that) she had a headache, but that he would go to the movie with me.
(べティは私に、頭痛がするけど、私と映画に行くとと言った。)
※ 伝える発言がand, but, orなどの等位接続詞で結ばれた文の場合、間接話法では2つのthat節を発言内容と同じ接続詞で結ぶ。最初のthatは省略できるが、and, but, orの後ろのthatは省略しないのがふつう。特に、接続詞の後の内容が言ったことなのかどうなのか判断がつかなくなるような場合にはthatを入れる。
3) I said to the salesperson, “I like this type of shirt. Do you have a large size?”
(私はその営業員に、「私はこのタイプのシャツがいいです。大きいサイズはありますか?」と言った。)
→I told the salesperson (that) I liked this type of shirt and (I ) asked(him/her) if[whether] he/she had a large size.
(私はその営業員に、このタイプのシャツがいいと言い、大きいサイズがあるか尋ねた。)
※ 伝える発言が平叙文と疑問文などのように、タイプの違う2つ以上の文の組み合わせになっている場合がある。その場合は、それぞれの文を伝える視点で言い直し、andやbutなど適切な接続詞を用いてつなげばよい。
上記の間接話法文では、I told the salesperson (that) I liked this type of shirt.の後に疑問文の内容を加える。I asked him/her if[whether] he/she had a large size.をandでつなぐと、上記の間接話法文のようになる。
〈抽出話法〉
直接話法と間接話法の中間的な形をもった話法が存在する。おもに小説などで効果的な演出をするために用いられる。代名詞や時制、指示語などは間接話法の形をとっているのだが、疑問文などの語順が直接話法のままになっているのが特徴である。
・The clerk said that he would get my shoes from the factory, and would I come back in two weeks.
(その店員は、私の靴を工場から取り寄せると言い、2週間後に私にまた来てほしいと言った。)
例文を直接話法にすると、以下のようになる。
→The clerk said, “I will get your shoes from the factory. Would you come back in two weeks?”
第16章 名詞構文・無生物主語(解説)
130 名詞構文
次の文を日本語に直しなさい。
1) We got to the station before the arrival of her train.
私たちは、彼女が乗った列車が到着する前に駅に着いた。
※ the arrival of her train (彼女の列車の到着)は、自動詞arrive(到着する)の名詞形arrivalを使った表現である。her trainが意味上の主語を表している。
→Her train arrived. (彼女の列車が到着した。)
名詞で表されている行為をだれ[何]がするにかを〈of+名詞〉で表現することもある。
・The judgement of the committee was accepted by the cabinet.
(委員会が下した判断は内閣には受け入れられた。)
2) She denied her knowledge of the fact.
彼女は、その真実を知らないと言った。
※ her knowledge of the factは「彼女がその真実を知らなかったこと」という意味で、他動詞know(~を知っている)の名詞形knowledgeを使った表現である。
→ She knew the fact.(彼はその真実を知っていた。)
knowledgeの前のherはknowledgeの意味上の主語を表している。また、knowledgeの目的語であるthe factが、of the factという形でknowledgeに続いている。
〈注意〉他動詞の名詞形の後に目的語を続ける方法
of 以外の前置詞を使って名詞の後に目的語を続けることがある。
・We are looking forward to your attendance at the meeting.
(あたなたがその会議に出席することを楽しみにしています。)
・This is my first visit to Spain.
(私がスペインを訪れたのはこれが最初です。)
行為をする主語が示されない場合もある。
・The doctor made a careful examination of my eyes.
(医者は私の目を注意深く診察した。)
この文のように、行為(この場合examine)をする主語にあたるものが、文の主語にあたるものが、文の主語と同じである場合は、だれ[何]がそれをするかは示さないのがふつう。
〈注意〉他動詞の目的語が所有格で表される場合
・We were opposed to the historic building’s destruction.
(その歴史的な建物を壊すことに私たちは反対した。)
the historic building’s destructionはdestroy the historic buildingが名詞化したもの。このように、名詞が表している行為(この場合はdestroy)の目的語が、所有格(この場合はthe historic building’s)で表現されることもある。
・Some mothers worry too much about their children’s education.
(子どもの教育に気をつかいすぎる母親もいる。)
their children’s educationは「子どもを教育すること」という意味。A’s educationには「Aが教育する」、「Aを教育する」の両方の意味があるので、実際には前後関係から判断しなければならない。
3) I understood her anxiety about her grandmother’s heart operation.
私は、彼女がおばあさんの心臓手術のことを心配しているのがわかっていた。
※ her anxiety about her grandmother’s heart operationは「彼女がおばあさんの心臓手術のことを心配していたこと」という意味である。Anxietyは形容詞anxiousの名詞形である。したがって、これは、She was anxious about her grandmother’s heart operation.(彼女はおばあさんの心臓手術のことを心配していた。)を名詞化した表現であり、herは〈be動詞+形容詞〉で表した文の主語を表していることがわかる。
〈名詞+to不定詞〉の名詞構文
A) We didn’t expect his refusal to sign the contract.
(私たちは彼がその契約書にサインするのを拒むとは思っていなかった。)
B) She showed a willingness to work overtime.
(彼女は残業を快くする気を示した。)
A)のhis refusal to sign the contractは、He refused to sign the contract.(彼は契約書にサインすることを拒んだ。)という他動詞を中心にした表現がもとになった名詞化表現で、B)のa willingness to work overtimeは、She was willing to work overtime.(彼女は残業することをいとわなかった。)という形容詞を中心にした表現がもとになった名詞化表現である。このように、〈名詞+to不定詞〉形の名詞化表現には、他動詞から派生したものと形容詞から派生したものがある。
4) Let’s have a walk in the park.
公園を散歩しましょう。
※ 上記文は、have a walkで「散歩する」という意味を表している。walkは「歩く」という意味の動詞として使われるが、ここでは名詞として使われている。
このように、〈have / take / make / giveなど+名詞〉の形で「動作」を表すことができる。このような名詞中心の表現を作る場合、それぞれの名詞と結びつく動詞は決まっているので、個々に覚えておくことが必要。
・Let me have a look at the photo.(その写真をちょっと見せてください。)
・I made a mistake.(間違いをしてしまった。)
・ He gave a cough.(彼はせきをした。)
このような表現では、動詞(have / take / make / giveなど)と名詞の組み合わせで動作を表している。また、名詞に形容詞をつけたり、SVOOの文型でもちいられることもある。
・You’ve made quick progress in English.(君は英語が急速に上達した。)
・I’ll give you a call tomorrow.(明日君に電話するよ。)
・We made the decision to accept his plan.
(私たちは彼の案を受け入れることに決めた。)
・He made the wrong choice.(彼は誤った選択をした。)
・Let’s give it a try.(やってみようよ。)
〈have+形容詞+名詞〉でさまざまな意味を表す
〈have / take / make / giveなど+形容詞+名詞〉という表現は、名詞の前に置く形容詞を変えることで、さまざまなニュアンスを表すことができる。
Can I have a look at it?(それを見せてもらえますか。)のhave a lookという表現は、look の前に置く形容詞によって、次のようなバラエティに富んだ言い表し方をすることができる。同じ「見る」という行為でも、その「見方」はさまざまである。
have a quick look (ざっと見る)
have a good look (じっくり見る)
have a careful look (注意深く見る)
have a closer look (もっとよく見る)
have a last look (最後に見る)
5) My father is a fast walker.
私の父は歩くのが速い。
※ 人の能力や技術を表すのに、上記文のa fast walkerのような、名詞を中心とした表現を使うことがある。上記文はwalk(歩く)の名詞形のwalker(歩く人)を使った表現。動詞walkを使うと、My father drives fast.となる。動詞を修飾するので、fastはここでは副詞を使っていることになる。同じような例をあげておこう。
・She is a good singer.(彼女は歌が上手だ。=sing well)
・He is a good cook.(彼は料理がうまい。=cook well)
・She is an early riser.(彼は早起きだ。=get up early)
・He is a good speaker of English.
(彼は英語を話すのがうまい。=speak English well)
・She is a good pianist.
(彼女はピアノを弾くのがうまい。=play the piano well)
131 無生物主語
日本語の意味に合うように、( )の語句を並べかえて英文を完成させなさい。
1) あなたは、どうして彼があのレスラーを負かすことができると思ったのですか。
(What mad you think) he could defeat that wrestler?
※ 上記文のmakeは、〈make+O+動詞の原形〉という形で「Oに~させる」という意味を表す。直訳すると「何があなたに彼があのレスラーをまかすことができると思わせたのですか。」となる。これを「あなた」を中心に解釈すると、「あなたはどうして彼があのレスラーを負かすことができると思ったのですか。」と、より自然な日本語にすることができる。
cause / force 「~させる」
「Oに~させる」という意味は、cause((何かが原因となって)~させる)、force((強制的に)~させる)を使って〈cause / force+O+to不定詞〉という形で表すこともできる。makeとは違い、動詞の原形ではなくto不定詞を使うことに注意。
・His failure in business caused him to start a new life.
(彼は事業に失敗したため、人生をやり直すことになった。)
・A bad headache forced me to stay in bed.
(ひどい頭痛のため、私は寝ていなければならなかった。)
allow「~を許す」
allowは、〈allow+O+to不定詞〉という形で「Oが~することを許す/Oに~させておく」という意味になる。「〈主語〉のおかでかOは~できる」と訳せる場合が多い。
・My part-time job allows you to save a lot of money.
(アルバイトのおかげで、私はお金をたくさんためることができる。)
enable「~できるようにする」
enableも、〈enable+O+to不定詞〉という形で、「Oが~できるようにする」という意味を表す。
・His advice enabled me to overcome the hardship.
(彼の助言のおかげで、私は困難を克服することができた。)
〈参考〉enableは、人に能力や手段などを与えて、何かをすることを可能にさせることを表す。
〈注意〉let / have / getは無生物主語では使わない。
Makeは無生物主語で使うことができるが、その他の使役動詞let / have / getを無生物主語で使うことはできない。
remindを使った表現
〈remind+O+of~〉で「Oに~を思い出させる」という意味を表す。
・This song reminds me of my holiday in Greece.
(この歌を聞くと、私はギリシャでの休日を思い出す。)
「この歌は私にギリシャでの休日を思い出させる。」という意味なので、「この歌を聞くと、私は~」という日本語にすることができる。
・That woman reminded me of your mother.
(あの女性を見て、私はあなたのお母さんのことを思い出した。)
remindは「人や物が記憶にあるものを思い出させる」という意味で使う。〈remind+O+to不定詞〉とすると「Oに~することを思い出させる」という意味になる。
・Remind me to buy some soy sauce.
(お醤油を買うのを忘れていたら言ってね。)
rememberは「何かを覚えている/思い出す」という意味。
・Remember to buy some soy sauce.(お醤油を買うのを忘れないでね。)
2) 急用のため、昨日は来れなかった。
(Urgent business kept me from) coming yesterday.
※ keepは、〈keep+O+from -ing〉の形で「〈主語〉がOに~させない」という意味で使うことができる。fromは〈分離〉を表すので、「Oをすることから離した状態にしておく」ということ。この場合、「〈主語〉のためにOは~できない[しないですむ]」のように、主語の部分を「~のために」とすると自然な日本語になる。
上記文は、直訳すると「急用は私に昨日来させなかった。」となるが、「私は」を中心に考え、「急用のため、私は昨日来ることができなかった。」とすればよい。
prevent+O+from –ing
preventやstopを使った〈prevent / stop+O+from -ing〉の形で、「〈主語〉がOに~させない」という意味を表すこともできる。
・The traffic jam prevented us from arriving on time.
(交通渋滞のせいで、私たちは時間どおりに到着できなかった。)
〈rob, depriveを使った無生物主語の表現〉
robとdepriveは〈rob[deprive]+O+of~〉で「Oから~を奪う」という意味を表す。「主語のために、Oは~を奪われる[失う]と考えればよい。
・The knee injury robbed her of her speed.
(ひざにけがをしたため、彼女はスピードを出せなくなった。)
・The knee injury deprived her of the chance to play in the final game.
(ひざにけがをしたため、彼女は決勝戦でプレーする機会を失った。)
「資質や能力を奪う」という意味ではrobを使い、「機会や権利を奪う」という意味ではdepriveを使う。
3) このグラフから、物価の急騰は明らかです。
(The graph shows a sharp rise) in prices.
※ show が無生物を主語にすると、「(事実や情報など)を明らかにする」という意味を表すことができる。
tell「~を示す」
tellが無生物を主語にすると、「(情報など)を示す」という意味になる。
・This meter tells you the temperature in Fahrenheit.
(このメーターは、温度を華氏(ファーレンハイト)で示します。)
say「~と書いてある」
sayは、次の文のように本や掲示などを主語にすると、「~と書いてある」という意味を表す。
・The sign says (that) smoking here is not permitted.
(その標示には、ここでの喫煙は禁止、と書いてある。)
4) 彼女の表情から、そのプレゼントが気に入っていないことがわかった。
(Her expression showed that she) was not pleased with the present.
※ 〈show+that節〉という形で、「~ということを証明する」という意味を表すことができる。
・His smile shows (that) he is in love with Lucy.
(彼の笑顔から、彼がルーシーに恋をしていることがわかる。)
5) 数分歩くと、私たちは湖に出た。
(A few minutes’ walk brought me to) the lake.
※ bringは、〈主語+bring+O+to~〉の形で、「主語がOを~へ連れて来る」という意味を表す。出来事・乗り物・道・もの・時間などを主語とする。
・The dunes bring lots of tourists to Tottori.
(砂丘があるので、多くの観光客が鳥取を訪れる。)
take「~を…へ連れて行く」
takeとleadは、〈道+take[lead]+O+to~〉の形で、「道がOを~へ連れていく[導く]という意味を表すことができる。
・This road takes[leads] you to the station.(この道を行けば、駅に着きます。)
takeは、主語が道だけでなく乗り物の場合にも使うことができる。
・The number 21 bus takes[leads] you to the Zoo.
(21番のバスに乗ると動物園に行けます。)
〈参考〉〈lead+O+to不定詞〉で「Oを導いて~させる/Oを~する気にさせる」
という意味になる
・What led him to leave this country?
(彼がこの国を去っていったのはなぜですか。
[←何が彼をこの国からさらせたのか])
save「~を省く」
saveは「~(する労力・時間・資源など)を省く」という意味で用いられ、主語がその原因を表す。「〈主語〉のおかげで、~が省ける」とすれば自然な日本語になる。
・The new dishwasher will save you a lot of water.
(この新しい皿洗い機を使えば、たくさんの水を節約できるでしょう。)
cost「~を払わせる」
costも主語がその原因を表す。「~を払わせる/~を犠牲にする」という意味をもち、金銭以外の事がらにも使うことができる。
・The hard work cost him his health.
(きつい仕事で、彼は健康を損なった。)
〈findを使った無生物主語の文〉
・The next morning found us on our way to Vienna.
(翌朝、私たちはウイーンへと向かっていた。)
findは「時」や「出来事」を表す名詞を主語として、〈S+find+O+~〉の形で、「Sの時、Oが~の状態である(のを見出す)」という意味を表すことがよくある。ただし、これは文章体である。
第17章 強調・到着・挿入・省略・同格(解説)
132 特定の語句をつけ加える強調 / 同じ語の繰り返しによる強調
日本語の意味に合うように、( )に適切な語句を与えられた語群から選んで入れなさい。
1) 私はたしかにメアリーにスカーフをあげました。
I (did) give a scarf to Mary.
※ do/does/didを動詞の前に置くことによって、その動詞を強調し、「本当に[確かに]~する[した]」という意味にすることができる。このdoは助動詞なので、動詞は原形となる。この場合、do/does/didは強く発音される。上記文では、動詞giveを強調している。
また、命令文の場合には「依頼・勧誘・提案」の気持ちが強く押し出される。
・Do feel free to call me any time.
(本当に遠慮なく、いつでも電話してきてくださいね。)
次のように、the/this/that/one’s veryを名詞の前に置いて名詞を強調し、「まさにその~/~そのもの/~こそ」という意味を表すことができる。このveryは形容詞である。
・This is the very book I’ve been looking for!
(これこそまさに私がずっと探していた本だ!)
次のjustのように、副詞によって語や句や節を強調することができる。
・Your dress is just wonderful!(君のドレスは本当にすてきだよ!)
・I just love your dress.(気のドレス、本当に気に入ったよ。)
simplyやreallyなども強調のために用いられる。
・It’s a really hot day, isn’t it?
(本当に暑い日ですね。)
2) いったい全体どうしてそんなことをしているんだい?
Why (on earth) are you doing such a thing?
※ 疑問詞の直後にon earth, in the worldなどを置き、疑問詞を強調して「いったい全体」という意味を表すことができる。上記文では、疑問詞Whyの後にon earthが使われている。
・What in the world did she say to Jim?
(彼女はいったい全体何てジムに言ったの?)
〈注意〉疑問詞のない疑問文の強調
疑問詞のない疑問文の意味を強調する場合は、at allを使う。
・Did you follow the doctor’s advice at all?
(そもそも君は医師のアドバイスに従ったのかね。)
3) 私たちがトーナメントで優勝する可能性は少しもないだろう。
There will be no chance (whatever) of our winning the tournament.
※ whatever(少しも)、in the least(少しも)、a bit(少しも)、at all(またく)、by any means(決して/どうしても)などの語句を否定語の後で用いて、否定の意味を強調することができる。上記では、whateverが否定の意味を強調している。
・I’m not interested in baseball in the least.
(私は野球には少しも興味がない。)
・I don’t believe his story at all.
(私は彼の話なんかまったく信じていない。)
Justを使って否定表現を強調することもできる。
・I just don’t like chicken.
(私はどうしても鶏肉が好きになれない。)
4) 彼は同じジョークを何度も何度も言う。
He tells the same jokes (again and again).
※ 同じ語を〈… and …〉とくり返すことで、その後を強調することができる。上記文は以下のように表すことも可能。
→ He tells the same jokes over and over (again).
次のように動詞をくり返すこともある。
・The child cried and cried during dinner.
(その子は食事のあいだずっと泣いていた。)
133 強調構文
次の文を強調構文を使って、( )内の語句を強調する英文に書き換えなさい。
Beth teaches music at the university.(ベスはその大学で音楽を教えています。)
※ 強調したい語句をIt is [ ] that …の[ ]の位置に入れて表すことがある。これを強調構文と呼ぶ。[ ]に入るのは、主語・目的語・補語になっている名詞や代名詞、または副詞の働きをする語句である。なお、強調構文では動詞や形容詞を強調することはできない。
1) (Beth)
It is Beth that[who] teaches music at the university.
※ (その大学で音楽を教えているのは、ベスです。)
上記文は元の文の主語であるBethが強調されている。「音楽を教えているのはベス
で、ほかの人じゃないんだよ」と言いたいのである。なお、強調する名詞が人の場
合は、thatの代わりにwhoを用いてもよい。
2) (music)
It is music that[which] Beth teaches at the university.
※ (ベスがその大学で教えているのは音楽です。)
上記文は元の文の目的語であるmusicが強調されている。強調する名詞が人以外の
場合はthatの代わりにwhichを用いてもよい。
3) (at the university)
It is at the university that [where]Beth teaches music.
※ (ベスが音楽を教えているのはその大学です。)
上記文は元の文の副詞句が強調されている。強調する副詞句が場所の場合はthat
の代わりにwhereを用いることもできる。
〈注意〉thatの省略 口語ではthatが省略されることもある。
・It was yesterday I borrowed your textbook.
(君の教科書を借りたのは、昨日だったよ。)
〈注意〉強調するものが代名詞の場合 主語であれば主格を用いる
・It is I who am responsible for safety in this theater.
(この劇場の安全管理責任者は私です。)
ただし、次のように目的格を使って表すことが多い。
→ It’s me that[who] is responsible for safety in this theater.
〈参考〉強調構文の否定文、疑問文は次のようになる。
・It wasn’t Mike that[who] caught a turtle in this pond yesterday.
(昨日この池でカメをつかまえたのは、マイクではなかった。)
・Was it yesterday that Jim caught a turtle in this pond?
(ジムがこの池でカメをつかまえたのは、昨日でしたか。)
〈強調構文で節、疑問詞を強調する〉
次のように強調構文を用いて節を強調することもできる。
・It is because pandas look cute that we like them so much.
(私たちがパンダを大好きなのは、かわいいからだ。)
また、次のように疑問詞を強調することもできる。この場合は語順に注意。
・Who was it that invented the telephone?
(電話を発明したのはいったいだれだったかな?)
疑問詞を強調する疑問文は、〈疑問詞+is[was] it that+平叙文の語順〉という形になる。It was [ ] that invented … の[ ]の部分が疑問詞になって文頭に出て、その後がwas itのように疑問文の語順になるのである。
134 関係詞などを使った強調
日本語の意味に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) 彼に欠けているのは、知識ではなく経験だ。
(What) he is lack in (is) not knowledge but experience.
※ 関係代名詞のwhatを使ったWhat … is[was]~の形を用いることで、強調したい語句を後ろに回すことができる。上記文は、What he is lack isと言った後にnot knowledge but experienceを続けることで、「かけているもの」が「知識ではなく経験」であることを強調している。
・What surprised me was her scream.
(私を驚かせたのは、彼女の悲鳴だった。)
2) このボタンを押すだけでいいのです。
(All) you have to do (is) (push) this button.
※ 上記文は、Allの後に関係代名詞thatが省略されたAll you have to doを主語、不定詞を補語として、「あなたがしなければならないすべてのことは~することだ」という意味を表している。「すべきなのは~することだけ」ということなので、「~しさえすればよい」という意味になる。上記文のようにbe動詞の前がto doの場合は、be動詞の後に動詞の原形を直接続けることができる。
→ All you have to do is (to) push this button.
また、次のような文も強調の表現である。
・The first thing to remember is not to criticize anyone.
(忘れてはいけない第一のことは、だれの悪口も言わないことだ。)
135 倒置
( )の語句をならべかえて英文を完成させなさい。
1) Never (have I failed to watch the TV program).
※ (私はそのテレビ番組を一度も見逃したことがない。)
上記文のnever(一度も[決して]~ない)のような否定の意味をもつ副詞(句)が強調のために文頭に置かれると、その後はYes/No疑問文と同じ語順になる。ふつうの語順だと次のようになる。
→ I have never failed to watch the TV program
文頭に置かれて倒置が起こるおもな副詞(句)には、ほかに次のようなものがある。
at no time(一度も~ない)
seldom(めったに~ない)
rarely(めったに~ない)
hardly(ほとんど~ない)
scarcely(ほとんど~ない)
little(ほとんど~ない)
on no account(決して~ない)
under no circumstances(どんな状況でも~ない)
・Rarely does he tell a joke.(彼はめったに冗談を言わない。)
・At no time did the actor mention his private life.
(その俳優は一度も私生活のことに触れたことはなかった。)
〈注意〉onlyも否定的な意味をもつ
onlyを含む副詞句が文頭に置かれる場合も、疑問文と同じ語順の倒置が起こる。
・Only in case of emergency can you use this exit.
(緊急の場合にだけ、この出口を使うことができる。)
〈否定語と副詞が文頭に出るNot until … 〉
・Not until I talked to him did I know he was homesick.
(彼と話して初めて、彼がホームシックになっていることがわかった。)
notの後に副詞句を続けたnot until I talked to himのようなまとまりが文頭に出ると、その後ろでは疑問文と同じ語順の倒置が起こる。もとの文は、次のとおり。
→ I did not know (that) he was homesick until I talked to him.
・Not until yesterday did he tell the truth.
(昨日になって初めて、彼は本当のことを話した。)
〈not only A but (also) B「AだけでなくBも」〉
・Not only does he draw illustrations but he (also) writes novels.
(彼はイラストを描くだけでなく小説も書く。)
not only A but (also) Bを使った文では、文頭にNot onlyを置くことがある。その場合は、疑問文と同じ語順の倒置が起こる。もとの文は次のとおり。
→ He not only draws illustrations but he (also) writes novels.
〈程度を表す副詞(句)が文頭に出る倒置〉
否定語以外でもwellのような程度を表す副詞が文頭に出た場合には、倒置が起こる。
・Well do I remember that day.(あの日のことはよく覚えています。)
この場合も、その程度がどうなのかを文頭の副詞で強調している。
また、so … that~, such … that~の場合も倒置が起こる。
・So terrible was the concert that I left the hall.
(そのコンサートはあまりにひどかったので、私はホールを後にした。)
2) No (other mistake did he make).
※ (彼は他のどんな間違いもしなかった。)
強調のために文頭に出た目的語にno, not, littleなどの否定語が含まれていると、倒置が起こり、疑問文と同じ語順になる。考え方は、否定の副詞(句)が文頭に出た場合と同じ。
・Not a word did she say.
(一言も彼女は口に出さなかった。)
・No hope did I have at that time.
(当時、私にはまったく希望がなかった。)
否定後を含まない目的語が文頭に出た場合には、次のように〈OSV〉の語順になり、倒置は起こらない。
・Spaghetti I like, but macaroni I dislike.
(スパゲッティは好きだが、マカロニは嫌いだ。)
3) Away (ran the bank robber ).
※ (逃げたのは銀行強盗だった。)
上記文のawayような方向や場所を表す副詞(句)が文頭に出ると、主語と動詞の位置が入れかわる。疑問文の語順になる倒置ではないことに注意。このような語順になるのは文脈による場合が多く、伝えたい情報である名詞が文の最後にまわされたと考えられる。
・Down fell an apple. (下に落ちたのはリンゴだった。)
・In my pocket was his business card.
(私のポケットの中にあったのは彼の名刺だった。)
〈注意〉代名詞の場合は倒置は起こらない
主語がitやheのような代名詞であれば、倒置は起こらない。代名詞は何を指すかわかっているものなので、わざわざ文末にまわす情報ではないからである。
・Into the room he walked. (部屋の中に彼は歩いて入った。)
There[Here]+VS
Thereやhereが文頭に出て〈There[Here]+VS〉という形になることがある。この場合のthereやhereは、相手の注意を引くために用いられている。(ただし、代名詞のときには〈There[Here]+SV〉の形。)
・Here comes the train. (ほら、電車が来るよ。)
・Here he comes. (ほら、彼が来るよ。)
4) Amazing (was the show at the Mirage Hotel in Las Vegas ).
※ (すごかったのはラスベガスのミラージュホテルでのショーだった。)
上記文では補語になっている形容詞amazingが文頭に置かれ、主語the show at the Mirage Hotel in Las Vegasと動詞wasの位置が入れかわっている。ふつうの語順ではThe show at the Mirage Hotel in Las Vegas was amazing..となる。このように、補語になっている形容詞が文頭に出ると、主語と動詞がいれかわる倒置が起こることがある。このような倒置が起こるのは、主語である名詞に前置詞句や関係詞節などの長い修飾語句がついている場合が多く、文のリズムを整えるためと考えられる。
・Wonderful was the view from the balcony.
(すばらしかったのは、そのバルコニーからの眺めだった。)
・Happy is the man who knows his business.
(幸せなのは、自分が何をすべきか知っている人だ。)
〈参考〉補語の形容詞が文頭に出ても主語が代名詞であれば倒置は起こらない。
◯ Happy he is.
× Happy is he.
慣用的な倒置
先に述べられた肯定文に同意を示す場合は、〈so+(助)動詞+主語〉の語順で、「〈主語〉も(また)そうだ」という意味を表す。
・“I was poor at math in school.” “So was I.”
(「学校じゃ、数学が苦手だったんですよ。」「私もそうでした。」)
先に述べられた否定文に同意を示し、「〈主語〉も(また)そうでない」と言うときは、〈neither[nor]+(助)動詞+主語〉となる。
・“I don’t like watching movies alone.” “Neither[Nor] do I.”
(「映画をひとりで 見るのは好きじゃないです。」「ぼくもです。」)
136 挿入
次の文を日本語に直しなさい。
1) The concert was, in the end, called off.
そのコンサートは結局中止になった。
※ 上記文は、in the endという句(副詞句)が挿入されている。このように挿入される語や句は副詞(句)が多い。挿入される部分はコンマ(,)、ダッシュ(-)、やカッコのあいだにはさみ込まれることが多い。
after all (結局)
as a matter of fact (実のところ)
as a rule (一般に)
for example (たとえば)
for sure (確かに)
however (しかしながら)
in a sense (ある意味で)
in fact (実際は)
indeed (実に)
moreover (さらに)
to be sure (確かに)
therefore (したがって)
nevertheless (それにもかかわらず)
on the other hand (他方では)
in the end (最後に/結局)
to make matters worse (さらに悪いことには)
to one’s surprise (〜が驚いたことに)
2) The book, to my surprise, sold well also in Japan.
その本は、私が驚いたことに、日本でもよく売れた。
3) This experiment, I’m afraid, is a failure.
この実験は、残念ながら失敗です。
※ 上記文は、I’m afraid that this experiment is a failure.と考えればよい。文中に〈主語+動詞〉で挿入されるものには、話者の判断を表す次のような表現がある。
I believe / suppose / think (私は思う)
I’m afraid (残念ながら)
I hope (願わくば)
it seems (どうやら)
また、he said (彼は言った)やyou know(わかるでしょ)のような表現もよく挿入される。
〈参考〉seldom, if ever, … という形で「(たとえあるにしても)きわめてまれに」という意味を表す。
・Bill seldom, if ever, watches TV. (ビルはまずめったにテレビを見ない。)
137 省略
次の文で省略できる部分を指摘しなさい。
1) Mr. Jones wasn’t angry, but Ms. Smith was angry.
→ Mr. Jones wasn’t angry, but Ms. Smith was.
※ (ジョーンズさんは怒っていなかったが、スミスさんは怒っていた。
上記文ではMs. Smith wasの後のangryはなくても何を言っているのかはっきりわかるので省略される。このように、補語になる語句がすでに出ていて、言わなくてもわかる場合は省略される。
次の文のように、動詞が省略されることもある。
・John ate a hamburger, and Mary French fries.
(ジョンはハンバーガーを食べ、メアリーはフライドポテトを食べた。)
上の文のように、andの前後で同じ構造の文が続く場合、後の文では、最初の文と同一の要素を省略することがよくある。すぐ前に出ているので、省略しても問題ないのである。
次のように、主語になる名詞が省略されることもある。
・John went upstairs and knocked at the door.
(ジョンは2階へ上がって行って、ドアをノックした。)
2) You can eat this pudding if you want to eat it.
→ You can eat this pudding if you want to.
※ (もし食べたければ、このプリンを食べてもいいよ。)
上記文では、toの後に動詞eatが省略されている。Toの後に続く動詞の原形が文脈上明らかな場合は、toだけを残して動詞の原形は省略する(この場合のtoを代不定詞と呼ぶ)。
・You may site wherever you want to.
(どこでも好きなところに座ってもいいよ。)
3) Did you visit Hollywood while you were traveling in the United States?
→ Did you visit Hollywood while traveling in the United States?
※ (合衆国で旅行中、ハリウッドを訪れましたか。)
when, while, if, unless, thoughなどの接続詞に導かれる副詞節の中では、〈主語+be動詞〉が省略されることがある。ただしその場合、副詞節中の主語は主節の主語と同一であることが多い。
・Though tired, she studied till late.
= Though she was tired, she studied till late.
(疲れていたが、彼女は遅くまで勉強した。)
ifの後の省略
if節中では、〈主語+動詞〉が頻繁に省略される。定型表現として使われるので、節中の主語が主節の主語と違っていることも多い。
・I’ll help you if necessary. [= if it is necessary]
(必要なら、あなたに手を貸しますよ。)
・I’d like to see you off if possible. [= if it is possible]
(できればあなたを見送りたい。)
・Please point out the mistake if any. [if there are any (mistakes)]
(もしあれば、間違いを指摘してください。)
ほかにもif so(もしそうであれば)、if not(もしそうでなければ)などがある。
見出しや広告での省略
新聞などの見出し、広告、掲示などでは冠詞やbe動詞が省略される。
・Kidnapper Arrested in Chicago (= The kidnapper was arrested in Chicago.)
(誘拐犯シカゴで逮捕)
・Road Closed (= The road is closed.) (道路閉鎖中)
共通語句
I tried but failed to stop her from going away.
(= I tried to stop her from going away but I failed to stop her from going away.)
(私は彼女が立ち去るのを止めようとしたが、できなかった。)
tried⇘
I <but> to stop her from going away.
failed⇗
このように、文を簡潔にするために1つの語句が共通語句として使われる場合がある。andやbut, orなどに注意して、それぞれの語句がどのような関係にあるかを把握することが大切である。
138 同格
次の文を日本語に直しなさい。
1) Carter, a friend of mine, graduated from Oxford University.
※ (私の友人のカーターはオクスフォード大学を卒業した。)
上記文では、Carterとa friend of mineが同格の関係にある。名詞を同格で並べるときには、上記のようにコンマを使う場合と、次のようにコンマを使わない場合がある。
・Her best friend Lisa is a nurse. (彼女の親友のリサは看護師だ。)
コンマを使うのは、最初の上記文のa friend of mineのように、補足説明をする場合であり、コンマをつかわないのは、her friend Lisaのように両者が1対1で結びつくような場合である。
2) My son is pleased with his name of Daisuke.
※ (私の息子は大輔という名前を気に入っている。)
his name of Daisukeは、「大輔という名前」となる。このように、同格のofを使って〈the[one’s]A of B〉という形で名詞同士を同格の関係で結ぶことができる。the name of Kate(ケイトという名)やthe city of Seattle(シアトルという都市→シアトル市)のように、人や都市の名前を表すときに使われることが多い。
名詞や代名詞を言い換えるときの表現
① コロン(:)やダッシュ(-)を用いる
・They need two kinds of support; economic and technical.
(彼らには2種類の援助が必要だ。つまり、経済的、技術的援助である。)
・There are two things I have trouble remembering – people’s names and phone numbers.
(私には覚えるのに苦労するものが2つある。人の名前と電話番号だ。)
② 「つまり/すなわち」という意味のthat is (to say)やnamelyを用いる。
・I read War and Peace, that is , one of the masterpieces by Tolstoy.
(私は『戦争と平和』、つまり、トルストイの傑作の1つを読んだ。)
③ 「言い換えれば」という意味のorを用いる
He studies astronomy, or the study of stars, at collage.
(彼は天文学、つまり星の研究を大学でしている。)
3) We heard the news that a thief had broken into Bill’s house.
※ (私たちはどろぼうがビルの家に侵入したという知らせを聞いた。)
名詞の内容を、それに続くthatから始まる名詞節が説明して、同格の関係となる場合がよくある。ただし、どんな名詞に対してもthatが使えるわけではないので注意が必要。
同格のthat節と結びつくおもな名詞
① 思考や認識を表す名詞
belief(信念)
concept(概念)
feeling(感情)
idea(考え)
knowledge(知識)
opinion(意見)
thought(考え)
② 要求・欲求・伝達を表す名詞
decision(決心)
demand(要求)
desire(願望)
expectation(期待)
hope(希望)
information(情報)
news(知らせ)
proposal(提案)
report(報告)
rumor(うわさ)
suggestion(提案)
③ その他の名詞
chance(見込み)
fact(事実)
possibility(可能性)
evidence(証拠)
plan(計画)
proof(証拠)
〈注意〉関係詞節と同格のthat節の区別
・I know the fact that she is trying to conceal.[関係詞節]
(彼女が隠そうとしている事実を私は知っている。)
concealの後に目的語がないので、thatは目的格の関係代名詞であることがわかる。
・I know the fact that she is trying to conceal the scandal.[同格のthat節]
(彼女がそのスキャンダルを隠そうとしているという事実を私は知っている。)
thatはthe factと同格の名詞節を導く接続詞。
〈参考〉whetherや疑問詞が導く節が同格節となることがある。
・We discussed the question whether a new baseball stadium should be built in the city.
(私たちは、新しい野球場がその都市に建設すべきかどうかという問題について議論した。)
準動詞を使った同格の表現
① 〈名詞+of+動名詞〉で同格を表現することもある。
His idea of making a fortune overnight is unrealistic.
(一晩で大もうけをするという彼の考えは非現実的だ。)
動名詞は、「実際に起きていること/習慣的なこと/客観的可能性」などを表す。ofは「~に関する」という意味合いをもち、idea, difficulty, dream, habit(習慣)などの名詞と結びつく。
② 〈名詞+to不定詞〉で同格を表現することもある。
She has a desire to succeed as an opera singer.
(彼女にはオペラ歌手として成功したいという願望がある。)
desire, planのように、「これからやりたい/やるべき/やろうとすること」にかかわる名詞は、to不定詞でその内容を説明することができる。
なお、同格のthat節と結びつくことができる名詞が限られているのと同様、〈of+動名詞〉と結びついて同格を作る名詞や、to不定詞と結びついて同格を作る名詞も、動名詞とto不定詞のニュアンスの違いにもとづいて決まっている。
×the habit to read → ○the habit of reading(読書の習慣)
×the mood of going out → ○the mood to go out(出かけたい気分)
第18章 名詞(解説)
139 普通名詞・集合名詞・物質名詞・抽象名詞・固有名詞の用法
( )内の語句のうち、正しいほうを選びなさい。
1) (Freedom) is as important as equality.
※ 自由は平等と同じくらい重要です。
freedomは抽象名詞(具体的な形のない抽象的なことを表す名詞)で数えられない名詞。
・数えられない名詞(U)
① 物質名詞:一定の形のない物質を表す名詞 (「金属」「液体・気体」「材料」など)
gold, iron, water, coffee, tea, milk, wine, rain, ink, air, smoke, wood,
meat, money, chalk, bread, cheese, sugar, stone, paper, clothなど
② 抽象名詞:具体的な形のない抽象的なことを表す名詞
beauty, kindness, honesty, happiness, love, peace, joy, work,
homework,, news, information, advice, silence, speech, freedom,
invention, weather, importanceなど
〈前置詞+抽象名詞〉で形容詞や副詞のように用いられることがある。
・He is a man of ability.(彼は有能な人物だ。)
・He struck the desk in anger.(彼は怒って机をたたいた。)
・This information is of no value to me.
(この情報は私には全く価値がない。)
of value (= valuable)
of importance (= important)
with care (= carefully)
with ease (= easily)
on purpose (= purposely)
by accident (= accidentally)
with more care (= more carefully)
of no importance (= unimportantly)
of no value (= valueless)
③ 固有名詞:人名や地名など、特定のものを表す名詞
London, Tokyo Dome, John, Januaryなど。また、the British Museaumのような公共施設などは、theと一緒に使う場合もある。
A) of…のついた地名など
the Cape of Good Hope(喜望峰), the University of Chicago
B) 複数形の固有名詞
The United States of America, the Alps(アルプス山脈)
C) 川、海、海峡など
the Hudson (River), the Pacific (Ocean)(太平洋)
D) 公共の建物・劇場、乗り物の名前など
the White House, the Nozomi(のぞみ号)
E) 新聞・雑誌[イタリック体(斜字)で表記される。]
the New York Times(ニューヨーク・タイムズ紙), the Economist
(エコノミスト誌)
2) (Wine is) made from grapes.
3) The Japanese are (a hardworking people).
※ (日本人は勤労な国民(民族)です。)
peopleは集合名詞(人や物の集合体を表す名詞)で数えらる名詞。ここでは、「国民・民族」という意味で、普通名詞と同じように扱われる。また、「人々」という意味のpeopleは単数で複数扱いとなる。People tend to keep quiet in elevators.(エレベーターの中では人は無口になりがちだ。)
・数えられる名詞(C)
① 普通名詞:同じ種類のものに共通して用いることができる名詞
table, chair, house, book, pencilなど
② 集合名詞:人や物の集合体を表す名詞
family, class, team, club, committee, group, crew, audience, people,
police, cattle(畜牛:牛の総称), staffなど
A) 1つのまとまった,ものとして考える場合:〈a/an+単数形〉となったり、複数形になる。
・We are a family of four.(うちは4人家族です。)
・A crowd gathered outside the hotel.
(多くの人がホテルの外に集まった。)
B) 1人1人に重点を置いて考える場合:形は単数でも複数扱いとなる。
・The class are preparing for the school festival.
(そのクラスの生徒は、学園際の準備をしているところだ。)
ただし、アメリカ英語では集団の構成員を意識するときでも単数扱いすることが多い。
(= The class is preparing for the school festival.)
C) 複数形がない集合名詞 (police, cattle, staff)
policeは「警察」という1つのまとまりではなく、「警察」を構成す
る「警察官たち」に重点が置かれるため、複数扱いとなる。police
は単数扱いすることはできないし、複数形もない。cattleも同じ用法。
また、staffも集合名詞なので、「私はスタッフです。」と言うときに、
×I’m a staff.とは言えない。
・The police are looking for the robber.
(警察はその強盗犯を探している。)
・I’m a member of the staff. (= I’m a staff member.)
(私はスタッフです。)
D) 注意すべき集合名詞
・furnitureの用法
furnitureは「机」や「タンス」などの家具の総称で、数えられ
ない名詞として扱われる。(baggage, luggage, clothing, jewelry,
music, poetry, foodも同様に用いる。)また、1つ、2つと数を
表す必要があるときは、a piece of furnitureやtwo pieces of
furnitureなどとする。
・fruitとfishの用法
fruitとfishは、furnitureと同様に、そのままの形で「くだもの全般」「魚全般」を表す。その種類に重点を置く場合や異なった種類を強調する場合にのみに複数形を使用するだけで、単数形を使用する場合がほとんどである。
・This lake is full of fish.(この湖は魚が多い。)
・There are various fishes in this lake.
(この湖にはいろいろな種類の魚がいる。)
4) He drank (three cups of coffee).
※ 彼はコーヒーを3杯飲みました。
形・容器・単位などを使った物質名詞の数え方
・形
a piece of paper [chalk] (紙1枚[チョーク1本])
a sheet of paper (紙1枚)
a slice [loaf] of bread(パン1枚[1つ])
・容器
a bottle of milk(牛乳1本)
three glasses of water(水コップ3杯)
a cup of tea(紅茶1杯)
・単位
a pound of butter(バター1ポンド)
two spoonfuls of sugar(砂糖スプーン2杯)
three liters of beer(ビール3リットル)
物質名詞の量や程度を表す表現
much, (a) little, a lot of, some, any, noを用いる。〈数〉が多いことや少ないことを表すmanyや(a) fewなどは使えない。
5) You must write in (ink), not with (a pencil).
140 数えられない名詞を普通名詞として使う
( )内の語句のうち、正しいほうを選びなさい。
1) I will never forget your many (kindnesses).
※ kindnessは抽象名詞としては「親切」という意味だが、普通名詞としては「親切な行為」という意味を表す。個々の行為を表す場合、数えらる名詞として使う。
・He will be an important addition to the team.
(彼はチームにとって重要な補強になるだろう。)
2) You must not throw (stones) in the park.
※ ここでは、stoneは「小石」という意味の普通名詞として使われているので、複数形になる。This bridge is made of stone.(この橋は石でできている。)のような場合、「石」は物質名詞で数えることはできない。
3) I want to be (an Edison).
※ 〈a/an+固有名詞〉で「~という人物」や「~の作品」という意味になる。
・He bought a Picasso in Paris.(彼はパリでピカソの作品を買った。)
・A Mr. Brooks is at the reception desk.
(ブルックスさんとおっしゃるかたが受付にいらしてます。
4) The bus (fare) is 210 yen.
※fareは交通機関の料金であり、feeは報酬、授業料、入場料などの料金になる。
使い分けに注意すべき名詞の例
(a) 「料金」を表す名詞
fare(交通機関の料金), fee(報酬、授業料、入場料), charge(手数料), price
(品物の値段), cost(費用)
(b) 「予約」を表す名詞
appointment(面会などの約束), reservation(席などの予約)
(c) 「天候」を表す名詞
weather(ある時点・場所での天気), climate(年間を通じての気候)
(d) 「習慣」を表す名詞
habit(個人の習慣/習癖), custom(社会的な習慣)
(e) 「客」を表す名詞
passenger (乗客), customer(顧客), audience(聴衆), spectator(観客), client
(依頼人), guest(招待客), visitor(訪問客)
141 規則変化・不規則変化
次の名詞の複数形を書きなさい。
1) pencils 2) cities 3) feet 4) women
5) Japanese 6) passers-by 7) boxes 8) children
※ 規則変化の例外
stomachs, pianos, roofs, safes(金庫), beliefs, the Coxs(コックス一家),
three Marys(3人のメアリー)
不規則変化
・単数形と複数形が同じ
means(手段), carp(コイ), sheep, deer, yen, species(種)
・外来語の複数形
datum→data,
medium→media
crisis→crises
analysis→analyses
phenomenon→phenomena
・文字、数字、略語の複数形
CD→CDs[CD’s]
UFO→UFOs[UFO’s]
the 90s[90’s]
・複合名詞の複数形
passer-by→passers-by
woman astronaut→women astronauts
142 複数形の意味と用法
下線の語句の意味に注意して、次の文を日本語に直しなさい。
1) It is bad manners to make a noise when you eat soup.
(スープを飲む時に音をたてるのは作法にかなっていません。)
※ ● 複数形になると別の意味になる名詞
glass(ガラス/コップ) → glasses(メガネ)
force(力) → forces(軍隊)
good(善/利益) → goods(商品)
arm(腕) → arms(武器)
custom(習慣) → customs(税関/関税)
manner(方法) → manners(作法)
letter(文字) → letters(文学)
day(日) → days(時代)
● 必ず複数形で用いられる名詞 (数える場合には、a pair of …のような形)
contact lenses, trousers, pants, scissors, shoes, socks, gloves
一対になったものの片方を指す場合はgloveやshoeのように単数形で用いる
I have lost my left shoe.(左足の靴下をなくしてしまった。)
● 学問を表す名詞は複数形で単数扱い
economics, physics, mathematics, politics, linguistics, statistics
● 金額・距離・時間のまとまりは単数扱い
One hundred dollars is enough to buy that sweater.
(100ドルあればそのセーターを買うのに十分です。)
Twenty miles is a long distance to run.
(20マイルは走るには長い距離です。)
Ten years is called a “decade.”(10年は”decade”と呼ばれる。)
2) We got to know each other during our college days.
(私たちは大学生時代に知り合いました。)
3) I changed trains for Nara at Kyoto.
(私は京都で奈良行きの電車に乗り換えました。)
※複数形の名詞を含む慣用表現
change trains(電車を乗り換える)
make friends with…(…と友達になる)
143 所有格・B of Aの形を用いて所有を表す
次の文の必要な語を所有格に直して、正しい英文にしなさい。
1) I borrowed Henry’s motorcycle yesterday.
2) It is ten minutes’ walk to the museum.
※ 人間と生物以外で所有格を用いる場合
① 時の表現(時間・日・週・月など)
ten minutes’ break(10分の休息)
tomorrow’s weather(明日の天気)
② 金額・距離・重さの表現
three dollars’ worth of candy(3ドル分のキャンディー)
a yard’s distance(1ヤードの距離)
ten kilograms’ weight(10キロの重さ)
③ 国名など
Japan’s climate(日本の気候)
the world’s population(世界の人口)
3) My sister sometimes stays at our grandmother’s.
※ 所有格の後の名詞は省略されることがある。
① 反復を避ける場合
This bicycle is my brother’s (bicycle).
(この自転車は私の兄のものです。)
② 家・商店などを表す場合
I’m going to stay at my uncle’s (house)
(おじさんの家に泊まるつもりです。)
Kate went to the baker’s (shop)
(ケイトはパン屋さんに行きました。)
第19章 冠詞(解説)
144 冠詞の働き(不定冠詞・定冠詞・無冠詞)
次の文の( )に適切な冠詞を入れなさい。無冠詞にするのが正しいときには×を入れなさい。
1) There is (an) apple on the table.
※ (テーブルの上にリンゴが1つある。)
「数えられる名詞」が単数形の場合、上記のan appleのように不定冠詞を使うと、具体的な1つのものを表す。複数形のときには不定冠詞は使えないので、次のように無冠詞になり、複数のものを表す。
There are apples on the table.(テーブルの上にリンゴがいくつかある。)
2) I ate a slice of cake. (The) cake was delicious.
※ (私はケーキを一切れ食べた。そのケーキはおいしかった。)
上記のa slice of cakeのaのように不定冠詞を使う場合は、「相手がそれまで意識していなかった・それまで食べたことのないケーキの話をする」ことになる。上記のThe cakeのtheのように定冠詞を使う場合は、「どのケーキのことを指しているのか、I ate a slice of cakeという直前の説明のおかけで聞き手にはわかっている(他のケーキとはっきり区別をつけることができる)」ことになる。
3) All living things live in (×) nature.
※ (全ての生き物は自然の中で生きている。)
同じnatureという単語を使っていても、冠詞の有無により意味が異なる。上記の
natureは「自然」という意味である。「自然」というものは、「どこからどこまで
が自然か」をはっきり示すことができない。このように、ほかのものとの区切りを
はっきりつけることのできない場合は定冠詞は使えない。定冠詞は、次のようにほ
かのものとの違いを示す境界線があるときに使うものである。
・What is the nature of your research?(あなたの研究の本質は何なのですか。)
この文のthe nature of your researchは「あなたの研究の本質」という意味である。
「あなたの研究の」という限定があれば、「本質」は1つに決まってくる。言い換
えれば、はっきりとほかのものと区別できるわけだ。こうした場合は定冠詞を使っ
て、the natureとする。
4) My daughter went to (×) bed at ten last night.
※ (私の娘は昨夜10時に寝ました。)
上記文のように無冠詞の場合は、具体的なものそのものよりも、そのもののもつ「働き」に焦点が当たることになる。つまり、ベッドというもの自体にではなく、ベッドが睡眠をとるための働きをするという事実に目を向けている。要は、「1台のベッド」という具体的なものを意識しているのではなく、「その場所では何をするのか」のほうに意識が向いているので、「もの」として数を教える必要性を感じないから無冠詞になるのだ。
次のように不定冠詞を使う場合は、「具体的な1つのもの」という意味になる。
・I want to buy a bed for my room.(私の部屋に置くベッドを買いたい。)
145 不定冠詞の用法
必要なところにaまたはanを入れて、正しい英文にしなさい。
1) I bought a mountain bike yesterday.
※ (私は昨日、マウンテンバイクを買った。)
それまで話に出てこなかったもの、つまり聞き手や読者が知らない事柄を示すときには、上記文のように不定冠詞が使われる(もちろん「数えられる名詞」の単数形のときだけである)。また、「数えられる名詞」の単数形が特定のものでないときにも、上記文のように不定冠詞を使う。この場合、具体的な「1台のマウンテンバイク」を意味することになる。
2) There are 60 minutes in an hour.
※ (1時間は60分ある。)
不定冠詞を使用して上記文や次のように数を強調したりする。
・Rome was not built in a day.(ローマは1日にして成らず。)
また、次のように「任意の/どれでもよいから1つ」を表したりする。
・Can you give me a hint?(ヒントをください。)
このように、話に初めて出てきた「1つの具体的なもの・こと・人」にはa / anを使う。
また、「1回の」という意味を表す場合もある。
・I had an accident on my way home yesterday.
(昨日帰り道に事故にあった。)
また、「ある/いくらかの」という意味を表す場合もある。
・That painting looks more beautiful from a distance.
(あの絵は少し離れて見ると、もっとすばらしく見える。)
3) My father works five days a week.
※ (私の父は1週間に5日働く。)
単位を表す語の前で、「~につき」という意味を表すことができる。
〈不定冠詞的な働きをするsome〉
複数形や数えられない名詞の前に置かれたsomeが、不定冠詞のような働きをすることがある。
・Open the window and let in some fresh air.
(窓を開けて、新鮮な空気を入れてください。)
この場合、「窓を開けたら入ってくる空気」は「ある一定量の空気」なので、someを使ってばくぜんと限定する。
・Some people dislike baseball.(野球が嫌いな人もいる。)
この場合、世の中の人全般が野球を嫌いなのではなく、「一部の人」が嫌っているということを表すためにsomeが使われている。
〈形容詞をともなうことによって不定冠詞が必要になる場合〉
ふつうは無冠詞か定冠詞とともに使う名詞でも、形容詞をともなうと不定冠詞が必要になる場合がある。
a good dinner (←dinner)
a half moon (← the moon)
形容詞をともなうと、「いくつもある種類のうちの~な1つ」「いくつもある側面のうちの~な1つ」という意味合いが生まれるからだ。a half moonは「満月」「半月」「三日月」「新月」という月が見せるいろいろな側面の「1つ」にすぎないので、不定冠詞を使うことになる。
146 定冠詞の用法
必要なところにtheを入れて、正しい英文にしなさい。
1) Do you mind if I open the window?
※ (窓を開けてもよろしいですか?)
上記文のように、話し手と聞き手のあいだでどれのことを言っているのかわかるものを指し示すときには、theが使われる。周囲の状況から特定することが可能な名詞であればtheが使われる。
・Did you remember to lock the door?(忘れずにドアに鍵をかけてきた?)
また、話の中にすでに出てきていて、指しているものが決まっているときに、次のようにtheを使う。
・You took a photo of me. Show the photo to me.
(あなた、私の写真を撮ったでしょ。あの写真を見せてよ。)
また、形容詞の最上級やonly, first, last, sameなどで限定されている名詞や、句や節によって特定されている名詞とともに、theは使われる。
・He is the only person I can trust.(彼は私が信用できる唯一の人だ。)
〈注意〉関係代名詞や同格が後続すれば何でも定冠詞になるわけではない
・I met an old man who was walking in the park.
(公園を散歩している老人に会った。)
このように不定冠詞を用いる場合は、「公園を散歩中の老人」というだけでは「1人」とは限らないことを表したり、「老人」の存在自体を聞き手がまったく意識していないだろうと話し手が判断していることを示す。the old manとすると「その時公園を散歩中の老人は1人しかいなかった」ことを聞き手がすぐに了解してくれることになる。そういう了解が成り立たないときには、theではなくaを用いる。
2) We are paid by the week.
※ (私たちは週単位で賃金をもらっている。)
上記文のように、単位を表す名詞の前で、「~単位で」という意味を表すことができる。by the meterなら「メートル単位で」という意味になる。単位の場合は、ほかの単位とはっきり区別するために、theを用いて、ほかとの境界線をはっきりさせるわけだ。the meterとすることで、センチメートルでもキロメートルでもなくただのメートルということを示しているのである。
・In England, we buy butter by the pound.
(イングランドでは、バターはポンド単位で買います。)
また、次のように、身体の一部を表す名詞とともに使われることもある。
・Jim took his daughter by the hand and left the room.
(ジムは娘の手を引いて、部屋から出ていった。)
hit me on the headなら「私の頭をなぐる」となる。
〈所有格とthe〉
所有格は、theに意味が1つ加わったものと考えればよい。〈the+私の〉でmyになる。だれのものかが明白な状況では、原則として所有格は使わない。
・Her boyfriend punched me in the face.
(彼女のボーイフレンドがぼくの顔をなぐったんだ。)
この例文の場合、「だれの顔なのか」はすでにmeで示されているので、「顔」はthe faceで表す。×Her boyfriend punched me in my face.
3) Can you play the guitar?
※ (あなたはギターを弾くことができますか?)
定冠詞は上記文のように、楽器とともに使われたり、〈the+形容詞[分詞]〉で、the old[elderly](老人)/ the young(若者)/ the unemployed(失業者)のように使われたりする。
〈参考〉楽器のほかにも、電話のような発明品を表す場合は普通名詞にtheをつける。
・The telephone was invented by A.G. Bell.
(電話はA.G.ベルによって発明されました。)
また、その普通名詞のもつ一般的な側面に焦点を当てる場合にも、theをつけることがある。
・The pen is mightier than the sword.(ペンは剣より強し。)
〈theとthat / this〉
thatやthisは、theに意味が1つ加わったものと考えればわかりやすい。thatは〈the+比較的遠くにあるもの〉、thisは〈the+比較的近くにあるもの〉を表す。ただし、日本語の「あの」や「この」に機械的にthatやthisを当てはめないように注意したい。that / thisは、ほかとの対比が意識されるときに使う。
・May I close the window?(窓を(全部)閉めてもいいですか。)
・You can close that window, but leave this one open.
(あの窓は閉めてもいいが、こっちの窓は開けておいてくれ。)
4) I want to travel around the world some day.
※ (私はいつか世界中を旅行したい。)
上記文のように、もともと1つしかないので誤解の余地がないものを指す場合にもtheを使う。このように、話し手にも聞き手にもわかる「特定のもの・こと・人」にはtheを使う。
147 無冠詞になる場合
文中の不要な冠詞に×をつけなさい。
1) He filled the glass with (×the) milk.
※ (彼は牛乳でコップをいっぱいにした。)
上記文では、牛乳はどこからどこまで区切ったらいいのかはっきりしないので無冠詞となる。
・It’s difficult to find water in the desert.(砂漠で水を見つけるのは難しい。)
〈注意〉the water
海や湖など、水がたまっている具体的な場所を指すときは、the waterという。
・She dived into the water.(彼女は水の中に飛び込んだ。)
また、「いろいろなブランドのミネラルウォーター」の場合は、mineral watersも可能。
「情報」もどこで区切って1つとするのかはっきしりない。
・I need information about flights to Hawaii.
(ハワイへの飛行機の情報が必要です。)
2) She went to the post office by (×a ) bicycle.
※ (彼女は自転車で郵便局へ行った。)
上記文のように手段を表すbyを使った場合は、具体的な1台の自転車をイメージすることはない。交通手段としての自転車についてばくぜんとイメージするだけなので、無冠詞になる。on my bicycleとした場合は、onが具体的に「(自転車)の上で」という意味合いをもつので、a / the / myなどが必要になる(どれを使うかは状況による)。
・They came to the wedding by car.(彼らは結婚式に車でやって来た。)
・I reserved the ticket by phone.
(私は電話でチケットを予約した。)[通信手段としての電話]
3) We don’t have to go to (×the) school on Sundays.
※ (日曜日には学校に行かなくてもよい。)
上記文では、学校を1つの建物として考えているのではなく、勉強などが行われる「場」としてとらえている。あるものの「働き」や「役割」「性質」に焦点を当てると無冠詞になる。その場合には、建物を数えるのではないので不定冠詞は使わない。a schoolは、1つの学校全体か、学校の建物を考えているときに使う。the schoolは特定された学校を指すときに使う。
go to bed〈寝る〉という表現も、bedのもつ役割に焦点を当てている。
・I went to bed late last night.(私は昨夜遅く寝た。)
4) Let’s play (×the) baseball in the park.
※ (公園で野球をしよう。)
次のような場合に無冠詞になる。
① 呼びかけ/家族関係/官職などが補語になる場合/食事・スポーツ・ゲームの名
Professor!
Mother!
He was elected mayor of the city.(彼はこの市の市長に選ばれた。)
We invited him for dinner.(彼を夕食に招待した。)
play baseball(野球をする)
play chess(チェスをする)
例えば、Professor!は× A professor!や× The professor!とはしない。呼びかけられた「教授」はProfessorという単語だけ聞けば、自分のことだとすぐにわかる。このように、「名詞だけ見れば(聞けば)だれのことか、または、どれのことかすぐわかる」場合は無冠詞になる。
また、King Lear(リア王)のように、称号や官職が名前の前に置かれた場合や、Dr. Smith, professor of linguistics(言語学者の教授のスミス博士)のように、称号や官職が名前と同格になる場合も無冠詞になる。
② 2つの名詞が対句になっている場合
from door to door(1軒ごとに)
day and night(昼も夜も)
③ 慣用句における無冠詞
at noon(正午に)
by accident(偶然に)
in fact(実際)
〈新聞の見出しで無冠詞になる場合〉
新聞の見出しなどでは冠詞の脱落が起こる。また冠詞だけでなく、あちこち細かく削って、極力簡潔な表現をする。
・President to Attend U.N. Talks on Arms Control
(大統領 軍縮に関する国連の会談に出席予定)
→The president is to attend the U.N. talks on arms control.
・Bomb Destroys U.S. Embassy in Nairobi
(ナイロビのアメリカ大使館爆破)
→ A bomb destroyed the U.S. embassy in Nairobi.
148 冠詞の位置
必要なところにa / an / theのいずれかを入れて、正しい英文にしなさい。
1) What a nice handkerchief you have!
※ (あなたがもっているハンカチはなんて素敵なんだろう。)
上記文では〈what a / an(+形容詞)+名詞〉という語順になる。名詞を修飾するときに、不定冠詞よりも前に置かなくてはならない語がある。whatやsuchを使う場合は、次のようにする。
○what a nice handkerchief
×a what nice handkerchief
○such a wonderful story
×a such wonderful sory
2) I have never seen so big an airplane.
※ (私はそんなに大きな飛行機を一度も見たことがない。)
上記文では〈so+形容詞+a / an+名詞〉という語順になる。名詞を修飾するとき、形容詞をともなって不定冠詞よりも前に出る語がある。so / how / as / tooを使う場合は、次のようにする。
○so big an airplane
×a so big airplane
×so a big airplane
さらに、この表現を使うときには、不定冠詞が存在しなくてはならない。したがって以下の表現は誤りとなる。
×so big airplanes
×so surprising news
〈注意〉so many people 次のように数量を表す場合は不定冠詞は不要。
so many people / so few people
so much water / so little water
3) She gave me such an interesting book.
※ (彼女はこのようなおもしろい本を私にくれた。)
4) Has he spent all his money I gave to him?
※ (彼は私があげたお金をすべて使ってしまったのですか。)
上記文では〈all the+名詞〉という語順になる。名詞を修飾するとき、定冠詞より
も前に出る語がある。all / both / half / doubleなどを使う場合は、次のようにする。
○all the books
×the all books
○both the books
×the both books
これはもともと、all of the booksという表現で、ofが脱落したものである。allbooksという形も用いられる。
〈a A and Bとa A and a B〉
次の2文の違いに注意
① I saw a black and white dog.(私は白黒ぶちの犬を1匹見かけた。)
② I saw a black and a white dog.(私は黒い犬と白い犬の2匹を見かけた。)
①には不定冠詞が1つしかない。これは、犬が1匹だったことを表している。よって、「白黒ぶちの犬が1匹」ということになる。それに対し、②では不定冠詞が2つ使われているから、犬は2匹いたことになる。「黒い犬と白い犬の2匹」をみかけたわけだ。
〈同じ名詞でも、組み合わせる冠詞によって言いたいことが変わる〉
① I don’t like sleeping on a bed.(私はベッドで寝るのが嫌いだ。)
② Carry our baby to the bed, please.(赤ちゃんをベッドまで運んでください。)
③ I went to bed late last night.(私は昨日遅く寝た。)
①は、ベッドならどんなベッドでも、とにかく「ベッド」の上で寝るのは嫌いだという意味。具体的に1つのベッドのイメージを思い浮かべているので、不定冠詞が使われている。②は、状況から赤ちゃんを運んでいくべきベッドは決まってくるので、theを使う。それに対して③は、「ベッドのところまで移動した」ということではなく、「(ベッドまで行って)寝た」という意味である。この場合、具体的なものとしてのベッドではなく、「寝るためのもの」としてのベッドの機能が問題になっている。このように機能が問題になっているときには具体的なものを指す語であっても無冠詞で用いられる。
もう1つ考えてみよう。
④ He is an only child.(彼は一人っ子だ。)
⑤ He is the only child in the club.(彼はそのクラブでたった1人の子どもだ。)
⑥ He is still child enough to believe in Santa Clause.
(彼はサンタクロースの存在を信じるほど子どもっぽい。)
④のan only childは「一人っ子」という意味。1つの家族にとっては「唯一」のこどもでも、世の中全体をみると一人っ子は何人もいるわけだから、「(複数あるうちの1人の)子ども」という意味で、不定冠詞を使う。⑤は「そのクラブ」という限られた中で「たった1人だけ子どもだ」という意味だから、定冠詞を使う。クラブの中には、ほかにだれも子どもはいないということになる。⑥は特殊な用法。この場合は具体的な子どもとう1つの存在は意識されず、代わりに「子どもっぽい」という「性質」が前面に出てくる。1つの存在をまるごととりあげるというより、そのもののもつ「性質」を問題にしているという意味では、③のgo to bedの用法に近いものがある。
〈固有名詞と冠詞〉
固有名詞にはふつう冠詞は不要である。しかし、冠詞が使われる場合もある。
① While you were out, a Mr. Richardson came to see you.
(リチャードソンという人が留守中に訪ねてきたよ。)
だれのことを指すのかまだ特定されない場合、不定冠詞を使って「リチャードソンという名前の1人の人」という意味合いを表す。
② He bought a Picasso in Paris.(彼はピカソの作品をパリで買った。)
芸術家などの場合、生みだした作品は複数あるのがふつうである。そういう
数ある作品のうちの1つを指す場合にも不定冠詞が使われる。
③ He wants to be an Einstein in the future.
(彼は将来アインシュタインのような人になりたいと思っている。)
著名な人物の場合、一種の「手本」になりえるので、「~のような人」という意味で不定冠詞とともに固有名詞が使われる。
④ We’re going to invite the Richardsons to dinner.
(私たちはリチャードソン夫妻[一家]をディナーに招待するつもりです。)
性を共有する1つの集団(夫婦、家族など)を指すときには、ほかの集団との区別をつけるために定冠詞を使う。「その性で呼ばれるあるグループ全員」という意味合いを表す。この場合、性は複数形となる。
⑤ the National Museum (国立博物館)/ the Panama Canal(パナマ運河)
museaumやcanalのように、普通名詞を固有名詞化した場合は、定冠詞で限定するのが原則。ただし、Shinjuku Station(新宿駅)/ Narita Airport(成田空港)のように、「駅」「空港」「公園」「橋」の名前は無冠詞になる。
〈「総称」表現について〉
「ライオンは危険な動物だ」というとき、「ライオン」の表現のしかたは、原則として次の3種類がある。
A) 無冠詞複数:Lions are dangerous animals.
B) 不定冠詞単数:A lion is a dangerous animal.
C) 定冠詞単数:The lion is a dangerous animal.
このうち、もっとも一般的に使われるのがA)の無冠詞複数である。これは「ライオン」というグループ全体をばくぜんとまとめることになる。B)の不定冠詞単数は、具体的なサンプルを取り上げて、それについて説明している感じなので、「具体的な1頭のライオン」にふさわしい文脈がないところで使うと不自然な感じがする。C)の定冠詞単数は、ほかのものと対比するイメージがある。つまり、「ライオン」と「トラ」を比べるときなどに使う。そのような対比がまったく感じ取れない文脈でthe lionと言うと、「(ほかのライオンではなく)そのライオン」という意味に解釈するのが自然だということになってしまう。また、文体も固くなるので、むやみに使わないほうがよい。
なお、the lionsとすると、限られたライオンの一群全部を指すことになってしまい、ライオン一般を指さないのがふつうである。
第20章 代名詞(解説)
149 人称代名詞(格変化 / ばくぜんと「人々」を指すyou/they/we / 所有代名詞)
次の文の下線部を適切な代名詞に変えなさい。
1) I bought a pair of shoes for my son. He was pleased with them.
※ (私は息子のために一足の靴を買ってあげました。彼はその靴に喜んでいました。)
上記のheのように、文中で主語として用いられる形を「主格」と呼ぶ。
〈注意〉目的格が主語の代わりに使われる
本来は主格の代名詞を使う場合に、目的格が使われることもある。口語では目的格が使われることが多い。
・“Who is it?” “It’s me.” (「どなたですか?」「私です。」)
・“I will go.” “Me, too.” (「ぼくは行くよ。」「私も。」)
〈「人々」を指すyou/they/we〉
・You can’t get a driver’s license until you’re eighteen.
(18歳になるまでは、運転免許をとることはできません。) [youは、具体的な人を指しているのではなく、ばくぜんと「人々」を表している。]
・They say she is getting married next month.
(彼女は来月結婚するらしい。)[theyは、ばくぜんと「人々」を表している。このようなtheyは、話し手も聞き手も含まれない場合に用いられる。文脈によっては、具体的な「彼ら」を指すことになるので、使うときには注意が必要。
・We had little rain last month.
(先月は雨がほとんど降らなかった。)[weは、話し手を含む「人々」の代表として述べている。この文では、「雨が降らなかった」のは「話し手が住んでいる地域」ということになる。]
〈oneで「人」を表す〉
oneをもちいて「人/人はだれでも」という意味を表すこともある。ただし、これは文章体である。
・One can never tell when an earthquake will occur.
(地震がいつ起こるかは決してわからない。)
2) Mike and I are good friends. We made the model plane in two days.
※ (マイクと私は良い友達です。私たちは2日で模型飛行機を作りました。)
3) Your room is as large as mine.
※ (あなたの部屋は私のと同じくらい大きい。)
代名詞の所有格は、my roomのように後ろに名詞を続けなければならない。それに対し、mine(私のもの)やyours(あなたのもの)のような所有代名詞は単独で用いることができる。所有代名詞は、mineを除き、所有格に-sがついた形になる。なお、hisはもともと-sで終わっているので、所有格と所有代名詞が同じ形になる。a, the, this, that, noなどと所有格を続けて用いることはできない。
〈参考〉a friend of mineは「友人が何人かいるうちの不特定の1人」を表し、my friendは「特定の1人の友人」を表す
・This is my friend Lisa. (こちらは私の友人のリサです。)
4) I borrowed a bicycle from Bob. His bicycle was nice
※ (私はボブから自転車を借りた。彼の自転車は良かった。)
上記のHis bicycleのように、名詞の直前に置かれ、日本語の「〜の」に相当する意味をもつ形を「所有格」と呼ぶ。所有格の代名詞は単独では用いられず、つねに名詞の直前に置かれる。
また、所有格の代名詞の後ろに形容詞のownを入れて、「自分自身の」「〜独自[独自の]という意味を付け加える場合がある。
・She has her own sense of fashion.
(彼女は彼女独特のファッションセンスをもっている。)
150 人称代名詞(再帰代名詞の再帰用法 / 強調用法)
日本語の意味に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) あなた自身が私にそう言ったのよ。
You told me so (yourself).
※ 上記のyourselfのように、人称代名詞の所有格、あるいは目的語に、-selfまたは-selvesのついた形を再帰代名詞と呼び、「(だれだれ)自身」という意味になる。
再帰代名詞は、名詞や代名詞を強調することができる。上記文では、「あなたが自分自身で」ということを強調している。
〈参考〉再帰代名詞を主語の後ろに置く場合もあるが、文章体となる。
・You yourself told me so.
2) 私たちはパーティーで楽しく過ごした。
We enjoyed (ourselves) at the party.
※ 上記のourselvesのように、他動詞の目的語が主語と同じ人やものである場合、目的語には再帰代名詞を用いる。
〈再帰代名詞を使った重要表現〉
・Help yourself to the salad. (サラダをご自由にお取りくださいね。)
・I couldn’t make myself understood in England.
(私の英語は通じなかった。[私は英語で自分の意思を伝えられなかった。]
・I had to shout to make myself heard in the noisy class.
(私は騒がしい教室で、自分の声を聞かせるために叫ばなければならなかった。)
・Please make yourself at home. (どうぞ楽にしてください。)
・Take care of yourself. (おからだをお大事に。)
・Did you tie your shoelaces by yourself. (靴ひもは自分1人で結んだのかい。)
・You should decide your course for yourself.
(自分の進路は自分で決めるべきだ。)
・He behaved himself at the party. (彼パーティーで行儀よくふるまった。)
・He introduced himself to everyone in the classroom.
(彼は教室でみんなに自己紹介した。)
・I fell down the stairs and hurt myself. (私は階段から落ちて、けがをした。)
151 itの用法
次の文の下線部のitが指している語句を答えなさい。
1) I have lost my handkerchief. I bought it only yesterday.
it = my handkerchief
※ (私はハンカチをなくしてしまった。それを昨日かったばかりなのに。)
itはすでに出た単数の名詞を指すことができる。
また、下記のように句や節の内容も指すことができる。
・We wanted to fly there directly, but it wasn’t possible.
[it = to fly there directly]
(そこまで直行便の飛行機で行きたかったが、それは不可能だった。)
・He likes eating sweets, but he won’t admit it. [it = He likes eating sweets]
(彼は甘いものが好きなのに、本人はそれをどうしても認めようとしない。)
また、下記のような様々な用法がある。
① 時や天候・距離などを表すときに使う(特に意味をもたないitを主語にする)
「曜日・日時」
・What day is it today? (今日は何曜日?)
・It is Culture Day today. (今日は文化の日です。)
「天候・明暗・寒暖」
・It’s very humid here, isn’t it? (ここはとてもむしむししますね。)
・It gets dark at around eight o’clock in the summer.
(夏は8時ごろ暗くなる。)
「距離」
・It’s about two kilometers to the town from here.
(ここからその町までは2キロほどあります。)
② 状況を表すときに使う。(「ばくぜんとした状況」や「事情」を表す)
・How’s it going? (調子はどう?)
・It was very comfortable in the First Class cabin.
(ファーストクラスの客室は、とても快適だった。)
2) It is difficult to win the race.
It = to win the race
※ 形式主語のit: 不定詞やthat節が主語として用いられる場合、主語の位置にitを形式的に主語として置き、真の主語である不定詞句やthat節を後ろにまわすことが多い。
・It is important that you follow the rules. (規則に従うことは大切だ。)
〈参考〉動名詞句が主語になる場合も、形式主語のitが用いられることがあるが、
それほど多くない。
・It is no use crying over spilt milk.
(こぼれたミルクのことで泣いてもむだだ。[覆水盆に返らず。])
〈注意〉that節以外の名詞節: 形式主語itが用いられている場合、真の主語として
that以外の名詞節が用いられる場合もある。
・It is not clear whether he did it himself or not.
(彼がそれを自分自身でやったかどうかは、はっきりしていない。)
〈節の内容を指すit〉
次のようなitは厳密に言うと形式主語ではないが、形式主語のitと同様の考え方ができる。
・Is it all right if I use this computer?
(私がこのコンピューターを使ってもよろしいですか。)
・It was quite a shock to me when he turned out to be a thief.
(彼がどろぼうだとわかった時は、私にはとてもショックだった。)
上記の2つのitはともにif節、when節の内容を指していると考えられるが、これらの節は両方とも副詞節なので真の主語と考えることはできない。このような場合は、あまり文法的な分類にこだわらず、itが何を指しているのかを文の内容から判断できればよい。
3) I think it necessary that you should do the homework by yourself.
it = that you should do the homework by yourself
※ 形式目的語のit: SVOC(第5文型)の文で、目的語として、不定詞句やthat節を用いると、述語動詞(V)と目的格補語(C)が離れてしまって文の構造がわかりにくくなってしまう。そのため、目的語の位置にitを形式的に目的語として置き、真の目的語である不定詞句やthat節を補語の後ろに置く。上記では、that you should do the homework by yourselfというthat節が真の目的語である。
〈参考〉形式目的語のitをとるおもな動詞には、find, think, make, take, consider,
believeなどがある。
〈参考〉形式目的語の場合と同様、動名詞句に対して形式目的語が用いられる場合があるが、それほど多くはない。
・They thought it dangerous climbing that mountain in winter.
(彼らは冬場にあの山に登るのは危険だと考えた。)
〈itを用いた表現〉
It takes + 時間 + to do (〜するのに〈時間〉がかかる)
・It takes two hours to get to the airport. (空港に着くまでに2時間かかる。)
It costs + 費用 + to do (〜するのに〈費用〉がかかる)
・It costs thirty dollars to fix the computer.
(そのコンピューターを修理するのに30ドルかかった。)
It makes no difference whether 〜 (〜かどうか関係ない)
・It makes no difference to me whether she comes or not.
(彼女が来ようが来まいが、私には関係がない。)
take it for granted that 〜(〜を当然だと思っている)
・They take it for granted that they have a car.
(彼らは、車を持っていることを当然だと思っている。)
152 指示代名詞
次の文を日本語に直しなさい。
1) The city library is a long way from here. That is the problem.
市立図書館はここからは遠い。それが問題だ。
※ thisやthatは具体的なものを指すだけでなく、すでに述べられた話の内容かを指すことがある。
〈参考〉That is (the reason) why … (そういうわけで…)のthatも、前の文の内容
を指している。
・Your blood pressure is too high. That is (the reason) why you must take this medicine.
(あなたの血圧は高すぎます。そういうわけで、あなたはこの薬を飲ま
なければならない。)
〈次の文の内容を指すthis〉
・Keep this in mind: the voters want reform.
(このことを覚えておきなさい。有権者は改革を望んでいるのです。)
thisは前に述べられたことを指すのが一般的だが、これから述べることに対して注意をひくために用いられることもある。上記文では、thisはthe voters want reformを指している。
2) The population of China is much larger than that of Japan.
中国の人口は東京の人口はよりもずっと多い。
※ 文中ですでに述べられた名詞の繰り返しを避けるために、〈the+名詞〉をthat(複数形の場合はthose)で代用することができる。上記文では、thatがthe populationの代用となっている。
〈those who … で「…である人々」を表す〉
・Those who wish to smoke must go outside.
(たばこを吸いたいひとは、外へ出なければいけません。)
those who[whose / whom]… の形で「…である人々」という意味になることがある。この場合、代名詞thoseは一般的な人々を表す。また、those present(そこにいる[いた]人々), those concerned(関係者), those around us((私たちの)身の回りの人々)のように、関係詞節以外の形容詞(句)が用いられる場合もある。
〈the sameの用法〉
sameは、the sameという形で「同じもの[こと]」という意味の代名詞として働く(theなしではふつうは使わない。
・If I try the new method of studying English, will you do the same?
(もしぼくがその新しい英語の勉強法を試したら、君も同じことをするか
い?)
・She’s almost the same height as I am.
(彼女がは私と背の高さがほとんど同じだ。)
the sameは形容詞としても用いることができるので、〈the same + 名詞〉
の形で「同じ〜」という意味になる。何と同じなのかを明記するためには、
後ろにas… をつけ足して表す。Asの後ろには節、名詞・代名詞が続く。
・I want the same shoes as yours. (君のと同じ靴がほしいな。)
・He is the same man that I saw yesterday.
(彼は昨日見かけた男の人と同じ人だ。)
・His opinion about this plan is much the same as yours.
(この計画についての彼の意見は、君のとほとんど同じだ。)
much the sameはalmost the same(ほとんど同じ)と言う意味で、補語として用いることができる。ほかにも、about the same(だいたい同じ), just the same(ちょうど同じ), exactly the same(まったく同じ)などの形がある。
153 不定代名詞(one / another / the other / others)
( )内の語句のうち、正しいほうを選びなさい。
1) “Do you have a red pen?” “Yes, I have (one).
※ (赤ペンをもっていますか。はい、もっています。)
代名詞のoneは、すでに出た数えられる名詞のくり返しを避けるために用いられる。上記文の場合、oneはred penの代わりに用いられている。このようにoneが単独で用いられると、〈a/an+名詞〉の意味を表すことになる。上記文では、oneはa red penを表している。(×a oneとはできない)。
〈oneを単独で用いることができるのは、不特定の1つ[1人]を意味する場合なので、特定のものを指す場合には、oneではなくitを用いなければならない。〉
・“Did you bring the red pen? “ “No, I didn’t bring it.”
(「あの赤ペンもってきた?」「いや、持ってこなかったんだ。」)
〈参考〉前に〈a/an+名詞〉があれば、必ずoneを用いるわけではない。
・If you find a pen, you can use it.
(ペンを見つけたら、それを使ってよい。)
この場合はa penそのものを指しているのでit を用いている。
〈形容詞がつくと冠詞が必要〉
・I lost my umbrella yesterday; I must buy a new one.
(昨日かさをなくしてしまった。新しいのを買わなければ。)
oneに形容詞がつく場合は、上記のように冠詞が必要。このoneは、umbrellaの代わりをしている。
・These boots have worn out. I need to buy some new ones.
(このブーツははき古してしまった。新しいのを買わなければ。)
複数形のonesは、上記のsome new onesのように、形容詞のような修飾語句をともなう場合に用いることができる。このonesは、前にでた名詞bootsの代わりをしている。
〈the one / the onesの用法〉
oneに修飾語句などがついて特定のものを表す場合は、次のようにthe oneやthe onesを用いる。
・This guitar is similar to the one I have. (= This guitar is similar to mine.)
(このギターは私が持っているものと似ている。)
・“Which are your shoes?” “The ones with red shoelaces.”
(「どちらが君の靴?」「赤い靴ひもがついているほうだよ。」)
〈that / thoseを使う場合〉
the oneやthe onesの後ろに修飾語句がついている場合は、the oneをthat, the onesをthoseで置き換えることもできる。特にof … が続く場合にはthatやthoseが用いられる。なお、the oneやthe onesは人を指すことができるが、thatの場合は人を指すことはできない。
・The man I saw was older than the one [×that] you were talking to.
(私が見た男の人は、君が話していた男の人よりも年をとっていた。)
〈参考〉不特定の複数のものを指す場合にはsomeを用いる。
・You have a lot of CD-ROMs; please give me some.
(君はたくさんのCD-ROMを持っているね。少しくれないか。)
[このsomeはsome CD-ROMsを意味している]
また、特定の複数のものを指す場合にはtheyを用いる。
・Look at the birds in the sky! They are eagles, aren’t they?
(空の鳥をみてごらん。ワシだよね)
〈oneを使うことができない場合〉
① 数えられない名詞の代わりに用いることはできない。
数えられない名詞を繰り返したいときはoneを代用せず、その名詞を繰り返
す。また、形容詞がある場合は、その名詞は省略してもよい。
・I like white wine better than red (wine).
(私は赤ワインよりも白ワインが好きです。)
② 所有格の後に続けることはできない。
×my oneとはせず、mineとする。
2) I have this kind of wallet. Please show me (another).
※ (私はこの種の財布は持っています。ほかのを見せてください。)
anotherは「もう1つ[1人]」という「他の不特定の1つ」を表す。上記でanotherが使われているのは、ほかにいくつかあるうちの1つを指しているからである。
また、anotherは、下記のように形容詞として使われ、後ろに名詞をともなうことができる。
・Would you like another piece of pie? (パイをもう1切れいかがですか。)
3) Hold the racket in one hand and the ball in (the other).
※ (一方の手にラケットを、もう一方の手にボールを持ちなさい。)
the otherは、「残りの1つ[1人]という「ほかの特定の1つ」を表す。上記では、「(残りの)1つ」について述べているので、the otherが使われている。
また、the otherは下記のように形容詞として使われ、後ろに名詞をともなうことができる。
・Tom was in the classroom but the other students were playing outside.
(トムは教室にいたが、ほかの生徒たちは外で遊んでいた。)
・Open the other hand. (もう一方の手を開きなさい。)
Open your other hand.とすることもできる。
4) We have four children. One is a college student, and (the others) are high school students.
※ (私たちはには4人の子供たちがいます。1人は大学生で残りは高校生です。)
残りのものが複数の場合にはthe othersという形で「ほかの全部」を表す。
また、othersは下記のように「ほかの複数の人[複数のもの]」という不特定のばくぜんとした数を表す。
・Some likes dancing, and others don’t.
(踊るのが好きな人もいるし、そうでない人もいる。)
また、形容詞として使われる場合は、下記のように〈other+名詞〉という形になる。
・He couldn’t find the CD, so he decided to check other stores.
(彼はそこでそのCDを見つけられなかったので、ほかの店を見てみることにした。)
〈each other〉
otherを使った表現にeach other(お互い)がある。each otherは代名詞なので自動詞と一緒に用いるときは前置詞が必要。
・They talked with each other. (彼らは話し合った。)
154 不定代名詞(some / any)
( )内にsomeかanyのいずれかを入れて、英文を完成させなさい。
1) If there is (any) milk left, could I drink (some)?
※ (コーヒーが(いくらかでも)残っていたら、少しいただけますか。)
anyは上記のように、「何かが少しでもあれば」という条件節でよく用いられる。
someは上記のmilkのような数えられない名詞についてある程度の量があることを、また下記のmembersのような数えられる名詞についてある程度の数があることを表す。
・Some of the members were tired. (メンバーの何人かは疲れていた。)
また、anyは下記のように何かが少しでもあるかどうかを尋ねる疑問文でも用いられる。
・I need some paper clips. Do you have any?
(ペーパークリップが必要なんです。お持ちですか。)
2) I’d like (some) information about the trip.
※ (私はその旅についていくらか情報をいただきたい。)
someは上記のように形容詞として使われ、後ろに名詞をともなうことができる。
someは肯定文で用いられるのがふつうだが、下記のように、「ある」と思って質問するときは、疑問文でもsomeを使う。
・Are there some messages for me, too? (私にも何か伝言がありますか。)
また、何かをすすめるような場面でもsomeを用いる。(これらの場合はYesという答えが想定されている)。
・Would you like some coffee? (コーヒーはいかがですか。)
3) I haven’t met (any) of her family yet.
※ (私はまだ、彼女の家族のひとりとも会っていない。)
anyは上記のような否定文で用いられると、「少しも…ない」という意味になる。
anyが肯定文で用いられると、3人以上の人や3つ以上のものについて、「どれも」という意味を表すことになる。この場合、単数形の名詞を修飾することが多い。下記では「どの生徒を選んでも」という意味を表している。
・Any student in this class can answer the question.
(このクラスのどの生徒でも、その質問に答えることができる。)
〈Any … not〜 の語順にしない〉
anyを否定文で用いるとき、×any … not〜のように、anyをnotよりも前に出すことはできない。以下のようにnone(代名詞の場合)やno(形容詞の場合)を用いる。
◯None of the students are from Canada. (カナダ出身の生徒はいません。)
×Any of the students are not from Canada.
◯No amount of money can buy happiness.
(どんなに多くのお金でも、幸せを買うことはできない。)
×Any amount of money cannot buy happiness.
155 不定代名詞(both / either / neither/ all / none / each / someone / everything)
( )内の語のうち、正しいほうを選びなさい。
1) I have two pretty birds and I like (both) of them.
※ (私は2羽のかわいい鳥をを飼っていて、両方とも好きです。)
bothは、2人の人や2つのものについて、「両方とも」という場合に用いられる。
下記のように、複数形の名詞の前に置いて「両方の〜」という意味の形容詞として用いることもできる。
・She broke both legs in the accident. (彼女はその事故で両足を骨折した。)
また、代名詞の所有格やthe, these/thoseとともに用いる場合、bothをその直前に置くこともある。
・Both my parents were brought up in Hokkaido.
(= Both of my parents were brought up in Hokkaido.)
(私の両親は2人とも北海道育ちです。)
〈人称代名詞+both〉
He invited us both.(彼は私たち2人を招待してくれた。)のように、人称代名詞の後にbothを続けることもできる。また、主語について「両方とも」という場合は、次のように、一般動詞の前、be動詞や助動詞の後で用いられる。
・We both went. (私たちは2人とも行った。)
・The ladies over there are both from Greece.
(あそこにいる女性は2人ともギリシャ出身です。)
〈either〉
2人の人や2つのものについて、「どちらか一方/どちらでも」と言う場合は次のようにeitherを用いる。eitherは単数扱いするのがふつう。
・Either of your parents can attend the PTA meeting.
(あなたの両親のどちらでも、PTAの会合にでることができます。)
次のように、名詞の前に置いて「どちらかの~」という意味の形容詞として用いることもできる。
・You can take either cake.(どちらのケーキをとってもいいですよ。)
また、eitherは、否定文で用いられると「どちらの~も…ない」という意味になる。
・You cannot touch either of these buttons.
(この2つのボタンのどちらにも触ってはいけない。)
また、eitherがsideやendなどの名詞と結びついて、「どちらにも」「両方とも」という意味になる場合がある。この場合、sideやendは単数形で使う。
・There were many cherry trees on either side of the river.
(その川の両岸には、たくさんの桜の木があった。)
・Place the cards at either end of the table.
(テーブルの両端に、カードを並べなさい。)
〈neither〉
2人の人や2つのものについて、「どちらも…ない」と言う場合にneitherを用いる。「片方がそうでなくて、もう片方もそうでない」という場合に用いる。次のようにeitherと同じで単数扱いがふつうだが、意味的に複数を表す文では、複数扱いとなることもある。
We passed two gas stations, but neither of them was[were] open.
(ガソリンスタンドを2ヵ所通過したが、とちらも開いていなかった。)
また、次のように返答のときにneitherだけをもちいることもある。
・“Which one of these two dogs would you chose?”
(「あなたならこの2匹の犬のうち、どちらを選びますか。」)
“Neither.”
(「どちら選びません。」)
また、次のようにneitherは後ろに名詞が続く形容詞として用いられることもある。
・I could find neither book I was looking for.
(探していた本は、どちらも見つからなかった。)
2) (None) of the ten girls watched the TV drama last night.
※ (その10人の少女のだれも、昨夜そのテレビドラマを見なかった。)
3人以上や3つ以上のものについて、「どれも[だれも]…ない」という意味を表すときにはnoneを用いる。none of の後に複数の名詞や代名詞が来る場合は、単数・複数の両方の扱いができるが、ofの後に数えられない名詞が来る場合は、単数扱いとなる。
・None of us agrees[agree] with you.
(私たちはだれも君の意見には同意しない。)
・None of the information is useful. (その情報はどれも役に立たない。)
noneは必ず代名詞として用いられ、形容詞としては用いられない。「どの〜も…ない」という意味を表すときは、下記のようにno, またはnot … anyを用いる。
・No student in this class could answer the question.
(クラスのだれもその質問に答えられなかった。)
I was not against any of these proposals.
(私はこれらのどの提案にも反対しなかった。)
また、noneは次のように単独で用いられることもある。(ただし、文章体。口語ではnothing, no one, nobodyをよく用いる。)
・I wanted some ice but there was none in the freezer.
(氷がほしかったが、冷蔵庫には少しも入っていなかった。)
〈all〉
allは次のように、3人以上の人や3つ以上のものについて、それら全体を指し「すべて」という意味を表す。この場合のallは複数扱いである。
・All of the members were against the proposal..
(メンバーは全員、その提案に反対だった。)
数えられない名詞について、その全体を「すべて」という場合にも用いられる。この場合はのallは単数扱い。
All of our furniture was damaged in the fire
(うちの家具はすべてその家事で損害を受けた。)[furnitureは数えられない名詞]
また、allは次のように後ろに名詞を続けて、「すべての~」という意味を表す形容詞としても用いることができる。また、both同様、theや所有格などの前に置き、〈all+the[所有格/these/those]+名詞〉の語順にできる。
・All [the] students have to take the test.
(生徒は全員、そのテストを受けなければならなかった。)
また、allは人称代名詞の後で用いることもできる。また、主語について「すべて」という意味で用いるときは、allの位置は一般動詞の前、be動詞や助動詞の後ろになる。
・We all love him.(私たちはみんな、彼が大好きです。)
・They were all excited.(彼らはみんな興奮していた。)
3) My uncle gave candies to (each) of us.
※ (僕のおじさんは僕たち1人1人にキャンディをくれた。)
eachは複数の人やものの1つ1つを指して、「それぞれ」という意味を表す。次のように形容詞として〈each+単数形の名詞〉の形で用いられることもある。
・Each book in the store was on sale for 100 yen.
(その店では、どの本も100円で売り出されていた。)
〈every「どの~も」〉
everyを使って次のようにすることもできる。
・Every book in the store was on sale for 100 yen.
everyは形容詞なので、おもに単数形の名詞を修飾して〈every+単数形の名詞〉の形になる。Everyは、eachのように単独では用いられない。Eachのほうが、1つ1つを個別に意識している意味合いが出る。
〈eachとeveryは単数扱い〉
代名詞eachや〈each+名詞〉、〈every+名詞〉は、「それぞれ1つずつ」を表すので、単数扱いとなる。
○Each participant is to be awarded a prize.(参加者全員に賞品があります。)
×Each participants are to be awarded a prize.
〈人称代名詞+each〉
eachは人称代名詞の後で用いることができる。また、主語について「すべて」と言うときは、一般動詞の前、be動詞や助動詞の後ろで用いる(金額や数量を表す場合は文末に置くこともある)。この場合の主語は複数扱いとなる。
・We each have (×has) our own room.
(私たちはそれぞれ自分の部屋をもっている。)
・They were each preparing for the examination.
(彼らはそれぞれ、試験の準備をしていた。)
・We were paid ten dollars each.
(私たちは、それぞれ10ドルずつもらった。)
〈eachとeveryの使い分け〉
eachは2人[2つ]以上、everyは3人[3つ]以上のことについて用いる。eachとeveryには大きな意味の差はないが、1つ1つを個別に考える場合は、eachのほうが好まれる。
・There are two books in my bag and each(×every)book is carefully wrapped in colorful paper.
(私のかばんには2冊の本が入っているが、それぞれの本はカラフルな紙で入
念に包装されている。)
〈注意〉Every+数詞+複数形の名詞
everyの後ろには単数形の名詞を置くのが原則である。しかし、every two weeks(2週間ごとに)のように、「~ごと(に)」という意味でeveryを用いる場合には、everyの後ろに数詞のついた複数形の名詞を置くことができる。
・The Olympic Games are held every four years.
(オリンピックは4年ごとに開催される。)
[この場合はeveryの前に前置詞をいれないこと]
・This school has one computer for every two students.
(この学校には生徒2人につき1台のコンピュータがある。)
4) I have (something) to do today.
※ (私は今日何かすべきことがある。)
some, every, any, noに-one, -body, -thingをつけた形の代名詞(no one
だけは1語にしない)はいずれも単数形として扱う。また、これらの代
名詞に形容詞がつく場合は、形容詞を後ろに置くことに注意。
・There is something strange about the taste of this pizza.
(このピザの味は何か変だ。)
〈参考〉someone, somebodyを代名詞で受ける場合、以前はheを用いていたが、言語上の性差別をなくすためにhe or sheという形を用いるようになった。現在ではtheyを使うことも多い。
第21章 形容詞(解説)
156 形容詞の用法
( )内の語句のうち、正しいほうを選びなさい。
1) China has (a large population).
※ (中国は人口が多い。)
名詞を修飾する形容詞は、修飾する名詞の前に置くのが原則。上記文では、largeは直後のpopulationを修飾している。このように、形容詞が名詞を修飾する用法を、限定用法と呼ぶ。
形容詞を並べる順序
・Come and see my ten cute small young white Dutch rabbits.
(私の10匹のかわいい小さな子どもの白いオランダうさぎを見においでよ。)
・I’m looking for a large brown leather bag.
(私は大きな茶色の皮のかばんを探しています。)
形容詞が名詞を修飾する場合、その形容詞が1語だけとは限らない。上の例のように、名詞を修飾する形容詞がいくつも続くこともある。そういう場合には、次のような順序の原則がある。ただし、あまりたくさんの形容詞を続けるとわかりにくくなるので気をつけよう。
冠詞や、人称代名詞や名詞の所有者 my a
数量 ten
主観的判断 (fine / lovely / niceなど) cute
大小 small large
年齢・新旧 young
色 white brown
材料・出所 Dutch leather
2) Please give me (something hot) to drink.
※ (何か温かい飲み物をください。)
上記文のsomethingのような-thingのつく代名詞を修飾する場合、形容詞はその後に置かれる。また、someoneのような-oneのつく代名詞の場合も同様である。
・Is there someone special in your life?
(あなたの人生において特別な人はいますか。)
3) Look at the (sleeping) baby.
※ (その眠っている赤ちゃんを見てごらん。)
次のように名詞を修飾する形容詞にほかの語句がついて、2語以上の語群となる場合には、名詞を後ろから修飾する。
・Look at the baby sleeping in the bed.
(そのベッドで眠っている赤ちゃんを見てごらん。)
I don’t like traveling in trains full of people.
(私は満員電車に乗るのが好きではない。)
・He tried to climb a fence two meters high.
(彼は2メートルの高さの柵をよじ登ろうとした。)
〈参考〉高さや長さ、年齢などを表す形容詞の場合は、それがどのくらいの数量なのかを表す語句が形容詞の前に置かれる。
a book 300 pages long (300ページの本)
a building ten stories high (10階建てのビル)
4) They caught the bear (alive).
※ (彼らはそのクマを生け捕りにした。)
SVC, SVOCの文型で、形容詞は補語(C)として用いられる。これを叙述用法と呼ぶ。
上記文は、SVOCの文型で、OとCには〈O is C〉の関係、つまりThe bear is alive.の関係が成り立つ。上記文のaliveは「生きて」という意味で、叙述用法でしか使われない。ここでのaliveは準補語で「…の状態で」という意味になる。したがって、名詞の前では用いられない。
この種の形容詞には次のようなものがある。
alone (ただ1人の/孤独の)
asleep (眠って)
afraid (恐れて)
awake (目覚めて)
aware (気づいて)
content (満足して)
glad (喜んで)
well (元気で)
逆に限定用法でしか使われない形容詞には次のようなものがある。
only (唯一の/たった1つの)
live (生きている)
living (生きている)
mere (ほんの/単なる)
elder (年上の)
former (前の)
latter (後の)
lone (1人の)
main (おもな)
golden (貴重な)
total (全部の)
daily (毎日の)
very (まさにその)
また、限定用法と叙述用法で意味が異なる形容詞には次のようなものがある。
certain a certain charm (ある種の魅力)
I’m certain this is the correct answer. (これが正解だと私は確信している。)
late the late news report (最近のニュース記事)
He was late. (彼は遅れた。)
present the present topic (現在の話題)
He was present. (彼は出席していた。)
right the right hand (右手)
He is right. (彼は正しい。)
ill ill temper (不機嫌)
He is ill. (彼は病気だ。)
5) My son was taller than all the (boys present).
※ (私の息子はそこにいるすべての少年達よりも背が高かった。)
present, responsible, concerned, involvedなどの形容詞は、単独で名詞の後に置かれることがある。名詞の前に置かれる場合と意味に違いが出ることがあるので注意が必要。
the present situation (現状), a person present (出席者)
the man responsible (責任者), a responsible man (頼りになる男)
the people concerned (関係する人), concerned people (心配している人)
available, requiredのように、名詞の前でも後でも意味に違いがないものもある。
また、available, possible, imaginableのように、-ableや-ibleで終わる形容詞がある。これらがall, every, noや最上級の形容詞とともに使われる場合は、名詞の後に置かれることがある。
・There is no bus service available after 11 o’clock.
(11時以降はバスは運行していません。)
・The sea was the deepest blue imaginable.
(その海が考えうる限りもっとも濃い青色だった。)
157 分詞形容詞
( )内の語のうち、正しいほうを選びなさい。
1) It’s so (boring) to spend the weekend alone.
※ (週末に1人で過ごすのはとても退屈だ。)
英語の形容詞の中には、分詞から派生しているものがある。その中でも、boring / boredのような感情を表す動詞から派生しているものに関しては、-ing形の形容詞と-ed形の形容詞の使い分けに誤解が生じやすい。分詞形容詞については、日本語の表現方法を、そのまま英語に持ち込まないようにすることが大切。
boringはもともとboreの現在分詞、boredはboreの過去分詞で、boreは「〜を退屈させる」という意味の他動詞。したがって、boringは「退屈させる」という能動の意味、boredは「退屈させられた」という受動の意味をもつことになる。
・I’m bored. (私は退屈だ。)
・It was an exciting game. (それはわくわくする試合だった。)
・I saw a lot of excited supporters. (私はたくさんの興奮したサポーターを見た。)
2) We were very (shocked) to hear the news.
※ (私たちはその知らせを聞いてとても衝撃を受けた。)
shockingとshockedの使い分けも同じである。
shockは「〜に衝撃を与える」という意味の他動詞なので、受動の意味をもつshockedは上記文のように「衝撃を受けた」という意味になる。
・a shocked boy (衝撃を受けた少年)
能動の意味をもつshockingは次のように使う。
・The news was shocking. (その知らせは衝撃(人に)衝撃を与えた。)
・shocking news. ((人に)衝撃を与える知らせ)
158 主語に注意すべき形容詞 / 可能性・確実性を表す形容詞 / such
( )内の語句のうち、正しいほうを選びなさい。
1) He is (likely) to succeed as a singer.
※ (彼は歌手として成功しそうだ。)
上記文のように人を主語にして〈S is likely to 不定詞〉とすると、「Sは〜しそうだ」という意味になる。形式主語を用いてIt is likely that … という形にして、「起こりそうなこと/ありそうなこと」を表すこともできる。
= It is likely that he will succeed as a singer.
possible
possibleは「可能な」という意味の形容詞で、次のようにIt is possible that … / It is possible for人 to 不定詞という形で用いる。likelyとは異なり、人を主語にすることはできない。
・Is it possible that you will come to the next meeting?
= Is it possible for you to come to the next meeting?
(君が次の会議に出席するのは可能ですか。)
probable
probableは、possibleよりも可能性が高いことを表す。次のようにIt is probable that … の形で用いられ、人を主語にしたり、to不定詞を使うことはできない。
It is probable that he will pass the exam. (彼はおそらくその試験に合格するだろう。)
2) It is (sad) to see him resign.
※ (彼が退職するのを知って残念です。)
形容詞の中には、sorry(残念に思う)のように、叙述用法では人を主語にしなければならないものがある。happy(うれしい)、glad(うれしく思う)も人だけを主語にして、物事を主語にすることはできない。この種の形容詞の多くは、おもに人間特有の性質や感情を表す形容詞である。
○I am sorry to see him resign. (彼が退職するのを知って残念に思います。)
×It is sorry to see him resign.
○I am glad to hear the news. (その知らせを聞いてうれしく思います。)
×It is glad to hear the news.
〈注意〉luckyの使い方 lucky(幸運な)はitを主語にすることができる。
・I was lucky to get the ticket.
= It was lucky for me to get the ticket.
(そのチケットを手に入れることができて、幸運でした。)
人を主語にできない形容詞
形容詞の中には、叙述用法では人を主語にすることのできないものがある。
convenient (都合のよい)
necessary (必要な)
essential (不可欠な)
・Is it convenient for you to meet us at ten?
(10時に私たちに会うということで、ご都合はいかがですか。)
×Are you convenient to meet us at ten?
・It is necessary for you to see a doctor.
(君は医者に診てもらう必要があるよ。)
×Are you necessary to see a doctor?
・It is essential for you to improve your English.
(あなたの英語力を向上させることは不可欠です。)
×Are you essential to improve your English?
また、dangerous (危険な)やdelightful / pleasant (楽しい)などは、人を主語にすると、He is dangerous. (彼は危険人物だ。)、She is delightful. (彼女は人を楽しくさせる人だ。)のような意味になるので注意しよう。
3) It is (certain) that he will win the election.
※ (彼が選挙で勝つのは確かだ。)
certain
certainはIt is certain that … という形で「…であることは確かだ」という意味を表すことができる。
次のように〈S is certain+to不定詞〉で「話し手が確信していること」を表すこともできる。
・He is certain to win the election. (彼はきっと選挙に勝つ。)
また、確信している人を主語にして〈S is certain that … 〉とすると、「Sは…であることを確信している。」という意味になる。
・I am certain that he will win the election.
(私は彼が選挙に勝つことを確信している。)
sure
sureは〈S is sure+to不定詞〉の形で、話し手が「Sはきっと〜する/Sが〜するのは確実だ。」と確信していることを表すことができる。
・He is sure to win the election. [sureは主観的確信]
= He is certain to win the election. [certainは客観的確信]
(彼はきっと選挙で勝つ。)
また、確信している人を主語にして〈S is sure that … 〉とすると、「Sは…であることを確信している。」という意味になる。×It is sure that …という形は使わない。
・I am sure that he will win the election. [sureは主観的確信]
= I am certain that he will win the election. [certainは客観的確信]
(私は彼が選挙に勝つことを確信している。)
× It is sure that he will win the election.
〈参考〉〈S is sure[certain]of -ing〉という形で「Sは〜すると確信している」という意味を表すこともできる。
・He is sure[certain] of winning the election. (彼は選挙で勝つことを確信している)
・I am sure[certain] of his winning the election.
(私は彼が選挙で勝つことを確信している。)
4) We can’t stay home on (such a nice day).
※ (私たちはこんな(とても)天気の良い日に家にいられない。)
suchは形容詞として「そのような〜/このような〜」という意味で用いられる。上記文では、suchが名詞a nice dayを修飾している。このように、suchの後ろに数えられる(形容詞+)名詞の単数形が来ると、〈such a / an+(形容詞+)名詞〉の語順になる。通常の形容詞とは異なり、suchをa/anの前に置くことに注意。上記文のようにsuchは、〈形容詞+名詞〉の前に置かれて、「本当に[とても]〜な」という意味で使われることもある。
・He is such a kind person. (彼は、本当にやさしい人だ。)
名詞の前に形容詞がない場合、次のように名詞が表す程度が強いことを表し、「そんなにすごい[ひどい]〜」という意味になる。
・I have never seen such a storm. (私はこんな(激しい)あらしは見たことがない。)
また、suchは、〈such A as B〉または〈A(,) such as B〉の形で「(例えば)BのようなA」という意味になり、Aの具体例をBで示す際に用いられる。
・In this zoo, you can see such rare animals as the panda an the koala.
= In this zoo, you can see rare animals, such as the panda and the koala.
(この動物園では、パンダやコアラのような、珍しい動物がみられます。)
〈代名詞のsuch〉
suchは「そのようなもの[人]」という意味の代名詞として使われることもある。
・They might refuse to give me a pay raise. Such being the case, I will resign.
(彼らは私の給料を上げるの拒むかもしれない。そうなったら、私はやめる。)
この文では、代名詞suchが前の文の内容を受けて、「そのようなこと」という意味を表している。Such being the caseは独立分詞構文で直訳すると「そのようなことが現実になれば」(=If such a thing is the case)となる。
159 数量を表す形容詞
( )内の語句のうち、正しいほうを選びなさい。
1) Taking too (much) salt is not good for your health.
※ (塩分の取りすぎは健康に良くない。)
「多い」を表す形容詞にはmanyとmuchがある。manyは数が多いことを表し、数えられる名詞(複数形)の前に置く。muchは量が多いことを表し、数えられない名詞の前に置く。なお、manyとmuchはおもに疑問文と否定文で用いられる。manyが主語を修飾するときは、肯定文でも用いられる。too, so, asをともなうと、muchもmanyも肯定文で用いられる。
・Do you have many books on history?
(あなたは歴史に関する本をたくさん持っていますか。)
・We haven’t had much rain this summer. (この夏は雨があまり降っていない。)
・Many students use the school cafeteria. (多くの学生が学食を利用する。)
・Ellis used to spend so much time playing video games.
(エリスはテレビゲームにとても多くの時間を費やしていたものだ。)
・There were so many people at the party.
(そのパーティーにはたくさんの人がいた。)
また、a lot ofとlots ofは数えられる名詞にも数えられない名詞にも用いることができる。ふつうは肯定文で用いられる。どちらも会話でよく用いられる表現で、lots ofはa lot ofよりもくだけた表現である。
・He has a lot of friends in Korea. (彼は韓国にたくさんの友人がいる。)
・Kate drank lots of wine at her birthday.
(ケイトは、誕生パーティーでたくさんワインを飲んだ。)
〈参考〉plenty ofも、a lot of / lots ofと同じようにつかうことができる。
〈参考〉a lot of / lots ofの代わりに次の表現が用いられることがある。
・数が多い
a great[large] number of+数えられる名詞(複数形)
・量が多い
a great deal [a large amount] of+数えられない名詞
2) She had (a few) friends in New York City.
※ 「少ない」を表す形容詞にはfewとlittleがある。fewは数が少ないことを表し、数えられる名詞(複数形)の前に置く。littleは量が少ないことを表し、数えられない名詞の前に置く。a few / a littleとaがつくと、「少しはある/少数の」という、肯定的な表現となるが、単独でfew / littleを用いると、「少ししか[ほとんど]ない」という否定的な表現となる。
・Few students handed in the homework.
(宿題を提出した生徒はほとんどいなかった。)
・Can you add a little pepper to this salad dressing?
(このサラダドレッシングに、少しこしょうを加えてください。)
〈参考〉severalを使うとa fewよりも多い数を表すことができる。
・Several boys are playing cards in the classroom.
(数人の男の子が教室でトランプをしている。)
〈fewとlittleを使った注意すべき表現〉
quite a few[little] 「かなり多くの数[量]の」
・Dr. Jones has quite a few books on ancient civilizations.
(ジョーンズ博士は、古代文明に関する本をかなりたくさん持っている。)
aを用いずにquite few[little]とすると「非常に少ない数[量]の」という意味になることに注意。
only a few[little] 「ほんのわずかの、ほんの少しだけの」
・There’s only a little food left in the refrigerator.
(冷蔵庫にはほんの少ししか食べ物が残っていない。)
not a few[little] 「少なくない数[量]の」
・Jim read not a few books for the report.
(ジムはレポートを書くために、少なからぬ数の[けっこうたくさんの]本を読んだ。)
この表現は文章体で、あまり使わない。
3) This town doesn’t have (many) parks.
※ (この町にはあまり多くの公園がない。)
第22章 副詞(解説)
160「様態」「場所」「時」「頻度」「程度」を表す副詞
( )内の語句のうち、正しいほうを選びなさい。
1) Bob opened (the box carefully).
※ (ボブはその箱を注意深く開けた。)
「様態(動作がどのようであるか)」を表す副詞(fast/well/happily/quietly/carefully/seriously)の文中での位置は、動詞が自動詞の場合はその直後に、また、上記文のように動詞が他動詞の場合は、目的語の直後に置くことが多い。
・They danced happily. (彼らは楽しそうに踊った。)
・She took my advice seriously. (彼女は私の助言を本気で聞き入れてくれた。)
〈参考〉副詞を動詞の前に出すこともできる。
・She quietly came into the room. (彼女は静かに部屋の中に入ってきた。)
目的語が長い場合は動詞の前に置かれることが多い。
・He carefully arranged the pieces of the jigsaw puzzle on the table.
(彼はテーブルの上のジグゾーパズルのピースを慎重に組み合わせた。)
〈注意〉助動詞がある場合の副詞の位置
文に〈助動詞+動詞〉の形があれば、副詞は助動詞の後、つまり助動詞と動詞のあいだに置く。受動態の場合も同様。
・You should carefully look at the broken statue.
(君はその壊れた像を注意深く見るべきだ。)
・The broken statue was carefully examined by the police.
(その壊れた像は警察によって注意深く調べられた。)
2) She (always) goes to school by bicycle.
※ (彼女はいつも自転車で学校に行く。)
「頻度」を表す副詞(always(いつも), usually(ふつう), often(しばしば), frequently(頻繁に), rarelyseldom, sometimes(ときどき), never(決して〜ない))の文中での位置は、一般動詞の前、be動詞・助動詞の後ろが原則。
・He is usually in his office until six on weekdays.
(彼は平日はたいてい6時まで会社にいます。)
・I will never forget what you said. (ぼくは君が言ったことを決して忘れないよ。)
〈参考〉sometimesやusuallyは文頭や文尾に置くこともできる。
「程度」を表す副詞(almost (ほとんど), nearly(ほぼ), barely(かろうじて), completely(完全に/すっかり), hardlyscarcelyなど)は修飾する語句の前に置くのがふつうだが、動詞を修飾する場合は、一般動詞の前、be動詞・助動詞の後ろに置くのが原則。
・The result of the experiment was hardly surprising.
(実験の結果は驚くほどのものではなかった。)
・I have almost finished my homework. (宿題はもうほとんど終わっています。)
〈注意〉almostの使い方
almostは、形容詞や副詞、動詞を修飾して「ほとんど〜」という程度を表す副詞である。
・Almost all the students in our class bring lunch to school.
(私たちのクラスのほとんどすべての生徒は、学校に弁当を持ってくる。)
したがって、次のように名詞を修飾することはできない。
×Almost students in our class bring lunch to school.
mostならmanyの最上級で「大多数の」という意味を表すので、次のように表現できる。
・Most students in our class bring lunch to school.
(私たちのクラスのほとんどの生徒は、学校に弁当を持ってくる。)
3) I’m going to live (in Paris next year).
※ (私は来年パリで住むつもりです。)
「場所」を表す副詞と「時」を表す副詞がいっしょに用いられる場合は、〈場所→時〉の順になることが多い。
・Rome is my favorite city. We must there last summer.
(ローマは大好きな都市です。私たちは昨年の夏そこで出会いました。)
「時」を表す副詞は文尾に置くことが多い。
・The sale started yesterday. (そのセールは昨日始まった。)
・We have a math test tomorrow. (明日は数学のテストがあります。)
〈参考〉「時」を表す副詞を文頭に置くこともできる。
・Tonight I have to do my homework. (今夜は、宿題をしなければならない。)
before, early, late, immediatelyはふつう文頭には出さない。
・You should go to the teachers’ room immediately.
(すぐに職員室に行ったほうがいいよ。)
「時」を表す複数の副詞が用いられる場合は、小さい単位から先に出す。
・I have an appointment at three o’clock tomorrow.
(私は明日の3時に面会の約束があります。)
4) My sister is traveling (abroad) now.
※ (私の妹は今海外旅行中です。)
abroad, homeの使い方
「私は外国へ行きたい」を英語にするときに、×I want to go to abroad.としてしまう人が多い。abroad(外国へ)は副詞なので、前置詞を前に置くことはできない。正しい文は、○I want to go abroadである。同じことがhome(家に)にも言える。「帰宅する」はcome[go] homeで、×come[go] to homeとしない。
「場所」を表す副詞は、動詞が自動詞の場合はその直後に、また動詞が他動詞の場合は、目的語の直後に置くのがふつう。「様態」を表す副詞がある場合は、「場所」を表す副詞の前に置かれる。
・My sister went upstairs. (私の姉は2階に行きました。)
・You can park your car here. (ここに車をとめてもいいですよ。)
・You must read quietly in the library.
(図書館では静かに本を読まなくてはいけません。)
〈参考〉この文のin the libraryのような前置詞句は、副詞として働く。
「場所」を表す複数の副詞が用いられる場合は、小さい単位から先に出す。
I want to live in a small house in the mountains.
(私は山の中の小さな家に住みたい。)
161 文を修飾する副詞
副詞が何を修飾しているのか考え、次の文を日本語に直しなさい。
1) She lives happily with her grandchildren.
(彼女は孫たちと一緒に幸せに暮らしています。)
※ 上記文では副詞happilyが動詞のlivesを修飾している。happilyは「様態」を表す副詞で、動詞を修飾する場合、動詞が上記のように自動詞の場合は動詞の直後に置く。
2) Happily, the typhoon didn’t approach Japan.
(幸いなことに、その台風は日本に接近しませんでした。)
※ 上記文では副詞happilyがthe typhoon didn’t approach Japanという文全体を修飾し、この内容について話し手や書き手がどう感じているかを表している。
文全体を修飾する副詞は、上記文のように文頭に置かれたり(この場合上記文のようにコンマを直後につけることが多い)、一般動詞の前や、be動詞・助動詞の後ろに置かれることが多い。
〈参考〉文修飾の副詞は文尾に置くこともできる。この場合は、副詞の前にコンマを
入れることがある。
・He was dissatisfied with the result, unfortunately.
(残念ながら、彼はその結果に不満だった。)
文を修飾する副詞には、文の内容の確実性に対する話し手の判断を表すobviously(明らかに), clearly(明らかに), probably(おそらく), possibly(もしかしたら)や話し手の気持ちや意見を表すhappily(幸いにも), fortunately(幸運にも), naturally(当然), unfortunately(不幸にも), luckily(幸運にも)などがある。
〈副詞は句や節を修飾することができる〉
副詞は修飾する句・節の直前に置かれることが
① 句を修飾する
My house is just behind my school. (私の家は学校のちょうど裏にある。)
② 節を修飾する
He wants a computer only because you have one.
(彼は君が持っているという理由だけで、コンピュータをほしがっている。)
〈名詞や代名詞を修飾する副詞〉
名詞や代名詞を修飾する副詞もあるが、次のような一部の副詞に限られる。
① 時や場所を表す副詞が名詞を後ろから修飾する。
In Japan, most teenagers nowadays want to own a smartphone.
(日本の最近の10代の人たちはスマートフォンを持ちたがる。)
② quite, even, onlyが名詞や代名詞の前に置かれる。
・He is quite a stranger to me. (彼は私がまったく知らない人です。)
・Everyone was late. Only he came here on time.
(みんな遅れてきた。彼だけが時間どおりここに来た。)
162 注意すべき副詞の形と意味
( )内の語句のうち、正しいほうを選びなさい。
1) Mayumi is sometimes (late) for school.
※ (まゆみは時々学校を遅刻する。)
late(遅く)とlately(最近)
・My father came home very late last night.
(父は昨夜、大変遅く家に帰ってきた。)
・He has been trying to loose weight lately. (彼は最近、減量にはげんでいる。)
2) I can (hardly) believe the news.
※ (私はその知らせがほとんど信じられない。)
hard(熱心に)とhardly(ほとんど〜ない)
・He always works hard. (彼はいつも熱心に働く。)
・I hardly know him. (私は彼のことをほとんど知らない。)
3) The boy (nearly) fell into the river.
※ (その少年は川に落ちかけた。)
near(近くに)とnearly(ほぼ)
・He came near to me. (彼は私の近くに来た。)
・My homework is nearly finished. (宿題はほぼできています。)
most(もっとも)とmostly(たいていは)
・This picture interested me most. (私はこの絵にもっとも興味をもちました。)
・She mostly goes shopping on Sundays.
(彼女はたいてい日曜日に買い物に行く。)
〈形容詞と副詞〉
副詞には、形容詞に-lyをつけたものが多い。しかし、形容詞の語尾によっては、単に-lyをつけるだけではいけないこともあるので注意。
slow → slowly [基本]
happy → happily [yで終わる語はyをiに変えてlyをつける]
probable → probably [leで終わる語はleをlyにする]
true → truly [ueで終わる語はeをとってlyをつける]
full → fully [llで終わる語はllをllyにする]
語尾が-lyであっても副詞であるとは限らない。次のような形容詞に注意。
friendly(友好的な), lonely(孤独な), lovely(すてきな)など
このような形容詞には、上のfriendlyやlovelyのように名詞に-lyがついたものが多い。
次のように、形容詞と副詞が同じ形の語もある。
・The question is hard to answer. (その問題は答えるのが難しい。)[形容詞]
・He works hard.(彼は熱心に働く。)[副詞]
形容詞と副詞が同じ形の語には次のようなものがある。
early(形:早い/副:早く)、fast(形:速い/副:速く)、last(形:最後の/副:最後に)、long(形:長い/副:長く)、far(形:遠い/副:遠くに)、well(形:健康な/副:よく)、
pretty(形:きれいな/副:かなり)など
163 very/much/ago/before/already/yet/still/too/either/neither
( )内の語のうち、適切なほうを選びなさい。
1) I met him two weeks (ago).
※ (私は2週間前に彼に会いました。)
agoとbeforeはどちらも「時間の長さ」を表す語句の後ろに置かれ、~ago, ~beforeで「~前」を表す。
agoが現在を基準にして、「(今より)~前」を表すのに対し、beforeは過去のある時点を基準にして、「(その時より)~前」を表す。上記文は現在よりも「2週間前」のことであるのでagoを用いる。次のように過去の時点から見た「2週間前」の場合はbeforeを用いる。
・I told her that I had met him two weeks before.
(私は彼女に、2週間前に彼に会ったと言った。)
beforeは次のように単独で用いられると、「今までに、以前に」という意味となり、過去または現在完了の文で用いることができる。
・I have heard that song before.(私はあの歌を前に聞いたことがある。)
また、次のように「過去のある時点よりも前」を表す場合もあり、この場合は過去完了が用いられる。
・I knew I had met her before, but I couldn’t remember where.
(以前彼女に会ったことがあるのはわかっていたのだが、どこで会ったのか
思い出せなかった。)
〈参考〉agoは単独では用いない。
2) This is a (very) interesting novel.
※ (これはとてもおもしろい小説です。)
very:形容詞や副詞を修飾
very(とても)形容詞を修飾したり次のように副詞を修飾したりする。また、上記文のinterestingやboring, excitingのような、形容詞化した現在分詞を修飾したり、tired, surprised, shocked, confusedのような形容詞化した過去分詞も修飾する。
・She speaks very slowly. (彼はとてもゆっくり話す。)
・This is a very boring documentary.
(これはとても退屈なドキュメンタリーだ。)
・I’m very pleased.(私はとてもうれしい。)
・I was very surprised at the news.(私はその知らせにとても驚いた。)
much:動詞や過去分詞を修飾
much(とても)は、動詞を修飾する。mcuhが単独で用いられるのは疑問文と否定文の場合である。肯定文で用いられるときは、very muchの形になる。また、形容詞化しておらず、状態ではなく、動作を表す過去分詞を修飾する。
・I don’t eat out much.(私はあまり外食をしません。)
・I like the song very much.(私はその歌がとても好きです。)
・He is much admired by young writers.
(彼は若い作家からとても尊敬されている。)
〈参考〉過去分詞を修飾するのに、veryやmuch以外の副詞を使うこともできる。
・I’m terribly pleased.(私はものすごくうれしい。)
・I was absolutely exhausted.(私はへとへとに疲れていた。)
muchは、形容詞と副詞の比較級および形容詞の最上級も修飾する。
3) She didn’t go to the party, and I didn’t, (either).
※ (彼女はそのパーティーに行かなかった。そして私も行かなかった。)
eitherは否定文で、tooは肯定文で用いられ、「…もまた~」という意味を表す。
・“I’m from Arizona.” “Really? I am, too.”
(「私はアリゾナの出身です。」「本当?私もそうです。」)
口語ではMe, too.と答えることが多い。
・“I can’t eat raw fish.” “I can’t, either.”
(「私は生の魚を食べられません。」「私もだめです。」)
口語ではMe, neither.と答えることが多い。
先に述べられた否定文を受けて、「〈主語〉も(また)そうでない」というときは、次のようneither[nor]を使って、〈neither[nor]+(助)動詞+主語〉という語順にする。
・“I don’t feel like eating any more.” “Neither[Nor] do I.”
(「もうこれ以上食べたくありません。」「ぼくもだよ。」)
4) I haven’t received the card (yet).
※ (私はまだそのカードを受け取っていない。)
yet
yetは否定文で用いられ、「まだ(~ない)」という意味を表す。疑問文で用いられると「もう/すでに」という意味になる。
・Have you typed that paper yet?
(君はもう、そのレポートをタイプしましたか。)
already
alreadyは「もう/すでに」という意味で肯定文で用いられることが多い。
I have already cleaned my room.(私はすでに自分の部屋のそうじをしました。)
疑問文や否定文で用いると、意外感や驚きを表す文になる
・Have you vacuumed the carpet already?
(もうカーペットにそうじ機をかかけてしまったの。)
still
stillは肯定文で用いられ、「まだ」という継続の意味を表す。疑問文でも用いることができる。否定文で用いることもあるが、その場合は否定語の直前に置く。
・I’m still feeling sick.(私はまだ気分が悪い。)
・Are you still feeling dizzy?(まだめまいがしますか。)
・I still can’t find a new apartment.
(私はまだ新しいアパートを見つけることができていない。)
164 so
日本語の意味に合うように、与えられた語句を並べかえなさい。
1) 「ナンシーはパーティーに来るの?」「ええ、たぶん。」
“Is Nancy coming to the party?” “(I guess so).”
※ soは前に出た節の内容を表す
上記文ではsoがguessの後に置かれ、肯定形のthat節と同じ意味を表している。つまり、I guess (that) Nancy is coming to the party.ということである。否定形のthat節の意味を表す場合は、I’m afraid not.のような形になる。
このsoは、think, hope, expect, believe, say, tell, hear, suppose, guess, imagineのような動詞の後に置かれることが多い。
“Do you think it will be sunny tomorrow?” “I hope so.”
(「明日は晴れると思うかい?」「そうだといいね。」)
do soで前に出た動詞句の内容を表す
・He told me to wait in a line and I did so.
(彼は私に並んで待つように言ったので、私はそうした。)
上記文では、soがdidの後に置かれ、すでに述べられた動詞表現のくり返しを避けるために用いられている。このdid soはwaited in lineという意味である。
2) 私は昨日学校に遅刻したが、兄もそうだった。
I was late for school yesterday, and (so was my brother).
※ so VS「〈主語〉もそうだ」
上記文のような〈so+(助)動詞+主語〉の形にすると「主語もまたそうだ」という意味になり、それ以前に述べられた内容が主語についても当てはまることを表す。この場合は主語を強く発音する。主語が伝えたい情報だからである。
・I often go to the library, and so does my sister.
(私はよく図書館に行きますし、姉もそうです。)
so SV「本当にそうだ」
・They say the greatest gift we have is our health, and so it is.
(最高の贈り物は健康であると言われるが、実際そのとおりである。)
上記文のような〈so+主語+(助)動詞〉の形にすると「本当にそうだ」という意味を表す。それ以前に述べられた文の内容を認めるときに用いるので(助)動詞を強く発音する。
・“It is getting dark in this room.” “So it is.”
(「部屋の中が暗くなってきましたね。」「そうですね。」)
165 2つの文の論理関係を表す副詞
( )内の語のうち、正しいほうを選びなさい。
1) Let’s take a taxi. It’s getting dark. (Besides), it’s starting to rain.
※ (タクシーに乗ろう。暗くなってきた。そのうえ、雨が降りだしている。)
上記文のBesidesは「そのうえ」という意味で前の文の内容をつなぐ働きをする。
2つの文の論理関係を表す副詞には、次のようなものがある。
otherwise(さもないと)
furthermore / moreover(さらに)
besides(そのうえ)
therefore / thus(したがって)
hence(それゆえ)
nevertheless(それにもかかわらず)
nontheless(それでもなお)
・Hurry up; otherwise we won’t get god seats.
(急ごう。さもないとよい席がとれないよ。)
・This computer is very good. However, it is too expensive.
(このコンピュータはとてもよい。しかし、値段が高すぎる。)
・I haven’t seen that movie. Therefore I can’t talk about it.
(私はその映画を見たことがないので、それについて話すことはできません。)
2) I tried hard to solve the problem. (However), I couldn’t.
※ (私は懸命にその問題を解こうとした。しかしできなかった。)
副詞と前置詞
これらの副詞は、2つの文がどういうつながりになっているかを示すものなので、使い方の点で接続詞とは区別しなければならない。例えば、I slept nine hours last night.(昨夜は9時間寝た。)という英文と、I’m still sleepy.(まだ眠たい。)という英文をつなぐ場合には、次のようにする。
I slept nine hours last night. However, I’m still sleepy.
I slept nine hours last night, but I’m still sleepy.
×I slept nine hours last night, however I’m sleepy.
[howeverは副詞なので、接続詞のように、2つの文を1つにすることはできない。]
第23章 前置詞(解説)
166 at / in / on
( )内の前置詞から、正しいものを選びなさい。
1) I saw your father standing (at) the bus stop.
※ (私はあなたの父がバス停で立っているのを見ました。)
at
atは〈一点〉を表すのが基本。上記文では「バス停」を〈場所の一点〉と考えるためatが用いられている。
また、次のように〈時の一点〉の場合もatが用いられる。
The meetings usually begin at ten.(会議はふつうは10時に始まる。)
会議が「始まる」のが、10時という〈時の一点〉なので、atを用いている。「10時から始まる」と日本語で考えて、fromを用いないように注意。
■ atの意味の広がり
● 目標
He aimed his bow and arrow at the target.
(彼は標的に弓矢を向けてねらいをつけた。)
● 所属
Lisa is a student at Prinston.(リサはプリンストン大学の学生です。)
● 従事
James is at work in the computer room.
(ジェームスはコンピュータ室で仕事中です。)
at table(食事中)、at school(在学中で)
● 状態
I feel at ease when I’m with you.(私はあなといるとくつろぐ。)
at a loss(途方にくれて)
● 価格・速度
I bought this coat at a discount.(私はこのコートを割引価格で買った。)
I was driving at forty miles per hour.
(私は時速40マイルで車を走らせていた。)
● 関連点
Susie is good at swimming.(スージーは水泳が得意だ。)
● 極限
The garden is at its best in June.(その庭は6月が最高だ。)
at (the) least(少なくとも)、at (the) worst(悪くとも)
● 感情の原因
We were surprised at his bad manners.(私たちは彼の無作法さに驚いた。)
in
場所に関するinは、立体の中を表すのが基本。
I happened to see Cindy in the theater.
(劇場の中でたまたまシンディーに会った。)
時に関するinはある期間の中を表す。「~という期間の中のある時に→~に」
I first visited Germany in 1991.(私は1991年に初めてドイツを訪れた。)
■ inの意味の広がり
● 運動の目標
I threw the letter in the fire.(私は炎の中に手紙を投げ込んだ。)
● 着用
I dressed in my best clothes to go to the opera.
(私はオペラに行くのに、一番よい服を着た。)
● 状況・環境
Don’t go out in the rain.(雨の中を出ていくのはやめなさい。)
● 状態
I’m in love with her.(私は彼女に恋をしている。)
● 従事
He is in publishing.(彼は出版関係の仕事をしている。)
● 関心の範囲
I am interested in Chinese history now.(私は今、中国史に関心がある。)
● 手段・方法
Please sign your name here in ink.(ここにインクでご署名ください。)
speak in English(英語で話す)
● 形態
The students stood in a line.(生徒達は一列になって立っていた。)
● 時の経過
I think he’ll be a millionaire in a year.
(1年後には、彼は大金持ちになっていると思う。)
〈時間の長さ〉に関する表現がinの後に置かれると、in~は「(現在を始点にして)~後に」の意味で使われる。この意味ではafterは使えない。
on
場所に関するonは線や平面との接触を表す。「~の上の」と訳せることも多いが、onは場所の上下のではなく、接触を表すことに注意。
・Pick up those toys on the table.
(テーブルの上のおもちゃを取って来なさい。)
・There is a fly on the ceiling.(天井にハエがいる。)
時に関するonは特定の日を表す。特定の日にちや曜日、特定の日を表す場合に用いる。
How about having dinner on Christmas Eve?
■ onの意味の広がり
● 接近
He owns a bookstore on Oxford Street.
(彼はオクスフォード通りに書店を所有している。)
a house on the river(川沿いの家)
● 動作の対象
He is concentrating on this experiment.(彼は実験に集中している。)
wait on~(~に仕える)
● 主題
He wrote an essay on modern pop music.
(彼は現代のポップミュージックについての評論を書いた。)
speak on~(~について講演する)
〈注意〉主題を表すonとabout
学問的で、専門家向けの主題を表すときはonを用い、一般的な内容に関するときはaboutを用いるのがふつう。
a book on ancient Roman art(古代ローマ美術に関する本)
a book for children about animals(子ども向けの動物に関する本)
aboutは「~について」という話題を表すときによく用いられる。
What are you talking about?(何について話しているの?)
● 依存
Don’t depend on others.(他人に頼るな。)
rely on~(~に頼る)、count on~(~をあてにする)
● 手段・方法
I usually go to school on foot.(私はふだんは歩いて学校に行く。)
speak on the phone(電話で話す)、watch a drama on television(テレビでドラマを見る)
● 状態・進行
The house is on fire.(その家が火事だ!)
on duty(仕事中で)、on sale(販売中)
● 同時
On getting home, I phoned Mik.(家に着くとすぐに、私はマイクに電話した。)
2) I usually get up (at) ten (on) Sundays.
※ (私は日曜日はふつう10時に起きます。)
時を表すon / at / inの使い分け
上記文のようにonは時刻よりは時間の幅の広い、日付や曜日を表すときに使うのが基本。
atは〈時の一点〉、つまり時刻を表すときに使うのが基本。
・We left the hotel at 10 a.m.(私たちは午前10時にホテルを後にした。)
inは日付や曜日よりも時間の幅がさらに広い、月・季節・年・世紀などに使う。
・Sally graduated from college in 1995.(サリーは1995年に大学を卒業した。)
〈morning / afternoon / eveningと前置詞〉
Jim often goes to the pub in the evening.
(ジムは夕方、そのパブに行くことがよくある。)
一日の中の部分(= morning / afternoon / evening)にはinを使う。nightの場合は、at nightとする。
ただし、ある特定の日の場合は、morning / afternoon / eveningだけでなく、nightの場合もonを使う。
・My sister was born on the night of July 7.
(私の姉は7月7日の夜に生まれた。)
167 from / to / for
日本語の意味に合うように、( )に適切な前置詞を入れなさい。
1) 私たちはパリからロンドンまで飛行機で飛んだ。
We took the plane (from) Paris (to) London.
※ fromは動作や運動なのど〈出発点・起点〉を表すのが基本。from A to B(AからBへ)のように、到着点を示す語句とともに用いられることも多い。
・I’ll be on vacation from July 24.(私は7月24日から休暇をとります。)
■ fromの意味の広がり
● 出身・起源
Steve is from Australia.(スティーブはオーストラリアの出身だ。)
● 分離
We must protect children from violence.
(私たちは子どもたちを暴力から守らなければならない。)
keep away from~(~に近づかない)、prevent O from ~ing(Oが~するのを妨げる)、prohibit O from~ing(Oが~するのを禁止する)
● 原因・根拠
He is suffering from a stomachache.(彼は腹痛に苦しんでいる。)
die from~(~が原因で死ぬ)、result from~(~から結果として生じる)
● 区別
Your viewpoint is totally difficult from mine.
(あなたの根拠は、私の根拠とまったく異なる。)
distinguish A from B / tell[know] A from B(AとBを区別する)
● 原料
Butter is made from milk.(バターは牛乳から作られている。)
材料に変化がある場合はfrom、変化ない場合はofを使う。
to
toは「~に向かって」という〈方向〉を表すが、方向だけでなく〈到達点〉を含んでいる。また、結合・付着も表し「何かにくっつく」というイメージがある。
・Let’s go to the park and feed the ducks.
(公園に行ってアヒルにえさをやろう。)
・Attach your name tag to your bags, please.
(かばんに名札をつけてくださいね。)
■ toの意味の広がり
● 行為の相手
He suddenly spoke to me.(彼は突然私に話しかけた。)
● 範囲・限界
I got wet to the skin.(びしょぬれになった。)
to some extent(ある程度まで)
● 結果
Eat to your heart’s content.(心ゆくまでたべなさい。)
〈参考〉to one’s joy[sorrow / disappointment / surprise / relief]で、「~が喜んだ
[悲しんだ/がっかりした/驚いた/ほっとした]ことに」という意味になる。
To my surprise, Sam was awarded the first prize.
(驚いたことに、サムは1等賞を与えられた。)
● 一致
I hope this gift is to your liking.
(この贈り物が君の好みに合っているといいのだが。)
● 比較
I think this novel is superior to that one.
(あれよりもこの小説のほうが優れていると思う。)
prefer A to B(BよりもAが好きだ)
2) 私はジュリアのためにダイヤモンドの指輪を買った。
I bought a diamond ring (for) Julia.
※ forは上記文のように利益・目的・追求の意味を表す。
They held a farewell party for me.
(彼らは私のために送別会を開いてくれた。)
The politicians are campaigning for the coming election.
(政治家たちは次の選挙のために選挙活動をしている。)
for
forは、場所を表す名詞が続くと、「~に向かって」という〈目標へ向かう方向〉を
表す。時を表す名詞が続くと、「~のあいだ(ずっと)」という〈期間〉を表す。for
ages(長いあいだ)もこの用法。
■ forの意味の広がり
● 対象
I’m looking for Martin.(マーティンを探しています。)
I recommend this racket for a beginner.
(初心者にはこのラケットをすすめます。)
care for~(~の世話をする)
● 交換・代用・代価
I took Steve for his brother.(スティーブを彼のお兄さんと間違えちゃった。)
I paid 10,000 yen for these sneakers.
(ぼくはこのスニーカーに1万円払った。)
stand for~(~を表す)、exchange A for B(AとBを交換する)、for nothing(無料で)
● 原因・理由
Joe was fined for speeding.(ジョーはスピード違反で罰金をとられた。)
for this reason(この理由で)、be famous for~(~で有名だ)
● 支持・賛成
Are you for his proposal?(彼の提案に賛成ですか。)
「反対」はagainstで表す。(Are you against his proposal?)
3) 冬休みのあいだにこの本を読んでみたら?
Why don’t you read this book (during) winter vacation?
※ 期間を表すfor / during / in の使い分け
duringは上記文の「冬休みのあいだ」のように、どういう期間なのかを表すときに使われる。forはあることがどのくらいの期間続いたかとう「長さ」を表す。
・I slept for ten minutes during the meeting.
(会議中に10分間寝てしまった。)
in は何かをするのにかかる時間を表すときに使われる。
・He learned how to use a computer in three weeks.
(彼はコンピュータの使い方を3週間で覚えた。)
・Can you finish this job in a day?
(この仕事を1日でできますか。)
168 of / by / until / with
日本語の意味に合うように、( )に適切な前置詞を入れなさい。
1) 彼は18歳で両親から独立した。
He became independent (of) his parents at the age of eighteen.
※ ofは〈分離〉を表し、上記文のように、heとhis parentsを引き離すような意味で使われる。be independent of ~(~独立している)、rob A of B(AからBを奪う)、derive A of B(AからBを奪う)。
■ ofの意味の広がり
● 部分
Three of my classmates got full marks in math.
(級友のうち3人が、数学で満点をとった。)
● 原因・理由
Mr. Jones died of cancer.(ジョーンズ氏がガンで亡くなった。)
● 材料
This pendant is made of crystal.(このペンダントは水晶でできている。)
〈ofとfromの使い分け〉
原因と材料/原料に関して、ofとfromの使い分けには次ような原則がある。
・原因:直接の原因はof、間接的な原因はfromを用いる。
Mr. Jones died of cancer.(ジョーンズ氏はガンで亡くなった。)
In some countries many people die from poverty.
(多くの人が貧困のために亡くなる国もある。)
・材料/原料:材料/原料に変化がなければofを、加工されて変化していればfromを用いる。
This jacket is made of leather.(このジャケットは革製だ。)
This burger is made from soybeans.(このバーガーは大豆でできています。)
ただし、これらの使い分けはあくまでも原則にすぎず、実際には区別せずに使うことが多い。
● 関連
I like to read stories of adventure.
(私は冒険(についての)小説を読むのが好きだ。)
remind A of B(AにBを思い出させる)もこの用法。
● 特徴・性質
Mr. Hamilton is a man of ability.(ハミルトン氏は有能な人だ。)
● 同格
The three of us went there.(私たち3人がそこに行った。)
2) 突然、知らない人から話しかけられた。
Suddenly, I was spoken to (by) a stranger.
※ byは上記文のように動作主を表すときに用いられることが多い。また、「~のそば/~の隣」という〈近接〉の意味を表すのが基本。
That man standing by Janet is Scott.
(ジェーンの隣に立っているあの男がスコットだ。)
That strange building was designed by my uncle.
(あの風変りな建物は、私のおじの設計です。)
■ byの意味の広がり
● 手段・方法
I reserved a hotel room by e-mail.(メールでホテルの部屋を予約した。)
by train(電車で)、by car(車で)もこの用法。
● 時間の期限
I’ll be back by 3:30.(3時半までには戻ります。)
● 差異
I missed the train by two minutes.(私は2分の差で、その列車に乗り遅れた。)
● 単位
Eggs are sold by the dozen.(卵はダース単位で売られる。)
● 経由
He came in by the back door.(彼は裏口から入ってきた。)
● 判断基準
You shouldn’t judge a person by his or her appearance.
(外見で人を判断すべきではない。)
3) 父は8時には家に帰っているでしょう。
My father will come home (until) eight o’clock.
※ byとuntilの使い分け
byは〈期限〉を表し、その時までに動作が完了することを表す。
・You must finish this job by noon.
(君はこの仕事を正午までに終えなければならない。)
until[till]は〈継続〉を表し、その時まで動作が続くことを表す。
・I waited for his call until[till] midnight.
(私は夜中の12時まで彼からの電話を待った。)
4) トムはナイフでそのロープを切った。
Tom cut the rope (with) a knife.
※ withは上記文のように道具・材料の意味を表す場合がある。
・Vicky ate her ramen with a fork.(ビッキーはラーメンをフォークで食べた。)
・He filled the bottle with spring water.
(彼はボトルにわき水をいっぱい入れた。)
〈注意〉交通や通信の手段を表す場合にはbyが用いられる。
・I want to send this letter by airmail.
(この手紙を航空便で送りたい。)
withは「~と一緒に」という〈同伴〉を表すのが基本。また、何かとの関係や関連を表すときにも用いられる。
・Come with me, please.(一緒に来てください。)
・Something is wrong with this computer.
(このコンピュータはどこかおかしい。)
・I have nothing to do with the robber.(私はその強盗とは何の関係もない。)
■withの意味の広がり
● 対象
I agree with you.(私はあなたと同意見です。)
argue with~(~と口論する)も同じ用法。
● 原因
She is busy with her homework.(彼女は宿題で忙しい。)
● 所有・携帯
I’m looking for an apartment with a garage.
(私は車庫つきのアパートを探している。)
I have no money with me.(私はお金の持ち合わせがありません。)
● 様態
She solved the problem with ease.(彼女は簡単にその問題を解いた。)
● 付帯状況
He entered the dark house with his legs shaking with fear.
(彼は恐怖で足をふるわせながら暗い家に入った。)[with fearのwithは「様態」を表す。]
169 about / after / before / along / across / through / around / in front of / behind / opposite / into / out of / onto / over / under / above / below / between / among
日本語の意味に合うように、( )に適切な前置詞を入れなさい。
1) この川は森を抜けて、海へ注いでいます。
This river runs (through) the forest and flows into the sea.
※ through
throughの基本的なイメージは「中を通り抜ける」
・I can see him through the windows.(窓越しに彼の姿が見える。)
throughが時について使われると、「~のあいだじゅう/~のはじめから終わりまで」
の意味になる。
・He lived in Texas all through the 1950s.
(彼は1950年代をずっとテキサスで暮らした。)
along
alongの基本的なイメージは「線に沿って進む」。
・We walked along the river.(私たちは川沿いに歩いた。)
across
acrossの基本的なイメージは「平面を横切って」。
・The man tried to swim across the channel.
(その男は海峡を泳いで渡ろうとした。)
acrossには、「~の向こう側に」という意味もある。
・My house is just across the street.(私の家は通りのちょうど向こう側です。)
2) その家の裏には、きれいな庭があった。
There was a beautiful garden (behind) the house.
※ behind
behindは「~の後ろに[裏に]」を表す。behindが時について使われると「〈定刻
など〉に遅れて」という意味になる。
・The concert started 30 minutes behind schedule.
(コンサートは予定より30分遅れて始まった。)
in front of
in front of は「~の前に[正面に]」を表す。
・Don’t park your car in front of this building.
(このビルの前に車をとめないでください。)
opposite
oppositeは「(通りなどをへだてて)~の向かいに」の意味。この意味ではacross (the street[road]) fromとすることも多い。
・The bank is opposite that building.(銀行はあのビルの向かいにあります。)
= The bank is across the street[road] from that building.
into / out of / onto
intoは「~の中へ」、out of は「~の中から外へ」、ontoは「~の上へ」が基本的な意味。なお、intoには「~に(なって)」という〈変化〉を表す用法もある。
・Please go into the living room.(どうぞリビングルームにお入りください。)
・Would you translate this sentence into English?
(この文を英語に訳していただけませんか。)
・Come out of the kitchen now!(すぐに台所から出てきなさい!)
・The cat jumped onto the TV set.(そのネコはテレビの上に飛び乗った。)
3) マイクの点数は平均より下だった。
Mike’s score was (below) average.
※ below / above
上記文のようにbelowとaboveはある基準よりも上か下かを表すときに用いられ
る。
・The temperature remained below zero.(気温は零度以下のままだった。)
・Your score is above average.(君の点数は平均より上だよ。)
belowは「~よりも低いところに/~よりも下に」のような意味で、aboveは「~よ
りも高いところに/~よりも上に」のような意味で使われる。
・The sun sank below the horizon.(太陽は地平線の下に沈んだ。)
・The people above us are very noisy.
(私たちの上の階の人たちはとても騒がしい。)
over / under
overとunderは垂直的な位置関係を表す。
overは〈上〉を表し、「~の上に/~の上の方に」のような意味で使われる。〈真上〉
を含み、「上の方で覆っている」というイメージがある。
・The rain clouds were over our heads.(雨雲が私たちの頭上にあった。)
〈移動を表す動詞とともに使われるover「~を超えて向こう側に」〉
The dog jumped over the fence.(その犬は塀を飛び越えた。)
〈接触を表すover「~の上を(部分的、または全体に)覆って」〉
He spread a plastic sheet over the table.
(彼はビニールシートをテーブルの上に広げた。)
〈注意〉overの注意すべき用法
① 「(数量などが)~を超えて」
He is well over 50 years old.(彼はゆうに50歳を超えている。)
② (話す・眠るなどの意味の動詞とともに)「~しながら/~に従事して」
We talked over a cup of coffee.
(私たちはコーヒーを飲みながら話をした。)
underは〈下〉を表し、「~の下に/~の下の方に」のような意味で使われる。overとは逆に〈真下〉を含み、「下の方に空間などが広がっている」というイメージがある。
・I found my key under the desk.(私はカギを机の下で見つけた。)
〈注意〉underの注意すべき用法
① 「~のもとで」
The team won the game under the new coach.
(チームは新しいコーチのもとでその試合に勝った。)
② 「〈動作・行為〉中で/~されていて」
This bridge is under construction.(この橋は建設中です。)
③ 「~(の状況)で」
I don’t want to work here under such conditions.
(そのような条件では、ここで働きたくない。)
4) 子どもたちがウサギのまわりに集まった。
The children gathered (around) the rabbit.
※ aroundの基本的なイメージは「~のまわりに(ぐるりと)」。「~のあちこちに」という意味もある。
・We walked around the small town.
(私たちはその小さな町のあちこちを歩き回った。)
5) 私は松林の中に小さな小屋を見つけた。
I found a small cabin (among) the pine trees.
※ between / among
betweenは、あるものとあるもののあいだに位置していることを表し、amongはあ
る集団に囲まれていたり、含まれていたりするときに用いる。
・Peter sat between Allison and Jane.
(ピーターはアリソンとジェーンのあいだに座った。)
・He disappointed among the people in the crowd.
(彼は群衆の中に消えた。)
〈注意〉amongの注意すべき用法
〈among+最上級+名詞の複数形〉は、「もっとも~な…の1つ」という意味。
・He is among the most popular comedians in Britain.
= He is one of the most popular comedians in Britain.
(彼はイギリスでもっとも人気のあるコメディアンの1人です。)
170 群前置詞
日本語の意味に合うように、( )に適語を入れなさい。
1) 病気のため、彼は旅行をキャンセルしなければならなかった。
He had to cancel the trip (because) (of) ill health.
※ because of = owing to = due to (~のせい[理由]で)
2) 家にいないで、外に出よう。
Let’s go out (instead) (of) staying home.
※ instead of (~の代わりに/~しないで)
群前置詞
① 2語からなる群前置詞
according to(~によれば), apart from(~から離れて/~を別にすれば), as for(~について言えば), as to(~については), because of(~が原因で), but for(~がなければ), due to(~のために), instead of(~のかわりに) , owing to(~のために), thanks to(~のおかげで), up to(~まで), with all(~にもかかわらず) など
② 3語以上からなる群前置詞
as far as(~まで), at the risk of(~の危険を冒して), by means of(~によって), by way of(~経由で), for fear of(~を恐れて/~しないように), for the sake of(~のために), in addition to(~に加えて), in case of(~の場合には), in front of(~の前に), in spite of(~にもかかわらず), on account of(~のために), on behalf of(~に代わって)), with regard to(~に関して)など
第24章 接続詞(解説)
171 等位接続詞の用法(and, but, or, nor, so, for)
日本語に合うように、( )内のうち、正しいほうを選びなさい。
1) 彼は野球選手であるだけではなく、フットボールの選手でもある。
He is not only a baseball player (but) also a football player.
※ not only A but (also) B
not only A but (also) Bは「AだけでなくBも」という意味で、Bのほうに重点が置かれる。as well asを使ってほぼ同じ意味を表すことができるが、B as well as Aという語順になって、前のBのほうに重点が置かれる。(not A but Bは「AではなくB」の意味)
= He is a football player as well as a baseball player.
〈参考〉not only A but (also) Bで、not onlyが文頭に出て倒置が起こることがある。
Not only a baseball player but (also) a football player is he.
〈参考〉not A but B / not only A but (also) Bの表現では、butで結ばれるとAとB
に、節や句が入ることもある。
・The question is not how he did it, but why he did it.
(問題は、彼がどうやってそれをしたのかではなく、なぜそれをしたのかだ。)
・I was fascinated not only by his smile but also by his voice.
(私は彼のほほえみだけでなく、声にも魅了された。)
〈参考〉as well as の後に動詞を続ける場合は、ing形にすることがある。
・He not only plays the guitar, but also sings.
・He sings as well as plays the guitar.
・He sings as well as playing the guitar.
(彼はギターを弾くだけではなく、歌も歌う。)
not A but B
not A but Bは「AではなくB」という意味。
・He has not one but two computers.
(彼は1台ではなく2台のコンピュータを所有している。)
and「…と〜」
andの基本は複数のものをつなぐことである。節と節、語と語、句と句を結ぶことができる。
・Gary arrived and we started the game.
(ゲーリーが到着して、私たちはゲームを始めた。)
・I bought a cheeseburger and French fries.
(私はチーズバーガーとフライドポテトを買った。)
〈参考〉3つ以上の語句をつなぐ場合は、最後の語句の前だけ
andをつければよい。例えば3つの語句をつなぐ場合はA,B(,) and Cとする。and の前のコンマは省略してもよい。
・He speaks English, German(,) and Chinese.
(彼は英語とドイツ語と中国語を話す。)
〈come and seeの表現〉
〈動詞+and+動詞〉の形で、〈動詞+to不定詞〉の意味を表すことがある。
・Come and see me tomorrow evening. (明日の夕方、会いに来てください。)
come and seeはcome to seeとほぼ同じ意味で使われている。この文のように命令文で使われるのがふつう。同様の表現にgo and see (〜を見に行く)やtry and see (〜を見ようと試みる)などがある。
but「…だが〜」
butは、butの前と後が内容的に対立することを表すときに用いられる。
・I thought the story was true, but it wasn’t.
(その話は真実だと思っていたが、そうではなかった。)
〈It is true … but〜 / may … but〜 / indeed … but〜〉
これらはいずれも「確かに…だが、〜だ」という〈譲歩〉を表す表現である。この場合は、but 以下に意味の重点が置かれている。
・It’s true that used cars are cheap, but they’re not always reliable.
(確かに中古車は安いが、安心して使えるとは限らない。)
・Pet cats may be cute, but they’re difficult to look after.
(ペットのネコはかわいいかもしれないが、世話をするのが大変だ。)
〈譲歩〉とは、自分の主張にとって都合の悪い事実を認めたうえで、それでもなお自分の主張は変わらないということを述べる表現方法のことである。
or「…か〜」
orは選択の対象を並べる場合に用いる。
I want to go to Hong Kong or Singapore this summer.
(私はこの夏、香港かシンガポールに行きたい。)
Shall we go shopping or stay at home?
(買い物に行きましょうか。それとも家にいますか。)
〈参考〉3つ以上の語句をつなぐ場合は、最後の語句の前にだけorをつければよい。
例えばA, B(,) or Cとする。Orの前のコンマは省略してもよい。
・Will you have tea, coffee(,) or orange juice?
(お茶、コーヒー、オレンジジュースはいかがですか?)
〈否定文で使われるor〉
否定文でorが使われると、「どちらも…ない」という意味になる。この場合、andは使わないことに注意。
・The road was not very wide or easy to find.
(その道はそれほど広くもなく、見つけやすくもなかった。)
〈参考〉ある語句をその直後で言い換えるときに、orを用いて「すなわち、言い換えれば」の意味を表すことができる。orの前にはふつうコンマを置く。
・I’m majoring in psychology, or the science of the mind.
(私は心理学、すなわち心の科学を専攻しています。)
2) 寒くなってきた。それで私たちは家に帰った。
It was getting colder, (so) we went home.
※ soは〈結果〉を後に続け(出来事→結果)、forは〈理由や根拠〉を後に続ける(結果←理由)。この2つの接続詞には、節と節を結ぶ用法しかない。また、直前にコンマを置くのがふつう。
・You broke up the speed limit, so you’ll have to pay a fine.
(スピード違反をしたので、罰金を払わなければならないでしょう。)
・I got up at five, for I wanted to watch the sunrise.
(私は5時に起きた。というのも、日の出を見たかったからだ。)
〈参考〉forはややかたい表現で、口語で用いることはあまりない。
3) パーティーにいったほうがいいよ。そうしないと彼女に会う機会を逃してしまう。
You should go to the party, (or) you will miss the chance to see her.
※ 命令文+or
命令文や上記文のようにshould, must, had betterを使った文の後にorがつかわれると、「そうしないと…」という意味を表す。
・Drive more slowly, or you’ll have an accident.
(もっとゆっくり運転しなさい。そうしないと事故を起こしますよ。)
・You had better take a taxi, or you’ll miss your train.
(タクシーにのりなさい。そうしないと電車に乗り遅れるよ。)
命令文+and
命令文の後でandが使われると、andは「そうすれば…」という意味を表す。
・Get up early tomorrow, and you’ll have time to eat breakfast.
(明日の朝早く起きなさい。そうすれば朝ごはんを食べる時間があるよ。)
4) 私の兄も私も早起きだ。
Bothe my brother (and) I are early risers.
※ both A and B
both A and Bは「AとBの両方とも」という意味で、「どちらも」を強調する表現。
・Steve can both speak and write Japanese.
(スティーブは日本語を話すことも書くこともできる。)
either A or B / neither A nor B
either A or Bは「AかBのどちらか」の意味で、「どちらか(一方)」を強調する表現。
Neither A nor Bは「AでもBでもない/AもBも…ない」という意味で、両者を否定するときに用いる。
・I think she is either a president or a director.
(彼女は社長か重役のどちらかだと思います。)
・The boy neither admits nor denies that he told a lie.
(その少年はうそをついたことを認めてもいないし、否定もしていない。)
5) 私は有名でないし、なりたいとも思わない。
I’m not famous, (nor) do I wish to be.
※ nor
上記文のような〈節, nor+節〉という形では、〈nor+節〉の部分は「そしてまた…しない」の意味になる。norに続く文では、上記文のdo I wish to beのように倒置が起こる。
・I don’t want to see a snake, nor do I want to touch one.
(私はヘビを見たくないし、触りたくもない。)
また、次のようnot, never, noなどの後で使われるA nor B(A,Bは語句)は、「AもBも…しない[…でない]」という意味になる。なお、このnorの代わりにorが使われることもある。Orよりも否定を明確にしたいときにはnorを使う。
・What I need is not fame, nor money.
(私が必要としているのは名声でもなければ、お金でもありません。)
〈参考〉3つ以上の語句をつなぐ場合は、2つ目以降のそれぞれの語句の前にnorをつけ
る。3つの語句をつなぐ場合なら、A nor B nor Cとする。
・This work cannot be done by you nor by me nor by anyone else.
(この仕事は、あなたにも私にもまたほかのだれにもできない。)
主語と述語動詞の一致
主語の数に合わせて述語動詞の形を決めるときは、以下の点に注意。
① 主語が〈A and B〉のように接続詞andでつながれている場合→複数扱い
Tom and Jerry are good friends. (トムとジェリーは親友だ。)
To say and to do are different things. (言うことと行うこととは別物だ。)
ただし、同一の人物や、まとまった1つのものを指す場合→単数扱い
The actor and singer is very popular among young people.
(俳優でもあり歌手でもあるその人は若者にとても人気がある。)
② 主語が〈either A or B〉や〈neither A nor B〉でつながれている場合→動詞はor / norの次の語Bに一致させるのが原則。
Either you or your brother has to apologize to him.
(あなたかあなたの兄のどちらかが、彼に謝らなければならない。)
Neither you nor he is right. (あなたも彼もどちらもただしくない。)
③ 主語が〈not only A but (also) B〉でつながれている場合→動詞はbutの次の語Bに一致させるのが原則。
Not only you but also I was wrong. (あなただけでなく私も間違っていた。)
④ 主語が〈B as well as A〉でつながれている場合→Bに一致させるのが原則。
I as well as you was wrong. (あなただけでなく私も間違っていた。)
172 名詞節を導く従属接続詞の用法
1) 困ったことに、ジムは飛行機での旅行が好きではないんだ。
The problem is (that) Jim doesn’t like traveling by air.
※ that節の補語の働き
上記文ではthat節は文全体の補語の働きをしている。
The problem is that … (問題は…ということだ)のほかにも、次のような表現でよく用いられる。なお、このthatは省略されることがある。
The fact is that … (事実は…ということだ)
The trouble is that … (問題は…ということだ)
The truth is that … (真実は…ということだ)
The reason is that … (理由は…ということだ)
that節の主語の働き
・It is true that Bill passed the entrance exam.
(ビルが入試に合格したのは本当です。)
上の文ではthat節が文全体の主語の働きをしている。That Bill passed the entrance exam is true.だと主語が長くなるので、形式主語のitを用いる。
that節の目的語の働き
・I can’t believe (that) he is an artist. (彼が芸術家だなんて、信じられません。)
上の文ではthat節が動詞believeの目的語になっている。that節が動詞の目的語になっている場合、thatは省略されることが多い。ただし、形式目的語のitを使った文ではthatを省略することはできない。
・He made it clear that we had to hand in our essays by the end of the month.
(彼は、私たちが月末までに作文を提出しなければならないということをはっきりさせた。)
形容詞に続く節を導くthat
・I’m sure (that) he will succeed in business. (彼はきっと事業に成功するだろう。)
that節はsure(確信して), glad(喜んで), sorry(気の毒に思って)などの〈感情/心理〉を表す形容詞の後でよく用いられる。なお、この場合のthatは省略されることが多い。
〈感情/心理〉を表す分詞形容詞の後でもthat節は用いられる。
・He was disappointed (that) you didn’t call him.
(君が彼に電話しなかったことで、彼はがっかりしていたよ。)
2) 彼が明日映画を見に行くかどうか知っていますか。
Do you know (whether[if]) he is going to see a movie tomorrow?
※ whetherとifは「…かどうか」という意味を表す名詞節を作り出す。ただし、whether節は、主語、補語、目的語として働くが、if節は原則的には上記文のように動詞の目的語としてしか用いられない。なお、ifはwhetherよりも口語でよく用いられる。
3) 私は娘が入試に合格したという知らせを受け取った。
I received the news (that) my daughter had passed the entrance exam.
※ that節の注意すべき用法
●同格を表すthat節
thatには〈同格〉の関係を表す用法がある。上記文のように〈名詞+that節〉という形で、直前の名詞の具体的な内容をthat節が表す。
We heard the news that she won the gold medal in Judo.
(彼女が柔道で金メダルをとったというニュースを聞いた。)
●前置詞の目的語として働くthat節
that節が前置詞の目的語になるのは、in that(…という点で/…であるから)という表現。
I’m lucky in that I have three brothers.
(私は3人も兄弟がいるという点で幸運である。)
4) ゲーリーがその申し出を受けるかどうかは定かではない。
It is uncertain (whether) Gary will take the offer.
※ whetherとifは「…かどうか」という意味を表す名詞節を作り出す。ただし、whether節は、主語、補語、目的語として働くが、if節は原則的には上記文のように動詞の目的語としてしか用いられない。上記文では、主語(この文では形式主語のitが用いられている)として働いているのでifは原則的に使用しない。
173 副詞節を導く従属接続詞の用法
( )内の語句のうち、正しいほうを選びなさい。
1) My mother was very delighted (when) I gave her a present.
※ (私の母は私がプレゼントをあげた時、とても喜んだ。)
when
whenは上記文のように「…する[…である]時に」という意味を表すときに用いられる。
・I used to go swimming in the river when I was a child.
(子どものころ、その川へよく泳ぎに行きました。)
・I was taking a bath when you called me.
(あなたが電話してきた時、私はおふろに入っていたんです。)
while
whileは「…する[…である]あいだに」という意味を表すときに用いられる。ある状態や動作が継続している期間を表すので、whileに続く節では、動詞が動作動詞の場合、進行形を用いることが多い。
・I found a wallet while I was jogging in the park.
(公園をジョギングしているあいだに、サイフを見つけた。)
〈対比を表すwhile〉
whileは「…だが一方~」という意味で〈対比〉を表すことがある。
・While I like the color of the shirt, I don’t like its shape.
(そのシャツの色は好きだけど、形が気に入らない。)
before / after
beforeは「…する前に」、afterは「…した後に」という意味を表すときに用いる。
・You need to get a visa before you enter that country.
(その国に入る前にビザを取ることが必要だ。)
・I learned German after I moved [had moved] to Berlin.
(私はベルリンに引っ越してからドイツ語を習得した。)
主節が過去形の場合でも、afterの後で過去完了形を使う必要はない。
〈注意〉before の後に否定文を続けない
before it gets dark(暗くなる前に)とすべきところを、「暗くならないうちに」と考えて、×before it doesn’t get darkとしないこと。
2) I’ll wait here (until) school is over.
※ (学校が終わるまで私はここで待ちます。)
until / since / by the time
until[till]は「…するまで」という意味で、主節の状態や継続している動作が終了する時点を示す。sinceは「…して以来」という意味で、主節の動作・状態が始まる時点を示す。by the timeは「…する時までに」という意味で、その時までに何かが完了することを表す場合に用いる。
・Wait here until[till] I get home.(私が戻るまで、ここで待っていなさい。)
・I’ve lived here since I was five years old.
(私は5歳の時からここに住んでいます。)
・The ship had sunk by the time the rescue helicopter arrived.
(救助のヘリコプターが到着するまでに、その船は沈没していた。)
as soon as / once
as soon asは「…するとすぐに」という意味を表す。なお、ほぼ同じ意味をthe moment[instant]やno sooner … than~でも表すことができる。onceは「いったん…すると」という意味の接続詞で、段階が進むとどうなるかを表すときに用いる。
・My dog started to bark as soon as he heard my voice.
(私の犬は私の声を聞くとすぐにほえ始めた。)
・The moment[instant] he stood up, he felt dizzy.
(彼は立ち上がった瞬間に、めまいを感じた。)
・Once you get a car, you can go anywhere you want.
(いったん車を手に入れたら、どこにでも行きたい所に行けますよ。)
〈参考〉hardly[scarcely] … when[before]~で「…するとすぐに~/…するかしないか
のうちに~」の意味を表す
・We had hardly[scarcely] found our seats when[before] the concert began.
(私たちが席を見つけるか見つけないかのうちに、コンサートは始まった。)
3) I will fix the roof (in case) we have heavy rain.
※ (雨が激しく降る場合に備えて屋根を直そう。)
in case
in caseは上記文では「…するといけないから/…する場合に備えて」という意味で使われている。この場合、in caseを導く節はふつう主節の後に置かれる。
・I’ll take an umbrella in case it rains.
(雨が降るといけないからかさを持っていこう。)
また、次のように、「…の場合は」という意味も表す。これはおもにアメリカ英語の表現である。
・In case I’m late, start without me.(私が遅れたら私ぬきで始めてください。)
〈注意〉in caseの使い方
in caseの後にthatを続けて×in case that … とすることはできない。また、in caseの後では未来のことを表すwillは使わない。
〈参考〉in caseが導く節でshouldを用いることがある。
・I’ll buy a flashlight in case there should be a power cut.
(停電の場合に備えて懐中電灯を買おう。)
for fear that … / lest … should~
・We hid in the basement for fear that the hurricane would destroy the house.
(ハリケーンで家が壊れるといけないから、私たちは地下に隠れた。)
for fear that … は「…するといけないから/…することをおそれて」という意味を表す。未来に起こるかもしれないことを表すので、ふつうwill[would]が入る。なお、口語では、thatが省略されることも多い。
・Speak quietly lest they should hear us.
(彼らに聞かれないように静かに話しなさい。)
lest … should~は「…が~しないように」という意味を表すが、文章体のかたい表現である。なお、lestが導く節ではshouldを用いるが、アメリカ英語ではshouldは用いず動詞の原形が来ることが多い。
「~しないように」という意味を表すには、so that … not~やso as [in order] not to doのほうがよく用いられる。
I’ll write it down so that I won’t forget.
I’ll write it down so as not to forget.
(忘れないようにそれを書きとめておこう。)
4) It was (such) a nice day that we decided to go for a drive.
※ (とても天気の良い日だったので、私たちドライブに出かけることにした。)
such … that~
suchの後に名詞を置いて、「とても…なので~」という意味を表す。上記文のsuch a nice dayのように名詞を修飾する形容詞をともなうことが多いが、次の文のように形容詞をともなわない場合もある。(thatは口語では省略されることが多い。)
He was in such a hurry that he forgot to lock the door.
(彼はとても急いでいたので、ドアにカギをかけ忘れた。)
〈参考〉かたい言い方では、suchの後に名詞がない、S+be動詞+such that~「S〈事〉
がとても大きいので~」という表現もある。このsuchはso greatという意味。
・Her astonishment was such that she nearly fell over.
(彼女の驚きは大変なものだったので、あやうく倒れそうになった。)
so … that~
so の直後に形容詞か副詞を置いてso … that~とすると、「とても…なので~」という意味を表したり、「~なほど…」という意味を表すことができる。(thatは口語では省略されることが多い。)
・The lecture was so boring that half the students fell asleep.
(その講義はとても退屈だったので、生徒の半分が寝てしまった。)
・He spoke so clearly that we could understand him.
(彼はとてもわかりやすく話したので、私たちは彼の言うことを理解でき
た。)
〈参考〉この構文で、〈a/an+形容詞+名詞〉の形容詞にsoをつけると、〈so+形容詞
+a/an+名詞+that~〉という語順になる。
It was so boring a lecture that half the students fell asleep.
ただし、この〈so+形容詞+a/an+名詞+that~〉はかたい表現で、ふつうはsuchを使った表現になる。
= It was such a boring lecture that half the students fell asleep.
〈参考〉強調のためにsoが文頭に出て、倒置が起こることがある。
= So boring was the lecture that half the students fell asleep.
so that / in order that
so thatは「…するために/…するように」という意味で、〈目的〉を表す。so that節の中では、文脈に応じて助動詞のcanやwill, mayを用いる。なお、口語ではthatが省略されることも多い。
・Lock the door so that no one can get in.
(だれも入れないように、ドアにカギをかけなさい。)
・Talk louder so I can hear you.
(聞こえるように、もっと大きな声で話してください。)
in order thatもso thatとほぼ同じ意味で使われる。ただし、in order thatのほうがかたい表現で、in order that節の中ではmayが使われることが多い。
・She spoke loudly in order that the people in the back might hear.
(後ろの人に聞こえるように、彼女は大きな声で話した。)
because / since / now that
becauseは〈直接の原因・理由〉を表し、「…なので/…だから」という意味になる。
・Mr. Brown was very angry because I didn’t tell the truth.
(ブラウン先生は私が本当のことを言わなかったので、とても怒っていた。)
〈参考〉because節を文頭に置くときは、節の終わりにコンマを入れる。また、この
場合becauseが強く読まれることが多い。
=Because I didn’t tell the truth, Mr. Brown was very angry.
sinceは、相手がすでに知っている〈原因・理由〉を述べるときに用いる。この意味では、sinceが導く主節の前に置かれるのがふつう。
・Since you have a fever, you should stay home tonight.
(熱があるのだから、今夜は家にいたほうがいいよ。)
〈参考〉asを使って理由を表すこともある。
・As he was not in his office, we had to wait in the lobby.
(彼はオフィスにいなかったので、私たちはロビーで待たなければならなか
った。)
now that … は「今やもう…だから」という意味の接続詞として使う。口語ではthatを省略することもある。now that … で現状を述べ、そのうえで成り立つことをその後に続ける。
・Now that we have children, we don’t go out very much.
(今はもう子どもがいるので、それほど出かけない。)
5) My father doesn’t use taxis (unless) it is absolutely necessary.
※ (私の父は、絶対に必要というわけでない限り、タクシーを利用しない。)
unless / if
unlessは「…の場合を除いて/…でない限り」の意味で、unlessの後には上記文のように主節の内容が成り立たない唯一の条件が続く。
He’ll be here at six unless his flight is delayed.
(飛行機が遅れない限り、彼は6時にここに来るでしょう。)
if は「もし…ならば/(仮に)…とすれば」の意味で、〈仮定〉や〈条件〉を表す。
Please read my report if you have time.
(時間があれば、私のレポートをよんでください。)
〈if … notとunless〉
unlessがif … notとほぼ同じ意味にとれることも多い。
He’ll be here at six if his flight isn’t delayed.
if … notをunlessで表せない場合もある。
・I’ll be surprised if Mike doesn’t complaint about it.
(マイクがそのことに文句を言わないなら、ぼくは驚くね。)
6) (Although) we did our best, we lost the game.
※ (私たちは最前を尽くしたが、その試合に負けた。)
though / although / (even) though
thoughとalthoughは「…であるけれども/…にもかかわらず」という意味で、譲歩
を表す。thoughやalthoughの導く節では実際に成り立っていることを述べている
ことに注意。althoughは比較的かたい表現で、thoughのほうが一般的である。強
調するときにはeven thoughを使う。
・Even though I don’t like comedies, I saw the movie because my girlfriend wanted to see it.
(コメディーは好きではないのだけれども、ガールフレンドが見たいと言ったのでその映画を見た。)
even if
even if も譲歩を表すが、thoughやalthoughとは異なり、even if の後には事実か
どうかわからないことが続く。「たとえ…でも」という意味。
・Never give up even if you make mistakes.
(たとえ間違いをしても、あきらめてはいけない。)
as long as / as far as
as long asは大きく2つの意味に分かれる。1つは「…するあいだは」という意味
で、次のように用いられる。
・You can swim in the pool as long as I’m here.
(私がここにいるあいだは、プールで泳いでいいよ。)
もう1つは次のような「…しさえすれば」という意味で、最低限の条件を表す使い
方である。so long asとすることもある。
・You can watch TV as long as you do your homework first.
(宿題を先にするなら、テレビを見てもいいよ。)
as far asは「…の(およぶ)限りでは/…に関する限り」という意味で、範囲や程度
を表す。
・As far as I know, he is not guilty.(私の知る限りでは、彼に罪はない。)
whether A or B
whether A or Bは「AであろうとBであろうと」という意味で、譲歩を表す。
whether A or notで「Aであろうとなかろうと」という意味を表す。
・You must eat the carrots whether you like them or not!
(好きであろうとなかろうと、そのニンジンを食べなさい!
・I don’t care whether you win or lose.
(あなたが勝とうが負けようが、私にはどうでもよい。)
suppose[supposing] / providing[provided]
suppose, supposing, providing, providedを使って〈条件〉を表すことができる。
・Suppose [supposing] it was fifty dollars cheaper, would you buy it?
(それが50ドル安いとしたら、あなたは買いますか。)
・You can go to the party providing [provided] you promise to return by
11:00.
(11時までに戻ってくると約束すれば、そのパーティーに行ってもいいよ。)
〈asの代表的な使い方〉
● 接続詞
① 「…する時/…するあいだ/…しながら」:「時」を表す
I saw Judy as I was getting off the train.
(電車を降りるときにジュディーを見かけた)
② 「…につれて」:「比例」を表す
As time went by, she became more beautiful.
(時がたつにつれ、彼女はいっそう美しくなった。)
③ 「…(する)ように/…(する)とおりに」:「様態」を表す
Why don’t you behave as I’ve always told you to?
(しなさいっていつも言っているようになぜしないのよ。)
④ 「…なので/…だから」:「理由」を表す
As it was getting late, he decided to check into a hotel.
(遅くなってきたので、彼はホテルにチェックインすることにした。)
⑤ 「…だけれども」:「譲歩」を表す
Angry as she was, she couldn’t help smiling.
(彼女は腹を立てていたが、思わずほほ笑んでしまった。)
● 前置詞
① 「…(である)と」:〈他動詞+目的語+as …〉の形で補語を導く
Her father regards her as a genius.
(父親は彼女が天才だと思っている。)
② 「…として」
She works as a cook at the restaurant.
(彼女はそのレストランでコックとして働いている。)
③ 「…の時に/…のころ」
As a child, he lived in Ireland.
(子どものころ、彼はアイルランドに住んでいた。)
長文読解
英語の長文を理解するためには、精読と多読の2つの読み方を使い分けることが重要です。どちらも効果的な読解スキルを向上させるために必要な読み方ですが、それぞれ目的やアプローチが異なります。
1. 精読とは?
精読とは、文章を細かく分析しながら、文法・語彙・構造をしっかり理解する読み方です。特に難解な文章や学術的な内容を読む際に必要となります。
“The rapid advancement of artificial intelligence has raised concerns about its potential impact on employment, ethics, and human decision-making. While AI can enhance efficiency, critics argue that it might replace human workers and lead to unforeseen consequences.”
読み方:
①語彙の確認:
advancement(進歩)、concerns(懸念)、potential impact(潜在的な影響)、efficiency(効率)、unforeseen consequences(予期せぬ結果)などの重要単語をチェック。
②文法・構造の分析:
・”The rapid advancement of artificial intelligence”
→ 主語
・”has raised concerns about…”
→ 動詞+目的語
・”While AI can enhance efficiency, critics argue that…”
→ 副詞節と主節の関係を理解
③内容理解:
AIの進歩が雇用や倫理に影響を与える可能性があることを述べている。
精読のメリット:
✅ 文法・語彙の強化
✅ 正確な理解
✅ 難解な文章の読解力向上
2. 多読とは?
多読とは、大量の文章をできるだけ辞書を使わずに読み、全体の意味を大まかに理解する読み方です。ストーリーの流れやテーマを掴みながら、速く読むことが目的です。
“John loved traveling. Ever since he was a child, he had dreamed of exploring new places and experiencing different cultures. As soon as he graduated from college, he packed his bags and set off on a journey around the world.”
読み方:
①全体の流れをつかむ:
ジョンが子供のころから旅行を夢見ていて、大学卒業後に世界旅行を始めたことが分かる。
②細かい単語は気にしない:
もし exploring(探検する)や set off(出発する)の意味が分からなくても、文脈から「ジョンが旅行を始めた」ことを理解できればOK。適当に読み飛ばすことではなく、わからない単語や意味が分からない部分に執着せず、理解できる箇所を手がかりにして読み進めます。
③辞書を使わない:
文全体の意味を推測しながら読む。
補足:文章の内容の推測
英文の最新テーマを日頃から把握し、さまざまな分野の知識を持っていると、文章の内容が予測しやすくなります。
多読のメリット:
✅ 読解スピード向上
✅ 語彙力の自然な増加
✅ 英語の文章に慣れる
精読と多読の使い分け
精読:正確に理解し、文法や語彙を学ぶ
(難解な文章を読むとき)
多読:全体の意味をつかみ、速読力を向上させる
(物語やニュース記事を楽しむとき)
まとめ:
精読でしっかりとした基礎力をつけ、多読で読解スピードを向上させることが、英語長文の理解力を高める鍵となります。
英語長文を効率的に読み、正しく理解するためには、適切な読解テクニックを使い分けることが重要です。本記事では、以下の4つのテクニックを解説し、それぞれの例文と解法を紹介します。
1. フレーズリーディング
2. スキャニング
3. スキミング
4. パラグラフリーディング
1. フレーズリーディングとは?
フレーズリーディング(Phrase Reading)とは、単語単位ではなく意味のある語のまとまり(フレーズ)ごとに読むテクニックです。1単語ずつ読むと遅くなるため、かたまりで捉えることでスムーズに読解できます。
“The development of renewable energy sources / has become a global priority / due to concerns about climate change.”
区切り方:
①1語ずつ読むのではなく、意味のまとまりごとに区切る。
・The development of renewable energy sources(再生可能エネルギーの開発)
・has become a global priority(世界的な優先事項となっている)
・due to concerns about climate change(気候変動への懸念のため)
②それぞれのフレーズの意味を理解することで、文全体の意味がつかみやすくなる。
フレーズリーディングのメリット:
✅ 読解スピードの向上
✅ 文構造を理解しやすくなる
✅ 文の流れを自然に把握できる
補足:速読の必要性とフレーズリーディング実践方法
●速読の必要性
速読が必要な理由は大きく2つあります。
① 短時間で多くの情報を得るため
② より正確な情報を得るため
一見、①「速く読むこと」と②「正確に読むこと」は矛盾しているように思えます。しかし、ゆっくり読むからといって正確に理解できるわけではありません。単語を一つずつ追うよりも、「語のカタマリ」で読む方が、全体の意味を正確に把握しやすくなります。
<単語を一つずつ追う>
Climate change has become a serious global issue, affecting millions of people and causing extreme weather conditions such as hurricanes, droughts, and heatwaves. Many scientists believe that human activities, including the burning of fossil fuels and deforestation, are the main causes of this problem. Governments around the world have started to take action by implementing policies to reduce carbon emissions and promote renewable energy sources such as wind and solar power. However, individuals also need to contribute by using less plastic, conserving energy, and supporting eco-friendly products. If we work together, we can slow down global warming and protect our planet for future generations.
<「語のカタマリ」で読む>
Climate change has become a serious global issue, / affecting millions of people / and causing extreme weather conditions / such as hurricanes, droughts, and heatwaves. Many scientists believe / that human activities, / including the burning / of fossil fuels and deforestation, // are the main causes of this problem. Governments / around the world // have started to take action / by implementing policies / to reduce carbon emissions / and promote renewable energy sources / such as wind and solar power. / However, / individuals also need to contribute / by using less plastic, / conserving energy, / and supporting eco-friendly products. / If we work together, // we can slow down global warming / and protect our planet / for future generations.
●フレーズ・リーディングの実践方法
「語のカタマリ」を意識して読む方法をフレーズ・リーディングといいます。以下のルールを守ると、効果的に読むことができます。
① 接続詞の前で区切る
「接続詞+SV…, S’V’~」の英文の場合には、2番目のS’の前で大きく区切る。
② 長い主語の後で区切る
主語の直後に長い修飾部分が続く場合、主部と述語動詞を大きく区切る
③ 前置詞の前で区切る
「前置詞+目的語」の「語のカタマリ」を作る
④「動詞+目的語」の「語のカタマリ」
動詞が出てきたら、「動詞+目的語」のカタマリを早く作る。
⑤ 不定詞・分詞・関係詞の前で区切る
句や節を意識してカタマリを作る。(不定詞は名詞句・形容詞句・副詞句、分詞の後置修飾は形容詞句、分詞構文は副詞節、関係詞は形容詞節。)
⑥ 慣用表現・熟語を早く見つける
単語と並行して慣用表現・熟語の学習が前提。
以上を実践すると、次のような読み方ができるようになります。
Climate change has become a serious global
issue, / affecting millions of people / and causing
分詞構文 熟語
extreme weather conditions / such as
熟語
hurricanes, droughts, and heatwaves. / Many
scientists believe / that human activities,
/ including the burning / of fossil fuels / and
前置詞+目的語 前置詞+目的語
deforestation, // are the main causes / of this
主部の後 前置詞+目的語
problem. Governments / around the world
前置詞+目的語
// have started to take action / by implementing
熟語 熟語 前置詞+目的語
policies / to reduce carbon emissions / and
不定詞
promote renewable energy sources / such as
動詞+目的語 熟語
wind and solar power. // However, / individuals
論理マーカー
also need to contribute / by using less plastic,
前置詞+目的語
conserving energy, and supporting eco-friendly
慣用表現(A, B, and C)
products. / If we work together, // we can slow
主語の前の区切り
down global warming /and protect our planet
動詞+目的語
/ for future generations.
前置詞+目的語
2. スキャニングとは?
スキャニング(Scanning)とは、特定の情報(数字・名前・キーワード)を素早く探すテクニックです。試験の長文問題では、設問の答えを探すときに役立ちます。
“The Great Wall of China stretches over 13,000 miles and was originally built to protect Chinese states from invasions.”
問題:
How long is the Great Wall of China?
解き方:
①「長さ」に関する情報を探すため、「miles」や「数字」に着目。
② 13,000 miles という数字を発見。
③ 周辺を読んで「The Great Wall of China」に関する記述であることを確認。
答え: 13,000 miles
スキャニングのメリット:
✅ 素早く特定の情報を見つけられる
✅ 試験時間を節約できる
3. スキミングとは?
スキミング(Skimming)とは、文章全体の要点や主題を素早く把握するために、流し読みをするテクニックです。詳細を読むのではなく、大まかな内容を理解することが目的です。
“The internet has transformed communication. People can now connect instantly through emails, social media, and messaging apps. While this has increased convenience, some experts warn about the negative effects, such as decreased face-to-face interactions.”
問題:
What is the main idea of the passage?
解き方:
① 最初の文を読む → “The internet has transformed communication.”(インターネットはコミュニケーションを変えた)
② 各段落の最初と最後の文を流し読み → インターネットの利点と欠点について述べていることを把握。
③ 主題をまとめる → 「インターネットがコミュニケーションを変えたこと」
答え: The internet has transformed communication.
スキミングのメリット:
✅ 文章の大まかな意味を素早く把握できる
✅ 試験の初見長文を読むときに有効
補足:段落の先頭文の活用
長文を効率的に理解するために、各段落の最初と最後の文を読むことにより、全体の要点を素早くつかむことができます。ただし、この方法が常に有効とは限りませんので、状況に応じて使い分けることが大切です。
4. パラグラフリーディングとは?
パラグラフリーディング(Paragraph Reading)とは、1つの段落ごとにその要点を把握しながら読むテクニックです。段落にはトピックセンテンス(主題文)があるため、それを中心に理解すると効果的です。
“Renewable energy sources, such as solar and wind power, are becoming increasingly important. They provide a sustainable alternative to fossil fuels, reducing carbon emissions and dependence on non-renewable resources. Governments worldwide are investing in these technologies to combat climate change.”
主題:
① トピックセンテンスを探す → 最初の文 “Renewable energy sources, such as solar and wind power, are becoming increasingly important.”
② 詳細情報を確認する → 再生可能エネルギーの利点や政府の投資について述べている。
③ 段落全体の要点をまとめる → 「再生可能エネルギーの重要性とその利点」
答え: The importance and benefits of renewable energy.
パラグラフリーディングのメリット:
✅ 段落ごとに整理して理解できる
✅ 長文の構造が分かりやすくなる
まとめ:テクニックの使い分け
1. フレーズリーディング:かたまりで読む (長文全体のスムーズな読解)
2. スキャニング:特定の情報を探す(数字・名前・データを見つけるとき)
3. スキミング:文章の主題をつかむ(初見の長文を読むとき)
4. パラグラフリーディング:段落ごとの要点を整理(長文の構造を把握するとき)
この4つのテクニックを使い分けることで、英語長文読解のスピードと正確性を向上させることができます。
英語の長文読解では、さまざまな形式の問題が出題されます。これらの問題に対応するためには、適切な読解テクニックを組み合わせることが重要です。本記事では、4つのテクニック(フレーズリーディング・スキャニング・スキミング・パラグラフリーディング)を活用しながら、以下の問題形式別の解法を詳しく解説します。
1. 空所補充問題
2. 内容一致問題
3. 下線部説明問題
4. 要約問題
1. 空所補充問題
問題の特徴:
・文の一部が抜けており、適切な語句を補う必要がある。
・文法・語彙・文脈の理解が求められる。
最適なテクニックの組み合わせ:
✅ フレーズリーディング(前後の文脈を把握するため)
✅ パラグラフリーディング(段落全体の意味を理解するため)
例題:
Artificial intelligence (AI) has significantly impacted various industries, including healthcare, finance, and education. In healthcare, AI-powered tools can analyze medical data faster than human doctors, allowing for early disease detection and personalized treatment plans. In finance, AI algorithms help detect fraudulent transactions and optimize investment strategies. Education has also been transformed by AI, with intelligent tutoring systems providing personalized learning experiences. However, some experts worry about the ethical implications of AI, particularly its potential to replace human jobs. While AI can increase productivity and efficiency, it is essential to ensure that its development is guided by ethical considerations and regulations. Many scientists believe that artificial intelligence will __ the way we work, making tasks easier and more efficient.
選択肢:
(A) destroy
(B) transform
(C) confuse
(D) ignore
解き方:
① フレーズリーディングを活用し、前後の文脈を確認。「AIは医療、金融、教育に影響を与えている」「仕事の効率が上がる」という文脈から、ポジティブな意味の単語が適切。
② パラグラフリーディングを活用し、段落全体の流れを整理。
AIの変革的な影響を述べているため、「破壊する (destroy)」「無視する (ignore)」「混乱させる (confuse)」は不適切。
正解: (B) transform(変革する)
2. 内容一致問題
問題の特徴:
・本文の内容と一致する選択肢を選ぶ。
・細かい情報の理解が求められる。
最適なテクニックの組み合わせ:
✅スキャニング(該当箇所を素早く見つけるため)
✅ パラグラフリーディング(正確な意味を理解するため)
例題:
The Amazon rainforest, often referred to as the "lungs of the Earth," plays a crucial role in regulating the planet’s climate. Covering over 5.5 million square kilometers, it absorbs large amounts of carbon dioxide, helping to slow down global warming. Additionally, it is home to millions of species, many of which cannot be found anywhere else. However, deforestation poses a severe threat to the rainforest. Each year, vast areas of trees are cleared for agriculture, logging, and infrastructure development. This not only reduces biodiversity but also contributes to increased carbon emissions. Governments and environmental organizations are working to combat deforestation by promoting sustainable land-use practices and reforestation projects. Despite these efforts, illegal logging and economic pressures continue to drive forest destruction.
問題:
What is the main function of the Amazon rainforest?
(A) It produces oxygen for the world.
(B) It absorbs carbon dioxide.
(C) It causes global warming.
(D) It has no effect on the climate.
解き方:
① スキャニングを活用し、「Amazon rainforest」や「function」に関連する部分を素早く見つける。
② パラグラフリーディングを活用し、詳細を確認。
「吸収する (absorbs)」「二酸化炭素 (carbon dioxide)」「地球温暖化を遅らせる (slow down global warming)」とあるため、(B)が正しいと判断できる。
正解: (B) It absorbs carbon dioxide.
3.下線部説明問題
問題の特徴:
・下線部の意味を説明する選択肢を選ぶ。
・文脈を正しく理解する必要がある。
最適なテクニックの組み合わせ:
✅ フレーズリーディング(下線部を正確に解釈するため)
✅ スキミング(大まかな流れを把握するため)
例題:
In the past few decades, space exploration has advanced significantly, leading to numerous scientific discoveries and technological innovations. Satellites provide essential data for weather forecasting, communication, and global navigation. Missions to Mars and beyond are helping scientists understand the potential for life outside Earth. However, some critics argue that the enormous cost of space programs could be better spent on solving pressing issues on Earth, such as poverty and climate change. On the other hand, proponents believe that investment in space exploration leads to invaluable scientific and economic benefits, including new technologies that improve everyday life. For instance, medical imaging techniques, originally developed for space missions, are now used in hospitals worldwide.
問題:
What does "invaluable" mean in this context?
(A) Not valuable at all
(B) Extremely valuable
(C) Slightly beneficial
(D) Completely unnecessary
解き方:
① フレーズリーディングを活用し、「invaluable scientific and economic benefits」の意味を確認。
「経済的・科学的な利益」とあるので、ポジティブな意味が必要。
② スキミングを活用し、全体の流れを確認。
「医療技術への応用」などの例が挙げられており、価値が高いことが示唆されている。
正解: (B) Extremely valuable
4. 要約問題
問題の特徴:
・本文全体の要点をまとめる必要がある。
・主要なポイントを把握する力が求められる。
最適なテクニックの組み合わせ:
✅ スキミング(文章全体の主題を素早く把握するため)
✅ パラグラフリーディング(各段落の要点を整理するため)
例題:
Renewable energy sources, such as solar, wind, and hydroelectric power, have gained increasing attention as sustainable alternatives to fossil fuels. These energy sources produce little to no carbon emissions, making them essential in the fight against climate change. Governments worldwide are investing heavily in renewable energy technologies, aiming to reduce dependence on coal, oil, and natural gas. However, challenges remain. The initial cost of setting up renewable energy infrastructure is high, and energy storage technology is still developing. Additionally, sources like solar and wind power depend on weather conditions, which can be unpredictable. Despite these obstacles, advancements in battery technology and grid management are helping to make renewable energy more reliable. Policymakers and researchers continue to explore innovative solutions to overcome these challenges, ensuring a sustainable energy future.
問題:
Which of the following best summarizes the passage?
(A) Renewable energy is useless.
(B) Renewable energy is important but has challenges.
(C) Governments should stop investing in renewable energy.
(D) Renewable energy sources are replacing fossil fuels entirely.
解き方:
① スキミングを活用し、全体の流れを把握。
「再生可能エネルギーの利点と課題」が主題。
② パラグラフリーディングを活用し、各段落のポイントを整理。
・最初の部分 → 重要性
・中盤 → 政府の投資
・最後 → 課題
正解: (B) Renewable energy is important but has challenges.
まとめ:問題別の最適な読解テクニック
空所補充問題:フレーズリーディング+パラグラフリーディング (前後の文脈を把握するため)
内容一致問題:スキャニング+パラグラフリーディング (該当箇所を見つけ、正確に理解するため)
下線部説明問題:フレーズリーディング+スキミング (下線部の意味と全体の流れを理解するため)
要約問題:スキミング+パラグラフリーディング (文章全体の要点を整理するため)
各問題に適したテクニックを使い分けることで、効率的に長文読解を攻略できます。
👈大学入試で最重要
英語の長文を読むとき、すべての文をじっくり読んでいると時間が足りなくなります。そこで、「重要な部分は丁寧に読む(精読)」「補足的な部分はサッと読む(速読)」という読み分けが大切です。この読み分けは以下の3つのレベル(1文内・1段落内・複数段落間)で考えます。
① 文の中での読み分け
ポイント
・英文の基本は「主語+動詞(主節)」です。ここが筆者の主張や結論になることが多いので、精読します。
・「because」「when」「which」「that」などで始まる部分は、理由や説明が多く、速読でもOKなことが多いです。
・「however」「therefore」「in fact」などは、重要な転換点や強調なので、精読しましょう。
コツ
英語は「追加情報を後ろに置く」ので、前から順に読むと理解しやすく、時間も節約できます。
例文
The experiment was successful because the conditions were ideal.
(その実験は成功した。なぜなら条件が理想的だったからだ。)
読み分けポイント: 「The experiment was successful」が主節 → 精読。「because以下」は理由 → 速読でもOK。
② 段落の中での読み分け
ポイント
・段落の最初や最後の文は「トピックセンテンス(主題文)」であることが多く、精読します。
・「for example」「however」「in conclusion」などの接続語の後は、重要な情報が来る可能性が高いので注意。
・段落の中の具体例や数字などは、設問に関係なければ速読でOK。
コツ
「主張→根拠」「抽象→具体」「比較」などのパターンを意識すると、読み分けがしやすくなります。
例文
Many researchers argue that sleep plays a crucial role in memory consolidation. In particular, deep sleep stages are believed to help the brain organize and store newly acquired information. For example, a study conducted at Harvard University found that students who took a nap after learning new material performed significantly better on memory tests than those who stayed awake. Additionally, sleep deprivation has been linked to reduced cognitive performance and increased stress levels. Therefore, getting enough sleep is not only beneficial for physical health but also essential for academic success.
(多くの研究者は、睡眠が記憶の定着に重要な役割を果たすと主張している。特に、深い睡眠段階は、新しく得た情報を脳が整理・保存するのに役立つと考えられている。例えば、ハーバード大学で行われた研究では、新しい内容を学んだ後に昼寝をした学生は、起きていた学生よりも記憶テストの成績が大幅に良かったことがわかった。さらに、睡眠不足は認知機能の低下やストレスレベルの上昇と関連している。したがって、十分な睡眠をとることは、身体の健康に良いだけでなく、学業の成功にも不可欠である。)
読み分けポイント
精読すべき文:
・段落冒頭の「Many researchers argue…」:主張文(トピックセンテンス)
・段落末尾の「Therefore, getting enough sleep…」:結論文
速読できる文:
・「For example」以下の具体例(研究内容)
・「Additionally」以下の補足情報(睡眠不足の影響)
このように、主張と結論を精読し、具体例や補足は設問に関係なければ速読でOKです。
③ 複数段落(文章全体)での読み分け
ポイント
・文章全体の流れ(序論→本論→結論)を意識します。
・序論で問題提起、結論でまとめや教訓があることが多いので、序論と結論は精読。
・中間の段落は、例や説明が多いので、設問に関係なければ速読。
コツ
段落をつなぐ接続語(However, On the other hand, In contrastなど)で、話の流れが変わることがあります。そこは精読ポイントです。
例文
Paragraph 1: In recent years, the popularity of electric vehicles (EVs) has grown rapidly due to concerns about climate change and fossil fuel dependency. Governments around the world have introduced incentives to encourage consumers to switch from gasoline-powered cars to EVs.
Paragraph 2: However, despite these efforts, many consumers remain hesitant. One major concern is the limited availability of charging stations, especially in rural areas. In addition, the initial cost of EVs is still higher than that of traditional vehicles, making them less accessible to low-income families.
Paragraph 3: On the other hand, technological advancements are gradually addressing these issues. Battery efficiency has improved, and fast-charging infrastructure is expanding in many countries. As a result, experts predict that EVs will become more affordable and convenient in the near future.
(第1段落: 近年、気候変動や化石燃料への依存に対する懸念から、電気自動車(EV)の人気が急速に高まっている。世界中の政府が、ガソリン車からEVへの乗り換えを促すための優遇措置を導入している。
第2段落: しかし、こうした取り組みにもかかわらず、多くの消費者は依然として慎重である。主な懸念点は、特に地方での充電ステーションの不足である。さらに、EVの初期費用は依然として従来の車より高く、低所得層には手が届きにくい。
第3段落: 一方で、技術の進歩によってこれらの問題は徐々に解決されつつある。バッテリーの効率は向上し、急速充電のインフラも多くの国で拡大している。その結果、EVは近い将来、より手頃で便利になると専門家は予測している。)
読み分けポイント
精読すべき箇所:
・第1段落の冒頭:「EVの人気が高まっている理由」→ 序論
・第3段落の結論:「EVの将来展望」→ 結論
・接続語「However」「On the other hand」の後→ 論理の転換点
速読できる箇所:
・第2段落の具体的な懸念点(充電ステーション、価格)
・第3段落の技術的詳細(バッテリー効率、インフラ)
このように、文章全体の構成(序論→問題点→解決→結論)を意識し、主張や結論を精読、詳細説明は速読することで効率的に読解できます。
まとめ:速読と精読の切り替えポイント
| レベル | 精読する部分 | 速読する部分 |
| 文内 | 主語+動詞(主節/逆接・強調語) | 理由・例示節(because, whichなど) |
| 段落内 | 最初・最後の文/接続語の後 | 具体例・数字・固有名詞など |
| 全体 | 序論・結論/論理の転換点 | 中間段落の詳細説明など |
- 問題
- 解答
- Phrase Reading
- 音読
英語長文 空所補充 (標準:英検2級・日東駒専)
Directions: Read the following passage and choose the best answer (A, B, C, or D) for each blank.
AI and Its Impact on Jobs
Artificial intelligence, or AI, is changing the way we live and work. In many industries, machines and computers can now do tasks that were once done by humans. For example, in factories, robots can build cars or check products. In offices, AI systems can help with scheduling or answering customer emails. These changes make work faster and sometimes cheaper, but they also create new ( 1 ).
Some people worry that AI will take away jobs. It is true that some jobs, especially simple or repeated ones, may disappear. However, AI also creates new kinds of work. People will be needed to design, control, and fix AI systems. Also, jobs that require human creativity, emotion, or communication skills—such as teachers, artists, or nurses—are ( 2 ) to be replaced by AI.
To prepare for these changes, it is important to learn new skills. Schools and training programs should teach people how to use technology and think in new ways. Governments and businesses should also help workers move to new jobs. If we work together, AI can become a tool that supports us, rather than a ( 3 ).
Questions:
( 1 )
A. dangers
B. rules
C. problems
D. possibilities
( 2 )
A. likely
B. unlikely
C. easy
D. dangerous
( 3 )
A. challenge
B. job
C. threat
D. machine
英語長文 空所補充 (標準) 解答・解説
AI and Its Impact on Jobs
Artificial intelligence, or AI, is changing the way we live and work. In many industries, machines and computers can now do tasks that were once done by humans. For example, in factories, robots can build cars or check products. In offices, AI systems can help with scheduling or answering customer emails. These changes make work faster and sometimes cheaper, but they also create new ( 1 ).
Some people worry that AI will take away jobs. It is true that some jobs, especially simple or repeated ones, may disappear. However, AI also creates new kinds of work. People will be needed to design, control, and fix AI systems. Also, jobs that require human creativity, emotion, or communication skills—such as teachers, artists, or nurses—are ( 2 ) to be replaced by AI.
To prepare for these changes, it is important to learn new skills. Schools and training programs should teach people how to use technology and think in new ways. Governments and businesses should also help workers move to new jobs. If we work together, AI can become a tool that supports us, rather than a ( 3 ).
Question
( 1 ) A. dangers B. rules C. problems D. possibilities
文脈上「仕事が早く・安くなる」変化は、「新たな可能性を生む」という前向きな内容であり、「dangers(危険)」や「problems(問題)」よりもポジティブな語が合う。
( 2 ) A. likely B. unlikely C. easy D. dangerous
AIが代替しにくい仕事の例(教師・看護師など)を挙げているので、「置き換えられる可能性が低い=unlikely」が適切。
( 3 ) A. challenge B. job C. threat D. machine
AIを「支える道具」として使うことが望ましいという文の対比構造から、AIが「脅威」になる可能性を示している。
英語長文 空所補充 (標準) フレーズリーディング用
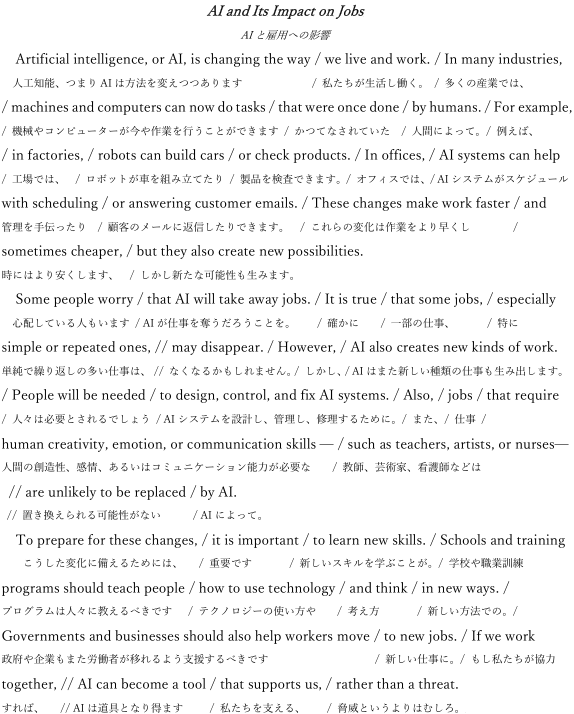
英語長文 空所補充 (標準) 音読用(英文)
AI and Its Impact on Jobs
Artificial intelligence, or AI, is changing the way we live and work. In many industries, machines and computers can now do tasks that were once done by humans. For example, in factories, robots can build cars or check products. In offices, AI systems can help with scheduling or answering customer emails. These changes make work faster and sometimes cheaper, but they also create new possibilities.
Some people worry that AI will take away jobs. It is true that some jobs, especially simple or repeated ones, may disappear. However, AI also creates new kinds of work. People will be needed to design, control, and fix AI systems. Also, jobs that require human creativity, emotion, or communication skills —such as teachers, artists, or nurses— are unlikely to be replaced by AI.
To prepare for these changes, it is important to learn new skills. Schools and training programs should teach people how to use technology and think in new ways. Governments and businesses should also help workers move to new jobs. If we work together, AI can become a tool that supports us, rather than a threat.
(和文)
AIと雇用への影響
人工知能、つまりAIは、私たちの生活や働き方を変えつつあります。多くの産業では、機械やコンピューターが、これまで人間が行っていた作業をこなせるようになっています。たとえば、工場ではロボットが自動車を組み立てたり、製品を検査したりできます。オフィスでは、AIシステムがスケジュール管理や顧客のメール対応を助けてくれます。こうした変化により、作業はより速く、時にはより安くなりますが、同時に新しい可能性も生み出されます。
AIによって仕事が奪われることを心配する人もいます。確かに、一部の仕事、特に単純で繰り返しの多いものはなくなるかもしれません。しかし、AIは新しいタイプの仕事も生み出します。AIシステムを設計したり、管理したり、修理したりする人が必要になります。また、人間の創造性や感情、コミュニケーション能力を必要とする仕事、たとえば教師、芸術家、看護師などは、AIに取って代わられる可能性が低いです。
こうした変化に備えるためには、新しいスキルを学ぶことが重要です。学校や職業訓練のプログラムは、人々にテクノロジーの使い方や新しい思考法を教えるべきです。政府や企業もまた、労働者が新しい仕事へ移ることを支援するべきです。私たちが協力すれば、AIは私たちを支える道具となり、脅威ではなくなるでしょう。
- 問題
- 解答
- 音読
英語長文 空所補充 (応用:英検準1級・GMARCH)
AI and Employment
In recent years, artificial intelligence (AI) has begun to transform workplaces across various industries. From automated customer service chatbots to advanced data analysis, AI is streamlining operations and improving efficiency. Many businesses have adopted AI not only to cut costs but also to gain a ( 1 ) edge.
However, the rise of AI has sparked concerns about its impact on employment. Jobs involving repetitive tasks, such as data entry and basic customer support, are especially ( 2 ) to automation. According to a recent study, nearly 40% of workers in developed countries may see their roles replaced or significantly altered by AI within the next two decades.
Despite these concerns, experts argue that AI will also generate new types of jobs. For instance, there will be greater demand for AI specialists, data analysts, and ethics consultants who can help guide the responsible development of AI technologies. In addition, some believe that by automating routine tasks, AI will allow humans to focus on more ( 3 ) and meaningful work.
Still, the transition will not be easy. Governments and companies must invest in education and retraining programs to help workers adapt to this rapidly changing job market. Without such efforts, the benefits of AI may come at the cost of social ( 4 ) and widespread unemployment.
In this context, many policymakers are calling for closer cooperation between the public and private sectors. They emphasize the importance of building inclusive strategies that ensure AI technologies are developed and applied in ways that benefit ( 5 ) , not just a select few. One proposed approach is the introduction of a universal basic income to support individuals who may be temporarily ( 6 ) during the transition period.
Question
(1) (A) competitive (B) financial (C) traditional (D) technical
(2) (A) resistant (B) aware (C) vulnerable (D) useful
(3) (A) creative (B) financial (C) repetitive (D) optional
(4) (A) media (B) inequality (C) security (D) mobility
(5) (A) machines (B) companies (C) everyone (D) managers
(6) (A) exhausted (B) embarrassed (C) unemployed (D) promoted
英語長文 空所補充 (応用) 解答・解説
AI and Employment
In recent years, artificial intelligence (AI) has begun to transform workplaces across various industries. From automated customer service chatbots to advanced data analysis, AI is streamlining operations and improving efficiency. Many businesses have adopted AI not only to cut costs but also to gain a ( 1 ) edge.
However, the rise of AI has sparked concerns about its impact on employment. Jobs involving repetitive tasks, such as data entry and basic customer support, are especially ( 2 ) to automation. According to a recent study, nearly 40% of workers in developed countries may see their roles replaced or significantly altered by AI within the next two decades.
Despite these concerns, experts argue that AI will also generate new types of jobs. For instance, there will be greater demand for AI specialists, data analysts, and ethics consultants who can help guide the responsible development of AI technologies. In addition, some believe that by automating routine tasks, AI will allow humans to focus on more ( 3 ) and meaningful work.
Still, the transition will not be easy. Governments and companies must invest in education and retraining programs to help workers adapt to this rapidly changing job market. Without such efforts, the benefits of AI may come at the cost of social ( 4 ) and widespread unemployment.
In this context, many policymakers are calling for closer cooperation between the public and private sectors. They emphasize the importance of building inclusive strategies that ensure AI technologies are developed and applied in ways that benefit ( 5 ) , not just a select few. One proposed approach is the introduction of a universal basic income to support individuals who may be temporarily ( 6 ) during the transition period.
(1) (A) competitive
解説: 「競争上の優位性を得るためにAIを導入する」という文脈から、”competitive edge”(競争上の優位性)が適切です。
(2) (C) vulnerable
解説: 「繰り返しの作業に関わる仕事は特に自動化に対して脆弱である」という意味で、”vulnerable”(脆弱な)が適切です。
(3) (A) creative
解説: 「AIによって人間はより創造的で意味のある仕事に集中できる」という文脈から、”creative”(創造的な)が適切です。
(4) (B) inequality
解説: 「AIの恩恵が社会的不平等や失業を引き起こす可能性がある」という文脈から、”inequality”(不平等)が適切です。
(5) (C) everyone
解説: 「AI技術が一部の人々だけでなく、すべての人々に利益をもたらすようにする」という文脈から、”everyone”(すべての人々)が適切です。
(6) (C) unemployed
解説: 「移行期間中に一時的に失業する可能性のある個人を支援する」という文脈から、”unemployed”(失業した)が適切です。
英語長文 空所補充 (応用)【音読用 英文】
AI and Employment
In recent years, artificial intelligence (AI) has begun to transform workplaces across various industries. From automated customer service chatbots to advanced data analysis, AI is streamlining operations and improving efficiency. Many businesses have adopted AI not only to cut costs but also to gain a competitive edge.
However, the rise of AI has sparked concerns about its impact on employment. Jobs involving repetitive tasks, such as data entry and basic customer support, are especially vulnerable to automation. According to a recent study, nearly 40% of workers in developed countries may see their roles replaced or significantly altered by AI within the next two decades.
Despite these concerns, experts argue that AI will also generate new types of jobs. For instance, there will be greater demand for AI specialists, data analysts, and ethics consultants who can help guide the responsible development of AI technologies. In addition, some believe that by automating routine tasks, AI will allow humans to focus on more creative and meaningful work.
Still, the transition will not be easy. Governments and companies must invest in education and retraining programs to help workers adapt to this rapidly changing job market. Without such efforts, the benefits of AI may come at the cost of social inequality and widespread unemployment.
In this context, many policymakers are calling for closer cooperation between the public and private sectors. They emphasize the importance of building inclusive strategies that ensure AI technologies are developed and applied in ways that benefit everyone, not just a select few. One proposed approach is the introduction of a universal basic income to support individuals who may be temporarily unemployed during the transition period.
Unit01【和文】
AIと雇用
近年、人工知能(AI)がさまざまな業界の職場を変革し始めている。自動化された顧客サービスのチャットボットから高度なデータ分析まで、AIは業務を合理化し、効率を向上させている。多くの企業がコスト削減のためだけでなく、競争力を得るためにもAIを導入している。
しかし、AIの台頭は雇用への影響に懸念を呼んでいる。データ入力や基本的なカスタマーサポートなど、反復作業を伴う仕事は特に自動化の影響を受けやすい。最近の調査によると、先進国の労働者の40%近くが、今後20年以内にAIに取って代わられるか、その役割が大きく変わる可能性があるという。
こうした懸念にもかかわらず、専門家はAIが新しいタイプの仕事も生み出すと主張している。例えば、AIの専門家、データアナリスト、AI技術の責任ある開発を指導できる倫理コンサルタントの需要が高まるだろう。さらに、AIが定型業務を自動化することで、人間はより創造的で意義のある仕事に集中できるようになるという意見もある。
それでも移行は容易ではない。政府と企業は、労働者がこの急速に変化する雇用市場に適応できるよう、教育や再教育プログラムに投資しなければならない。そのような取り組みがなければ、AIの恩恵は社会的不平等と広範な失業の代償としてもたらされるかもしれない。
こうした背景から、多くの政策立案者が官民の緊密な協力を求めている。彼らは、AI技術が一部の人たちだけでなく、すべての人に利益をもたらす方法で開発・応用されるよう、包括的な戦略を構築することの重要性を強調している。提案されているアプローチのひとつは、移行期間中に一時的に失業する可能性のある個人を支援するためのユニバーサル・ベーシック・インカムの導入である。
- 問題
- 解答
- フレーズリーディング
- 音読
英語長文 内容一致 (標準:英検2級・日東駒専)
AI and Its Impact on Jobs
Artificial intelligence (AI) is transforming the way people work, bringing both opportunities and challenges to the job market. As AI systems become more advanced, they are increasingly capable of performing tasks traditionally carried out by humans. This shift has significant implications for various industries and the future of employment.
One of the key benefits of AI in the workplace is its ability to automate repetitive tasks. In industries such as manufacturing and logistics, AI-powered robots can handle tasks like assembly, packaging, and inventory management with high efficiency. This allows human workers to focus on more complex and creative responsibilities, potentially leading to greater job satisfaction.
AI is also making significant contributions in fields like healthcare and education. For example, AI systems can assist doctors in diagnosing diseases or help teachers create personalized learning plans for students. These applications have the potential to improve the quality of services while enabling professionals to work more effectively.
However, the rise of AI also presents challenges, particularly in terms of job displacement. Many routine and low-skill jobs are at risk of being replaced by AI systems, leading to concerns about unemployment and economic inequality. To address these challenges, governments and organizations are emphasizing the importance of reskilling and upskilling workers so they can adapt to the changing job market.
Another issue is the ethical considerations surrounding AI in the workplace. Questions about privacy, data security, and decision-making transparency are critical as AI systems take on more responsibilities. Ensuring that AI is used responsibly and equitably will be key to realizing its benefits while minimizing its drawbacks.
The impact of AI on jobs will depend largely on how societies respond to these changes. By embracing lifelong learning and developing policies that support workers, it is possible to create a future where AI enhances human potential rather than replacing it.
Questions
1.What is one benefit of AI in the workplace mentioned in the passage?
(A) It eliminates all human jobs.
(B) It automates repetitive tasks.
(C) It reduces efficiency in manufacturing.
(D) It makes low-skill jobs more important.
2.How does AI contribute to fields like healthcare and education?
(A) By replacing doctors and teachers entirely.
(B) By assisting professionals and improving services.
(C) By automating all aspects of patient care and teaching.
(D By reducing the need for skilled professionals.
3.What is one challenge associated with the rise of AI?
(A) An increase in repetitive tasks for workers.
(B) Job displacement in routine and low-skill roles.
(C) A decline in the demand for lifelong learning.
(D) Complete elimination of economic inequality.
4.What ethical issue is raised by the use of AI in the workplace?
(A) Concerns about economic growth.
(B) Transparency in decision-making.
(C) Increased reliance on manual labor.
(D) Reduced focus on job satisfaction.
5.What does the passage suggest about the future of AI in the workplace?
(A) Societies must adapt to changes through lifelong learning.
(B) AI will lead to the permanent loss of all jobs.
(C) Governments should avoid policies that support workers.
(D) AI will only impact manufacturing and logistics.
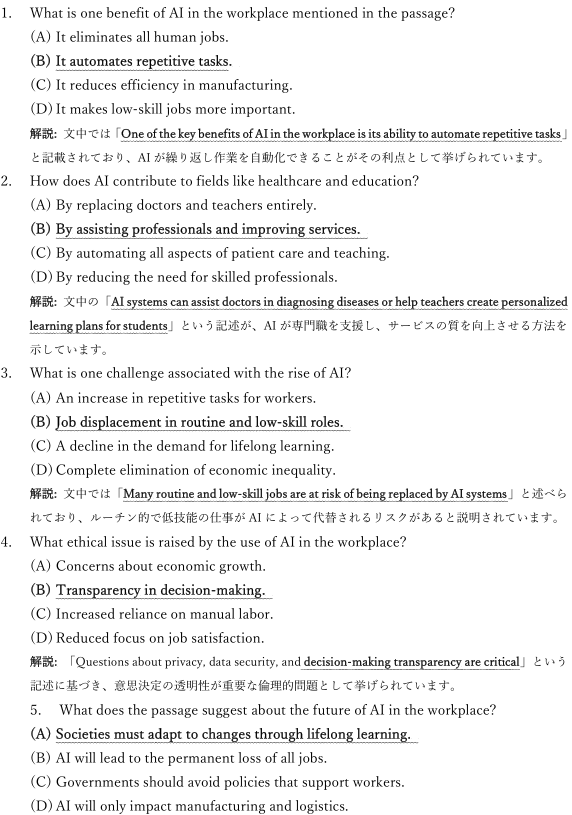
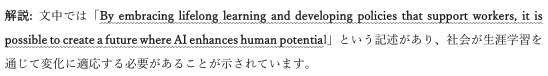
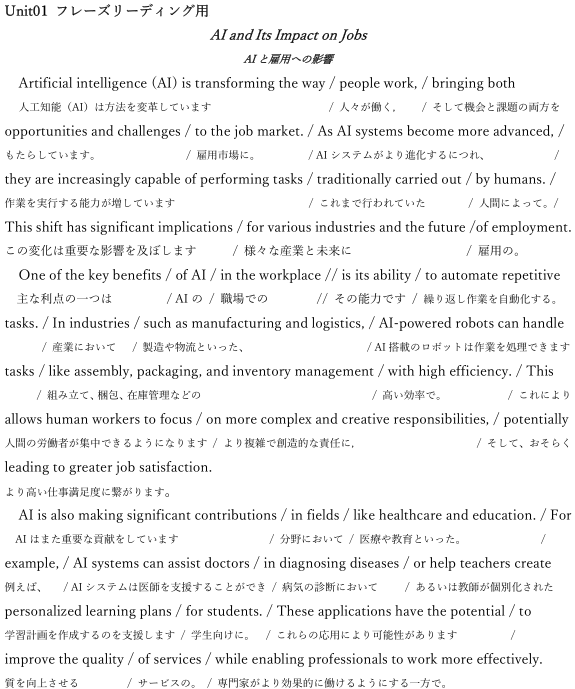
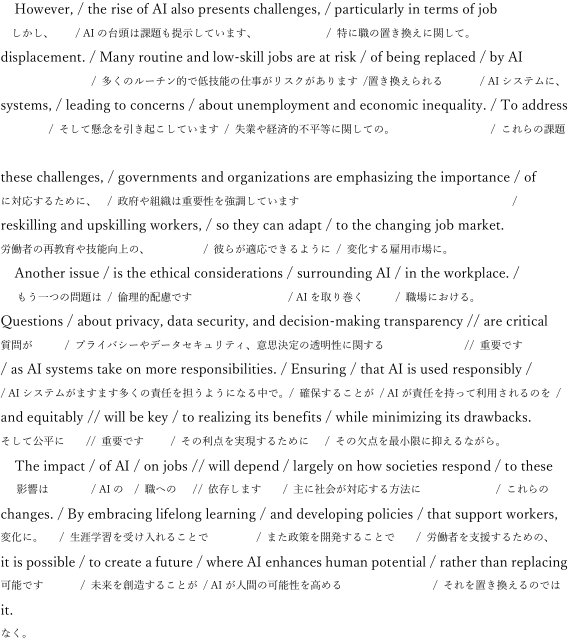
英語長文 内容一致 (標準) 音読用
(英文)
AI and Its Impact on Jobs
Artificial intelligence (AI) is transforming the way people work, bringing both opportunities and challenges to the job market. As AI systems become more advanced, they are increasingly capable of performing tasks traditionally carried out by humans. This shift has significant implications for various industries and the future of employment.
One of the key benefits of AI in the workplace is its ability to automate repetitive tasks. In industries such as manufacturing and logistics, AI-powered robots can handle tasks like assembly, packaging, and inventory management with high efficiency. This allows human workers to focus on more complex and creative responsibilities, potentially leading to greater job satisfaction.
AI is also making significant contributions in fields like healthcare and education. For example, AI systems can assist doctors in diagnosing diseases or help teachers create personalized learning plans for students. These applications have the potential to improve the quality of services while enabling professionals to work more effectively.
However, the rise of AI also presents challenges, particularly in terms of job displacement. Many routine and low-skill jobs are at risk of being replaced by AI systems, leading to concerns about unemployment and economic inequality. To address these challenges, governments and organizations are emphasizing the importance of reskilling and upskilling workers so they can adapt to the changing job market.
Another issue is the ethical considerations surrounding AI in the workplace. Questions
about privacy, data security, and decision-making transparency are critical as AI systems take on more responsibilities. Ensuring that AI is used responsibly and equitably will be key to realizing its benefits while minimizing its drawbacks.
The impact of AI on jobs will depend largely on how societies respond to these changes. By embracing lifelong learning and developing policies that support workers, it is possible to create a future where AI enhances human potential rather than replacing it.
(和文)
AIと雇用への影響
人工知能(AI)は人々の働き方を変革し、雇用市場に機会と課題の両方をもたらしています。AIシステムがより進化するにつれ、これまで人間によって行われていた作業を実行する能力が増しています。この変化は、さまざまな産業と雇用の未来に重要な影響を及ぼします。
職場でのAIの主な利点の一つは、繰り返し作業を自動化する能力です。製造や物流といった産業において、AI搭載のロボットは組み立て、梱包、在庫管理などの作業を高い効率で処理できます。これにより、人間の労働者がより複雑で創造的な責任に集中できるようになり、結果としてより高い仕事満足度に繋がる可能性があります。
また、AIは医療や教育といった分野において重要な貢献をしています。例えば、AIシステムは病気の診断において医師を支援したり、教師が学生向けに個別化された学習計画を作成するのを助けたりします。これらの応用により、サービスの質を向上させる可能性があり、専門家がより効果的に働けるようになります。
しかし、AIの台頭は課題も提示しています。特に、職の置き換えに関してです。多くのルーチン的で低技能の仕事がAIシステムに置き換えられるリスクがあり、失業や経済的不平等に関する懸念を引き起こしています。これらの課題に対応するために、政府や組織は労働者の再教育や技能向上の重要性を強調しています。
もう一つの問題は、職場におけるAIを取り巻く倫理的配慮です。プライバシーやデータセキュリティ、意思決定の透明性に関する問題は、AIシステムがますます多くの責任を担うようになる中で重要です。AIが責任を持って公平に利用されることを確保することが、その利点を実現しながら欠点を最小限に抑えるために重要です。
AIが職に与える影響は主に社会がこれらの変化に対応する方法に依存します。生涯学習を受け入れ、労働者を支援するための政策を開発することで、AIが人間の可能性を置き換えるのではなく高める未来を創造することが可能です。
- 問題
- 解答
- 音読
英語長文 内容一致 (応用:英検準1級・GMARCH)
Use of AI in the Medical Field
Artificial Intelligence (AI) is rapidly transforming the healthcare industry. From assisting doctors in making accurate diagnoses to predicting patient outcomes, AI-powered technologies are enhancing the quality and efficiency of medical care. One of the most promising areas is the use of AI in medical imaging. Machine learning algorithms can analyze X-rays, CT scans, and MRIs with remarkable accuracy, sometimes even outperforming experienced radiologists.
Another important application is in drug discovery. Traditionally, developing a new drug can take over ten years and cost billions of dollars. AI can significantly shorten this process by analyzing massive datasets and identifying potential compounds more efficiently. For instance, during the COVID-19 pandemic, AI tools were used to search for existing drugs that might be effective against the virus, speeding up the early stages of treatment development.
AI is also being integrated into personalized medicine. By examining an individual’s genetic data, lifestyle, and medical history, AI systems can help doctors tailor treatment plans to meet each patient’s unique needs. This personalized approach has the potential to improve treatment outcomes and reduce side effects.
However, the use of AI in healthcare also raises concerns. One issue is data privacy. AI systems rely on large amounts of patient data, and protecting this sensitive information is critical. If such data were to be leaked or misused, it could result in serious harm. Another concern is the lack of transparency in how AI algorithms make decisions, often referred to as the “black box” problem. This can make it difficult for doctors and patients to fully trust the recommendations generated by AI.
Despite these concerns, most experts agree that AI will play an increasingly important role in the future of healthcare. The key is to find a balance between innovation and responsibility, ensuring that AI technologies are used in ways that respect patient rights and support medical professionals.
Q1. What is one benefit of using AI in medical imaging?
(A) It reduces the number of patients needing treatment.
(B) It can sometimes be more accurate than human experts.
(C) It eliminates the need for radiologists entirely.
(D) It prevents the spread of disease.
Q2. How does AI contribute to drug discovery?
(A) By testing drugs directly on patients.
(B) By automatically manufacturing new medicines.
(C) By speeding up the search for effective compounds.
(D) By avoiding the need for clinical trials.
Q3. What does the passage suggest about personalized medicine?
(A) It uses AI to make general treatment plans.
(B) It creates the same treatment for every patient.
(C) It helps doctors create treatments suited to individual needs.
(D) It is still not possible even with AI.
Q4. What is one concern related to using AI in healthcare?
(A) AI systems may be too cheap to maintain quality.
(B) AI might take over all decision-making from doctors.
(C) Patient data could be exposed or misused.
(D) Hospitals do not allow the use of AI systems.
Q5. What is the “black box” problem?
(A) Patients refusing to accept AI in treatment.
(B) AI systems making decisions that are hard to understand.
(C) The loss of physical records in hospitals.
(D) Power failures in AI equipment.
Q6. What is the author’s attitude toward AI in healthcare?
(A) Completely negative due to privacy concerns.
(B) Supportive but cautious about risks.
(C) Uninterested in new technologies.
(D) Neutral and undecided.
Q7. Which of the following is NOT mentioned in the passage?
(A) AI may improve treatment outcomes.
(B) AI helps in analyzing patient data.
(C) AI makes all medical decisions without human input.
(D) AI was used in response to the COVID-19 pandemic.
英語長文 内容一致 (応用) 【解答・解説】
Use of AI in the Medical Field
Artificial Intelligence (AI) is rapidly transforming the healthcare industry. From assisting doctors in making accurate diagnoses to predicting patient outcomes, AI-powered technologies are enhancing the quality and efficiency of medical care. One of the most promising areas is the use of AI in medical imaging. Machine learning algorithms can analyze X-rays, CT scans, and MRIs with remarkable accuracy, sometimes even outperforming experienced radiologists.
Another important application is in drug discovery. Traditionally, developing a new drug can take over ten years and cost billions of dollars. AI can significantly shorten this process by analyzing massive datasets and identifying potential compounds more efficiently. For instance, during the COVID-19 pandemic, AI tools were used to search for existing drugs that might be effective against the virus, speeding up the early stages of treatment development.
AI is also being integrated into personalized medicine. By examining an individual’s genetic data, lifestyle, and medical history, AI systems can help doctors tailor treatment plans to meet each patient’s unique needs. This personalized approach has the potential to improve treatment outcomes and reduce side effects.
However, the use of AI in healthcare also raises concerns. One issue is data privacy. AI systems rely on large amounts of patient data, and protecting this sensitive information is critical. If such data were to be leaked or misused, it could result in serious harm. Another concern is the lack of transparency in how AI algorithms make decisions, often referred to as the “black box” problem. This can make it difficult for doctors and patients to fully trust the recommendations generated by AI.
Despite these concerns, most experts agree that AI will play an increasingly important role in the future of healthcare. The key is to find a balance between innovation and responsibility, ensuring that AI technologies are used in ways that respect patient rights and support medical professionals.
Q1. What is one benefit of using AI in medical imaging?
(A) It reduces the number of patients needing treatment.
(B) It can sometimes be more accurate than human experts.
(C) It eliminates the need for radiologists entirely.
(D) It prevents the spread of disease.
【解説】医療画像診断でAIは経験豊富な放射線科医を上回る精度を持つことがあると明記されています。
Q2. How does AI contribute to drug discovery?
(A) By testing drugs directly on patients.
(B) By automatically manufacturing new medicines.
(C) By speeding up the search for effective compounds.
(D) By avoiding the need for clinical trials.
【解説】AIは莫大なデータを分析し、候補化合物を効率的に特定することで、薬の開発期間を短縮します。
Q3. What does the passage suggest about personalized medicine?
(A) It uses AI to make general treatment plans.
(B) It creates the same treatment for every patient.
(C) It helps doctors create treatments suited to individual needs.
(D) It is still not possible even with AI.
【解説】遺伝情報や生活習慣などに基づき、個別に適した治療計画を立てられるのがAIの利点。
Q4. What is one concern related to using AI in healthcare?
(A) AI systems may be too cheap to maintain quality.
(B) AI might take over all decision-making from doctors.
(C) Patient data could be exposed or misused.
(D) Hospitals do not allow the use of AI systems.
【解説】個人データがAIに使われることでプライバシー侵害の懸念があります。
Q5. What is the “black box” problem?
(A) Patients refusing to accept AI in treatment.
(B) AI systems making decisions that are hard to understand.
(C) The loss of physical records in hospitals.
(D) Power failures in AI equipment.
【解説】AIがどのように判断を下しているのかが不透明(=ブラックボックス)であることが問題。
Q6. What is the author’s attitude toward AI in healthcare?
(A) Completely negative due to privacy concerns.
(B) Supportive but cautious about risks.
(C) Uninterested in new technologies.
(D) Neutral and undecided.
【解説】イノベーションと責任のバランスが重要だと結論しているため、前向きかつ慎重な態度です。
Q7. Which of the following is NOT mentioned in the passage?
(A) AI may improve treatment outcomes.
(B) AI helps in analyzing patient data.
(C) AI makes all medical decisions without human input.
(D) AI was used in response to the COVID-19 pandemic.
【解説】 「AIがすべての医療判断を行う」という内容は記述されていません。
英語長文 内容一致 (応用)【音読用 英文】
Use of AI in the Medical Field
Artificial Intelligence (AI) is rapidly transforming the healthcare industry. From assisting doctors in making accurate diagnoses to predicting patient outcomes, AI-powered technologies are enhancing the quality and efficiency of medical care. One of the most promising areas is the use of AI in medical imaging. Machine learning algorithms can analyze X-rays, CT scans, and MRIs with remarkable accuracy, sometimes even outperforming experienced radiologists.
Another important application is in drug discovery. Traditionally, developing a new drug can take over ten years and cost billions of dollars. AI can significantly shorten this process by analyzing massive datasets and identifying potential compounds more efficiently. For instance, during the COVID-19 pandemic, AI tools were used to search for existing drugs that might be effective against the virus, speeding up the early stages of treatment development.
AI is also being integrated into personalized medicine. By examining an individual’s genetic data, lifestyle, and medical history, AI systems can help doctors tailor treatment plans to meet each patient’s unique needs. This personalized approach has the potential to improve treatment outcomes and reduce side effects.
However, the use of AI in healthcare also raises concerns. One issue is data privacy. AI systems rely on large amounts of patient data, and protecting this sensitive information is critical. If such data were to be leaked or misused, it could result in serious harm. Another concern is the lack of transparency in how AI algorithms make decisions, often referred to as the “black box” problem. This can make it difficult for doctors and patients to fully trust the recommendations generated by AI.
Despite these concerns, most experts agree that AI will play an increasingly important role in the future of healthcare. The key is to find a balance between innovation and responsibility, ensuring that AI technologies are used in ways that respect patient rights and support medical professionals.
英語長文 内容一致 (応用)【和文】
医療分野におけるAIの活用
人工知能(AI)は、医療業界を急速に変革しています。医師の診断支援から患者の予後予測まで、AI技術は医療の質と効率を高めています。特に注目されているのが、医療画像への応用です。機械学習アルゴリズムは、X線、CTスキャン、MRIを非常に高い精度で分析でき、時には経験豊富な放射線科医を上回ることさえあります。
もう一つ重要な応用例は、新薬の開発です。従来、新薬の開発には10年以上の歳月と数十億ドルのコストがかかります。AIは膨大なデータを分析して、有望な化合物を効率的に 特定することで、このプロセスを大幅に短縮できます。例えばCOVID-19のパンデミック時には、既存の薬の中から有効なものを見つけるためにAIが活用され、治療開発の初期段階を加速させました。
AIは、個別化医療にも組み込まれています。遺伝情報、生活習慣、病歴などをもとにAIが解析し、各患者に適した治療計画を医師が立てる手助けをします。このような個別対応は、治療効果の向上や副作用の軽減につながる可能性があります。
しかし、医療分野でのAIの活用には懸念もあります。一つはデータのプライバシー問題です。AIは膨大な患者データを必要とするため、情報の保護が極めて重要です。もしデータが流出したり悪用されたりすれば、深刻な被害が生じる可能性があります。また、AIの判断プロセスが不透明である「ブラックボックス問題」もあります。これにより、医師や患者がAIの提案を完全に信頼することが難しくなるのです。
それでも、多くの専門家は、AIが医療の未来においてますます重要な役割を果たすと考えています。重要なのは、革新と責任のバランスを取りながら、AIが患者の権利を尊重し、医療従事者を支援する形で活用されるようにすることです。
【和文要約の学習ポイント】
- まず、「最初は必ずノーヒントで自力で要約を書く」ことが大切です。辞書や解答に頼らず、英文を自分の力で読み取りながら、各段落で重要だと思う語句に下線を引きます。そのうえで、下線部をもとに各段落の要点をまとめ、最後に一つの段落に統合します。その後で模範解答の要約と見比べます。このとき、要約が一字一句同じである必要はありません。
- 模範解答と自分の要約を比較し、共通する要素と、自分の要約に欠けている要素を確認します。そのうえで、削りすぎた部分や不要な部分を見直すことで、どの情報が「要約に必要か」を判断する力が養われます。
- 文字数を気にして少なく書くよりも、最初はオーバー気味に書いておくのがおすすめです。短く書こうとすると、同じ内容を言い換えたり繰り返したりして、内容が薄くなりがちです。むしろ、幅広く要素を盛り込んだうえで、重複や重要度の低い部分を削って文字数を調整する方が、内容が充実し、要約力の上達も早くなります。
【和文要約における論理構成と情報の取捨選択のコツ】
① 段落ごとの論理展開を見抜く
英文は多くの場合、三段構成(導入・展開・結論)で書かれています。
まずは各段落の「役割」と「中心文(topic sentence)」を見つけましょう。
| 段落 | よくある構成 | 着目ポイント |
| 第1段落 | テーマ提示・問題提起 | 筆者が「何について述べたいのか」。最初か2文目にテーマ文(主題)がある。 |
| 第2段落 | 具体例・理由・背景 | 「なぜ」「どのように」という説明が中心。主張の根拠や例示が多い。 |
| 第3段落 | まとめ・主張・提言 | 筆者の結論や意見、今後の見通しなどが述べられる。最後の1~2文が要点。 |
段落ごとに以下を1行でメモするのがおすすめです:①何を述べているか ②どんな関係で前段落とつながっているか(例:理由、対比、結果など)
② 段落同士の関係を理解する
要約では、段落の「つながり(論理関係)」を理解することが重要です。段落間の関係は次のようなパターンで表せます。
| 構成パターン | 段落のつながり | 要約に入れるべき情報 |
| ①「問題 → 理由 → 解決策」 | 1段落=問題提起/2段落=原因説明/3段落=提案 | 問題の概要+筆者の主張(解決策)を中心に。原因は簡潔に。 |
| ②「主張 → 例 → 再主張」 | 1段落=主張/2段落=事例/3段落=再確認 | 主張と事例の関係を1文でまとめる。事例は簡潔に。 |
| ③「現状 → 対立意見 → 筆者の立場」 | 1段落=現状説明/2段落=反対意見/3段落=筆者の見解 | 筆者の最終的立場を中心に、前提として現状・対立の概要を一文で添える。 |
段落を読んだら、「この段落は筆者の主張を支えるためにどんな役割を果たしているか」を一言で説明できるようにします。
→ 例:「第2段落は主張を裏づける理由を述べている」など。
③ 要約に盛り込む情報の範囲
要約に入れるべき情報は、「筆者の主張に直結する要素」に限ります。以下のように考えると整理しやすいです。
| 情報の種類 | 要約に含めるか | 判断基準 |
| 全体のテーマ(話題) | ✅ 必ず含める | 「何について書かれているか」を最初の一文で示す。 |
| 筆者の最終的主張 | ✅ 必ず含める | 最後の段落の結論部分。要約の核になる。 |
| 主張を支える主要理由・要素 | ✅ 簡潔に含める | 「なぜそう言えるか」を1~2文で要約。 |
| 具体例・データ・固有名詞 | ❌ 基本は削除 | 主張理解に不可欠でない限り省く。 |
| 比喩・背景説明・補足情報 | ❌ 省略 | 内容を薄める原因になりやすい。 |
目安:
200~250語の英文を150~180字でまとめる場合、各段落から最も重要な1点ずつ(計3点)を抜き出し、それらを「テーマ提示 → 理由や背景 → 主張や提案」の順に1段落で整理する。
④ 情報の取捨選択の実践手順
- 各段落で重要語句に下線を引く(topic sentence と supporting ideas)
- 下線部のうち、「筆者の立場を支える内容」に印をつける
- 例や数字、補足説明などを削除する
- 残った内容を「テーマ → 理由 → 主張」の流れで日本語に並べる
- 全体を150~180字に収まるように削りながら、意味の流れを滑らかに整える
まとめ(学習のコツ)
- 各段落の「主題文」と「役割」を意識する。
- 筆者の立場(どちら側か)と主張(何を言いたいか)を最優先で押さえる。
- 具体例や数字は原則カット。ただし、筆者の主張を支える“象徴的な例”であれば短く残してもよい。
- 最後に、要約を読んだときに「この英文のテーマと筆者の結論がわかるか」を確認する。
英検(2級・準1級)
英語を聞き取れるようになるためには 精聴と多聴の2つの方法があります。
① 精聴
精聴とは、英語をじっくり理解しながら何度も繰り返し聞くことです。
※ これに対して「多聴」は、大まかな意味をつかみながらたくさん聞くことを指します。
精聴のポイント
✅ 短時間でも意味のわかる英語を聞く!
✅ スクリプトと解説がある教材を使う!
✅ 中学レベルの簡単な英語から始める!
✅ 一語一句を暗記するくらい繰り返す!
精聴を続けると…
✅ 聞こえる音と実際の英語が一致する
✅ カタカナ英語の発音から抜け出せる
✅ 音の変化(リエゾン)を感覚で理解できる
例えば…
💬like it は 『ライク イット』 ではなく 『ライキッ』
精聴のコツ
✅簡単な会話集(1スキット30秒)を選ぶ!
✅「理解したら終わり」ではなく聞き込む!
✅音変化・イントネーション・文法に注意!
✅シャドーイングやディクテーション活用!
📌 シャドーイング
聞こえた英語の音をそのままマネして発音
📌 ディクテーション
聞こえた英語を一語一句書き取る練習
② 多聴
多聴とは、一語一句を完璧に聞き取るのではなく、大まかに意味をつかむ練習です。
例えば…
💬「あ~、これは旅行の話だな」
💬「だいたい仕事の話をしているっぽい」
多聴のポイント
✅ すべての単語を聞き取る必要はない!
✅ 「何の話なのか」をつかむことが大事!
✅ 少しレベルが高めの英語を使う!
多聴のステップ
1️⃣ まずはスクリプトなしで一度聞いてみる
(どのくらい理解できるかチェック!)
2️⃣ 3~5回くり返し聞く
(少しずつ細かい部分を聞き取る)
3️⃣ スクリプトを見て答え合わせ
(聞き取れなかった単語を確認!)
4️⃣ もう一度スクリプトなしで聞く
(理解できるかチェック!)
5️⃣ 重要な単語やフレーズをメモする
(ノートや単語帳に書き出すのもOK!)
多聴のコツ
✅ 聞き取れない音があっても落ち込まない!
✅ 「何の話か」をつかむことを優先する!
✅ 学習した音源は「ながら聞き」で復習!
まとめ
📌 リスニングの基本は「精聴」と「多聴」!
📌 初心者は「精聴」からスタート!
📌 英語の音を理解をマスター➡「多聴」へ!
📌 既習音源➡「ながら聞き」で何度も復習!
- Dialogue
- Monologue
【共通テストレベル】
(音声:音読さん)
男女が箱について話しています。
Why is she asking him to help her move the boxes?
① The boxes are heavy.
② There are too many boxes.
③ The members are busy.
④ She is tired.
- ➡
- 正解
- スクリプト・訳
②
<be動詞の現在形>
Woman: Kelly, can you help me?
Man: OK. What can I do for you?
W: Please help me carry these boxes to the third floor.
M: Sure. Are the boxes heavy?
W: No, they are all light. There are just too many.
M: I see. We need more help. Let’s ask the members of the sales department for help.
W: OK. They’re not busy today.
M: That’s good news.
訳
女:ケリー、ちょっと手伝ってもらえる?
男:オーケー。何をすればいい?
女:これらの箱を3階まで運ぶのを手伝って。
男:いいよ。箱は重いの?
女:いいえ、全部軽いわ。ただ、たくさんありすぎて。
男:そうか。もっと手伝いが必要だね。営業部のメンバーに手伝いを頼んでみよう。
女:そうね。今日はあの人たち、忙しくないもの。
男:それは良かった。
【英検2級レベル】
(音声:音読さん)
Where is the central train station located according to the conversation?
① Two blocks straight, then left at the intersection.
② Two blocks straight, then right at the intersection.
③ Five blocks straight, then right at the intersection.
④ Five blocks straight, then left at the intersection.
- ➡
- 正解
- スクリプト・訳
②
道案内
A: Excuse me, can you help me? I’m trying to get to the central train station.
B: Sure! Walk straight for two blocks and then turn right at the big intersection.
A: Is it far from here?
B: Not really. It should take about five minutes on foot.
A: Thank you very much for your help!
B: You’re welcome. Have a nice day!
訳:
A: すみません、助けてもらえますか?中央駅に行こうとしているんですが。
B: もちろん!2ブロックまっすぐ進んで、大きな交差点で右に曲がってください。
A: ここから遠いですか?
B: いや、徒歩で約5分くらいですよ。
A: ご親切にありがとうございます!
B: どういたしまして。よい一日を!
【英検準1級レベル】
(音声:音読さん)
What does the man suggest in response to the issue of single-use plastics?
① Encouraging the use of more sustainable alternatives.
② Banning all plastic products.
③ Stopping recycling programs.
④ Ignoring the problem.
- ➡
- 正解
- スクリプト・訳
①
環境問題
M: Have you considered the detrimental effects of single-use plastics on marine ecosystems?
W: I have, and it’s alarming how these plastics disrupt the food chain and harm wildlife.
M: We really need to advocate for sustainable alternatives and stricter recycling measures.
W: Absolutely, both individuals and governments must take responsibility.
M: I hope our efforts will eventually lead to a healthier environment.
W: Collective action is indeed our best hope.
訳:
M: 使い捨てプラスチックが海洋生態系に与える悪影響について考えたことはありますか?
W: はい、これらのプラスチ用プラスチックが食物連鎖を乱し、野生動物に害を及ぼしているのは衝撃的です。
M: 持続可能な代替品と、より厳格なリサイクル措置を推進する必要がありますね。
W: 全くその通りです。個人も政府も責任を持つべきです。
M: 私たちの努力がやがてより健全な環境につながることを願っています。
W: 集合的な行動こそが最良の希望です。
スピーキングにおいてもリスニング同様に「英語を英語のまま理解する」ことが重要です。
リスニングの場合
英語を聞いて、そのままイメージを思い浮かべられることが理想です。例えば、 "He is a good tennis player."(彼はテニスが上手です) この文を聞いたときに、次の2つの方法で理解できます。
① 日本語を経由する方法(初心者向け)
英語を聞く ⇒ 日本語で理解 ⇒ 様子を思い浮かべる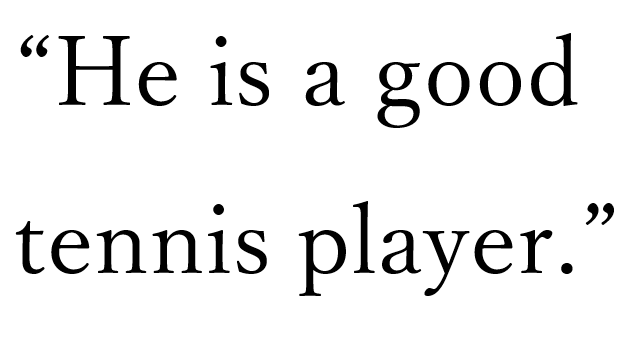 ⇒
⇒ 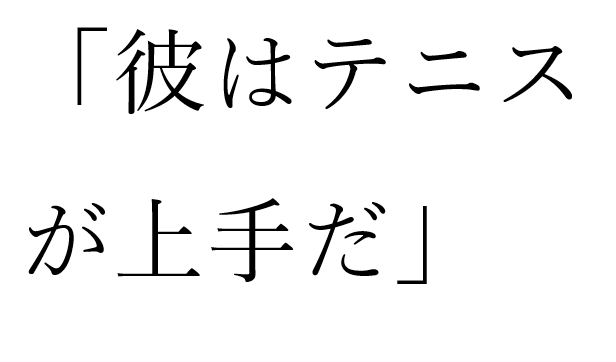 ⇒
⇒
② 直接イメージする方法(理想的な形)
英語を聞く ⇒ 様子を思い浮かべる
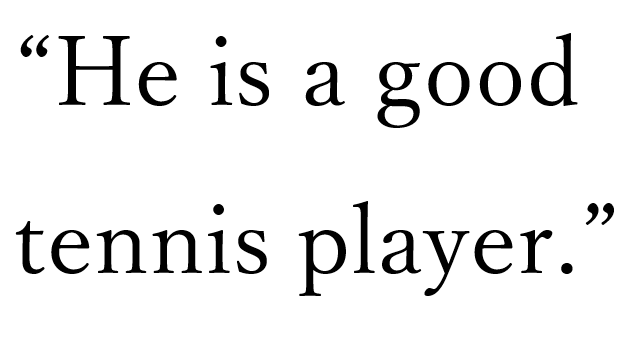 ⇒
⇒
初心者のうちは①の方法になりますが、最終的には②の方法で英語を理解できるようになるのが目標です。
スピーキングの場合
英語を話すときも次の2つの方法があります。
① イメージで直接英語を話す(理想的な形)
様子を思い浮かべる ⇒ イメージをそのまま英語ヘ
 ⇒
⇒ 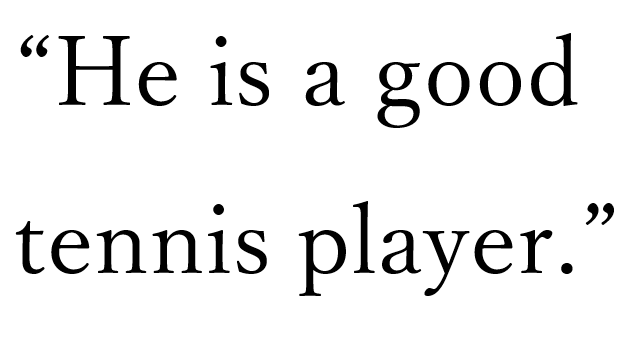
② 日本語を考えてから英語ヘ(初心者向け)
様子を思い浮かべる ⇒ 日本語で考える ⇒ 英語に変換
 ⇒
⇒ 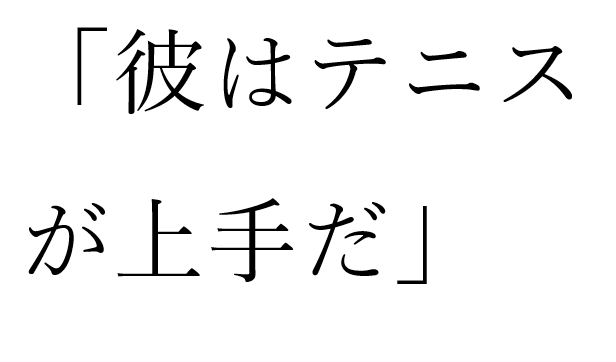 ⇒
⇒ 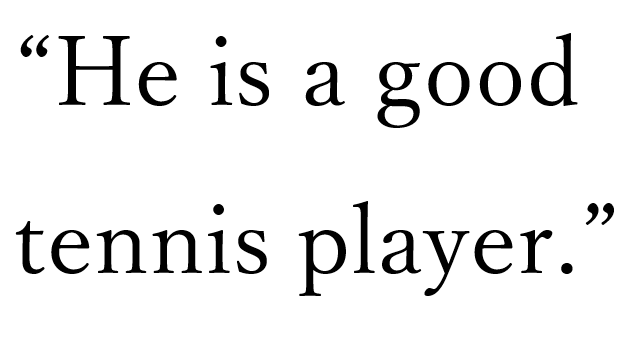
英語をスムーズに話せるようになるには、②の段階から①に移行することが大切です。そのトレーニングには瞬間英作文が有効です。
瞬間英作文
瞬間英作文は、日本語の文章をすぐに英語に変えて口に出すトレーニングです。この練習を続けることで、英語をスムーズに話せるようになります。
瞬間英作文のコツ
初心者のうちは、日本語を一語ずつ英語に変換しがちです。
✖悪い例
1. 彼は → He
2. 〜です → is
3. 上手な → good
4. テニスをする人 → a tennis player
このやり方だと、話すのに時間がかかってしまいます。
〇 良い例
1.「彼はテニスが上手だ」とイメージする
2. "He is a good tennis player." と英語へ
つまり、英語を話すときも 「イメージ → 英語」 の流れが重要です。
「日本語 → イメージ → 英語」の習慣をつける
瞬間英作文をするときは、日本語を単なる翻訳のツールにしないことが大切です。
日本語を一語ずつ訳すのではなく、イメージを英語にする意識を持ちましょう。
例えば:
「彼はテニスが上手だ」 という文章を見たら、テニスをしている彼の姿をイメージする
そのイメージを英語で表現する → "He is a good tennis player."
このように、英語を「絵」として思い浮かべながら話すこと を意識すると、日本語を介さずに英語が口から出るようになります。
瞬間英作文が効果的な理由
このトレーニングを続けると、さまざまなシチュエーションに対応できるようになります。
いろんな場面を想像しながら英語にすることで、表現の幅が広がります。
まとめ
✅ 英語を「イメージ」で理解する習慣付け
✅ 一語ずつ訳さず全体のイメージで英語へ
✅ 「日本語 → イメージ → 英語」の習得
上記により日本語を介さずに英語が話せるようになる
初心者でも、毎日少しずつ瞬間英作文を続けることで、英語をスムーズに話せるようになります!マスターすれば、英検などのスピーキングスコアも向上します。
(標準:英検2級スピーキングQ3&4形式)
●●●は英文
1 AIがいつもあなたの仕事に役立つとは限らない。人間の感情が必要な仕事もあり、AIにはそのような感情はない。 ●●●
2 プラスチックごみは環境に良くない。リサイクルのためにプラスチック製品を燃やすと、地球温暖化の原因となるCO2を排出する。 ●●●
3 ファーストフードをよく食べるのは健康に良くない。毎日昼にハンバーガーを食べると栄養不足になる。 ●●●
4 プラスチックゴミは環境に良くない。店は買い物袋を持参させるべきだ。 ●●●
5 買いたいものがあるとき、スマートフォンで簡単に注文できる。お店に行かなくていいので、時間の節約にもなる。 ●●●
6 人には好きなものを着る権利がある。男性が女性の服を着るのは自由だと思う。 ●●●
7 日本は海外から多くの製品を輸入し、それに頼っている。外国からの支援がなければ、日本人は生きていけないと思う。 ●●●
8 AI翻訳は読んだり書いたりするのには役に立つ。しかし、対面でのリアルタイムのコミュニケーションにおけるリスニングやスピーキングには役立たない。 ●●●
9 日本は核兵器を持つことを許されていない。他国が核兵器を持つのはフェアではない。 ●●●
10 オンラインゲームは幼い子供が友達を作るのに適している。学校では内気な子どもでも、家ではゲームで友情を育むことができる。 ●●●
11 タブレットで電子書籍を読むのは目に良くない。特に小さい子どもは目を守るために紙の本を読むべきだ。 ●●●
12 SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サイト)では無記名でメッセージを送ることができる。自分が攻撃されないので他人を攻撃しやすい。 ●●●
13 スマートフォンがあれば、買い物や勉強、ゲームなど、やりたいことが何でもできる。もはやスマートフォンなしでは生きていけない。 ●●●
14 インターネットができるスマートフォンを持っていれば、ビデオアプリを通して他の国の人とコミュニケーションができる。わざわざその国に行かなくてもいい。 ●●●
15 火星には水があると言われている。もしそうなら、そこに生物がいる可能性が高い。 ●●●
16 日本では自分の身を守るために銃を持つというルールはない。もしルールが変わって銃を持つようになったら、犯罪も増えると思う。 ●●●
17 食品に含まれる化学物質は健康に良くない。もし体内に入れれば、ガンのリスクを高めるかもしれない。 ●●●
18 地球温暖化は環境にとって大きな問題である。プラスチックごみを増やし、CO2を排出し続ければ、地球は生きていけなくなる。 ●●●
19 英語で正しくエッセイが書けるということは、英文法をよく理解しているということです。また、論理的思考ができるということでもある。 ●●●
20 田舎に住んだ方が子供にとって健康的だと思う。車や工場からの汚染が少ない。 ●●●
21 日本はほとんどの種類の食品を海外から輸入することができる。また、そのような食品は通常、日本で栽培されたものよりも安い。 ●●●
22 健康食品は高価なものが多い。新鮮な野菜を食べた方が安くて健康的だと思う。 ●●●
23 ペットと遊ぶとリラックスできる。ペットは寂しさを和らげてくれる。 ●●●
24 多くの教育用コンピューターゲームが学校で使われている。生徒は楽しいゲームをしながら学ぶことができる。 ●●●
25 スーパーマーケットはコンビニエンスストアより値段が安い。また、野菜や果物の種類も多い。 ●●●
26 他人を攻撃するネット犯罪はたくさんある。攻撃された人にとって、ソーシャルメディアは有害である。 ●●●
27 今の社会はますます忙しくなり、電話に出られなくなっている。ネットでメッセージを送るのは、電話するよりもずっと効率的だ。 ●●●
28 英語をマスターするには何年もかかる。できるだけ早くから学ぶべきだ。 ●●●
29 多くのスーパーマーケットが食品廃棄を減らす努力をしている。賞味期限が近づいた食品の販売価格を下げるところもある。 ●●●
30 人々は環境保護のためにもっと行動を起こす必要があることに気づいている。これは子供たちの未来のために重要である。 ●●●
31 スマートフォンにはたくさんの教育アプリケーションがある。生徒が各教科をより深く理解するのに役立つ。 ●●●
32 その国に住んでいる人に直接会った方が文化を理解できる。教科書やネットには載っていない話が聞ける。 ●●●
33 今ではインターネットを使って自宅で仕事ができる。また、オフィスに行く時間を無駄にしなくてすむ。 ●●●
34 スマートフォンでいつでも簡単に好きなものを注文できる。また、実店舗に行く時間も節約できる。 ●●●
35 オンラインレッスンはスクールに通う時間が節約できる。また、他の声に邪魔されずにレッスンが受けられる。 ●●●
36 スマートフォンでは好きな曲をいつでも簡単にダウンロードできる。また、ショップに行く手間も省ける。 ●●●
37 テレビよりユーチューブの方が情報が早い。また、より面白い様々な番組を見ることができる。 ●●●
38 最近はAIの技術が進歩している。天気予報や地震予報の精度やスピードも上がっている。 ●●●
39 無料の教育アプリがたくさんあり、勉強にかかるお金を節約できる。また、語学や芸術など、学びたいことをいつでも学ぶことができる。 ●●●
40 障がい者も行きたいところに行くべきだということを、人々は理解している。多くの公共の場所を改善することは、そのような人々にとって平等な社会のために重要である。 ●●●
41 日本にはまだ高品質の製品がたくさんある。他の国の人は簡単に技術を真似できない。 ●●●
42 24時間営業をやめれば夜中の犯罪が減る。また、労働者の残業も減る。 ●●●
43 人々は、化学薬品で作られた食品が健康に良くないことに気づいている。化学薬品を使っていない新鮮な果物や野菜を買う傾向がある。 ●●●
44 セキュリティーシステムが完全に確立されているわけではない。仮想通貨を使うことを怖がる人がまだ多い。 ●●●
45 学生はアルバイトをせずに授業に集中すべきだ。学校卒業後に実務経験を積むことができる。 ●●●
46 クレジットカードでお金を使いすぎるのは簡単だ。多くの人がクレジットカードの支払いに苦労している。 ●●●
47 親が子供に携帯電話を使わせることで、子どもの安全を守ることができる。いつでも子供の様子を見ることができる。 ●●●
48 英語は国際語だと言われている。もっと多くの場所で英語のアナウンスがあってもいいと思う。 ●●●
49 若い人が一人で家を借りるのは高すぎる。また、一緒に住むことはコミュニケーションのいい経験になる。 ●●●
50 子供に見せたくない。暴力的になるかもしれない。 ●●●
- 問題
- 模範解答
- ポイント
英文要約(標準:英検2級)
●以下の英文を読んで、その内容を45~55語の英語で要約し、解答欄に記入しなさい。
●解答は、解答用紙のB面にある英文要約解答欄に書きなさい。なお、解答欄の外に書かれたものは採点されません。
●解答が英文の要約になっていないと判断された場合は、0点と採点されることがあります。英文をよく読んでから答えてください。
Online learning has become more popular in recent years, especially after the global pandemic. Many schools and universities started offering classes over the internet so that students could continue studying from home. This trend is expected to continue even after the pandemic ends.
One of the main advantages of online learning is its flexibility. Students can attend classes from anywhere and often watch recorded lectures at any time. This makes it easier for people who work part-time or have family responsibilities to continue their education. In addition, schools can reach more students, even those living in remote areas.
However, online learning also has some drawbacks. It can be difficult for students to stay motivated and focused without face-to-face interaction. Some students may also lack access to stable internet or devices. Furthermore, teachers might struggle to keep students engaged during online lessons.
Online learning has become common since the pandemic. It offers flexibility and wider access to education, helping busy students and those in remote areas. However, it also causes problems such as low motivation, poor internet access, and difficulties for teachers to keep students engaged.
(パンデミック以降、オンライン学習が一般的になった。多忙な学生や遠隔地の学生にとって、柔軟で幅広い教育へのアクセスを提供する。しかし、モチベーションの低下、インターネットへのアクセスの悪さ、教師が生徒を飽きさせないことの難しさといった問題も生じている。。)
要約のポイント
以下の点を元の英文から「言い換え」て「短く」することに尽きます。
1.背景(背景情報の把握)
なぜそのトピックが重要なのか、いつから起こったのかを一文でまとめる。
2.メリット(良い点)
具体的な例を列挙せず、「何が良いのか」を大まかにまとめる。
3.デメリット(課題点)
複数の欠点が挙げられている場合、共通点や主要な問題に要約する。
4.文法と語彙は基礎レベルで
中学〜高校初級で学ぶ語彙・構文を使いながら、自然で読みやすくする。
言い換え
| 元の英文 | 要約での英文 |
| Online learning has become more popular in recent years, especially after the global pandemic. (オンライン学習は近年、特に世界的なパンデミック以降、より一般的になってきました。) | Online learning has become common since the pandemic. (パンデミック以降、オンライン学習は一般的になっています。) |
| This trend is expected to continue even after the pandemic ends. (この傾向は、パンデミックが終わった後も続くと予想されています。) | (「一般的になっている“has become common since the pandemic.”」という表現の中に暗示的に含まれています。) |
| One of the main advantages of online learning is its flexibility. (オンライン学習の主な利点のひとつは柔軟性です。) | It offers flexibility and wider access to education… (それは柔軟性と、より広い教育へのアクセスを提供します。) |
| Students can attend classes from anywhere and often watch recorded lectures at any time. (学生はどこからでも授業に参加でき、多くの場合、録画された講義をいつでも見ることができます。) | (「柔軟性を提供する“offers flexibility”」に要約されています。) |
| This makes it easier for people who work part-time or have family responsibilities to continue their education. (アルバイトをしている人や家庭の責任がある人にとって、学び続けやすくなります。) | …helping busy students… (忙しい学生を助ける) |
| In addition, schools can reach more students, even those living in remote areas. (さらに、学校はより多くの学生、特に遠隔地に住む人々にも届けることができます。) | …and those in remote areas. (遠隔地に住む人々にも) |
| It can be difficult for students to stay motivated and focused without face-to-face interaction. (対面の交流がないと、学生がやる気を保ったり集中したりするのが難しくなります。) | …low motivation… (やる気の低下) |
| Some students may also lack access to stable internet or devices. (一部の学生は安定したインターネットやデバイスを利用できないこともあります。) | …poor internet access… (インターネット環境の悪さ) |
| Furthermore, teachers might struggle to keep students engaged during online lessons. (さらに、教師はオンライン授業中に生徒を引きつけ続けるのに苦労するかもしれません。) | …difficulties for teachers to keep students engaged. (生徒の集中を保たせることが教師にとって困難) |
(80~150字:序論・本論:論拠・結論)
共通テスト(リーディング・リスニング)
過去問演習(早慶・GMARCH・成成明学・日東駒専)
難関私大に合格するための英語の一般試験・共通テスト・推薦試験・外部試験利用対策はお任せください。是非、お気軽にお問い合わせください。
英文ビジネスライティング
ビジネスライティングで使用する英語は、形式的で、ありふれた表現になりがちです。このような表現は時として情報や意図を正確に伝えることができないばかりでなく、自然なコミュニケーションの流れを妨げてしまうことがあります。人間的な暖かみのある本当のビジネスコミュニケーションを達成するための書き方をお伝えいたします。次の基本ルールを踏まえて進めていきます。
- 明確で、簡潔であること
- 相手を思いやること
- 自然な英語を使用すること
下記のカテゴリーに分類して、課題添削形式で進めていきます。特に、相手に落ち度がある場合に怒りが込み上げてきた場合、あるいは、自分に落ち度があった場合にその事実を認めながらも相手に理解を求める書き方をお伝えいたします。
照会および照会への返答
添削例
🔺相手に落ち度(例:質問に対する回答が不十分)
✖️ You didn’t answer my question clearly.
✔️ I appreciate your response; however, I would be grateful if you could clarify point #3, as it remains a bit unclear.
ポイント:"however" を用いたクッション表現+ "a bit unclear" で角が立たない。強い感情を抑えて冷静に促す表現。
添削例
🔻 自分に落ち度(例:不十分な情報を渡してしまった)
✖️ We are sorry we didn’t explain well.
✔️ We apologize for the lack of clarity in our previous message. We hope the following explanation addresses your concern.
ポイント:"apologize for the lack of clarity" という丁寧な言い回しで非を認めつつ、前向きに補足説明。
注文および注文の確認・返答
添削例
🔺 相手に落ち度(例:注文内容の誤送信)
✖️ You sent the wrong order again.
✔️ Unfortunately, once again, it appears the items we received do not match our original order. Could you kindly look into this matter at your earliest convenience?
ポイント:"Unfortunately, it appears…" で冷静な指摘。相手に非があっても "kindly" などの丁寧語を添える。
添削例
🔻 自分に落ち度(例:注文書のミス)
✖️ We are sorry for the mistake.
✔️ We sincerely apologize for the error in our order form. We have corrected it and appreciate your patience and understanding.
ポイント:"appreciate your patience" で相手の理解を求める姿勢を表すのがビジネス的に好印象。
ルーチン内容
添削例
🔺 相手に落ち度(例:何度も資料を再送させられる)
✖️ You asked for the file again and again.
✔️ Just to clarify, we have attached the file once more in case the previous email didn’t reach you. Please let us know if there are any issues accessing it.
ポイント:"Just to clarify"+"in case…" という穏やかな前置きで、相手の非に触れつつも責めないトーン。
添削例
🔻 自分に落ち度(例:リマインド漏れ)
✖️ We forgot to inform you.
✔️ Please accept our sincere apologies for not sharing the update earlier. Thank you for your understanding and we will make sure to keep you informed going forward.
ポイント:"not sharing the update earlier" という表現で過失を認め、今後の対応策を約束。
案内・お知らせ
添削例
🔺 相手に落ち度(例:変更の連絡が遅い)
✖️ You should have told us earlier.
✔️ We would have appreciated receiving this update earlier, as it impacts our internal scheduling. We would be grateful if you could keep us informed promptly going forward.
ポイント:"would have appreciated" という過去仮定+"going forward" で今後への要望を冷静に伝える。
添削例
🔻 自分に落ち度(例:イベント日程の誤案内)
✖️ We are sorry for the confusion.
✔️ Please accept our apologies for the confusion regarding the schedule. We have corrected the date and attached the revised notice below.
ポイント:"Please accept our apologies" で丁寧に謝罪し、"corrected the date" で対応を示す。
苦情およびお詫び
添削例
🔺 相手に落ち度(例:納期遅延の繰り返し)
✖️ This is the third time your delivery was delayed.
✔️ We have noticed repeated delays in delivery, which have impacted our operations. We would appreciate it if you could review your internal process and advise how this can be prevented.
ポイント:"noticed"・"impacted"・"appreciate it if…" のコンビで、穏やかにしつつ、はっきりと不満を伝える。
添削例
🔻 自分に落ち度(例:納品ミス)
✖️ We are sorry, it won’t happen again.
✔️ We deeply regret the mistake and are taking steps to prevent a recurrence. We truly value your continued support.
ポイント:"taking steps to prevent a recurrence" で再発防止の具体性を伝え、"value your support" で関係維持に配慮。
支払いについて
添削例
🔺 相手に落ち度(例:支払いの遅延)
✖️ You haven’t paid yet.
✔️ Our records indicate that the payment due on April 30 is still outstanding. We would appreciate it if you could confirm the status at your earliest convenience.
ポイント:"indicate that…" + "still outstanding" という受け身・事実の提示型で冷静に催促。
添削例
🔻 自分に落ち度(例:こちらの支払いが遅れた)
✖️ We are sorry we forgot to pay.
✔️ We sincerely apologize for the delay in payment. Due to internal processing issues, the remittance was delayed, but the transfer has now been completed.
ポイント:"due to internal processing issues" で事情を丁寧に説明、"has now been completed" で責任を果たしたことを明示。
添削もしくは生成AIプロンプトをご希望の場合も、是非、お気軽にお問い合わせください。

